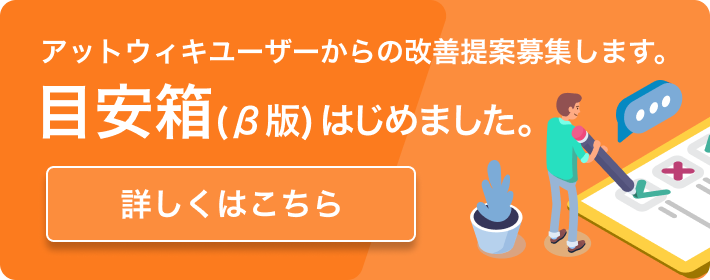オブリビオン図書館
ゾアレイム師匠伝
最終更新:
oblivionlibrary
-
view
ゾアレイム師匠伝
ギ・ナンス 著
トーバルにある「踊る双子の月の神殿」は何百年ものあいだ、足と拳が資本の戦士にとって、タムリエルの中でも屈指の訓練場でありつづけてきた。師匠たちは帝都各地からやってくる生徒を年齢に関係なく受け入れ、いにしえの技術から近代的な応用技まで幅広く教えている。過去に卒業した多くの門弟たちが成功を収めた。私もそこで学んだひとりだ。子供のころ、最初の師匠であるゾアレイムに訊いたことを覚えている。神殿の教えをもっとも深く理解したのはどの卒業生でしょうか、と。
「あの男に会ったとき、私はまだ師匠ではなく一介の生徒だった」と、ゾアレイムは言った。懐かしむように笑みを浮かべて。師匠のしわだらけの大きな顔が、しなびたバスラムの木の実のように見えた。「ずいぶんと昔の話だ。おまえの両親が生まれるよりも前のことだ。何年も神殿で修練を積んでいた私は、踊る双子の月の神殿の誇る博覧強記の師匠が教鞭をとる、非常に難度が高く、求められるものも大きい授業を受けるほどまでになっていた」
「ギ・ナンス、おまえにもやがてわかる時がこよう。逞しい体は逞しい心と共に鍛えられることを。この神殿には、リドル・サーの流儀に従って我らが何年もかけて築いてきた、基幹となるべき訓練の手法がある。私は階段を登りつめて大いなる力とスキルを手にした。たとえ魔術や神がかり的な力を使おうとも、素手による戦いでこの私に勝てるものはほとんどいないだろう」
「その当時、神殿には奉公人がいた。私や授業仲間よりもいくらか年上のダンマーだ。が、彼のことなどまったく眼中になかった。もうかれこれ数年間、こっそりと訓練場に入ってきて、数分で掃除をすませ、黙ったまま出ていくのが彼の日課になっていたからだ。もっとも、彼が何かしゃべっていたとしても、我らは上の空だったろうが。訓練と授業に入り込んでいたからな」
「最後の師匠が、私を含めた数名の徒弟に向かって、神殿を後にするか師となるときが来たようだと告げると、盛大な祝祭が催された。『たてがみ』もわざわざ足を運んで祝祭をご覧になられた。昔も今もここは哲学と戦闘の神殿であるため、神殿の格闘場では、数名のエリートだけでなく全生徒が参加しての討論会や競技会が行われた」
「祝祭の初日、初戦の相手は誰なのだろうかとグラディエーターの登録名簿をながめていると、背後の会話が耳に入ってきた。奉公人が神殿の大僧正と話していたのだ。ダンマーの声を聞いたのはそのときが初めてだった。そして初めて彼の名を知った」
「モロウウィンドで戦っている郷里の仲間と再会したいという気持ちはよくわかるとも、タレン」と、大僧正は言った。「残念至極ではあるがな。おまえはもう、この神殿になくてはならない存在であったから。みんなさみしがるだろうが。私にできそうなことがあったら、なんなりと申しつけるがいい」
「なんとも嬉しいお心遣いでしょう」と、ダンマーは答えた。「ひとつだけ頼みがございますが、おいそれと認められることではないかもしれません。この神殿にやってきてからずっと、修練にはげむ生徒たちの姿を目にしているうちに、自分でも職務の合間を縫って練習を続けてきたものです。私はしがない奉公人でしかございませんが、格闘場で戦うことをお許しいただけるのなら、まことに名誉でありましょう」
「あまりにおかどちがいなエルフの放言に、私はあえぎかけた。修練を積んだわれわれと対等に戦わせてほしいなどと、よくもぬけぬけと言えたものだ。驚いたことに、大僧正はふたつ返事で請け合うと、初心者階級の登録名簿にタレン・オマサンの名を書き加えたのだ。私はエリートの同輩たちにこの話を耳打ちしたくてうずうずしていたが、あと数分で自分の初戦が始まるところだった」
「私は十八戦連続で戦い、全勝した。格闘場に集った観衆は私の才能のことを知っていて、対戦が終わるたびに控えめな、驚きの少ない拍手を浴びせてきた。どんなに戦いに集中しようとしても、格闘場の他のグラディエーターのほうに注目が集まっていくのが気になってしかたがなかった。観客はひそひそ話に勤しみ、無傷の連勝記録よりもはるかに刺激的で、先の読めない対戦を求めて何人もが席を立ちはじめていた」
「踊る双子の月の神殿で教えるもっとも大切な授業のひとつが、虚栄心を捨てることだろう。私はそのとき、心と体の個人的共時性を成し遂げることの、無意義な外部的影響をはねつけることの大切さを理解してはいたが、心では受け入れていなかったのだな。自分が強いことはわかっていながら、自尊心が傷ついたのだ」
「とうとうチャンピオン決定戦となった。私は勝ち残ったふたりのうちのひとりだった。対戦相手の戦士を目にしたとき、傷だらけの威厳に満ちていた私の心は不信感に染まった。私の敵は奉公人のタレンだったのだ」
「これは冗談にちがいない、哲学的な最終試験にちがいないと、私は自分に言い聞かせた。それから観衆を見やると、世紀の一戦が始まるという期待感で誰もが目を輝かせていた。タレンと敬意を取り交わした。私はぎくしゃくと、彼はいかにも慎み深く。戦いが幕を開けた」
「最初はさっさと終わらせる気でいた。タレンなど格闘場を掃除するほどの価値もないのに、そこで戦うなどもってのほかだと思っていた。まったくとんちんかんな考えだったよ。タレンも私と同じように、何人もの生徒を倒して決勝の舞台まで勝ち上がってきたとわかっていたはずなのに。タレンは私の攻撃に対してよくあるカウンターで応じ、殴られたら殴り返した。幅広いスタイルを持っていて、洗練された難しい足技を使ったかと思えば、次の瞬間には単純なジャブやキックを放ってきた。私は執拗に攻撃を繰り出してタレンを圧倒しようとしたが、私の才能を恐れるような、あるいは見下すような色がその顔に浮かぶことはなかった」
「長い戦いになった。いつ敗北を覚悟したのかは覚えていないが、試合が終わっても結果をすんなりと受け入れた。普段は感じないようなうそ偽りのない謙虚さでもって、私は彼に一礼した。が、万雷の拍手に送られながら格闘場をあとにするとき、私は訊かずにはいられなかった。いったいどうやって師匠級の腕前をこっそりと磨いていったのかと」
「私の立場ではそうするしかなかったのです」と、タレンは言った。「毎日毎日、私は優秀な生徒の訓練場を掃除し、それが終わると初級の生徒の訓練場を掃除してきました。そのせいか、初歩的な失敗や教訓、技術を忘れるという不運に見舞われることなく、師匠のあるべき道を観察し、学んでいくことができたのです」
「翌朝、タレンはトーバルを後にして故郷へ帰っていった。それ以来、彼とは会っていない。人づてに僧侶や師になったという話を耳にはしたが。私も師になって、踊る双子の月の神殿で訓練を始めたばかりの子供達や、才能ある者達の面倒を見ている。そして傑出した生徒がいれば、ゆめゆめ初心を忘れることのないよう、未熟な戦いを見物しに連れていくことにしているのだ」