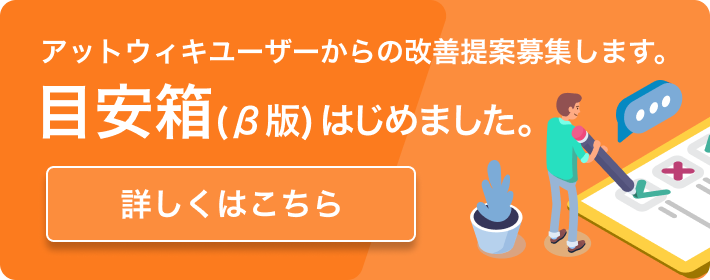オブリビオン図書館
2920 第一紀 最後の年
最終更新:
oblivionlibrary
-
view
2920 暁星の月(1巻)
第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 暁星の月1日
モルンホールド(モロウウィンド)
アルマレクシアは毛皮のベッドに横たわり、夢を見ていた。太陽が窓に当たり、彼女の肌色の部屋に乳白色の光が注ぎ込まれて、ようやく彼女はその目を開けた。それは静寂と静けさであり、彼女が見ていた血と祝典で溢れていた夢とは驚くほどに違っていた。数分間、彼女は天井を見つめビジョンの整理を試みた。
彼女の王宮の宮廷には冬の朝の涼しさで湯煙を立てている、沸き立つプールがあった。手の一握りで湯煙は消え、彼女の恋人ヴィヴェックの顔と姿が北の書斎に見えた。すぐには話しかけたくなかった: 赤のローブを着て、毎朝のように詩を書く彼はりりしく見えた。
「ヴィヴェック」彼女が言うと、彼は笑顔とともに顔を上げ、何千マイルもの彼方から彼女の顔を見ていた。「戦争の終わりのビジョンを見たわ」
「80年も経った今、誰にも終わりは見えないと思うが…」と、ヴィヴェックは笑顔とともに言ったが、真剣になり、アルマレクシアの予言を信じた。「誰が勝つ? モロウウィンドか、それともシロディール帝都か?」
「ソーサ・シルがモロウウィンドにいなければ、私たちは負けるわ」と、彼女は返答した。
「私の情報によると、帝都は北部を春の早い段階で攻撃するであろう。遅くとも蒔種の月にはね。アルテウムへ行き、戻るよう彼を説得してくれるか?」
「今日発つわ」と、彼女は即座に言った。
2920年 暁星の月4日
ギデオン (ブラック・マーシュ)
女帝は牢獄のなかを歩き回っていた。冬の季節が彼女に必要のない体力を与えていたが、夏はただ窓の近くに座り、彼女を冷ましにきた、ムッとするような沼地の風に感謝するだけであった。部屋の反対側では、帝都宮廷での舞踏会を描写した、未完成のつづり織りが彼女を嘲るように見えた。彼女はそれを枠から破り取り、床に落としながら引き裂いた。
その後、自らの無駄な反抗の意思表示を笑った。修理するのに十分な時間があり、その上で更に100枚作る時間もあった。皇帝は7年前に彼女をギオヴェッセ城に監禁し、おそらく彼女が死ぬまでそこに拘留するつもりであろう。
ため息とともに、彼女の騎士ズークを呼ぶ綱を引いた。帝都衛兵にも相応しい制服を着た彼は、数分以内に扉の前に現れた。ブラック・マーシュ出身のコスリンギーの民のほとんどは裸でいることを好んだが、ズークは衣服に前向きな楽しみを覚えていた。彼の銀色で反射する皮膚はほとんど見えず、顔、首、手のみを露出していた。
「殿下」と、お辞儀をしながら彼は言った。
「ズーク」と、女帝タヴィアは言った。「退屈である。今日は夫を暗殺する手段を話そうぞ」
2920年 暁星の月14日
帝都 (シロディール)
南風の祈りを宣告する鐘の音が帝都の広い大通りや庭園に鳴り響き、皆を神殿へと呼んでいる。皇帝レマン三世はいつでも最高神の神殿の礼拝に参列したが、彼の息子にして継承者である王子ジュイレックは、各宗教的祝日はそれぞれ違う神殿にて礼拝に参列するほうが政治上より良いと思っていた。今年はマーラの慈善大聖堂であった。
慈善での礼拝は幸い短かったが、皇帝が王宮から戻れたのは正午を大きく回ってからであった。その頃には、闘技場の闘士たちは式典の始まりをしびれを切らして待っていた。ポテンテイト・ヴェルシデュ・シャイエがカジートの軽業師の一座による実演を手配していたため、群集はそれほど落ち着かない様子ではなかった。
「そちの宗教は我が宗教よりも都合がよいな」と、皇帝はポテンテイトに謝罪するかのように言った。「最初のゲームは何であるか?」
「優れた戦士2人による、一対一の決闘であります」と、ポテンテイトが立ち上がりながら言った。うろこ状の皮膚が、日の光を受け止めていた。「彼らの文化に相応しい武装で」
「よいぞ」と皇帝は言い、手を叩いた。「競技を開始せよ!」
二人の戦士が群衆の声援が沸き立つ闘技場に入るや否や、皇帝レマン三世はこのことについて数ヶ月前に約束したが、忘れてしまっていたことに気がついた。闘士の1人はポテンテイトの息子サヴィリエン・チョラック。ギラギラした象牙色のうなぎは、アカヴィリ剣と小剣を一見細く、弱そうな腕で握っている。もう一方は、皇帝の息子、王子ジュイレック。黒檀の鎧とともに野蛮なオークの兜と盾、そしてロングソードを携えている。
「この見物は興味をそそります」と、ポテンテイトが息を漏らすように言い、細い顔でにこやかに笑った。「シロディールがアカヴィルとこのように戦うのを見た覚えがありません。通常は、軍対軍ですからな。やっとどちらの考え方が良いのか決着がつけられます── あなた方のように、剣と戦うために鎧を作るのか、それとも、我々のように、鎧と戦うために剣を作るのか」
まばらにいるアカヴィリの参事とポテンテイト以外はサヴィリエン・チョラックの勝ちを望んではいなかったが、彼の優雅な動きを目にしたとき、皆息を呑んだ。彼の剣は体の一部のようで、尻尾が腕から伸び、後ろの腕に合わせる。重量を平衡させる業で、若い蛇男を丸まらせ回転しながら、攻撃姿勢のままでの舞台の中央への移動を可能とさせた。王子はそれほど印象的ではない、普通の移動方法で、とぼとぼと前へ進んだ。
二人がお互いに飛び掛ると、群集は歓喜の叫びを上げた。アカヴィリはまるで彼が王子の衛星軌道上の月であるかのように、後ろからの攻撃を試みるために楽々と彼の肩を飛び越えたが、王子は盾で防ぐためにすぐに旋回した。彼の反撃は、敵が地面に倒れこみ、スルスルと彼の足の間を抜けながら足を引っ掛けたので空を切った。王子は大きな衝突音とともに地面に倒れた。
王子はすべて盾で防いだが、サヴィリエン・チョラックが幾度となく王子に攻撃をしかけると、金属と空気が溶けて融合した。
「私たちの文化に盾はありません」と、ヴェルシデュ・シャイエが皇帝に呟いた。「息子には盾が奇妙に見えているのでしょう。私たちの国では、殴られたくなかったら、避けるのです」
サヴィリエン・チョラックが再度目もくらむような攻撃に備えて後ろ足で立ったとき、王子は彼の尻尾を蹴り彼を一瞬後ろに退かせた。彼はすぐに立ち直ったが、王子も地に立っていた。二人ともお互いの周りを回っていたが、そのうち蛇男が、アカヴィリ剣を突き出して前に回転しながら出てきた。王子は敵の策を見破っており、アカヴィリ剣をロングソードで、そして小剣を盾で防いだ。その短く突き抜く刃は金属にめり込んでしまい、サヴィリエン・チョラックは平衡を崩されてしまった。
王子のロングソードがアカヴィルの胸を切り、突然の激しい痛みが彼に両方の武器を落とさせてしまった。直後、戦いは終わった。サヴィリエン・チョラックは王子のロングソードを首に突きつけられた。解体される家畜同然であった。
「ゲームは終了である!」と、皇帝は叫んだが、闘技場内の拍手の音でかすかに聞こえただけである。
王子はにっこりと笑い、サヴィリエン・チョラックが立ち上がるのを手伝い、治癒師へ連れて行った。皇帝は安堵しながらポテンテイトの背中を叩いた。戦いが始まったとき、息子が勝つ可能性の低さに気付いていなかった。
「彼はいい戦士になります」と、ヴェルシデュ・シャイエが言った。「そして、偉大な皇帝に」
「これだけは憶えておけ」皇帝は笑った。アカヴィリには派手な技が多いが、我々の攻撃が1度でも通用すれば、それで終わりなのだ」
「よく憶えておきます」ポテンテイトは頷いた。
レマンの残りのゲームの最中、その言葉のことを考えていて心底楽しめなかった。ポテンテイトも、女帝がそうであったように敵なのだろうか? この件は監視することにした。
2920年 暁星の月21日
モルンホールド(モロウウィンド)
「なぜ私があげた緑のローブを着ない?」と、モルンホールドのデュークは若い娘が服を着るのを見ながら聞いた。
「合わないからよ」トゥララは笑った。「それに、赤が好きなのを知っているでしょう」
「合わないのは、太り始めているからだ」と、デュークは笑い、彼女をベッドに引き込み、胸や腹部に口づけをした。くすぐったくて彼女は笑ったが、起き上がり、赤いローブを羽織った。
「女性らしく出るところは出ているのよ」と、トゥララは言った。「明日会える?」
「いや」と、デュークは言った。「明日はヴィヴェックをもてなさなければならない、そして次の日はエボンハートのデュークがここを訪れる。アルマレクシアが居なくなるまで、私はアルマレクシアと彼女の政治手腕を大切に思っていなかった。信じられるか?」
「私と同じね」トゥララは微笑んだ。「私が居なくなって初めて大切に思うのよ」
「そんなことはない」デュークはせせら笑った。「今、大切に思っているさ」
トゥララは扉を出る前に、デュークに最後の口づけを許した。彼女は彼の言った言葉を考え続けた。彼女が太り始めているのは彼の子を宿しているからだと知ったら、彼はどれだけ彼女を大切に思ってくれるのだろうか? 結婚するほど大切に思ってくれるだろうか?
時は薄明の月へと続く。
2920 薄明の月(2巻)
第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 薄明の月3日
アルタエルム島(サマーセット)
見習いたちが一人一人オアッソムの木へと浮かび上がり、高いほうの枝から果実もしくは花を摘み、地面へと舞い降りてくる様子を、その身のこなしの個人差を含めて、ソーサ・シルは眺めていた。彼は満足げにうなずきつつも、一瞬その日の天気を楽しんだ。大魔術師自身が遥か昔に手本となって作られたとされるシラベインの白い像が、湾を見下ろす崖の近くに立っていた。淡い紫色のブロスカートの花がそよ風に揺られて前後していた。その向こうには大海と、アルタエルムとサマーセット本島を分けるもやがかった境界線が見えた。
「概ね良好だな」最後の見習いから果実を受け取りながら、彼は講評を述べた。手を一振りすると、果実も花も元あった位置へと戻っていた。もう一振りすると、見習いたちは半円状に妖術師を取り囲んだ。彼は白いローブの中から直径一フィートほどの小さな繊維質の玉を取り出した。
「これが何かわかるか?」
修練僧たちは質問の意図を理解していた。すなわち、謎の物体に鑑定の呪文を唱えよとのことだった。彼らは一人一人、目を閉じ、その塊が万物の真実の中にあるのを思い浮かべた。あらゆる物質および精神体がそうであるように、玉は独特の響きを発しており、それには負の要素、鏡面要素、相対経路、真の意味、宇宙における歌、時空の中での性質、そして常にあり続け、いつまでもあり続けるであろう存在の側面があった。
「玉です」ウェレグと名乗る若いノルドが口にすると、年の若い修練僧たちの間で忍び笑いをする声も聞こえたが、ソーサ・シル本人を含め、多くの者は眉をひそめた。
「愚かな答えを返すなら、せめて愉快な答え方をするがいい」妖術師は叱るように言うと、困惑した様子の、若い黒髪のハイエルフの娘に目を向けた。「わかるか、リラーサ?」
「グロムです」と、リラーサは自信なさげに答えた。「ドルーがメフするものです。ク… ク… クレヴィナシムの後で」
「正確にはカルヴィナシムだが、良い答えだ」と、ソーサ・シルは言った。「どういう意味なのか、説明はできるか?」
「わかりません」リラーサは認めた。他の修練僧たちも首を振った。
「物事の理解にはいくつかの層が存在する」と、ソーサ・シルは言った。「そこらの者であれば、物を見る際に自らの考えの中に当てはめる。古き習わし、すなわちサイジックたちの法、神秘に長けた者たちは、物を見てその役割から素性を知ることができる。だが理解に達するには、もう一枚、剥がすべき層が存在する。物をその役割と真実から鑑定し、その意味を解釈する必要があるのだ。この場合、この玉は確かにグロムである。大陸の北部および西部に生息する水棲種族、ドルーが分泌する物質の名称だ。ドルーはその生活環のうち、一年間カルヴィナシムを経て、陸上を歩くことになる。その後、水へと戻ってメフすることになる。すなわち陸上での生存に必要であった皮膚と器官を自ら貪る。そしてこのような小さな玉状のものを吐き出す。グロム、すなわちドルーの吐しゃ物のことだ」
修練僧たちは妙な表情で玉を見つめていた。ソーサ・シルはこの講義が何よりも好きだった。
2920年 薄明の月4日
帝都(シロディール)
「密偵だ」皇帝は風呂につかり、足にできたこぶを見つめながら漏らした。「余のまわりは裏切り者と密偵だらけだ」
妾のリッジャは皇帝の腰に両脚を絡めたまま、その背中を流した。長年の経験より、性と官能の使い分けは心得ていた。皇帝がこのような機嫌の時は、落ち着かせるように、なだめるように、誘惑するかのように官能的であるのが正解だった。かつ、直接何かを尋ねられない限りは一言も発しないことだった。
もっとも、すぐに質問がとんできた。「皇帝陛下の足を踏みつけた者がいたとして、『申し訳ありません、皇帝陛下』と言ってきたらどう思う? 『お許しください、皇帝陛下』のほうが適切だと思わんかね。『申し訳ありません』では、まるであのアルゴニアンめが私が皇帝陛下であることを申し訳無く思っているかのようではないか。我々がモロウウィンドとの戦に負ければいいと願っているかのようにな。そう聞こえる」
「いかがなさいますか?」と、リッジャは問いかけた。「鞭打ちに処すべきでしょうか? 所詮はソウルレストの武将に過ぎません。足元に気をつけるよう、思い知らせてやるのもいいでしょう」
「余の父であれば、鞭打ちにしていただろう。祖父であれば処刑していたな」と、皇帝は不満そうに言った。「だが私は足くらいならいくら踏まれてもかまわん。相応の敬意さえ表してくれればな。そして、謀叛を企てなければな」
「せめてどなたかは信用なさらないと」
「おまえだけだよ」皇帝は微笑み、僅かに身体をひねってリッジャに接吻をした。「息子のジュイレクもだろうな。あいつにはもう少し慎重さがほしいが」
「議会と、摂政様は?」と、リッジャは尋ねた。
「密偵の群れと、蛇だ」皇帝は笑い、再び妾に接吻した。愛し合い始めつつ、彼はささやいた。「おまえさえ忠実であれば、世は何とでもなる」
2920年 薄明の月13日
モーンホールド(モロウウィンド)
トゥララは黒い、装飾された街の門の前に立っていた。風が彼女の体に吹きつけていたが、何も感じなかった。
公爵はお気に入りの愛人が妊娠したと知って激怒し、彼女を追放したのだった。何度も何度も面会をと懇願したものの、衛兵に追い返されてしまったのだ。彼女はついに家族のもとに帰り、真実を伝えたのであった。真実を隠し、父親が分からないと言い張りさえしていれば。兵士でも、流れ者の冒険者でも、誰でもよかったのに。だが彼女は父親は公爵、すなわちインドリル家の一員であると話したのだった。誇り高きレドラン家の者である以上、彼らのとった対処はやむを得ないものであり、そのことは彼女も承知していた。
トゥララの手には、父が泣きながら押しつけた追放の烙印が焼きついていた。だが、彼女にとっては公爵に受けた仕打ちのほうが遥かに苦痛であった。トゥララは門を通して真冬の荒野を見渡した。歪んだ姿で眠り続ける木々と、鳥のいない空。もはや、モロウウィンドに彼女を受け入れてくれる者などいない。遠くへ行かなければ。
重い、悲痛な足取りで、彼女の旅は始まった。
2920年 薄明の月16日
アネクイナ(今日のエルスウェーア)、センシャル
「何かご心配事でも?」と、ハサーマ王妃は夫の機嫌の悪さに気づいて尋ねた。普段は恋人の日の夜となると、夫は大抵上機嫌になり、他の招待客と共に舞踏場で踊っているのが常であったが、今夜は早めに引き上げてきたのであった。王妃が様子を見に行くと、彼は寝床で身体を丸め、眉をひそめていた。
「あの忌々しい吟遊詩人が聞かせたポリドールとエロイサの物語、あれで気分を害してしまったよ」王は不満そうに唸った。「どうしてあのような気の滅入るような話をするのだ?」
「ですが、それこそがあの物語の真実ではないのですか? 世の理の残酷さゆえに破滅を迎えたのでは」
「真実かどうかは、どうでもいいことだ。くだらん話に、下手な語り手だ。もう二度とやらせはすまい」ドローゼル王は寝床から跳ね起きた。その目は涙で曇っていた。「どこの出だと言っていたか?」
「ヴァレンウッド東端のギルヴァーデイルだったかと」と、王妃は動揺した様子で答えた。「あなた、何をなさるおつもりなのです?」
ドローゼルは一瞬で部屋を出、塔へと続く階段を駆け上がっていった。ハサーマ王妃は夫の意図を察していたとしても、彼を制しようとはしなかった。最近は妙な言動やかんしゃくが目立ち、ひきつけさえ起こしていたのだった。だが彼女は王の乱心の根深さも、吟遊詩人、および彼が語って聞かせた人間たちの残酷さと異常さに関する物語に対し、王がどれだけ憎しみを感じていたかも気づいていなかったのである。
2920年 薄明の月19日
ギルヴァーデイル(ヴァレンウッド)
「もう一度よく聞くんだぞ」と、年老いた大工は言った。「三つめの部屋に黄銅のくず鉄があるなら、二つめの部屋に金の鍵がある。一つめの部屋に金の鍵があるなら、三つめの部屋には黄銅のくず鉄がある。二つめの部屋に黄銅のくず鉄があるなら、一つめの部屋に金の鍵がある」
「わかったわ」と、婦人は言った。「言われた通りにね。だから一つめの部屋に金の鍵があるわけでしょう?」
「違う」と、大工は答えた。「もう一度最初からいくぞ」
「お母さん?」と、少年が母親の袖を引っ張って言った。
「ちょっと待っててね、お母さんお話し中なの」母親は答えると、謎かけに意識を集中させた。「あなた言ったわよね、『二つめの部屋に黄銅のくず鉄があるなら、三つめの部屋に金の鍵がある』って」
「いや、違う」大工は根気良く答えた。「三つめの部屋に黄銅のくず鉄があるのは、二つの……」
「お母さん!」少年が悲鳴を上げた。母親はようやくその意図に気づいた。
明るい赤色の霧が波となって街に押し寄せ、建物を次々と飲み込みつつあった。その前を赤い皮膚の巨人、デイドラのモラグ・バルが大股で歩いていた。その顔に笑みを浮かべて。
2920年 薄明の月29日
ギルヴァーデイル(ヴァレンウッド)
アルマレクシアは辺り一面の泥沼の中で馬を止め、川の水を飲ませようとしたが、飲みたがらないどころか見ずに嫌悪を覚えているようであった。モーンホールドからかなりとばして来たことを考えれば、喉も渇いているはずである。妙だ。彼女は馬を下りると、一行のいる方へと足を運んだ。
「現在位置は?」と、アルマレクシアは尋ねた。
婦人の一人が地図を取り出した。「ギルヴァーデイルという町に近づきつつあるはずですが……」
アルマレクシアは目を閉じ、すぐにまた開けた。その光景は耐え難いものであった。従者たちが見ている中、彼女は煉瓦と骨の欠片を拾い上げ、その胸に抱いた。
「アルテウムへと急ぐぞ」と、彼女は静かに言った。
この年は、蒔種の月へと続く。
2920 蒔種の月(3巻)
第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 蒔種の月15日
カエル・スヴィオ (シロディール)
皇帝レマン三世は、丘の上の見晴らしの良いところから、帝都にそびえる尖塔をじっと見ていた。彼には自分が温かい家、故郷から遠く離れ地にいることが分かっていた。この地の領主、グラヴィアス卿の邸宅は豪華なものだったが、帝都軍を敷地内にまるまる収容できるほどのものではなかった。山腹に沿ってテントが並び、兵士たちはみな卿自慢の温泉に行くのを楽しみにしていた。それもそのはず、そこにはまだ冬の空気が立ち込めていた。
「陛下、ジュイレック王子のご気分がすぐれないようです」
支配者ヴェルシデュ・シャイエに声をかけられ、皇帝は飛び上がった。このアカヴィルが草地の中、一切の音を立てずにどうやって近づいてきたのか不思議だった。
「毒に違いない」と皇帝はつぶやいた。「早急に治癒師を手配しろ。いくら給仕が反対しても、息子にも私のように毒味役をつけるのだ。いいか、我々の周りにはスパイが大勢いることを忘れるな」
「そのように取り計らいます、陛下」とヴェルシデュ・シャイエは答えた。
「現在
政局は非常に不安定でございます。モロウウィンドでの戦いに勝利するためには、戦場に限らず、いかようなる手にも用心するにこしたことはございません。それ故、私が申し上げたいのは、陛下にこの戦いの先陣から退いていただきたいのです。陛下の輝ける先人、レマン一世、ブラゾラス・ドール、レマン二世がそうしたように、陛下も先陣を切りたいというお気持ちは重々承知でございます。しかし、あまりにも無謀ではないかと思われます。私のような者の言葉にどうかお気を悪くなされないでください」
「さようか」と皇帝はこの意見に賛同の意を表した。「しかし、それでは私の代わりに誰が先陣を切るというのだ?」
「お身体が回復されれば、ジュイレック王子が適任かと。もしだめなら、左翼にファーランのストリグとリバーホールドのナギー女王を、右翼にリルモスの将校ウラチスではいかがでしょう」とシャイエは言った。
「左翼にカジート、右翼にアルゴニアンをあてがうだと?」と皇帝は顔をしかめた。「私は獣人を信用しておらん」
皇帝の言葉をアカヴィルはまったく気に留めなかった。皇帝の指す「獣人」とはタムリエルに住む原住民を意味するものであり、彼のようなツァエシとは別であることを十分に承知していたからである。「陛下のお気持ちは分かります。しかし、彼ら獣人がダンマーを嫌っていることをお忘れなく。特にウラチスは領地の奴隷がみなモーンホールドのデューク率いる軍隊に襲われたことを恨んでいます」
それを聞いた皇帝は渋々納得し、ヴェルシデュ・シャイエは下がっていった。皇帝は驚いたが、この時初めてヴェルシデュ・シャイエが信頼に足る人物、味方として優秀な人物であると思えた。
2920年 蒔種の月18日
アルド・エルファウド (モロウウィンド)
「今、帝都軍はどのあたりに?」と、ヴィヴェックは尋ねた。
「2日の行軍でここへ辿り着きます」と、副官は答えた。「我々が今晩夜通し行軍を進めれば、明朝にはプライアイの小高い場所へと辿り着けるでしょう。情報によりますと皇帝は軍の殿を務めることになり、ファーランのストリグが先陣を、リバーホールドのナギーとリルモスのウラチスがそれぞれ左翼と右翼につくそうです」
「ウラチスか……」とヴィヴェックはつぶやいたが、ある考えが浮かんだ。「ちなみにその情報は信用してよいのだな? その情報はどうやって手に入れたのだ?」
「帝都軍に潜んでおりますブレトンのスパイです」と副官は答え、砂色の髪をした若い男に、前に進み出るよう促した。ヴィヴェックの前へ出たその男は頭を下げた。
ヴィヴェックは微笑んで、「名はなんと言う? なぜにブレトンがシロディールと戦う我が軍のために働くのだ?」と尋ねた。
「私はドワイネンのキャシール・オイットリーと言います。この軍のために働いているとしか申し上げられません。諜報活動を行なう者はみな神のために働いているとは言いかねるからです。はからずも私はこの仕事のおかげで食べていけております」と男は答えた。
ヴィヴェックは笑って、「お前の情報が正しければそうであろうな」と言った。
2920年 蒔種の月19日
ボドラム (モロウウィンド)
ボドラムの閑静な村からは、曲がりくねった河、プライアイを見下ろすことができる。それは非常にのどかな風景で、ささやかに木が生い茂り、河の東には険しい崖に囲まれた渓谷、西には美しく彩られた花々が咲きほこる牧草地が広がる。モロウウィンドとシロディールの境界でそれぞれの珍しい植物が出会い、見事にまじりあっていた。
「仕事が終われば、あとはたっぷり眠れるぞ!」
兵士たちは毎朝この一声で目覚めた。夜な夜な続く行軍だけでなく、崖に切り立つ木々をなぎ倒したり、溢れかえる河の水をせき止めたりしなければならなかった。彼らの多くは、疲れたと文句を言うこともできなくなるほど疲労困憊であった。
「確認しておきたいのですが……」とヴィヴェックの副官は聞いた。「崖道を進めば敵の上から矢や呪文で攻撃することができる。そのために木々をなぎ倒すのですね? 氾濫する河をせき止めるのは、敵の動きを封じ込め、泥沼の中で立ち往生させるためですよね?」
「半分は当たっておる」とヴィヴェックは満足げに答えた。ちょうどなぎ倒した木を運んでいた近くの兵をつかみ、「待て。その木の枝から真っ直ぐで丈夫な枝を選び抜き、それをナイフで削って槍を作るんだ。100人ぐらいの兵を集めてとりかかれば、我々が必要とする量は2─3時間で作れるだろう」
そう命じられた兵士はいやいやながら従った。他の者も作業に加わり、槍をこしらえた。
「このような質問は失礼かもしれませんが……」と副官は聞いた。「兵士たちにはこれ以上の武器は必要ないのではありませんか? 疲れている上、もうこれ以上の武器を持てやしません」
「あの槍は戦いで使うために作らせているのではない」とヴィヴェックはささやいた。「兵士たちを疲れさせておけば、今夜はぐっすり眠れるからな」ヴィヴェックが兵士たちを指揮する仕事に取り掛かる前によく眠っておけということだ。
ところで、槍というものは先端が鋭いのは当然のことながら、全体の重量とのバランスも大事である。最もバランスのとれた槍の先端部分には、よく見られる円錐形ではなくピラミッド型が望ましい。ヴィヴェックは槍の強度や鋭さ、安定さを測るため兵士に投げさせ、壊れれば新しいものを渡し、測定をくり返した。こうして兵士たちは疲労を抱えながらも槍の良し悪しを身をもってわかるようになり、最高の槍を作りだせるようになっていく。一度投げてみてから、ヴィヴェックは兵士たちにこの槍をどこにどのように配置するかを指示した。
その夜は戦の前日に行なわれる酒盛りもなければ、新米兵士たちが眠れず夜を明かすこともなかった。陽が落ちると同時に見張りを除いて皆が眠りに落ちた。
2920年 蒔種の月20日
ボドラム (モロウウィンド)
ミラモールは疲れていた。この6日間、彼は賭博へ売春宿へと夜通し遊び回り、昼は昼で行軍を続けていた。ミラモールは戦いの日を待ち望んでいた。しかし、何よりも待ち望んでいたものは戦いのそのあとの休息だった。彼は皇帝指揮下の後方部隊についており、そこが死から一番遠い場所であるのは良かったが、一方で前方の兵士がこしらえたぬかるみだらけの泥道を歩かなければならず、寝坊してしまえば隊から取り残されてしまう危険性もあった。
野生の花々が咲き乱れる中を進むも、ミラモールたち兵士の足元は足首まで冷たい泥に浸かっていた。進むのには骨が折れた。ストリグ卿に指揮された軍の先陣ははるか遠く、崖のふもとの草地に見えた。
その時だった。
崖の上に、昇り行くデイドラのごとくダンマーの軍隊が現れ、たちまちに砲火と矢の雨が先陣に降りそそいだ。その時、モーンホールドのデュークの旗を掲げた一団が馬に乗って岸辺へ飛び出してきたかと思えば、東の谷間の木立へと続く浅瀬の川べりに沿って消えていった。右翼を固めるウラチスはそれを見るや怒号を上げて追跡した。ナギー女王は崖の軍隊に補足するため、自分の軍を西の土手に進ませた。
皇帝はどうしたらよいか分からなかった。彼が率いる後方部隊は泥道にはまってしまい、前に素早く動けず、戦いに参加できないのだ。しかし彼はモーンホールドの軍に包囲されまいと、東の森林に向け突き進むよう命じた。モーンホールドの軍とは出くわさなかった。しかし、ほとんどの兵士は戦いを放棄し、西へ向かっていた。ミラモールは崖の上を見ていた。
そこで背の高いヴィヴェックと思しき一人のダンマーが合図を送った。その合図を受けた魔闘士たちは西の何かに向かって呪文を発した。何かが起こった。ミラモールはそれをダムのようだと思った。ものすごい激流が左翼のナギー女王を先陣へと押し流し、そのまま先陣と右翼の隊は東へと流されて行った。
打ち負かされた軍が戻って来るのではないかと皇帝はしばらく立ち止まっていたが、すぐさま退避を命じた。ミラモールは激流がおさまるまで急いで身を隠し、それから出来るだけ静かに急いで崖を渡った。
モロウウィンドの軍は野営地まで退いていた。ミラモールが河岸に沿って歩いていると、頭上から彼らが勝利を祝う歌声が聞こえてきた。東の方には帝都軍が見えた。兵たちは河にかけられた槍の網に引っかかり、下からウラチスの右翼軍、その上にストリグの先陣、さらにその上にナギーの左翼軍の兵たちが数珠つなぎに刺さっていた。
ミラモールはその死体のポケットや荷物を漁り、金目のものを探していたが、すぐにその場を離れ河を下りて行った。水が血で汚れていないところに行くまでは、何マイルも先へと進まなければならなかった。
2920年 蒔種の月29日
ヒゲース (ハンマーフェル)
「帝都からあなた宛にお手紙が届いてるわよ」尼僧長はそう言いながらコルダへ羊皮紙を渡した。若い尼僧たちは笑みを浮かべながらも驚いた表情をしていた。コルダの姉、リッジャは頻繁に、少なくとも月に一度は手紙を書いてよこすのだった。
コルダは手紙を受け取り、お気に入りの場所、庭で手紙を読もうと出て行った。そこは砂色で単調な修道院の世界の中で唯一のオアシスであった。手紙自体には大した内容は書かれていなかった。宮廷内のゴシップや最新の流行ファッション(ちなみにワインダーク色のベルベット素材が流行るらしい)、ますますひどくなる皇帝の妄執などについてであった。
「あなたはこんな生活から離れて暮らせて本当にラッキーよ」とリッジャは綴っていた。「皇帝はどうやら最近の戦での大失敗は身内にスパイが潜んでたせいと確信してるみたい。私まで疑われる始末よ。ラプトガ様があなたにあたしと同じようなおかしな生活を送らせませんように」
コルダは砂の音に耳をそばだて、ラプトガにまったく逆の祈りを捧げた。
時は恵雨の月へと続く。
2920 恵雨の月(4巻)
第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920 恵雨の月3日
コールドハーバー (オブリビオン)
暗い王宮の濁った水に浸された廊下を、ソーサ・シルは全速力で進んでいた。彼のまわりでは、気味の悪いぶよぶよした生き物が葦の茎の間を這い回り、頭上のアーチでは白い炎が明るく燃え上がっては消え、死の腐敗臭と花の香水の香りが交互に襲ってきた。オブリビオンにデイドラの王子たちを訪ねるのはこれが初めてではないが、ここへくるたびに違ったものに出迎えられるのだった。
だが、彼には目的があり、まわりの奇怪なものに気をとられている時間はなかった。
八人の最も位の高いデイドラの王子たちが、溶けかけた丸屋根の広間で彼を待っていた。黄昏の王子アズラ、企みの王子ボエシア、知恵のデイドラハルマ・モラ、狩人ハーシーン、呪いの神マラキャス、災いの王子メルエーンズ・デイゴン、憤怒の王子モラグ・バル、そして狂ったシェオゴラスである。
頭上の空から歪んだ影が落ち、彼らの集いを覆い隠していた。
2920 恵雨の月5日
アルテウム島 (サマーセット)
ソーサ・シルの声が洞窟に響き渡った。「岩をどかせ!」
すぐに、修練僧たちが巨石を転がして脇へやり、夢見る洞窟への入り口を開いた。現れたソーサ・シルの顔は灰にまみれ、ひどくやつれていた。彼は何ヶ月、いや何年も旅してきたように感じていたが、実際は数日しかたっていなかった。ライラザが彼の腕をとり、支えようとしたが、彼は優しくほほえみ、首を振ってそれを断った。
「それで…… うまくいったのですか?」と、彼女はたずねた。
「デイドラの王子たちはこちらの提案を受け入れた」彼は感情のない声で言った。ギルヴァーデイルに起こったような災いはこれ以上起こらない。彼らは今後、魔女や妖術師を通じてのみ、人間やエルフと関わることになる」
「それで、そのかわりに何を約束してきたんですか?」と、ウェレグというノルドの子供がたずねた。
「デイドラとの契約は──」アイアチェシス宮殿を、サイジック団団長の居所へ向かって進みながらソーサ・シルは言った。「入門まもない者には聞かせられない」
2920 恵雨の月8日
帝都 (シロディール)
嵐が皇太子の寝室の窓を叩き、湿った空気が香炉の吐き出す香やハーブの香りと混じりあっていた。
「お母様の皇后陛下からのお手紙をお持ちしました」と、使者が言った。「その後のお体の具合を心配しておられます」
「心配性な母親だ」ジュレック皇太子はベッドの中で笑った。
「母親が息子を心配するのは当然のことです」と、君主の息子サヴィリエン・チョラックが言った。
「アカヴィル、我が家では何一つ当然のようにはいかないのだ。母は追放され、父が私を反逆者と疑い、毒を盛ったのではないかと案じている」皇太子はうんざりした様子で枕に頭を沈めた。「皇帝は皇帝で、自分のように食べるもの全てを毒見させるよう勧めてくる」
「多くの陰謀がありますから」アカヴィルはうなずいた。「あなたは3週間近くも床につき、国中の治癒師が舞踏会のダンスの相手のようにとっかえひっかえあなたの治癒にあたりました。とにかく、今は回復に向かわれているようですが」
「早くモロウウィンドへ兵を率いて行けるぐらいに回復したいものだ」と、ジュレックが答えた。
2920 恵雨の月11日
アルテウム島 (サマーセット)
修練僧たちは、庭園の開廊に整列していた。彼らの目前には大理石で覆われた長く深い溝があり、中ではまぶしいほどに火が焚かれていた。溝の上の空気は炎の熱気でゆらめいていた。サイジック団の一員として、修練僧は恐れを顔に出さないようつとめていたが、彼らの恐怖は眼前の炎のように明らかだった。ソーサ・シルは目を閉じ、火炎耐性の呪文を唱えた。そして、ゆっくりと燃え盛る炎の中を歩き、無事に溝の反対側へついた。彼の白いローブには焦げ目一つついていなかった。
「他の呪文と同じように、この呪文も唱える者の思いの強さや能力によってその効力が高まる」と、彼は言った。「想像力と意思の力が鍵となる。空気に対する耐性や花に対する耐性が必要ないのと同じように、この呪文を唱えた後は火炎耐性の必要も忘れてしまうだろう。勘違いしてはいけない、耐性というのは、炎がそこにないと思い込むことではない。炎そのものを感じ、その質感や、攻撃性や、熱さえもを感じた上で、それらが何の害もなさないようにするのだ」
生徒たちはうなずき、一人また一人と呪文を唱え炎の中を歩いた。両手で炎をすくいあげ、空気にかざして燃え上った炎を指の間からこぼれ落とさせる者すらいた。ソーサ・シルはほほえんだ。彼らは見事に自身の恐怖を克服していたのだ。
監督官長のサーガリスが回廊の向こうから走ってきて言った。「ソーサ・シル! アルマレクシアがアルテウムに到着した。アイアチェシス様が君を呼んでおられる」
ソーサ・シルが一瞬サーガリスのほうを向いたそのとき、叫び声が聞こえた。彼はそれが何を意味するか知っていた。ノルドの少年ウェレグが呪文を間違えて炎に焼かれていたのだ。髪や肉の焼ける臭いがあたりにたちこめ、慌てふためいた他の生徒たちが溝から脱出しようと引っ張り合っていた。しかし、溝に入ったばかりの場所は容易に後戻りができないように深く作られており、出ることができないのだった。ソーサ・シルは腕を振り、炎を消した。
ウェレグと他の数人が火傷を負ったが、それほど重傷ではなかった。妖術師ソーサ・シルは彼らに回復の呪文をかけ、それからサーガリスに向きなおった。
「今からアルマレクシアに会いに行くが、すぐ戻る。彼女と彼女の従者も長旅で疲れているだろうからな」ソーサ・シルは生徒に向かっていった。彼の声には感情がなかった。「恐怖は呪文を損なわないが、呪文を唱える者は疑いや自信のなさを捨てなくてはならない。ウェレグ君、荷物をまとめたまえ。明日の朝、船が君を本土へ送り返す」
アルマレクシアとアイアチェシスは書斎でお茶を飲みながら笑いあっていた。アルマレクシアは、ソーサ・シルの記憶よりも美しくなっていた。とはいえ、彼女は彼の覚えているようなきちんとした格好ではなく、毛布にくるまり、濡れた黒い髪を火にかざして乾かしていた。ソーサ・シルが歩みよると、彼女は飛び上がって彼を抱きしめた。
「モロウウィンドから泳いできたのか?」彼は笑った。
「スカイウォッチから海岸までの間が大雨だったの」と、彼女は笑顔で説明した。
「1.5マイルも離れていないが、ここでは雨など降っていない」と、アイアチェシスが自慢げに言った。「ここはいつもサマーセットや本土の騒動とは無縁だ。だが、外の世界へ行っていた者の話を聞くのは楽しいものだ。外の世界は騒動と混乱に満ちているからな。ああ、騒動といえば、このごろ聞こえてくる戦争の話は何なのだ?」
「この80年ほど、大陸を血で染めているあの戦争のことですか、団長?」と、ソーサ・シルは面白がって言った。
「多分そうだろうな」アイアチェシスは肩をすくめた。「今その戦争はどうなっているのだ?」
「私がソーサ・シルを説得してアルテウムから連れて行けなければ、我々が負けるでしょう」そう答えたアルマレクシアの顔からは笑顔が消えていた。そのことについては後でソーサ・シルと個人的に話すつもりだったが、アルトマーの老人は彼女に続けるように促した。「そういう未来が見えたのです。そうなると確信しています」
ソーサ・シルは少しの間黙り込み、アイアチェシスを見ながら言った。「モロウウィンドへ戻ります」
「君の性格はよく知っている。心を決めたなら止めても無駄だろうな」老いた団長はため息をついた。「サイジック団は何者にも倒されない。戦争は戦いで、国々は起こり滅びる。君が行くなら、我々も行かなくてはなるまい」
「どういうことですか、アイアチェシス? 島を離れるおつもりですか?」
「そうではない。島が海を離れるのだ」と、アイアチェシスは夢見るような声で言った。「数年のうちに霧がアルテウムを覆い、我々は去るだろう。我々は生まれついての指導者だ。タムリエルには指導者が多すぎる。我々は去り、この地上が我々を必要としたときに、また戻ってくる。時をこえてな」
老アルトマーは危なっかしく立ち上がり、残っていたお茶を飲み干し、ソーサ・シルとアルマレクシアをその場に残して立ち去った。「最後の船に乗り遅れるではないぞ」
時は栽培の月へと続く。
2920 栽培の月(5巻)
第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 栽培の月10日
帝都 (シロディール)
「殿下」と、支配者ヴェルシデュ・シャイエが自分の部屋の扉を開けながら笑顔で言った。「このところお目にかかりませんでしたね。ひょっとしたら殿下は…… リッジャ様が愛らしすぎて具合が悪くなったのかと」
「彼女ならミル・コラップで風呂に入っている」と、皇帝レマン三世が惨めったらしい声で言った。
「どうぞお入りください」
「とうとう3人の人間しか信じられないようなところまで来てしまった。お前と、我が皇太子と、リッジャだ」と、いらだたしそうに皇帝が言った。「元老院は単なるスパイ集団だ」
「どうかなさいましたか、殿下?」と、支配者ヴェルシデュ・シャイエが同情した様子で言いながら、部屋の暑いカーテンを閉めた。大理石の廊下を歩く人の足音や、春先の庭で鳴く鳥の声など、外からの物音はすべてすぐに遮断された。
「ボドラムでの戦いが始まる前に我々が野営をしていた際、わしの息子に毒が盛られたことがあった。その時、ブラック・マーシュ出身のオルマの部族民でカッチカと呼ばれる悪名高い毒殺者が、ケイル・スヴィオで軍隊と一緒にいたという情報をつかんだのだ。本当はわしを殺したかったことは間違いないが、その機会がなかったんだろう」と、忌々しげに皇帝が言った。「だが彼女を告訴するならまず証拠を出すべきだと元老院は言っている」
「もちろんそうでしょうね」と、思いやりを示すようにポテンテイトが言った。「特に、もしその中の一人二人が自ら筋書きに加担していたとすれば。私に考えがあります、殿下」
「何だ?」と、待ちきれない様子でレマンが言った。「早く言いたまえ!」
「この件は撤回すると元老院に申し出てください。私は衛兵を派遣してカッチカの所在を突き止めさせ、尾行させます。彼女と共謀しているのが誰なのかが判明するでしょうし、殿下の命を狙うこの陰謀が果たしてどの程度の大きさのものなのかもつかめるでしょう」
「そうだな」と、満足げに眉を寄せてレマンが言った。「それは名案だ。相手が誰であろうと、そのやり方で突き止めよう」
「もちろんです、殿下」ポテンテイトは微笑みながら、皇帝が部屋を出られるようにカーテンを開けた。部屋の外の廊下にはヴェルシデュ・シャイエの息子、サヴィリエン・チョラックがいた。少年は皇帝に会釈をしてからポテンテイトの部屋に入った。
「何か面倒なことにでもなってるの、お父さん?」と、アカヴィリの少年はささやいた。「皇帝が、ナントカっていう毒殺者の情報をつかんだって聞いたけど」
「話術の最大のコツは──」と、ヴェルシデュ・シャイエが息子に語りかけた。「こちらが相手にさせたいと思っていることを相手がしたくなるように仕向けながら、相手が聞きたがっている言葉を言ってあげることだ。お前には、カッチカに手紙を届けてもらいたい。そして、そこに書かれている指示に完全に従わなければ、命が危なくなるのはこちらよりもむしろ彼女の方だということをちゃんと理解していることを、確認してきて欲しい」
2920年 栽培の月13日
ミル・コラップ(シロディール)
リッジャはぷくぷくと泡を立てている温泉にゆったりと浸かり、無数の小さな石で肌がくすぐられているような感覚を味わっていた。頭の上に突き出している岩のおかげで霧雨は当たらず、日の光だけが木々の枝の間から筋となってたっぷりと降り注いでいた。それは牧歌的な生活におけるのどかなひとときであり、入浴後には自分の美しさがすっかり蘇っているはずだということを彼女は知っていた。唯一足りないものは一杯の水だった。温泉のお湯は匂いこそ素晴らしいが、必ずチョークの味がした。
「水!」と、召使いに向かって叫んだ。「水をちょうだい!」
目隠しするように顔に布を巻いた、一人のやせこけた女がリッジャのそばに駆けてきて、ヤギ皮の水袋を落とした。そのあまりの慎み深さにリッジャは思わず笑い出しそうになった──自分が素っ裸でいることを恥ずかしいとは思っていなかったのだ──が、布の透き間から見えた老婆の顔にはそもそも瞳がないことに気がついた。話には聞いたことがあるが一度も会ったことはないオルマの部族民のようだった。生まれつき目がない彼らは、それ以外の感覚がずば抜けて優れている。ミル・コラップの君主は召使いの雇用に関してずいぶんと異国趣味のようだと、リッジャはひそかに思った。
すぐに女は立ち去り、その存在は忘れ去られた。そこにいると日の光と温泉のこと以外は何も集中して考える気になれないことをリッジャは感じていた。水袋のコルクを抜いてみたが、中の液体は妙に金属臭い匂いがした。気がつけば、そこにいるのは彼女一人ではなかった。
「リッジャ様」と、衛兵隊長が言った。「カッチカとお知り合いのご様子ですね?」
「知らないわ、そんな人」と、どもりながら言った。そして、憤然とした様子で言葉を続けた。「ここで何してるの? 私の身体は下品な視線にさらすためのものじゃないのよ」
「お知り合いではないとおっしゃる。ついさっきご一緒におられたようですが」と言いながら隊長は水袋を拾い上げ、匂いを嗅いだ。「ネイヴー・イコーを持ってきたようですね? 皇帝に毒を盛るためですか?」
「隊長」と、駆け寄ってきた衛兵の一人が言った。「アルゴニアンの姿が見当たりません。どうやら森に消えたようです」
「ああ、連中にはお手のものだからな」と、隊長は言った。「だが問題はない。宮中の連絡係を見つけたからな。殿下もお喜びになるだろう。この女を捕まえろ」
身もだえする裸の女を衛兵たちが湯ぶねから引き上げると、彼女は叫んだ。「濡れ衣だわ! 私は何も知らないし、何もしていない! 皇帝がこれを知ったら絞首刑になるわよ!」
「ああ、もちろんそうなるだろうな」隊長が微笑んだ。「皇帝がお前を信用されればの話だが」
2920年 栽培の月21日
ギデオン (ブラック・マーシュ)
酒場「ブタとハゲワシ」は人目につくことなく行動できる場所で、今回のような相手に会う際にズークが好んで用いる店だった。彼とその連れ以外、薄暗い店の中にいるのは霧のような存在の数人の老人のみで、しかも酔いつぶれてほとんど意識がなくなっていた。汚れっぱなしの真っ黒な床は目ではなく足で確かめて歩くべきものだった。空中に浮かんだおびただしい埃はじっとして動かず、わずかに差し込んでくる夕陽の光に映し出されていた。
「激しい戦闘に加わった経験は?と、ズークが訊ねた。「割のいい仕事だが、その分、危険も非常に大きい」
「戦闘経験なら言うまでもない」と、ミラモールが横柄に答えた。「2ヶ月前にボドラムの戦いに行ってきたばかりだ。そっちが責任を果たして、約束どおりの日時に、最小限の護衛を伴って皇帝が馬でドーザ峠を通るようにしてくれれば、俺は俺の責任を果たす。皇帝が変装しないで来るようにさせることだけは忘れないでくれ。皇帝レマンが隠れているかもしれないと疑って、峠を通る隊商を皆殺しにするのはごめんだからな」
ズークが微笑み、ミラモールはそのコスリンギー独特の思慮深そうな顔に自分の姿を見た。彼はその見た目が気に入っていた。完ぺきな自信に満ちたプロの顔だった。
「よろしい」と、ズークは言った。「残りの金は仕事が済んでからだ」
ズークは二人の間にあるテーブルの上に大きな収納箱を置き、立ち上がった。
「数分してから出てくれ」と、ズークは言った。「後はつけないように。依頼主は匿名のままでいたいと望んでいるから、万が一、君が捕まって拷問にかけられた場合のことも用心してる」
「心配するな」と、酒のおかわりを求めながらミラモールが言った。
ズークは馬に乗って迷路のように狭く入り組んだギデオンの道を駆け、ようやく門を抜けて国に入った時には、彼も馬もほっとため息をついたかのようだった。ジョヴェーゼ城に続く本街道は、春になると毎年そうであるように水浸しになっていたが、ズークは丘を越える近道を知っていた。枝にまで苔が生えて垂れ下がっている木の下を走り、つるつると滑りやすく危険な岩場も駆け抜けて、彼は2時間もかからずに城門に辿り着いた。そして直ちに、一番高い塔のてっぺんにあるタヴィアの独房へと駆け上がった。
「どんな男だった?」と、女帝が訊ねた。
「愚か者です」と、ズークは答えた。「しかし、この手の仕事にはむしろそのほうが好都合です」
2920年 栽培の月30日
サーゾ要塞 (シロディール)
リッジャは、ただひたすら叫び続けた。独房の中でその声を聞き届けているのは、厚い苔に覆われてはいるがびくともしない大きな灰色の石壁のみだった。外にいる衛兵たちは、彼女だけでなくすべての囚人に対して聞く耳を持っていなかった。遠い彼方の帝都にいる皇帝にも、無実を訴える彼女の叫びはまったく届いていなかった。
おそらくもう誰も聞いてくれないことは十分に分かっていたが、それでも彼女は叫んだ。
2920年 栽培の月31日
カヴァス・リム峠 (シロディール)
シロディールであろうとダンマーであろうと、トゥララが人の顔というものを最後に見てから何日、いや何週間も経っていた。道を歩きながら彼女は、これほどまでに住む人が少ないシロディールが皇帝の住まい、すなわち帝都となったのは本当におかしなことだと考えていた。ヴァレンウッドのボズマーにだって、このハートランドよりは住む人の多い森があるに違いない。
彼女は回想していた。モロウウィンドからシロディールに入る国境を越えたのは1ヶ月前、それとも2ヶ月前? 今よりずっと寒かったのは確かだが、それ以外に時間的な手がかりは何もなかった。衛兵たちはぞんざいな態度ではあったが、彼女が何も武器を持っていなかったため、国境通過を許可するほうを選んだのだ。以来、彼女はいくつかの隊商に出会ったし、キャンプを張っていた冒険者たちと食事を共にしたことさえあったが、町まで乗せていってくれる者には一度も出会わなかった。
トゥララはショールを外し、後ろに引きずって歩いた。一瞬、背後にいる誰かの音が聞こえた気がして、振り返ってみた。誰もいなかった。小鳥が枝に留まって、笑い声に似た鳴き声を出しているだけだった。
彼女は歩き続け、立ち止まった。たいへんなことが起きようとしていた。お腹の赤ん坊はそれまでにも蹴ることがあったが、今回のけいれんは違う種類のものだった。うめき声を上げて彼女はよろよろと道の脇に向かい、草の上に倒れ込んだ。赤ん坊が生まれようとしていた。
彼女は仰向けになって力んでみたが、痛みと落胆で涙があふれてほとんど何も見えなくなるばかりだった。なぜこんなことになってしまったのだろう? 荒れ地の中、一人きりでモーンホールド公爵の子を出産することになるなんて。激しい怒りと苦悩で発した叫び声に、木々の鳥が一斉に飛び立った。
先ほど彼女を笑っていた小鳥が道に降りてきて留まった。トゥララがまばたきすると小鳥は消え、そこにダンマーほど浅黒くはないがアルトマーほど青白くもない、一人のエルフの男が裸で立っていた。アイレイドのワイルド・エルフだということは、彼女にもすぐに分かった。トゥララは叫んだが、男が彼女を押さえつけた。数分間のもみ合いの後、すっと力が抜けていく感じがして、彼女は気を失った。
目を覚めさせたのは、赤ん坊の泣き声だった。その子はきれいに拭かれて彼女の隣に寝かせられていた。トゥララは女の赤ん坊を抱き上げ、その年に入ってから初めて喜びの涙が頬を伝うのを感じた。
頭上の木々に「ありがとう」とつぶやき、赤ん坊を両腕に抱えて彼女は道を西へと歩き始めた。
時は真央の月へと続く。
2920 真央の月(6巻)
第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 真央の月2日
バルモラ (モロウウィンド)
「帝都軍が南に集結しております」キャシールは言った。「二週間の進軍でアルド・イウバルとコロチナ湖に到達するでしょう。それと、きわめて重装備でありました」
ヴィヴェックはうなずいた。アルド・イウバルと湖の対岸の姉妹都市、アルド・マラクは戦略の要地とされる城砦だった。ここしばらく、敵が動くのではないかと懸念していた。ヴィヴェックに仕える将軍がモロウウィンド南西部の地図を壁から引きはがすと、開け放しの窓から舞い込んでくる心地よい夏の海風と格闘しながら、手で撫でつけてまっすぐに伸ばした。
「重装備だと言ったな?」と、将軍は訊いた。
「はい、将軍」キャシールは言った。「ハートランドはベサル・グレイにて野営しておりました。どの鎧も黒檀製やドワーフもの、デイドラものばかりで、上等な武具や攻城兵器も確認できました」
「魔術師や船は?」と、ヴィヴェックは訊いた。
「魔闘士の軍団がおりましたが──」キャシールは答えた。「船はないものかと」
「それほどの重装備なら、ベサル・グレイからコロチナ湖までは確かに二週間はかかる」ヴィヴェックは地図をじっくりとながめた。「さらに北からまわり込んでアルド・マラクへ向かおうとすれば、沼地にはまってもたつくことになろう。となれば、この海峡を越えてアルド・イウバルを攻め落とそうと考えるにちがいない。それから湖岸沿いに東進し、南からアルド・マラクを奪おうとする」
「海峡を越えてくるなら、やつらは袋のねずみですな」と、将軍は言った。「半分ほど渡りきってしまえばもうハートランドには引き返せない。そこで一気に襲いかかるのです」
「またもやそなたの機知に助けられたようだ」ヴィヴェックはそう言い、キャシールに笑いかけた。「今一度、帝都の侵略者どもを撃退してやろうぞ」
2920年 真央の月3日
ベサル・グレイ (シロディール)
「勝利しておきながら、かように帰還なさるおつもりですか?」ベサル卿は訊いた。
ジュイレック王子はまるでうわの空だった。野営地の後片づけをしている軍隊に意識を集中させていた。肌寒い森の朝だったが、雲ってはいなかった。午後の進軍は暑さとの戦いになりそうだった。これだけの重装備ならなおさらだ。
「早期撤退は敗北してこそするものでしょう」と、王子は言った。遠くの牧草地で、支配者ヴェルシデュ・シャイエが、村の食料や酒、それに女を用立ててくれた執事に謝金を渡しているのが見えた。軍隊とはじつに金がかかるものだ。
「しかしながら、王子……」と、ベサル卿は不安げに訊いた。「このまま東進なさるおつもりですか? それではコロチナ湖の湖畔にたどりつくだけでしょう。南東から海峡へ向かわれたほうがよいのでは」「あなたは村の商人が約束の報酬をもらったかどうかを案じていればいい」と、王子は笑みを浮かべて言った。「軍隊の行き先は私が考えましょう」
2920年 真央の月16日
コロチナ湖 (モロウウィンド)
ヴィヴェックは広大な青い湖面の向こうをながめた。みずからと軍の姿が青い水面に映りこんでいた。が、帝都軍の姿は映り込んではいなかった。森で待ち受ける災難を嫌って、とっくに海峡へ到着しているはずだった。羽のように薄っぺらなひょろ長い湖岸の木々が邪魔になって海峡の様子はほとんどうかがえなかったが、かさばる重装備に身を包んだ一団が誰の目にもとまらずに音もなく移動することなど不可能だった。
「もう一度地図を見せてくれ」ヴィヴェックは将軍を呼ばわった。「他の進路があるとは考えられないか?」
「北の沼地には哨兵を配備しております。浅はかにも、やつらが沼地に入ってもがいている可能性もないとは言えませんからな」と、将軍は言った。「少なくとも報告があるでしょう。が、湖を越えるとしたら海峡を抜けるより他はありません」
ヴィヴェックはまた湖面に映った影を見つめた。彼をからかうようにゆらゆらと揺れていた。それから、ヴィヴェックは地図に視線を戻した。
「スパイか……」ヴィヴェックはそう言うと、キャシールを呼びつけた。「敵軍は魔闘士の一団を引き連れていたと言ったが、どうして魔闘士だとわかったのだ?」
「灰色の法衣に謎めいた紋章を身につけておりましたから……」と、キャシールは述べた。「魔闘士だと直感しました。あれだけの大人数でしたし。軍が治癒師ばかりを同道させているとは思えませんので」
「浅はかなやつめ!」ヴィヴェックは怒鳴った。「やつらは変性の技巧を学んだ神秘士なのだぞ。水中呼吸の魔法を全軍にかけたにちがいない」
ヴィヴェックは手ごろな見通しのきく場所へ走って、北の方角を見渡した。水平線に浮かぶ小さな影でしかなかったが、対岸のアルド・マラクから襲撃の火の手があがっているのが見えた。ヴィヴェックは怒りの雄たけびをもらした。将軍はただちに、城砦を守るべく湖をまわり込むよう軍隊に指示を出しなおした。
「ドワイネンに帰れ」ヴィヴェックはキャシールに向かって言い放つと、戦いに加勢すべく出発した。「わが軍はもはやおまえの力を必要としていない」
モロウウィンド軍がアルド・マラクに迫ったときにはもう手遅れだった。街は帝都軍の手に落ちていた。
2920年 真央の月19日
シロディール領帝都
支配者ヴェルシデュ・シャイエが帝都に凱旋すると、熱烈な歓迎が待っていた。男も女も通りにずらりと並んで、アルド・マラク陥落の象徴である大君主を褒め称えた。王子が帰還していたらこれ以上の群集が出迎えたであろうことは、シャイエにもわかっていた。それでも、彼は大いに気を良くしていた。タムリエルの民がアカヴィル人の到着を歓迎するなど、それまでにないことだった。
皇帝レマン三世は心のこもった抱擁で彼を出迎えると、やおら王子から届いた手紙を突きつけてきた。
「どういうことかね」皇帝はようやく言った。喜んでいながらもとまどっていた。「湖にもぐったと?」
「アルド・マラクは、難攻不落の要塞です」大君主はそう言った。「それに加えて、われらの動きを警戒しているモロウウィンド軍が周囲を巡回しています。攻め落とすには不意を突いて、鎧の頑丈さにものを言わせて攻撃するしかありません。水中でも呼吸できる魔法をかけることで、われらはヴィヴェックに感づかれないうちに移動することができました。水中では鎧の重みもさほど気になりません。そして守備のもっとも手薄な砦の西側の水締めから攻め入ったのです」
「すばらしい!」皇帝は歓声をあげた。「驚くべき戦術家だな、ヴェルシデュ・シャイエよ! そなたの父親にもそれだけの才覚があったら、タムリエルはアカヴィルの領土になっていただろう!」
実のところ、その計画はジュイレック王子が考えたものだった。シャイエとしては、王子の功績を横取りする気はみじんもなかったが、大失敗に終わった260年前の祖先の侵略のことに皇帝が触れたとき、決心したのだった。シャイエは控えめな笑みを浮かべて、おもうぞんぶん賞賛を味わった。
2920年 真央の月21日
アルド・マラク (モロウウィンド)
サヴィリエン・チョラックは腹ばいになって壁まで進み、モロウウィンド軍が沼地と砦に挟まれた森の中へ撤退していくのを銃眼からじっと見つめた。絶好の攻撃の機会のように思われた。敵軍もろとも森を焼き払ってしまえばいい。ヴィヴェックさえ捕らえてしまえば、敵軍はアルド・イウバルもおとなしく明け渡すかもしれない。ショラックはその案を王子に持ちかけてみた。
「ひとつ忘れているようだけど」ジュイレック王子は一笑にふした。「休戦交渉中は敵の兵士や指揮官に手を出さないと約束しているんだ。アカヴィルでの戦いに誇りは不要なのかい?」
「お言葉ながら、私はタムリエルで生まれ育ち、祖国を訪れたことはございません」蛇男は答えた。「が、それでも、あなたの流儀はどうも解せない。五ヶ月前に帝都の闘技場で戦ったときも、あなたは金銭を求めようとせず、私は一銭も払わなかった」
「あれは遊びだから」王子はそう言うと、執事にうなずいてみせ、ダンマーの戦士長を迎え入れた。
ジュイレックがヴィヴェックに会うのは初めてだった。この男が神の化身であるという話は聞いていたが、目の前に現れたのはひとりの男だった。屈強で端正な顔した男で、知性にあふれる顔をしていたものの、やはりただの男だった。王子はほっとした。ただの男となら話せる。神であるなら話はべつだが。
「はじめまして、わが称えるべき好敵手」と、ヴィヴェックは言った。「お互いに手詰まりのようだな」
「そうともかぎりません」王子は言った。「あなたはモロウウィンドを明け渡したくはないし、私としてもそれをとがめることはできません。が、外敵の侵略から帝都を守るため、モロウウィンドの沿岸地域はどうしても押さえておきたい。それと、この場所のような、戦略の要地である国境の砦もほしい。アルド・ウンベイル、テル・アルーン、アルド・ランバシ、テル・モスリブラもすべて」
「して、見返りは?」と、ヴィヴェックは訊いた。
「見返りだと?」サヴィリエン・チョラックは笑い飛ばした。「いいか、勝者はわれらだ。おまえじゃない」
「見返りとして」ジュイレック王子は慎重になって言った。「帝都はモロウウィンドを襲わないと約束しましょう。もちろん、そちらから攻めてきた場合は別として。侵略者があれば、帝都海軍が助けに駆けつけましょう。それから、領土も分け与えましょう。ブラック・マーシュから好きな土地を選んでください。帝都にとって無用な土地であればですが」
「悪くない条件ですが」間をおいて、ヴィヴェックは言った。「即答はできかねますな。シロディールが奪ったぶんだけ補償してくれるなど、これまでになかったことですから。数日の猶予をいただけますか?」
「では、一週間後に会いましょう」王子はそう言って微笑んだ。「それまでにそちらが攻撃をしかけてくることがなければ、秩序は保たれるでしょう」
ヴィヴェックは王子の私室をあとにした。アルマレクシアの読みの正しさを感じながら。戦争は終結した。ジュイレック王子は立派な皇帝になるだろう。
時は南中の月へと続く。
2920 南中の月(7巻)
第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 南中の月4日
帝都 (シロディール)
皇帝レマン三世と支配者ヴェルシデュ・シャイエは、2人並んで宮殿の庭園をぶらついていた。彫像や噴水で飾られた、北の方の庭園が皇帝の今の気分に合っていた。何より夏の暑さを避けるのに好都合であった。よく手入れされた、青灰色と緑色に染まった花壇が、歩いて行く彼らの周りに階段状に広がっていた。
「ヴィヴェックは王子の和平の申し出を受け入れたようだな」と皇帝は言った。「息子は2週間もすれば帰ってくるそうだ」
「素晴らしい知らせですね」ヴェルシデュ・シャイエは注意深く答えた。「ダンマーが約束を守ってくれればいいのですが。ブラックゲート要塞の件もありますし、それに関しては、私達も強く出るべきでしょう。しかし、王子は妥当な方法を採られたと思います。決して、平和のためだけに帝都を陥れるようなことはなさらないでしょう」
「このところ私が考えていることは、なぜリッジャが私を裏切ったかということだ」と言って皇帝は立ち止まると、奴隷女王アレッシアの像を崇め、言葉を続けた。「一つだけ考えられる理由は、彼女が王子の方になびいていたのかもしれない、ということだ。確かに私の権力や人柄には惚れ込んでいたのだろうが、しかし王子は若い、そして美しい。それに、ゆくゆくは皇位を継ぐことになる。もし私を暗殺してしまえば、彼女は若さと権力の両方をそなえた皇帝を手に入れられるのだから」
「王子が? 彼がこの謀略に関係していると?」ヴェルシデュ・シャイエは尋ねた。皇帝の被害妄想の矛先はどこに向かうのか予想できなかった。
「いや、もちろん本気でそうだとは思っていない」と皇帝は笑って言った。「王子は私のことをとても愛してくれている」
「コルダのことはご存知ですか? リッジャ様の妹で、ヒゲースにあるモルワ修道院の生徒なのですが」とシャイエは聞いた。
「モルワ? そこは何の神だったかな?」と皇帝が聞いた。
「官能と豊穣を司る、ヨクーダの女神ですよ」とヴェルシデュ・シャイエは答えた。「もっとも、ディベラほどの好色でありませんが。つまり、上品な官能なんです」
「私は官能的な女性にはうんざりだ。リッジャ女帝は欲望が過ぎる。強すぎる愛への切望は、強い権力への切望に通じているものだ」と皇帝は肩をすくめた。「しかし、ある程度の健康的な欲求を持った司祭見習いなら、理想的というもの。ところで、ブラックゲート要塞の件についてはどう思う?」
2920年 南中の月6日
サーゾ要塞 (シロディール)
皇帝がリッジャに話しかけたとき、彼女は冷たい石床にじっと目を落としていた。これほどまでに青白くやつれた姿を、彼は見たことがなかった。少なくとも、自由の身になって故郷に戻れることを彼女は喜んでいるのかも知れない。何故なら、彼女が帰る頃には、ハンマーフェルでは「商人の祝典」が開かれているからだ。だが、彼の見たところ、彼女は何の反応も示さなかった。このサーゾ要塞での1ヶ月半が、彼女の心をすっかり壊してしまったのだ。
「私はこう考えている」ととうとう皇帝は切り出した。「お前の妹のコルダを、しばらく宮殿に置こうと思う。きっと、ヒゲースの修道院よりは気に入ってくれると思うんだが。そう思わないかい?」
彼女は反応した。キッと彼の方を見据えると、獣のような怒気を投げつけたのだ。そして、長年の監禁で伸び放題になっていた爪を、彼の顔面、目に向かって振り下ろした。彼が痛みに声をあげると、衛兵がすぐに駆けつけ、彼女を剣の峰でもって気絶するまで激しく殴った。
すぐに治癒師が呼ばれたが、皇帝レマン三世は右眼を失った。
2920年 南中の月23日
バルモラ (モロウウィンド)
水から出ると、ヴィヴェックは肌に照りつける太陽の熱を感じた。そして、召使いからタオルを受け取った。ソーサ・シルがこの古い友人の様子をバルコニーから見ていた。
「傷跡がまた増えたようだね」とその妖術師は言った。
「アズラの話では、しばらくはこれ以上増えることはないはずだがね」とヴィヴェックは笑った。「いつこっちへ?」
「1時間くらい前だ」とソーサ・シルは言って、階段を降り、彼のそばに近寄った。「戦争は終わりに近付いているようだな。しかも、私の手を借りず、君の手によって」
「まあ、いくら終わらないとはいえ、80年は長すぎる」ヴィヴェックはそう返すと、ソーサ・シルと抱き合った。「こちらも譲歩したし、あちらも譲歩した。今の皇帝が死ねば、私達は黄金期に入るだろうね。ジュイレック王子は、年の割に聡明な青年だ。ところで、アルマレクシアはどこだ?」
「モーンホールドへ公爵を呼びに行っている。明日の昼には、2人ともここへ到着するだろう」
彼らは、ふと邸宅の角の方を見やった。2人に向かって、馬に乗った女が近付いて来ていた。長い道のりを走破して来たのは明白である。書斎に招じ入れられると、息を切らして話始めた。
「裏切られた」と女があえぐように言った。「ブラックゲートが帝都軍によって奪取されたわ」
2920年 南中の月24日
バルモラ (モロウウィンド)
ソーサ・シルがアルテウム島に行った後で、モロウウィンドの法廷のメンバー3人が1同に会するのは、実に17年振りであった。しかし、このような形での再会は、3人の誰も願ってはいなかった。
「我々の情報によれば、王子の指揮する帝都軍が南方のシロディールへと立ち去るのと入れ代わりに、別の帝都軍が北方から迫って来たようだ」と、石のように固まった表情の仲間に向かって、ヴィヴェックが言った。「もちろん、王子がこの攻撃を知らなかったという可能性もある」
「だが、その逆も考えられる」とソーサ・シルが答えた。「王子が気を引いている間に、皇帝がブラックゲートを討つ。いずれにせよ、これは講和協定の破棄と見るべきだな」
「モーンホールド公爵はどこに?」とヴィヴェックが尋ねた。「彼の意見も聞きたい」
「テル・アルーンの夜母と会っているところよ」とアルマレクシアが静かに答えた。「あなたと話すまで待つよう言ったんだけど、でも、『この問題については、もう待てない』と」
「モラグ・トングを巻き込むつもりなのか? 国の問題だぞ?」と言ってヴェヴェックは首を振ると、ソーサ・シルに言った。「全力を尽くして欲しい。暗殺は事態を逆戻りさせるだけだ。この問題には、外交もしくは戦闘しかない」
2920年 南中の月25日
テル・アルーン (モロウウィンド)
大広間の夜母とソーサ・シルを、月の光だけが照らしている。彼女はこの上なく美しいドレスの上に簡素な絹の黒ローブを羽織って、長椅子にもたれかかっていた。夜母は赤マントの衛兵達を退室させると、彼にワインを勧めた。
「ちょうど公爵と入れ違いね」と彼女は囁いた。「彼、悲しんでいたわ。でも、私達がしっかり解決してみせます」
「公爵は、皇帝を殺すモラグ・トングの暗殺者を雇ったんだろう?」とソーサ・シルが尋ねた。
「はっきり言うわね。いいわ、そういう人、好きよ。時は金なりね。もちろん、私と公爵との話をあなたに教える訳にはいかないけど」と彼女はにっこり笑った。「商売上の守秘義務だから」
「もしも、皇帝の暗殺を止めさせるのに、同じだけの金を出すとしたらどうする?」
「私達モラグ・トングは、メファーラの栄光と利益のために動いているの」と夜母は言ってグラスを傾けた。「これは単なる殺しじゃない。そんなのは冒涜に過ぎない。三日以内に公爵から金が入れば、仕事にとりかかって、終わらせる。でもその逆の仕事をするなんてあり得ないこと。確かに、私達は利益を求めて動くけれど、単なる需要と供給に屈するわけにはいかないのよ、ソーサ・シル」
2920年 南中の月27日
内海 (モロウウィンド)
ここ2日間ずっと内海を眺めていたソーサ・シルは、ついに目当ての船がやってくるのを見つけた。モーン・ホールドの旗を掲げた重装船である。妖術師ソーサ・シルは先手を取って、船が港へ着くのを妨害した。炎の帯が彼の体から噴き出し、声が変わり、炎はデイドラの形に変化した。
「その船を捨て去れ!」と彼は大声で唸った。「さもなくば、船もろとも沈めてやろう!」
実際に放った火の球は一つだけだったが、彼の思惑通り、乗組員達は暖かい海へと飛び込んで行った。全員が飛び込んだのを見計らって、彼は強烈なエネルギーを破壊的な波動に込めた。その波動は、空気と海水を震わせながら、公爵の船をことごとく粉砕し、船はモラグ・トングの報酬になるはずだった公爵の金と共に、内海の深くへと沈んでいった。
「夜母よ」と、沿岸警備員に救助が必要な船乗りがいることを知らせるために岸に向かって泳いでいる間、ソーサ・シルは考えていた。「需要と供給には誰もが従わねばならないのだ」
時は、収穫の月へと続く。
2920 収穫の月(8巻)
第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 収穫の月1日
モーンホールド (モロウウィンド)
彼らは黄昏時に公爵の中庭に集まり、温かい焚き火とビターグリーンの葉の香りを楽しんだ。小さな燃えかすが空へ舞い上がってはすぐに消えた。
「私は軽率だった」公爵は、冷静な口調でそう認めた。「そして、ロルカーンは彼らに味方し、全てが彼らの思うままになった。私がモラグ団に支払った報酬が内海に沈んだ今、皇帝の暗殺は失敗だ。君はデイドラの王子たちと協定を結んだのではなかったのか」
「船乗りたちがデイドラと言っていたものが、本当にデイドラかどうか」と、ソーサ・シルが答えた。「船を壊したのは、狂暴な魔闘士や稲妻の類かもしれません」
「皇太子と皇帝は、我々との休戦協定に基づいてアルド・ランバシを占領するため、かの地へ向かっている。自分らの利権については交渉してくるくせに、我々には交渉の余地を与えないとは、シロディールの連中らしいよな」ヴィヴェックは地図を取り出した。「アルド・ランバシの北西の、このファーヴィンシルという村で彼らを待つんだ」
「でも、そこで彼らを待って、話し合いをするのですか?」アルマレクシアがたずねた。「それとも戦うのですか?」
誰もそれには答えなかった。
2920年 収穫の月15日
ファーヴィンシル (モロウウィンド)
夏の終わりのスコールが小さな村を襲っていた。空は暗く、時折稲妻が曲芸のように雲から雲へと渡った。通りはかかとほどの深さのある川のようになり、皇太子はそう遠く離れた場所にいない指揮官たちと話すのに大声で叫ばなければならなかった。
「あそこに宿屋がある! あそこで嵐が過ぎるのを待ってからアルド・ランバシへ進むぞ!」
宿屋の中は暖かく、外の雨とは無縁のようで、にぎわっていた。バーの女たちがせわしなく、グリーフやワインを奥の部屋へ運んでいた。どうやら重要な人物が来ているようだった。タムリエル皇帝の後継者などよりもずっと重要な人物が。ジュレックは面白がって彼女らの様子を見ていたが、そのとき、彼女らの一人が「ヴィヴェック」という名前を口にした。
「ヴィヴェック閣下……」と、ジュレックは奥の部屋に駆け込んで言った。「信じていただきたい。ブラックゲートへの攻撃は、私のあずかり知らないところで行なわれたのです。もちろん、直ちに賠償をさせていただきたいと思います」彼は一瞬沈黙し、部屋の中に見慣れない人物がたくさんいるのに気付いた。「失礼しました、私はジュイレック・シロディールです」
「アルマレクシアです」皇太子が今までに見た中で一番美しい女性が名乗った。「こちらへお入りになりませんか?」
「ソーサ・シルです」白いマントをつけた厳格な面持ちのダークエルフが皇太子と握手し、椅子を勧めた。
「インドリル・ブリンディジ・ドローム、モーンホールド大公です」と、皇太子が席に着くと、隣に座っていた大柄な男が言った。
「先月に起こったことからもわかるとおり、帝都軍は私の指揮下にはないのです」皇太子はワインを注文し、話しはじめた。「帝都軍は父のものですから、まあ当然なのですが」
「皇帝陛下もアルド・ランバシへいらっしゃるのでしょう」と、アルマレクシアが言った。
「表向きはそういうことになっていますが……」と、皇太子は慎重に言葉を選びながら言った。「実際は、まだ帝都に残っているのです。不運な事故がありまして」
ヴィヴェックは公爵を見てから、皇太子のほうを向いた。「事故?」
「皇帝は無事なのです」と、皇太子は慌てて言った。「命に別状はないものの、片目を失明しそうなのです。この戦争とはまったく無関係の諍いの結果です。不幸中の幸いは、皇帝が回復するまで私が皇帝の代理になるということです。今、この場で結んだ条約は全て帝都に持ち帰られ、皇帝の代はもちろん、私が正式に皇帝になってからも効力を失うことはありません」
「それなら、さっそく始めましょう」アルマレクシアがほほえんだ。
2920年 収穫の月16日
ロス・ナーガ (シロディール)
ロス・ナーガの小村の眺めは、キャシールの目を楽しませた。色とりどりの家がロスガリアン山脈の大地を見下ろす断崖に立ち並び、遠くハイ・ロックまでを見渡すことができた。息をのむような素晴らしい眺めに、彼は最高の気分だった。しかし同時に、このような小さな村では、彼と彼の馬が満足な食事をとることはできなさそうだとも思っていた。
彼が馬で村の中心の広場まで来ると、そこに「イーグルズ・クライ」という宿屋があった。厩番の少年に馬をあずけ、餌をやるように言いつけてから、キャシールは宿屋に入った。宿屋の中の雰囲気は、キャシールを圧倒するようなものだった。ジルダーデールで見たことのある吟遊詩人が、地元の山男たちに陽気な音楽を奏でていた。そういった陽気さは、今の彼にはうっとうしかった。音楽と喧騒から離れた場所にテーブルが一つあり、陰気なダークエルフの女性が座っていた。キャシールは自分の飲み物を持ってそちらへ行き、同じテーブルについた。その時初めて、彼はその女性が生まれたばかりの赤ん坊を抱いていることに気付いた。
「モロウウィンドから着いたばかりなんです」彼はどぎまぎして、声を落としながら話しかけた。「ヴィヴェックとモーンホールド公爵の側で、帝都軍と戦っていたんですよ。自分と同じ人種を裏切ってきたわけです」
「私も、同じ人種の人たちを裏切ってます」と、女性は言い、手に刻まれた印を見せた。「もう、故郷には帰れません」
「まさか、ここに滞在するつもりじゃないでしょうね?」キャシールは笑った。「ここは確かにいいところですが、冬までいてごらんなさい、目の高さまで雪が積もるんですよ。赤ん坊がいられるところじゃありません。その子、名前は何ていうんです?」
「ボズリエルです。『美しい森』という意味です。これからどちらへ行かれるのですか?」
「ハイ・ロックの海沿いにある、ドワイネンというところです。よかったら一緒に行きませんか。連れがいたほうがいいんです」キャシールは手を差し出した。「キャシール・オイットリーです」
「トゥララです」と、一瞬考えてから、彼女は答えた。風習に従って苗字を先に言おうとしたのだが、その名がもはや彼女の名前ではないことに気付いたのだった。「ありがとう、ぜひ、ご一緒させてください」
2920年 収穫の月19日
アルド・ランバシ (モロウウィンド)
城の大広間に、5人の男と、2人の女が黙って立っていた。聞こえてくる音といえば、羽ペンが羊皮紙の上を滑る音と大きな窓を叩く雨の音だけだった。皇太子が文書にシロディールの印を押し、公式に戦争が終わりを告げた。モーンホールド公爵は喜びの声をあげ、80年間続いた戦争の終結を祝うため、ワインを持ってくるように言いつけた。
ソーサ・シルだけが、喜ぶ人々の輪から離れて立っていた。彼の顔からは、どんな種類の感情も読み取れなかった。彼は物事の終わりや始まりといったものを信じておらず、ただいつまでも続く繰り返しの一部分としか思っていなかったのだ。
「皇太子殿下」城の執事が、祝いの最中に申し訳なさそうに入ってきた。「お母様の皇后陛下からの使者が到着し、皇帝陛下に謁見したいとのことだったのですが、間に合わなかったために──」
ジュレックは周囲に断り、使者と話すためにその場を離れた。
「女帝は帝都に住んでいないのか?」とヴィヴェックがたずねた。
「ええ」アルマレクシアは、悲しい顔で首を横に振った。「皇帝が、女帝が反逆を企てていると疑って、彼女をブラック・マーシュに幽閉したのです。女帝は莫大な資金を持ち、西コロヴィア地方の多くの領主と同盟関係にあったため、皇帝は彼女を処刑することも離婚することもできませんでした。皇帝と女帝は、ジュイレック王子がまだ子供のころから17年間、離れて暮らしています」
数分後、皇太子が戻ってきた。平静を装おうとしていたが、彼の顔からは不安の色がにじみ出ていた。
「母が私を呼んでいる」と、彼は簡潔に言った。「申し訳ないが、行かなくてはなりません。もしよければ、この条約文書を持っていって女帝に見せ、喜ばしい平和条約が結ばれたことを報告したいと思います。その後、文書は帝都に持ち帰り、公式に発効させます」
ジュイレック王子はモロウウィンドの3要人に丁寧な別れの挨拶を延べ、広間を出た。馬に乗った皇太子が夜の雨の中を南のブラック・マーシュへ向けて走ってゆくのを窓から見ながら、ヴィヴェックは言った。「彼が皇帝になれば、タムリエルはずっと良い国になるだろうな」
2920年 収穫の月31日
ドルザ・パス (ブラック・マーシュ)
荒涼とした石切り場の上に月がのぼり、熱い夏の間に溜まった沼気が立ち上っていた。皇太子と二人の護衛は馬で森を抜けたところだった。太古の昔、この地に住んでいた人々は北からの侵入者を防ぐために泥と肥やしを高く積み上げて土塁をつくり、それは彼らが滅び去った今も残っていた。しかし、侵入者たちはこの土塁を破っていたようだ。ドルザ・パスと呼ばれる道が、この何マイルも続く土塁を貫いていた。
土塁の上にはねじ曲がった黒い木々が生え、絡み合った網のような奇妙な影を落としていた。皇太子は、母の手紙のことを考えていた。その謎めいた手紙には、侵略の脅威がほのめかされていた。もちろん、そのことをあのダークエルフたちに伝えることはできなかった。少なくとも、もっと詳しいことを知り、皇帝に報告した後でなければ。何よりも、手紙は彼だけに宛てて書かれていたのだ。急を要しそうなその文面に、彼は直接ギデオンへ出向くことを決めたのだった。
女帝からの手紙には、最近、解放された奴隷たちがドルザ・パスで行商人を襲うことが多いので気をつけるようにとも書かれていた。そして、奴隷を使っていたダークエルフではないことを示すため、皇帝家の紋章が入った盾を目立つように掲げるようにとの助言が付け加えられていた。背の高い草が不愉快な川のように道を横切って生い茂っている場所があり、そこを通るときに、皇太子は盾を掲げるように命じた。
「奴隷たちが通行人を襲うならこのあたりでしょうな」と、護衛隊長が言った。「ここは待ち伏せにぴったりです」
ジュレックはうなずいたが、心では別のことを考えていた。女帝のいう侵略の脅威とは何だろうか? アカヴィリがまた海から攻めてきたのか? もしそうだとしても、ジオヴェーゼ城に幽閉されている母がなぜそれを知り得たのか? そのとき後方の草の中で何かが動く音と、短い叫びが聞こえたので、彼の考えは中断された。
振り向くと、皇太子は一人になっていた。護衛が消えていたのだ。
皇太子は、月明かりに照らされた草原を見渡してみた。道を吹き抜ける風に草原はまるで大海原で潮が満ち引きするように揺れ、その様子は幻惑的ですらあった。この揺れ動く草の下で、兵士が格闘していても馬が死にかけてもがいていても、わかりそうになかった。ひゅうひゅうと吹く風がまわりの音を消し、伏兵にやられた兵士が声をあげても彼の耳には届かないだろう。
ジュレックは剣を抜き、どうすべきか考えた。理性が、混乱する心に落ち着くよう告げていた。彼は、道の入り口よりも出口に近い地点にいた。護衛を殺した者は、おそらく後ろにいるはずだった。馬をとばせば、逃げ切れるかもしれない。彼は馬に拍車をかけ、前方に見える黒い泥の丘へ向けて駆け出した。
彼の体が宙を舞ったとき、あまりにも突然すぎて、彼にはいったい何が起こったのかわからなかった。少し離れた先の地面に投げ出され、衝撃で肩と背中の骨が折れたようだ。全身がしびれ、馬のほうを見ると、かわいそうに腹に大きな傷を負って死にかけていた。草の高さのあたりから突き出ている数本の槍でやられたのだろう。
ジュイレック王子は、草むらから出て来た者の顔を見ることも、動いて身を守ることもできなかった。皇帝家の人間にふさわしい死の儀式もないまま、彼は喉を切り裂かれた。
ミラモールは、月明かりに照らされた死体の顔を見て悪態をついた。彼は以前、ボドラムの戦いで皇帝の指揮下で戦い、その際に皇帝の顔も見ていたので、この人物が皇帝でないことはすぐにわかった。死体の服を探り、彼は手紙と条約文書を見つけ出した。モロウウィンドを代表するヴィヴェック、アルマレクシア、ソーサ・シル、そしてモーンホールド公爵と、シロディール帝都を代表するジュイレック・シロディールの署名のある平和条約だった。
「ついてない」と、草のざわめく音の中、ミラモールはぶつぶつと独り言を言った。「皇太子しか殺せなかった。何の得にもならない」
ミラモールはズークに言われたとおり、手紙を始末し、条約文書はポケットにしまった。大抵、こうした珍しいものには金を出そうという者がいるのだ。彼は用のすんだ罠を取り外し、次はどこへ行こうかと考えた。ギデオンに戻り、依頼主に皇帝ではなくその後継者を暗殺したと報告し、いくらかでも報酬をもらえないかたずねてみようか? それとも他の土地へ行こうか? 少なくとも、彼はボドラムの戦いで2つの有用な能力を身に付けていた。ダークエルフからは、槍を使った強力な罠の作り方を学んだ。そして、帝都軍を去ることで、草むらに忍んで動き回る能力を身に付けたのだった。
時は薪木の月へと続く。
2920 薪木の月(9巻)
第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 薪木の月2日
ギデオン (ブラック・マーシュ)
女帝タヴィアは彼女のベッドに横たわり、独房のなかを行ったり来たりする晩夏の熱風を感じられずにいた。喉は燃えるようにひりついていたが、それでも彼女は抑えきれずにすすり泣き、最後のつづれ織りを手で握りつぶした。彼女の嘆きの声はギオヴェッセ城の誰もいない廊下中をこだまし、洗い物をしていた召使いの手や衛兵の会話を止めた。彼女の召使いの1人が細い階段を登ってきたが、彼女の衛兵長ズークが入り口に立ち、首を振った。
「彼女はたった今、息子の死を知った」と、彼は静かに言った。
2920年 薪木の月5日
帝都 (シロディール)
「陛下――」ポテンテイト・ヴェルシデュ・シャイエは扉を挟んで言った。「扉を開けても大丈夫です。お約束します、完全に安全です。誰も陛下を殺そうとはしていません」
「ああ、マーラよ!」押さえ込むような乱心の混じった皇帝レマン三世の声がした。「誰かが王子を暗殺したのだ。そして彼は私の盾を持っていた。私であると思いこんだのかもしれないではないか!」
「確かにその通りです、陛下」ポテンテイトは軽蔑しながらも声から一切のあざけるような口調を消し去り言った。「そして、我々は陛下の息子の死に対して責任を負うべき悪人を探し、処罰しなければなりません。しかし、陛下なくしてそれはできません。帝都のために勇敢でおありください」
返答はなかった。
「最低でも出てきてリッジャ貴婦人の処刑指令書に署名願います」ポテンテイトは呼びかけた。「我々の知る、裏切り者であり暗殺者である1人を処分しましょう」
しばらく沈黙が続き、そして家具が床の上を引きずられる音がした。レマンは扉をほんの少しだけ開いたが、怒り、恐れている顔と、以前は彼の右目があった場所にある、引き裂かれた皮膚の盛り上がりがポテンテイトには見えた。帝都の最高の治癒師の治療もむなしく、サーゾ要塞でのリッジャ貴婦人からの恐ろしい置き土産がそこにあった。
「指令書をよこせ」皇帝は怒鳴り声を出した。「喜んで署名してやる」
2920年 薪木の月6日
ギデオン (シロディール)
沼地の気体と霊的なエネルギーの組み合わせであると教えられたウィル・オ・ウィスプの奇妙な青い光は、窓の外を見るたびにタヴィアを怖がらせてきた。今は妙に慰めているように見えた。沼地の向こうにはギデオンの街がある。17年間も毎日見てきたのに、あの街の街路に1度も足を踏み入れたことがないことを可笑しく思った。
「何か私が忘れているものを思いつくか?」彼女は忠実なコスリンギー・ズークに振り返りながら聞いた。
「何をすればよいのか、明白に分かっております」と、彼は簡単に言った。彼が笑ったように見えたが、彼女の笑顔が彼の銀色に光る肌に反射されたのだと女帝は気付いた。彼女は自分が笑っていることに気が付いていなかった。
「尾行されていないことを確認するのだぞ」と、彼女が警告した。「この長きに渡り、どこに我がゴールドが隠されているのかを夫には知られたくない。あと、自分の分け前はしっかりと取るのだぞ。そなたは良き友であった」
女帝タヴィアは前へと踏み出し、霧の中へと視界から消え落ちた。ズークは塔の窓に鉄格子を戻し、ベッドの上の枕に毛布を被せた。運がよければ明日の朝まで芝生に横たわる彼女を発見しないであろう。そしてそのころには、彼はモロウウィンドの近くまで辿りつけていることを期待していた。
2920年 薪木の月9日
フィルギアス (ハイ・ロック)
周囲にある奇妙な木々が、赤や黄色やオレンジがほとばしる毛糸の束のように見え、それはまるで虫の巣に火をかけ、様々な彩りの生き物が一斉に出てきたようであった。ロウスガリアン山は霧のかかった午後にかすんでいった。トゥララは広い牧草地へと馬をゆっくりと進めながら、見慣れない、モロウウィンドとはまったく違った景色に驚いた。後ろでは、頭を縦に振りながら、キャシールがボズリエルを抱きかかえたまま眠った。一瞬、トゥララは野原をさえぎるペンキで塗られた低い柵を飛び越えようかと考えたが、それはやめておいた。キャシールに手綱を渡す前に、あと数時間寝かせてあげようと思った。
馬が野原に進み入ると、トゥララは森に半分隠れている小さな緑の家を隣の丘の上に見た。その姿は絵に描いたように美しく、彼女は半眠状態に引き込まれていくのを感じた。そのとき、ホーンの爆音が身震いとともに彼女を現実へと引き戻した。キャシールは目を開けた。
「今、どこ?」と、彼が息をもらすように言った。
「分からないわ」トゥララは目を見開き、どもった。「あの音はなに?」
「オーク」と、彼はささやいた。「狩り集団だ。やぶの中へ、急いで」
トゥララは馬を小走りで木が数本集まっているところへと走らせた。キャシールは子供を彼女に渡し、馬から降りた。彼は、荷物を引き降ろし始め、やぶの中にそれらを投げ入れた。そのとき、音が鳴りはじめた。遠い足音の轟音、徐々に大きくなり、近づいてくる。トゥララは慎重に馬から降り、キャシールが馬から荷を降ろすのを手伝った。その間、ボズリエルは目を見開いて見ていた。トゥララは時々、子供がまったく泣かないことを心配したが、今はそれに感謝している。すべての荷を降ろしたところで、キャシールは馬の尻を打った。そしてトゥララの手を取り、茂みのなかにしゃがみこんだ。
「運が良ければ――」彼はひそひそと言った。「彼らはあの馬のことを野生か農場の馬だと思ってくれて、乗り手を探しには行かないだろう」
彼がそう言ったとき、オークの大群がホーンを轟かせながら野原に殺到した。トゥララは以前オークを見たことがあったが、これほど多数でもなければ、これほど野蛮な自信に溢れてはいなかった。馬とその混乱ぶりに狂喜しながら、彼らはキャシール、トゥララ、ボズリエルが隠れている茂みを急ぎ通り越していった。彼らの暴走で野花が舞い上がり、空気中にそのタネを撒き散らした。トゥララはくしゃみを押さえ込もうとし、上手くいったと思った。しかし、オークのうちの1匹が何かを聞きつけ、調査のためにもう1匹連れてきた。
キャシールは静かに剣を抜き、自分の中の自信をできる限りかき集めた。彼の能力、あまり良いとは言えないそれは、間諜であり戦闘ではなかった。しかし、彼はトゥララと赤子をできるだけ長く保護すると誓っていた。彼は思った、もしかしたらこの2匹は殺せるかもしれないが、叫んで大群の残りを呼び寄せる前には無理である。
突然、見えない何かが風のように茂みの中を通りすぎていった。2匹のオークは後ろに飛ばされ、背を地につけて死んでいた。トゥララは後ろを振り向き、近くの茂みから真っ赤な髪を持つ、しわくちゃの老婆が出てくるのを見た。
「私のところに連れてくるつもりかと思ったぞ」彼女はささやいた、微笑んでいる。「一緒にきたほうがよい」
三人は丘の上の家に向かって生えている、茨の付いた茂みの裂け目をとおりながら老婆の後についていった。逆側に出ると、老婆はオークたちが馬の残骸をむさぼり食っているのを見に振り返った。それは複数のホーンの拍子に乗った、血まみれの祝宴であった。
「あの馬はあんたのかい?」と、老婆が聞いた。キャシールがうなずくと、彼女は声をあげて笑った。「あれはいい肉すぎじゃの。あのモンスターどもは、明日には腹痛をおこして、腹がふくれ上がっていることじゃろう。いい気味じゃ」
「歩き続けなくて平気なの?」老婆の大声に肝を抜かれて、トゥララは声を低くして言った。
「奴らはここへはこんよ」笑みを浮かべ、笑い返すボズリエルを見ながら老婆は言う。「奴らは我々を恐れておるのでな」
トゥララは首を振っているキャシールのほうを向いた。「魔女か。ここは古きバービンの農場、スケフィントン魔女集会と思って間違いではないかな?」
「おりこうさんじゃの」老婆は悪名高きことを嬉しく思い、若娘のようにクスクスと笑った。「私の名はミニスタ・スケフィントンじゃ」
「さっきの茂みの中で… あのオークたちには何をしたの?」と、トゥララが聞いた。
「霊魂の拳を頭の右側に放ったのじゃ」とミニスタは言い、坂を上り続けた。その先には農場が開け、井戸や鶏舎や池があり、様々な年齢の女性たちが家事を行い、はしゃぐ子供たちの笑い声がした。老婆は振り向き、トゥララが理解していないことに気が付いた。「あんたの故郷には魔女がおらんのかね?」
「知る限りでは、いないわ」と、彼女は言った。
「タムリエルには実に様々な魔法の使い手がおる」彼女は説明した。「シジックたちは、彼らのつらい義務であるかのように学ぶ。真逆の対象として、軍の魔闘士たちは呪文を矢の如く浴びせかける。我々魔女たちは、呼び出し、集い、祝うのじゃ。あのオークたちを倒すには、私が親密な関係を持つ風の精霊たち、アマロ、ピナ、タラサ、キナレスの指、そして世界の風にあの雑魚どもを殴り殺すようささやきかけただけじゃ。召喚とは、力や謎解きや古い巻物を苦しみながら読むことではないのじゃ。召喚とは良き関係を築くことである。仲良くすること、とも言えるの」
「特に、私たちと仲良くしてくれていることには感謝する」と、キャシールは言った。
「そうじゃが、さらに言うとな――」ミニスタは咳払いをした。「あんたらの種族が2千年前にオークの母国を破壊したのじゃ。それまでは、やつらがここまできて我々の邪魔をすることもなかったのじゃ。さて、旅のほこりを落として、食事にでもしようかの」
そう言うとミニスタは彼らを農家へと案内し、トゥララはスケフィントン魔女集会の一家と知り合いになった。
2920 薪木の月11日
帝都 (シロディール)
リッジャは前の晩、寝ようともしていなく、今彼女の処刑時に演奏されている悲しい音楽には催眠効果があると思った。それはまるで、斧が振り下ろされる前に、自発的に無意識になろうとしているようであった。彼女の目は覆われていたので、彼女の前に座り片目でにらんでいる元愛人、皇帝の姿は見えなかった。彼女は、金色の顔に勝利の表情を浮かべ、彼の下で尻尾がきれいに巻かれたポテンテイト・ヴェルシデュ・シャイエの姿を見えなかった。彼女を抑えようと触れた執行者の手の感触は、しびれながら感じられた。夢から覚めたものが起きようとするように跳ね上がった。
最初の一撃は頭の裏にあたり、彼女は悲鳴をあげた。次の斬撃は首を叩き切り、彼女は死んだ。
皇帝は疲れたような素振りでポテンテイトに向き、「これは終わったな。それで、彼女にはコルダという名のかわいい妹がハンマーフェルにいたと言ったな?」
2920年 薪木の月18日
ドワイネン (ハイ・ロック)
魔女たちが売ってくれた馬は、前の馬ほどよくはなかったとキャシールは思った。霊の崇拝や生けにえや姉妹関係は霊の召喚には便利で役立つのかもしれないが、荷役用の動物にはあまり効果がないらしい。それでも、彼には文句を言う理由がなかった。ダンマーの女とその子供が彼の手を離れ、彼は予定よりも早く到着できた。先には彼の母国を囲う壁が見えた。ほぼ同時に、彼の周りには旧友や家族の人々が群がった。
「戦争はどうだったの?」従兄弟が叫びながら道に出てきた。「ヴィヴェックは王子との和平に応じたのに、それを皇帝が拒否したって本当なの?」
「そうじゃないだろう、違うのか?」と、友達の1人が輪に入りながら言った。「ダンマーが王子を殺させて、その後、条約の話をでっち上げたけど証拠がないって俺は聞いたぜ」
「ここでは何も面白いことは起きていないのか?」キャシールは笑った。「本当に、これっぽっちも戦争やヴィヴェックについて語る気がしない」
「おまえはコルダ貴婦人の行列を見逃したぞ」と、友が言った。「大勢の取り巻きと一緒に湾を横切ってきて、帝都に向かって東に行ったんだ」
「でもそんなのは大したことないや。それで、ヴィヴェックって、どんななの?」従兄弟が熱心に聞いた。「彼は現人神のはずだよね?」
「もしシェオゴラスが退いて、他の乱心の神が必要になったなら、彼がうってつけだな」と、キャシールは偉そうに言った。
「それで、女は?」極稀な機会にしかダンマーの女性を見たことがない青年が聞いた。
キャシールはただ微笑んだ。トゥララ・スケフィントンが一瞬頭をよぎり、すぐに消えた。魔女集会と一緒にいれば彼女は幸せであろうし、子供の面倒もしっかりと見てくれるであろう。しかし彼女たちは、今では戦争や場所などの永遠に忘れたい過去の一部であった。彼は馬から降りて街に踏み入り、イリアック湾での毎日の小さな噂話に花を咲かせた。
2920 降霜の月(10巻)
第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 降霜の月10日
フィルギアス(ハイ・ロック)
彼女たちの前に立っている生き物はどんよりとした意識のないような目を瞬きさせ、口の働きを再確認するように開け閉めを繰り返していた。ひと筋のネバネバした唾の塊が牙の間からこぼれ落ち、垂れ下がっていた。トゥララは今までにこのような大きく、2本足で立つは虫類のようなものを見たことがなかった。ミニステラは夢中になって拍手をした。
「我が娘よ……」と、彼女は得意げに言った。「短期間でよくここまで成長したのう。このデイドロスを召喚したときに、何を考えておったのじゃ?」
トゥララは何かしらを考えていたか思い出すのに少々時間がかかった。彼女は単に、現実の壁を超えてオブリビオンの領域に手を伸ばし、精神の力だけでこの忌まわしい生き物をこの世に召喚できたことに驚いていた。
「赤色を考えていたわ」と、トゥララは集中しながら言った。「赤の簡素さとその透明度。そして―― 望み、呪文を詠唱したの。これが召喚されてきたものよ」
「望むということは、若い魔女にとっては強力な力じゃ」ミニステラが言った。「そして、この瞬間うまく調和しておる。霊の単純な力でなかったとしたら、このデイドロスはなんでもないからのう。簡単に望めた時と同じように、その望みを捨てられるか?」
トゥララは目を閉じ、退散の祈りを口にした。モンスターは混乱しているように瞬きをしながら、日にあせた絵画のように薄くなっていった。ミニステラは歓喜の笑いとともにダークエルフの愛弟子を抱きしめた。
「信じ難いが、魔女集会とともに暮らし始めて1ヶ月と1日、既にここで暮らす大多数の女性たちよりも遥かに進歩しておる。そなたの中には強力な血が流れておる、トゥララ、そなたは恋人に触れるように霊に触れられる。いつの日か、そなたはこの集会を導くであろう―― 私には見える!」
トゥララは微笑んだ。褒められるのは心地よかった。モルンホールドのデュークは彼女の可愛い顔を、そして、その名誉を汚す前の家族は彼女の礼儀作法を褒めてくれた。キャシールはただの旅仲間だったので、彼の賛辞は何の意味も持たなかった。しかし、ミニステラとともにいると、我が家にいるような気がした。
「まだまだ、この先何年間もあなたがこの魔女集会を導くわ、偉大な姉さん」と、トゥララは言った。
「もちろん、そのつもりじゃよ。だが、霊は素晴らしき友であり、真実の語り手ではあるが、『いつ、どのように』に関しては往々にして不明確じゃ。それに関して彼らを責めることはできんのう。『いつ、どのように』は、彼らにとってあまり意味のないことだからのう」ミニステラはデイドロスの苦い悪臭を消散させるために小屋の窓を開け、秋の風を吹き込ませた。「さて、これから使いでウェイレストへ行って欲しいのじゃ。ドリャサとセレフィナを持ち帰ってきて欲しい。自給自足を実践してはおるが、ここでは育たない薬草があって、莫大な量の貴重品をまったく時をかけずに使ってしまうようじゃ。街の人々がそなたをスケフィントン魔女集会の女性であると認識することも重要じゃ。悪名高きことの不便さよりも、利点のほうが遥かに多いことに気が付くであろう」
トゥララは指示されたとおりにした。彼女と他の姉妹が馬に乗る最中、ミニステラは彼女の子、生後5ヶ月のボズリエルを母親との別れの口づけをさせるために連れてきた。魔女たちは邪悪なデュークを父に持ち、帝都の森の奥深くでアイレイドのエルフたちによってこの世に引き出された、小さなダンマーの子をこよなく愛した。この子守役たちは、命をかけて彼女の子を守るであろうことをトゥララは知っていた。たくさんの口づけと別れの挨拶の後、3人の若い魔女たちは赤色や黄色やオレンジ色が覆う、輝く森の中へと去って行った。
2920年 降霜の月12日
ドワイネン(ハイ・ロック)
水曜日の夜にしては酒場、「愛されないヤマアラシ」はものすごく混んでいた。部屋の中央に掘ってある穴の中では、轟音をあげる炎が常連たちに邪悪そうな輝きを与え、それによって人々の集まりがアラクトゥリアの異教によって触発された懲罰のつづれ織りのような装いを見せていた。キャシールは従兄弟たちと一緒にいつもの席に着き、エールの大瓶を注文した。
「もう男爵には会いに行った?」パリスは聞いた。
「うん、ウルヴァイアスの王宮で仕事をさせて貰えるかもしれない」誇らしげにキャシールは言った。「でも、これ以上は言えない。国の秘密とかの関係でね、分かるよな。何で今夜はこんなに人が多いんだ?」
「船でたくさんのダークエルフたちが港に到着したらしい。戦地からきたみたいだ。戦争体験者として紹介するために君が来るのを待っていたのさ」
キャシールは赤面したが、落ち着きを取り戻し、聞いてみた。「彼らはここで何をしているんだ? また停戦協定でも成立したのか?」
「よくは分からないんだが――」パリスは言った。「でも、皇帝とヴィヴェックはまた交渉しているらしい。この人たちはここでの投資を確認したがっていて、湾の周りの状況も十分落ち着いていると判断したんだろう。でも、実際のところは彼らと話してみないと分からないな」
それを言ったパリスは従兄弟の腕をつかみ、突然彼をすごい勢いで部屋の反対側へと引っ張っていった。ダンマーの旅人たちは4つのテーブルを占領して、街の人々と談笑していた。彼らは主に身なりを整えた商人らしい、感じのよい若い男たちであった。彼らは酒のおかげで身振り手振りが必要以上に大げさになっていた。
「失礼します」と、パリスは会話に入り込みながら言った。「私の照れ屋の従兄弟、キャシールも現人神、ヴィヴェックのために戦争で戦ってきました」
「俺が聞いたことのある唯一のキャシールは――」彼の空いている手を握り、大きく気さくな笑顔を携えたダンマーの1人が酔った口調で言った。「それはヴィヴェックに歴史上最悪の密偵だと言われたキャシール・ホワイトリーだけだ。俺たちはヤツの下手な諜報のおかげでアルドマラクで負けたんだ。友よ、あんたのためにもあんたとヤツが間違われないことを祈るぜ」
キャシールは微笑んだままこの無骨者が彼の失敗談を面白おかしく話し、皆から大きな笑いを誘うのを聞いていた。何人かは彼のほうを見たが、地元の人間は皆、物語の愚かな主人公がここに立っていることを伝えなかった。一番突き刺さったのは、ドワイネンに英雄として戻ったと信じていた彼の従兄弟の視線であった。そのうち、男爵も当然この話を耳にするであろう。何度も語られるうちに、彼の愚かさが数倍にも増した形で。
魂の底から、キャシールは現人神ヴィヴェックを呪った。
2920年 降霜の月21日
帝都(シロディール)
ヒゲース・モルハー音楽学校の女祭司の制服である、目が眩むような白さのローブを身にまとったコルダは、今季初の冬の嵐が通り過ぎる中、帝都に到着した。雲間から日が差し、麗しい10代のレッドガードの女性が大きな街路に護衛とともに現れ、王宮へと馬を進めた。彼女の姉は背が高く、細身で骨張り、高飛車であったが、コルダは小さく、丸い顔と大きな茶色の目を持った少女であった。地元の人々はその2人を比較するのが素早かった。
「リッジャ貴婦人の処刑から1ヶ月も経ってないのにね」お手伝いの女性が窓から外をのぞきながら、ブツブツと近所の人に言った。
「それとさ、女子修道院から出て1ヶ月さえも経ってないのにね」破廉恥な事態に喜びをあらわにしながら女性はうなずいた。「この娘は前途多難な道を進むことになるねえ。彼女の姉は無垢じゃあなかったけど、最後にどうなったかは知ってのとおりだしねえ」
2920年 降霜の月24日
ドワイネン(ハイ・ロック)
キャシールは港に立ち、季節外れの凍雨が水面に落ちるのを見ていた。生まれつき船酔いする自分の性質を彼は残念がった。もうタムリエルの東も西も、彼が行ける場所はどこにもない。ヴィヴェックから生まれた、彼の密偵としての未熟さの物語は、酒場から酒場へと止めどなく広がっていた。ドワイネンの男爵も彼を仕事から放免した。ダガーフォールでも彼のことを笑っているに違いなく、ドーンスター、リルモス、リメン、グリーンハートも同じであろう。それに恐らくアカヴィルも、そしてついでに言えばヨクーダでも彼は笑いものであろう。もしかしたら、このまま水に飛び込んで沈んでしまったほうがいいのかもしれない。しかし、その考えは長くは残らなかった。彼の心を悩ませたのは、失望感ではなく怒りだったからである。それは、果たすことのできない無力な怒りであった。
「失礼します」彼の後ろから声がして、彼を跳びあがらせた。「お邪魔してもうしわけありません。一夜をすごせる、安い酒場を教えていただけないかと思いまして」
それは肩に袋をぶら下げた、若いノルドの男性であった。明らかにたった今どこかの船から降りてきたのであった。ここ何週間かぶりに誰かが彼を、有名なとてつもない間抜け以外の何かとして見ていた。気持ちは晴れなかったが、友好的にならざるを得なかった。
「たった今、スカイリムからきたのかい?」と、キャシールは聞いた。
「いいえ、そこへ行くのです」と、若者は言った。「働きながら家へと向かっているのです。ここの前はセンチネル、その前はストロスメカイ、その前はヴァレンウッドのウッドハース、そしてその前はサマーセットのアルテウム。名前はウェレグです」
キャシールは自己紹介をして、ウェレグと握手を交わした。「アルテウムからきたって言ったかい? シジックなのかい?」
「いいえ、もう違います」若者は肩をすくめた。「除名されました」
「デイドラの召喚に関して何か知っているかい? 現人神と呼ぶ人もいるような、とある強力な人に対して呪いをかけたいのだけれど、なかなか上手くいかなくてね。男爵は私と目も合わせてくれないが、男爵夫人は私に同情してくれて、彼らの召喚の間を使うことを許してくれた」キャシールは唾を吐いた。「すべての儀式を行い、生けにえも捧げたが、何も得られなかった」
「それは私の昔の師匠、ソーサ・シルによる影響ですね」苦々しそうにウェレグは言った。「デイドラの王子たちは、最低でも戦争が終わるまで素人には召喚されないと合意したのです。シジックと、一握りの魔女や、妖術師のみがデイドラと交信できます」
「魔女と言った?」
2920年 降霜の月29日
フィルギアス(ハイ・ロック)
トゥララ、ドリャサ、セレフィナが馬を進めていると、薄い日差しが森を洗う霧の向こうでキラキラと輝いている。地面は薄い霜の膜でぬれていて、荷で重くなっているため舗装されていない丘は滑りやすかった。トゥララは魔女集会へ戻れることに対する興奮を抑えようとしていた。ウェイレストは冒険であったし、街の人々が投じた恐怖と尊敬の眼差しは気に入っていた。しかし、ここ数日は姉妹たちと子供の元へ戻ること以外考えられなかった。
寒風が彼女の髪を前へとなびかせたので、正面の道しか見えなかった。騎手が彼女の真横に近寄ってくるのを、彼が手で触れるほど近寄るまで聞こえなかった。振り向いてキャシールを見たとき、旧友と会えたことに驚きと同等の喜びで叫んだ。彼の顔は青ざめやつれていたが、それは単に旅のせいだと思った。
「何の用事でフィルギアスへ戻ったの?」彼女は微笑んだ。「ドワイネンではあまり優遇されなかったの?」
「十分だったよ」と、キャシールは言った。「スケフィントン魔女集会にお願いがあってね」
「一緒にいきましょう」とトゥララは言った。「ミニステラのところへ案内するわ」
四人はそのまま乗り続け、魔女たちはキャシールをウェイレストの話で楽しませた。ドリャサやセレフィナにとっても、古きバービンの農場を離れるのはめったにない楽しみであったことは明白である。彼女たちはあそこで、スケフィントンの魔女たちの娘や孫娘として生まれたのである。平凡なハイ・ロックの都市生活は、彼女たちやトゥララにとっても魅惑的であった。キャシールはあまり話さなかったが、微笑みうなずいていたので、それだけでも十分な励ましになったはずである。幸いにも、彼女たちの話はどれも彼の愚かさにまつわる話ではなかった。少なくとも、彼には言わなかった。
見覚えのある丘を越えたとき、ドリャサは酒場で聞いた、質屋に一晩中閉じこめられた盗賊の話をしていた。突然彼女は話をやめた。納屋が見えるはずであるが、見えなかったのである。他の3人の視線も彼女の見つめる霧の先を追い、次の瞬間、全員出せる限りの速さでスケフィントン魔女集会があった場所へと急いだ。
炎はだいぶ前に燃え尽きていた。灰と骨と壊れた武器が残されているだけであった。キャシールは即座にオーク襲撃の形跡を見分けた。
魔女たちは馬から滑り落ち、亡骸へと走り、泣き叫んだ。セレフィナがミニステラのマントの切れ端と分かる、破れた血まみれの布を見つけた。彼女は灰で汚れた頬にその布を押し当て、すすり泣いた。トゥララはボズリエルの名を叫んだが、戻ってくる答えは灰の上を行く風の笛吹音だけであった。
「誰がこんなことを?」涙が頬を伝いながら、彼女は叫んだ。「オブリビオンの炎を呼び起こしてやる! 私の子に何をしたのよ?」
「誰の仕業かはわかってる」キャシールは馬から降り、彼女に向かって歩きながら静かに言った。「この武器は前に見たことがある。責任がある悪魔のようなやつらにドワイネンで会ったようだが、あなたを見つけるとは思っても見なかった。これは、モルンホールドのデュークによって雇われた暗殺者の仕業だ」
嘘は簡単に出てきた。臨機応変に。その上、彼女がそれを信じたことがすぐに分かった。デュークが見せた残酷さに対する彼女の憤りは、おさまってはいたが決して消えてはいなかった。彼女の燃え上がるような瞳を見た瞬間、それは彼女がデイドラを召喚し、彼と彼女の復しゅうをモロウウィンドに加えるであろうことを彼に告げていた。さらによいことに、デイドラたちは聞き入れると彼は確信していた。
そして、彼らは聞き入れた。望む力より強いのは怒りである。間違った方向に向けられた怒りであったとしても。
2920 黄昏の月(11巻)
第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 黄昏の月2日
テル・アルーン (モロウウィンド)
「男が一人謁見に来ております」と、衛兵が夜母に声をかけた。「帝都軍の要塞が置かれたギデオン地方ブラック・マーシュから来たコスリンギー族のズーク卿と申しております。信任状もあるそうです」
夜母は不快な表情を浮かべ、「私が会いたいと思える人物ですか?」
「帝都にいらした女帝の手紙を預かっているというのです」
「まったく忙しいというのに……」と、夜母は笑みをたたえながらも、すばやく手を打ち鳴らし、「お通しして」と告げた。
ズークは謁見室に通された。唯一露出している顔や手は、金属的に光る肌をのぞかせ、暖炉の炎や外の嵐の夜の稲妻を反射させた。夜母は、ズークの目に映っている自分の穏やかで美しい、恐怖をかきたてるような姿に気付いた。ズークは物言わず、ただ女帝から預かった手紙を手渡した。夜母はグラスにワインを注ぎ、手紙を読み始めた。
夜母は読み終えた手紙を折りたたみながらこう言った。「今年の頭に、モロウウィンドのデュークからも皇帝の暗殺計画を持ちかけられました。今となってはその報酬も海の底に沈んでしまいましたが。これ以上のやっかいごとは御免こうむりたいの。ただでさえ、宮廷に手下をまわすのが大変だったのですから。そもそもお金はちゃんとご用意できて? 死者からお金をせびるわけにもいかないですからね」
「用意できております」と、ズークは率直に答えた。「外に待たせてある馬車の中にあります」
「では、それをここへお持ちくだされば、すべてが丸く収まります」と、夜母は笑って答えた。「皇帝は今年の暮れには命を落とすことになるでしょう。お金はアパラディスに渡してから帰っておくれ。それとも、ご一緒にワインでもいかが?」
ズークは夜母の申し出を丁重に断り、謁見室をあとにした。部屋を出た際、ミラモールが闇色のタペストリーから音もなくすっと出てきた。夜母はミラモールにワインを勧め、彼はグラスを受け取った。
「あの男のことはよく知っております」と、ミラモールは慎重に答えた。「だが、亡き女帝に仕えていたとは知らなかった」
「よければあなたの考えを聞かせて頂戴」と、夜母は言った。ミラモールが断らないことを知っていたのである。
「私の優秀ぶりをお見せいたしましょう。皇帝が独りになれば間違いなく、息子と同様に世から消してみせましょう。私は身を隠すこともできます。先ほど、タペストリーの後ろから物音立てずに現れたことをご覧いただけましたかと思います」
夜母は微笑んだ。
「あたなたがダガーの一つでも使いこなせたら、ボドラムで殺してみせるでしょう」と、夜母はミラモールにこれからの暗殺の手順を説明したのであった。
2920年 黄昏の月3日
モーンホールド (モロウウィンド)
デュークは窓の外をじっと眺めていた。四日目の早朝。窓は赤い霧にすっぽり覆われて、稲妻の閃光が走っていた。通りには吹き荒れる風が巻きおこり、城の旗を強くなびかせ、家々の窓を固く閉じさせた。何か不吉な事が起こりそうな予感であった。彼自身、学識はそれほど高くはなかったが、彼の家臣も同様に、これから何か悪いことが起こりそうな気配を感じていた。
「伝令はいつ届くのだ?」と、デュークは城主に向かってうなるように言った。
「ヴィヴェック様は皇帝と協定交渉のため、遥か北の方へいらっしゃるのです」と、城主は恐怖におびえながら言った。「アルマレクシア様とソーサ・シル様はネクロムにいらっしゃいます。数日内には連絡をつけられると思われます。」
デュークは頷いた。確かに伝令が到着するのも速いだろうが、それよりもオブリビオンの手の方が速いことを知っていたのだった。
2920年 黄昏の月6日
ボドラム (モロウウィンド)
松明の火の光が霧のような雪に反射し、まるでそこは別世界のようであった。双方のテントから出てきた兵士たちが、大きなかがり火のまわりに集まった。冬の寒さは、敵対する者たちでさえも固く寄り添わさせるが、一方で帝都の言葉を話せる少数のダンマーとの暖を奪い合う戦いの場となることもあった。そんなかがり火へ、美しいレッドガードの娘が同じく暖を取ろうと雪の中を歩いてくるも、すぐさま協定交渉が行なわれているテントに引っ込んでいった。そして、双方の兵士たちの目線は、娘の入っていったテントに釘付けとなった。
皇帝レマン三世はこの交渉をすぐさま切り上げたかった。ひと月前の彼であったならば、ヴィヴェック率いる軍隊には負けたものの、うまくおさまったとして喜んでいたかもしれないが、思いのほかこの場所で起こった悪夢がまざまざと蘇ってきたのであった。ヴェルシデュ・シャイエの主張によると、川はその石によって元から赤いと言われているが、戦死した兵士の血によって赤く染まっているようにも見えるのであった。
「これで協定を結ぶ準備が整った」と、皇帝はコルダから熱いユエルの入ったグラスを受け取りながら言った。「しかし、ここは調印にはふさわしくない場所だ。この歴史に残る儀式は帝都の厳かな王宮で行なうべきだ。アルマレクシア、そしてウィザードも連れてくるがよい」
「ソーサ・シルです」と、ヴェルシデュ・シャイエは耳打ちした。
「時はいつ?」と、ヴィヴェックは辛抱強く問いただした。
「ちょうど本日より8ヶ月後に……」皇帝は笑顔をふりまきながら、ぎこちなく立ち上がった。「華やかな舞踏会を準備して祝おう。では、散歩に出掛けてくる。コルダ、この寒さで脚がひきつってしまったようだ。一緒に歩いてくれないか?」
「もちろん御供いたします、陛下」と、コルダは返答し、皇帝を支えながらテントの出口へと連れて行った。
「私も御供しましょうか、陛下?」と、ヴェルシデュ・シャイエは訪ねた。
「私もよろしいでしょうか?」と、最近新たに相談役として宮廷に招かれたセンチャルのドローゼル王も尋ねてきた。
「必要ない。すぐに戻る」と、皇帝はそう言って断った。
ミラモールは8ヶ月前と同じように林の中に身を潜めていた。前と違うのは地面が雪で覆われ、木々が氷と化しているところだ。ちょっと動くだけでも音がするのであった。ちょうどその時、かがり火を囲んだ2つの軍隊、モロウウィンド軍と帝都軍が歌う大音響の二部合唱が聞こえてこなければ、ミラモールは皇帝らのそばへとこっそり近づくことはできなかっただろう。氷できらめく木々に囲まれた崖の下で、皇帝とコルダとヴェルシデュの3人は、流れの凍りついた小河を眺めて立っていた。
ミラモールはそっとダガーを鞘から抜き出した。彼はやや自分の剣の腕前を誇張して夜母に話していた。実際、皇子の喉を掻き切れたのは皇子を襲う際、相手に臨戦態勢に入るすきをまったく与えなかったからであった。しかし、今回の相手は年老いた一人の男。この簡単な殺しに、どれほどの剣の腕が必要だというのだろうか?
そして絶好のタイミングが訪れたのだった。森の奥深くで皇帝の側を歩いていたコルダが、奇妙な形をした氷柱を見つけ、駆け出していったのである。皇帝は笑みを浮かべながら、その場に残った。兵士たちの歌声の聞こえる崖の方を向き、暗殺者に背を見せた。ついに、その瞬間がやってきた。ミラモールは氷の地面に用心しながら、皇帝に近づき、攻撃した。だが、失敗した。
突如、背後から抱え込まれ喉に強い一撃を食らったのであった。ミラモールは声も出なかった。皇帝は依然として崖を見上げたままだった。林の中に引きずり込まれ、背中からバッサリと切り殺されたミラモールの存在などまったく気づかなかったのであった。
皇帝は連れの者と崖のキャンプ場に戻っていった。そして、吹き出す血が凍りついた地面の上で結晶になりゆくさまをミラモールはただ見ていただけだった。
2920年 黄昏の月12日
モーンホールド (モロウウィンド)
モーンホールド城の中庭は、燃え盛る炎と化し、その火は沸き立つような雲を突き抜けていった。厚い煙が通りを駆け抜け、木や紙、燃えそうなものすべてを焼き尽くしていった。物陰に避難していた住人たちはコウモリに似た生き物たちに襲われ、追い立てられるように表に出たところを今度は軍隊の前へと現れることになった。モーンホールドの完全たる崩壊を唯一妨げていたのは、飛び散っていく濡れた血ぐらいであった。
メエルーンズ・デイゴンは崩れいく城を見つめながら、微笑んだ。
「これを見逃すところだったとは……」と、混乱する街中で声を轟かせて言った。「最高のショーだ」
彼は、赤黒い影の渦巻く空の中に針のように細い閃光のようなものを捉えた。光を発しているもとに目を追うと、街を見下ろす丘の上にいる男女二人の姿に辿り着いた。白いローブを身にまとったその男はすぐにソーサ・シルとわかった。なぜならソーサ・シルはここ最近オブリビオンの王子たちのところを駈けずり回っていたからだ。
「モーンホールドのデュークを探しているなら、残念だがここにはいない」と、メエルーンズ・デイゴンは笑って答えた。「だが、もしかしたら今度雨が降ったときには彼の破片に会えるかもしれないな」
「デイドラよ、貴方を殺すことはできません」と、アルマレクシアは決心したように言った。「だが、すぐに後悔することになるでしょう」
その生ける神2人とオブリビオンの王子との戦いの火蓋は、モーンホールドの廃墟の中、切って落とされた。
2920年 黄昏の月17日
テル・アルーン (モロウウィンド)
「夜母様」と、衛兵は声をかけた。「帝都の代理人様からご連絡が入っております」
夜母は書面を注意深く読んだ。計画は無事成功、ミラモールはまんまと捕まり、殺された。皇帝の警備は手薄となった。夜母は早速、返事をした。
2920年 黄昏の月18日
バルモラ (モロウウィンド)
表情の読めない顔つきのソーサ・シルは、宮廷前の大広間でヴィヴェックと挨拶を交わした。ボドラムでのテントでその戦いの知らせを聞いたヴィヴェックは、目にも留まらぬスピードでダゴス─ウルでの危険も顧みず、何マイルもの距離を駆け抜けていった。船を走らせる途中、南方の空に赤い雲が渦巻くのが見え、以前戦いが、それも昼夜問わず続いているのが見て取れた。ニーシスに着いた彼はソーサ・シルから送られた伝令を受け取ったが、そこにはバルモラに戻るよう書かれてあった。
「アルマレクシアはどこに?」
「奥へ……」と、弱りきった声でソーサ・シルは答えた。下顎には長く醜い切り傷が刻み込まれていた。「アルマレクシアは怪我を負ったが、メエルーンズ・デイゴンも当分の間オブリビオンから戻ってはこられないだろう」
アルマレクシアはシルクのベッドに横たわり、ヴィヴェックの治癒師から治療を受けていた。彼女の唇は石のように灰色に染まり、巻きつけられた包帯からは血がにじみ出ていた。ヴィヴェックは彼女の冷たい手を取った。アルマレクシアは口を動かしたが、言葉にならなかった。彼女は夢の中にいた。
炎が渦巻く嵐の中、彼女は再びメエルーンズ・デイゴンと戦っていた。夜空に飛び散る火花と崩れた城の黒い跡に囲まれていた。デイドラの爪が彼女の腹を深くえぐり、メエルーンズの首に手をかけ必死に抵抗するも、腹の傷口部分から体中の静脈へと毒が回っていった。地面へと叩きつけられながら彼女が目にしたのは、炎に飲まれたモーンホールド城ではなかった。帝都の王宮であった。
2920年 黄昏の月24日
シロディール (帝都)
冬の強風が街を駆け抜け、帝都の王宮にあるガラス製のドームの窓を打ち付けた。揺さぶられる灯りの光線は不思議な陰影を描いていた。
皇帝は大宴会の準備を、家臣たちに大声で指示していた。それは皇帝にとって、戦よりも好きな行事であった。ドローゼル王も先頭に立ち、演目の仕切りをしていた。皇帝は自ら献立に口を出すなどしていた。焼いたニブフィッシュの魚、かぼちゃのマロー、クリームスープ、バターで炒めたヘレラック、コッドスクラムそしてアスピックなどが並んだ。ヴェルシデュも意見を述べたが、それにしてもアカヴィルの味覚は非常に変わっていた。
陽が落ちると、コルダは皇帝の自室へ行き、皇帝と一夜を過ごした。
時は星霜の月へと続く。
2920 星霜の月(12巻)
第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920 星霜の月1日
バルモラ (モロウウィンド)
窓に凍りついたクモの巣の隙間から冬の朝の光が差し込み、アルマレクシアは目を覚ました。老齢の治癒師は安堵の笑みを浮かべて、濡れた布で彼女の頭を拭いた。彼女のベッドの脇の椅子ではヴィヴェックが眠りこけていた。治癒師はキャビネットから急いで水差しを取ってきた。
「ご気分はいかがですかな?」と治癒師は尋ねた。
「とても長い間眠っていたようです」とアルマレクシアは答えた。
「仰るとおり、実に15日間も眠られていましたよ」と治癒師は言い、そばにいるヴィヴェックの腕を揺り動かした。「起きてください。アルマレクシア様が目覚められましたよ」
ヴィヴェックは跳ね起き、アルマレクシアが目覚めたのを確認するやいなや顔が嬉しさでほころんだ。ヴィヴェックは彼女の額にキスをし、手を取った。少なくとも、彼女の体は温かさを取り戻していた。
しかし、アルマレクシアの穏やかな休息は終わった。「ソーサ・シルは……」
「彼も無事だ」とヴィヴェックは答えた。「またどこかで機械をいじってるさ。先ほどまでここで一緒に心配していたが、彼はあの一風変わった魔術で君にしてやれることがあると気付いたんだ」
そこへ城主が戸口に現れ、「お邪魔をしてしまい申し訳ございません。早急にお耳に入れたいことがございます。昨夜、帝都に向けてお送りした伝令の件で」と言った。
「伝令?」とアルマレクシアは尋ねた。「ヴィヴェック、何が起きたのです?」
「6日に皇帝と停戦協定を結ぶ約束だったのだが、延期を申し込んだのだ」
「あなたはここにいてはいけません」とアルマレクシアは言い、自力でなんとか起き上がろうとした。「あなたが今協定を結ばなければモロウウィンドは再び戦火の渦に巻き込まれ、平和を取り戻すのにさらにもう80年かかるかもしれません。お供を連れて今すぐここを発てば1、2日遅れるだけで済みます」
「本当にあなたはもう大丈夫なのか?」とヴィヴェックは尋ねた。
「今あなたを必要としてるのは、私ではなくモロウウィンドです」
2920 星霜の月6日
帝都 (シロディール)
皇帝レマン三世は玉座に腰掛け、謁見室を見渡していた。それは豪華な眺めであった。垂木からぶら下がる銀の飾り紐、四隅には香草の焚かれる大釜が置かれ、ピアンドニアのチョウが歌うように宙を舞っていた。松明に火が点され、使用人たちが一斉に火に向かって扇をはたき始めると、この部屋がきらめく夢の世界へと変わるようであった。そうこうしているうちに厨房の方からおいしそうな香りが漂って来た。
支配者ヴェルシデュ・シャイエとその息子、サヴィリエン・チョラックは謁見室へそっと滑り込んできた。2人ともツァエシの頭飾りや宝石で着飾っていた。その黄金に輝く顔に笑みはなかった。もっとも、それはいつものことだったが。皇帝はこの信頼できる相談相手に嬉しそうに挨拶の言葉をかけた。
「野蛮なダークエルフたちもこれには驚くであろう」と皇帝は笑っていった。「お客はいつ到着するのだ?」
「ヴィヴェックからの伝令が先ほど到着いたしました」とシャイエは厳かに答えた。「陛下お一人でお会いするのがよいかと」
皇帝の顔から笑みが消え、使用人たちに下がるよう命じた。扉が開き、コルダが羊皮紙を片手に部屋に入ってきた。彼女は後ろ手で扉を閉め、皇帝と目を合わせようとしなかった。
「伝令は手紙をそなたに渡したのか?」とレマンは疑わしい口調で言い、椅子から立ち上がり手紙に手を伸ばした。「この受け渡し方は極めて非礼であろう」
「ですが、手紙の内容は実に礼儀正しいものでしたよ」とコルダは皇帝の神の目を見つめて答えた。瞬きする暇もなく、彼女は手紙を皇帝の顎へと突きつけた。突きつけられた手紙に視線を落とし皇帝は怒りに顔を歪ませた。そこにはただ小さな黒い刻印が書かれてあった。それはモラグ・トングの刻印だったのだ。次の瞬間、手紙は床に落ち、その陰に隠されたダガーが姿を現した。コルダは腕をひねって、皇帝の喉仏を骨まで切り裂いた。皇帝は音もなく静かに倒れこんだ。
「どれぐらいの時間が必要だ?」とサヴィリエン・チョラックが尋ねた。
「5分ね」とコルダは手に付いた血をぬぐいながら答えた。「10分くれればその分ありがたいわ」
「わかった」謁見室から走り去ろうとするコルダの背に向かってヴェルシデュ・シャイエがそう答えた。「彼女みたいな人物がアカヴィルであればよかった。女性で剣の腕がたつとは実に稀有な存在だ」
「私はアリバイ作りに行ってきます」とサヴィリエン・チョラックは言い残し、皇帝の側近でしか知り得ない秘密の通路へと消えていった。
「1年前の事を覚えていらっしゃいますか、陛下」と、ヴェルシデュ・シャイエは笑顔で瀕死の皇帝を見下ろしながら問いかけた。「私に向かって『そなたらアカヴィルの動きは派手派手しい。しかし、我々の攻撃が一度でも当たれば、そなたもおしまいだ』とおっしゃいましたが、陛下こそ、このお言葉を覚えておくべきでしたね」
皇帝は血の塊を吐くのと同時にこうもらした。「この蛇め」
「いかにも私は表も裏も蛇でございます、陛下。しかし、嘘はついておりません。ヴィヴェックからの伝令は届いております。どうやら到着が遅れるそうです」と言ってヴェルシデュ・シャイエは肩をすくめながら秘密の通路へと消えていった。「ご心配なさらず。食事の管理は私にお任せを」
タムリエルの皇帝はこの豪華に飾られた謁見の間で自らの血溜まりに溺れていった。衛兵が彼を見つけたのはその15分後のことであった。その頃コルダは姿形もなく消え去っていた。
2920 星霜の月8日
カエル・スヴィオ (シロディール)
ヴィヴェックとその連れが到着した際、一番最初に挨拶をした密使はグラヴィアス卿で、彼は森を通ってくる道のひどさをやたらと詫びた。邸宅を囲む葉の落ちた木々には燃える球の飾りが幾重にもつけられており、冷たい夜風に優しく揺れていた。邸宅の方からささやかな祝宴の料理のにおいが漂い、高音の悲しい調べが聞こえてきた。それはアカヴィルの伝統的な冬の祝歌であった。
ヴェルシデュ・シャイエは正面扉のところでヴィヴェックに挨拶した。
「あなたが帝都へ来られる前に伝令を受け取れたのは良かった」と言ってヴェルシデュ・シャイエはヴィヴェックを広く暖かい客間へと案内した。「我々は今厳しい時代、いわば過渡期におります。当面は、議事堂での職務は控えることにしました」
「王位後継者の方はいらっしゃらないのですか?」とヴィヴェックは尋ねた。
「公式にはいらっしゃいません。玉座を狙う遠戚の方は大勢おられますが。ともかく、当分の公式行事は、私が先の主の代わりに務めることを貴族の方々にはご了解いただいております」そう言って支配者ヴェルシデュ・シャイエは使用人に2脚のゆったりとした椅子を暖炉の前に運ぶよう指示した。「今すぐこちらで協定を結んだほうがよろしいですか? もしくは先にお食事でも?」
「あなたは先帝の協定をそのままお引継ぎになられるのですか?」
「私はすべてを皇帝と同じように執り行うつもりでおります」とヴェルシデュ・シャイエは答えた。
2920 星霜の月14日
テル・アルーン (モロウウィンド)
道中で土ぼこりにまみれたコルダは夜母の腕に飛び込んだ。しばらくの間2人はしかと抱き合い、夜母は娘の髪を優しくなでつけ、額にキスした。そして袖から一通の手紙を取り出し、コルダに渡した。
「これは?」とコルダは聞いた。
「支配者ヴェルシデュ・シャイエからのお礼の手紙よ」と夜母は答えた。「彼は今回の暗殺の支払いをすると言ってきたのだけれど、もう返事は送ったの。皇后様から皇帝暗殺の報酬は十分にいただいたもの。必要以上の強欲はメファーラが許しませんからね。同じ暗殺の報酬を2度受け取る必要はない、と返したわ」
「皇帝はリッジャを殺したわ」とコルダは静かに言った。
「だからこの暗殺はあなたがやるべきだったのよ」
「これからあたしはどこへ行ったらいいの?」
「有名になりすぎて聖戦を続けられなくなった聖者は、ヴヌーラと呼ばれる島へ行くことになっています。ボートで1ヶ月かそこらの旅ですよ。その聖域であなたが優雅な日々を暮らせるよう手はずは整えておきました」夜母は娘のこぼれる涙にキスをし、「そこでたくさんのお友達ができますよ。永遠に平和で暮らせますよ」と言った。
2920 星霜の月19日
モーンホールド (モロウウィンド)
アルマレクシアは再建されていく街並を見て回っていた。黒こげに焼け落ちた古き建物の上に新たな骨組みを組む中を歩きながら、彼女は「ここの市民の志には実に心を打たれる」と思った。かつて街道沿いに並木を作ったコムベリーとルーブラッシュの低木は、しなびてはいたがかろうじて生命をつないでいた。アルマレクシアは鼓動を感じた。春が訪れる頃には緑が黒を追いやっているだろう。
デュークの後継者である、高い知能と不屈のダンマーの勇気を兼ね備えた1人の青年が、北方より父親の領地へと向かっていた。この地は存続するだけではなく、力を備え、広がりを見せるであろう。アルマレクシアは今見ているものより、未来を思って心強く感じた。
彼女が唯一確信したことは、この地モーンホールドが少なくとも一人の女神の永遠の故郷であると思っているということだ。
2920 星霜の月22日
帝都 (シロディール)
「シロディールの血筋は途絶えた」とヴェルシデュ・シャイエは帝都宮殿の伝えし者のバルコニー下に集まった大衆に向け発表した。「しかし、帝都はこれからも生き続ける。信頼のおける諸貴族たちは、次期王位にはこれまで長く受け継がれてきた皇族の遠戚たちの中に相応しいものがいないと判断した。よって、先帝レマン三世から最も信頼されたこの私が、先帝の意思と職務を引き継ぐことなる」
このアカヴィルはそこで一呼吸置き、自分の発した言葉が大衆に理解されるのを待った。だが、大衆はただ彼を無言のまま見上げるだけだった。雨が街の道という道を洗い流したが、ほんのわずかな間、冬の嵐を小休止させるように太陽が顔を出した。
ヴェルシデュ・シャイエは続けて「私が帝位を受け継ごうとしているのではないことをわかっていただきたい。私はこれからも支配者ヴェルシデュ・シャイエとしてここに立つが、あなた方にとっては1人の外国人にすぎない。だがしかし、新たな後継者が出現するまで、私はこの第二の祖国を守り通すことをここに誓う。そこで早速、最初の仕事として、この歴史的に記念すべき日を称え、本日を暁星の月、第一日目と定め、第二紀の始まりであることをここに宣言する。まず先帝の喪失を悼み、そして未来に期待しよう」と言った。
この言葉に拍手を送ったのはたった1人だけだった。その1人とはセンチャルのドローゼル王であり、彼は今日このタムリエルの地に華々しいスタートが切られたことを信じきっていた。もちろん、この時彼は完全におかしくなっていた。
2920 星霜の月31日
エボンハート (モロウウィンド)
ソーサ・シルが、彼の不思議な機械で未来を作り出した都市の下に横たわる煙たい地下墓地で、思いがけないことが起こった。今まで壊れることのなかった歯車の間から油性の泡が吹きこぼれていた。ソーサ・シルはすぐそれに気付き、泡を発生させているチェーンを調べた。パイプが左に半インチずれてしまい、かみ合わせが1ヶ所外れてしまっていた。コイルも巻き戻り、反対方向へと回り始めていた。1000年もの間ただの一度も壊れることなく左から右へと動いていたピストンが、突然右から左へと逆方向へ動き出した。どこも壊れてはいないが、すべてが変わってしまった。
「すぐには直りそうにないな」と妖術師は静かに言った。
天井の隙間から夜空を見上げた。真夜中であった。こうして第二紀は混乱のスタートを切ったのであった。