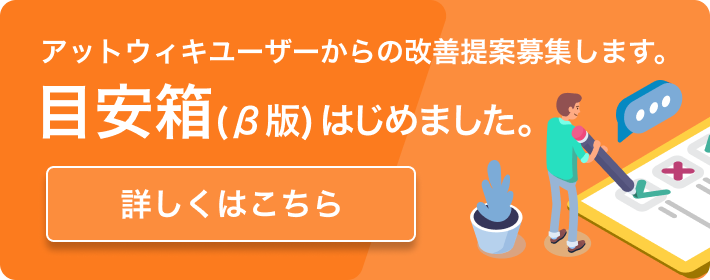オブリビオン図書館
火中に舞う
最終更新:
oblivionlibrary
-
view
火中に舞う 第1章
ウォーヒン・ジャース 著
場所:帝都 シロディール
日付:第三紀397年 10月7日
正に宮殿と呼べるような建物に、アトリウス建設会社は入っていた。ここは帝都内のほとんどすべての建設事業に対し、建設や公証を行う、事務手続きと不動産管理の会社だった。宮殿の広場は質素で、豪奢な飾りつけなどはされていなかったが、この建物はマグナス皇帝の時代から250年間立っていて、飾りが質素で荘厳な広間と豪華な広場を構えていた。そこでは精力と野望に満ち溢れた中流階級の若い男女が働いていた。デクマス・スコッティのように、安穏と働く中年もいた。誰もこの会社がない世界など想像していなかった。スコッティもまた例外ではなった。正確には、彼は自分がこの会社にいない世界など想像していなかった。
「アトリウス卿は君の働きぶりにいたく感銘を受けているよ」と主任は後ろ手でスコッティの職場へと通じる扉を閉めながら言った。「しかし、世間の物事はだな、なんとも難しいものなのだよ」
「はい」スコッティは堅い表情で答えた。
「ヴァネック卿の遣いが近頃我々にハッパをかけてきておるし、我が社もこの先を生き抜くためにはもっと効率を上げなければならない。実に悲しいことだが、過去素晴らしい働きぶりを見せたとしても、現在が業績不振であれば、年配の働き手といえども解雇せざるをえないのだよ」
「わかります。仕方ありません」
「わかってもらえて良かったよ」と主任は笑顔になったが、その笑いはすぐに消えさり、「それでは早急に君の机をかたづけてくれ」と言った。
スコッティは後任者に明け渡すため机回りの整理を始めた。おそらく次の後任者は若いイムブラリウスという男であろう。そうしなければならなかったのだろうと彼は哲学的に考えた。その若者は、仕事をつかむ術を知っているのだ。スコッティは、イムブラリウスが神殿から委託された聖アレッシア像建設の契約をどうするつもりなのかといぶかっていた。「きっと彼なら、仕事上の架空のミスを作り出し、前任者である私に罪をおしつけ、修正費用をせしめることさえやりかねないだろうな」
スコッティがその声の主を見ると、丸々とした顔の配達人が事務所の中へと入ってきて、封のされた1巻の巻物を渡してきた。彼は配達人にチップを渡し、早速広げてみた。乱暴な筆跡と書き損じとひどい文法と誤字で、この手紙の主がすぐにわかった。リオデス・ジュラスだ。彼も数年前は同じ職場の友であったが、この会社の道義に反した慣例に嫌気がさし、去っていったのだった。
──
『スクッティへ
俺に一体全体、何が怒ったかと思ってるだろ。そして俺が今一体どこにいるのかと思ってるはずだ。森の中だと? まあ、実はその通りだ。ハハッ。おまえが頭のキレるヤツで、アトリウス卿のために、えらい稼ぎたいなら(もちろん自分の分もだ、ハハッ)、ここ、ヴァリーニウッドに恋。世の流れにツイてってる、ツイてってなくても、ボッシュマーとその隣のエルスワーの愛だで2年も続いた戦があったことは知ってるだろうか? 昨今ようやく落ち着きを取り戻して、各地で再建が始まったのさ。
今、抱えきれないほどの仕事の波が着ている。手助けしてくれそうなヤツを探してる。筆が進む優秀な代理店がいないかと考えていたら、友よ、おまえさんが頭に浮かんだんだ。ヴァリーニウッドのファリンネスティにあるマザー・パスコスの酒場で遭おう。オレは2週間いる予定だ。悪い酔うにはしない。
ジュラスより
追伸:ついでに、木材を煮馬車1台分もってきてくれないか。』
──
「何を持ってらっしゃるんですか?」と、尋ねる声がした。
スコッティはその声に驚いた。声の主はイムブラリウスだった。彼はドア越しにやたらハンサムな顔を覗かせ、手厳しい顧客やがさつな石工屋の心さえも溶かしそうなとびきりの笑顔を浮かべていた。スコッティはあわてて手紙を上着のポケットへとねじ込んだ。
「私的な手紙だよ」と、スコッティはあしらった。「すぐにここを片付けるから待ってくれ」
「そんなに急がなくてもいいじゃありませんか」と言いながら、イムブラリウスはスコッティの机の上にあった何も書いていない契約書をつかみとり、「私に任せてください。若い書記の字なんか、まったくひどくて読めやしませんからね。あなたが心配することは何もないですよ」
イムブラリウスはそういい残し、去っていった。スコッティはもう一度手紙を取り出して読んだ。彼は自分の人生について考えた。普段の彼ならまったくしないことだが。今のスコッティの視界は、漠然と切り立つ黒い壁に阻まれた、灰色の海のようであった。その切り立つ黒い壁を抜けるのには、たった1本の細い道筋しかない。彼は考えが変わる前に、急いで「皇帝御用達アトリウス建設会社」と書かれ金箔をあしらわれた未記入の契約書を何枚かつかみ、かばんに私物と一緒に放り込んだ。
翌日、彼はなんの躊躇もせず、目が眩むような冒険へと旅立った。その週に帝都を出発して南東に向かう1人引きのキャラバンに、ヴァレンウッドまでの席を1人分用意してもらった。ほとんど荷造りをする時間はなかったが、馬車1台分の木材を用意することは忘れなかった。
「その木材用の馬は追加料金ですよ」と、キャラバンの護衛長は顔をしかめながら言った。
「もちろん」と、スコッティはイムブラリウスのようなとびきりの笑顔をつくってみせた。
十台の荷馬車は午後にシロディールを出発し、見慣れた風景は徐々に小さくなっていった。野生の花々が咲き誇る草地を過ぎ、森や小さな村を穏やかな調子で過ぎていく。石道に当たる馬のひづめの音を聞いていると、確かこの道はアトリウス建設会社が建設した道だったなと思い出した。この石道が完成するまでに18もの契約書が必要であったが、そのうち5つはスコッティが作成したものであった。
「そんなふうにして木材を運ぶとは、賢いお方ですな」と灰色のひげをたくわえたブレトンの男が話しかけてきた。「かなりの商売人ですね」
「そんなところです」と、スコッティはためらいながらも答えた。「どうも、私、デクマス・スコッティといいます」
「グルィフ・マロンです」と、男は答えた。「私は詩人なんですが、今は古代ボズマー文学の翻訳もやっておりまして。2年前に発見されたムノリアダ・プレイ・バーの小冊子の研究をしているのですが、ちょうど戦が始まり、私も避難せざるをえなかったもんですから。ムノリアダはご存じかと思いますが、“緑の約束”という作品を耳にされたことがありますかな……」
スコッティは彼の話す内容をまったく理解できなかったが、ただうなずいていた。
「普通に考えれば、ムノリアダがメー・アイレイディオンと同じくらい有名だとか、ダンサー・ゴルと同じくらい時代を感じてしまうとまでは申しません。ただ彼の作品は、ボズマーの心情の本質を理解するにはもっとも意義のあるものなのです。本来、ウッドエルフは木を切ったり、植物を食べるのを嫌いますが、逆に異文化から植物全般を積極的に輸入している。このことはムノリアダのある一節と深く結びついていると思うのです」そう言うと、マロンはその一節とやらを探して自分の荷物をごそごそと探り始めた。
今夜の宿営地に馬車が止まり、スコッティはようやく開放された。そこは高い崖の上で、下には灰色の小河が流れ、ヴァレンウッドの広大な谷が広がっていた。海鳥の声が聞こえてきた。西の入り江に海があるようだった。ここの木々は背丈もあり、また幹も太かった。ねじれながら伸びていて、遥か昔から筋くれだっているようで、ちょっとやそっとでは切り倒せそうになかった。一番下の枝までの高さが50フィートぐらいの木が宿営地のそばの崖に何本か生えていた。このような風景はスコッティにとって見慣れないものであり、こんな荒野に入っていくことに不安を覚え、なかなか眠れそうになかった。
幸いにもマロンは、古代文化の難題を語り合える別の同胞を見つけたようだった。夜も更けこんできたころ、マロンがボズマーの詩を原文と自分の翻訳したものと併せて朗読していた。すすり声をあげたり、うめき声を出したり、小声にしてみたりとその場ごとに合わせて声色を変えていた。次第にスコッティは眠気に襲われ、ウトウトしていたところに突然、木々の激しく折れる音がした。彼の目は一気に覚めた。
「あれはなんです?」
マロンは笑顔で答えた。「ここは僕の好きな一節だ、『月ない月夜に悪が集う、火中の舞い……』」
「木の上にものすごく大きな鳥がいるみたいです」と、スコッティは小声で言いながら、頭上で動く真っ暗な物体を指差した。
「あれなら心配ご無用」と、マロンは言ったが、聴衆に邪魔されて不機嫌そうだった。「それよりも、ハルマ・モラの第4巻18節の祈祷文を、詩人がいかにして読み解いたかを聞いていただきたい」
木々にひそむその暗い影は、止まり木に止まる鳥のようなもの、ヘビのように這うもの、人間のように直立するものなど様々だった。マロンは詩を朗読し始めたが、スコッティはそのもの達が静かに枝から枝へと飛び移り、翼もなしに信じられない距離を飛ぶのを見ていた。それらは何組かに分かれ、宿営地を囲むように周りの木々へと再び散らばった。そして、突如として急降下してきたのである。
「おい!」と、スコッティは叫んだ。「雨みたいに落ちて来るぞ!」
「おおかた種子のさやでしょう」と、マロンは顔を上げずに肩をすくめてみせた。「このあたりには変わった性質の木があって……」
突然宿営地は混沌の世界へと変わり果てた。荷馬車には火がつき、馬は暴れ回り、真水や酒がそこらじゅうに流れ出した。スコッティとマロンのそばを1つの影がすばやく通りすぎ、穀物と金が入った袋を、驚くほど機敏かつ優雅な動きでかっさらっていった。スコッティだけがその姿を捉えた。すぐそばで炎があがり、その明かりに照らされたのはつやつやと光る生き物で、尖った耳、横長の黄色い目、まだら模様の毛皮、鞭のような尻尾をしていた。
「人狼だ」と言って、スコッティはすすり泣きながら体を縮めた。
「いや、キャセイ・ラートだ」マロンはうめくように言った。「人狼よりさらにタチが悪い。カジートのいとこかそんなようなものだ。略奪に来たのだ」
「なんてこった!」
襲撃も早ければ、退去するのも早かった。キャラバンの護衛としてついていた魔闘士や騎士たちが敵を確認する前にはもう、崖から飛び降りていた。マロンとスコッティは絶壁近くまで駆け寄ると、100フィートも下で水から飛び出し、体についた水を振り切ると森の中へと消えていく小さい姿が見えた。
「人狼はこんなに俊敏じゃない」と、マロンは言った。「絶対にキャセイ・ラートだ。恐ろしい盗賊たちです。ステンダール神の御加護のお陰で、このノートを奪われずにすみました。助かった」
火中に舞う 第2章
ウォーヒン・ジャース 著
完全に失った。キャセイ・ラートは数分で、隊商の中にあった価値のあるものをすべて盗み、破壊して行った。デクマス・スコッティがボズマーとの貿易を見込んでいた木の積み荷には火をかけられ、絶壁から落とされた。彼の衣服や仕事の契約書は引き裂かれ、こぼれたワインや土のぬかるみの中にすり込まれていた。一行の巡礼者や商人や冒険者たちは皆、愚痴をこぼし泣きながら、夜明けの太陽が昇る中、残った持ち物を集めた。
「なんとか『ムノリアド・プレイ・バー』の翻訳に必要な覚え書きを手放さずにすんだことは、誰にも言わないほうがいいな」と、詩人グリフ・マロンはささやいた。「おそらく皆が私を狙うであろう」
スコッティはどれだけマロンの所持品に対して微少な価値しか見出せないかを伝える機会を辞退した。その代わり、彼は自分の財布のなかのゴールドを数えた。34枚。これから新しい仕事を始めようとしている起業家にとっては、いかにも少ない。
「おーい!」と、森の中から叫び声が聞こえた。武器を携え、皮の鎧を着たボズマーの小集団が茂みから現れ、「敵か? 味方か?」
「どちらでもない」と、隊商の代表者が唸りあげた。
「あんたたち、シロディールだな」背が高く、スケルトンのように痩せ、長細い顔を持った小集団の隊長が笑った。「あんたたちが旅をしていることは聞いていた。どうやら、我々の敵も聞いていたようだな」
「戦争は終わったと思っていたのに」と、すべてを失った隊商の、すべてを失った商人が低く言った。
ボズマーはまた笑い、「戦争ではない。ちょっとした境界線の小競り合いだ。ファリネスティへ向かうのか?」
「俺は行かない」隊商の代表者は首を振った。「俺の役目はもう終わった。馬がいなくなる、即ち隊商もなくなる。俺にとっては大損だ」
男も女も皆、代表者の周りに集まって抗議したり、脅したり、嘆願したが、彼はヴァレンウッドに足を踏み入れることを拒否した。もしこれが新しい平和の形ならば、彼は戦争時代が戻ってきてほしいと言った。
スコッティは違う方法を試みようと、ボズマーに話を持ちかけてみた。彼は不機嫌な大工との交渉時に使うような、有無を言わせないが、友好的な声で話した。「私をファリネスティまで護衛して貰えないでしょうか? 私はアトリウス建設会社という重要な帝都機関の代理人であり、あなたたちの地方に、カジートとの戦争がもたらした問題を修復して緩和する手伝いをしに来たのです。」
「20ゴールド、それと、荷物があったら自分で運ぶ」と、ボズマーは返答した。
不機嫌な大工との交渉も、めったに彼の思いどおりにはならなかったことを思い出していた。
支払いのためのゴールドを、6名の熱心な人々が持っていた。資金がない人々のうち、1人は詩人であり、彼はスコッティに手助けを願い出た。
「グリフ、ごめんなさい、私には14ゴールドしか残っていないのです。ファリネスティに到着しても、まともな部屋をとることすらできないのです。できるならば、本当に助けてあげたいのですが」これが本心であると自分を説得しながら、スコッティは言った。
六名とボズマーの護衛の一団は、絶壁に沿って険しい道を下り始めた。一時間も経たずに彼らはヴァレンウッドのジャングル奥深くにいた。果てしなく続く茶色と緑の天蓋が、空を見えなくしていた。何千年もの間に落ちた葉が、彼らの足の下で腐敗した厚い敷物を形成していた。この滑りの中を、数マイル歩いて通り抜けた。そしてさらに歩き続けてから、彼らは落下した枝や低く垂れ下がる大木の主枝の迷路を横断した。
何時間もの間、疲れを知らないボズマーたちがあまりにも早く歩くので、シロディールたちは取り残されないよう必死だった。足の短い赤ら顔の商人は、腐った枝に足を取られて倒れそうになった。同郷のものが立ち上がるのを助けなければならなかった。ボズマーは一瞬だけ立ち止まり、絶えず頭上の木陰に目を配り、また迅速な歩調で歩き出した。
「彼らは何に対してあれほど神経をとがらせているんだ?」イライラしながら商人があえいだ。「キャセイ・ラートがまたくるのか?」
「馬鹿なことを言うな」説得力なくボズマーは笑った。「これほどヴァレンウッドの奥深くでカジート? 平時に? あいつらには無理だろう」
一行が沼地から臭いがある程度消されるくらい高いところを通過したとき、スコッティは突然の空腹による胃の痛みを感じた。彼は1日4食のシロディールの習慣に慣れていた。食べずに何時間もの休みなき激しい活動を行うのは、十分な報酬を与えられている書記の摂生習慣の一部ではなかった。多少意識が混濁するなか、彼はどれくらいジャングルの中を駆け回っているかを考えた。12時間? 20時間? 1週間? 時間にはあまり意味がなかった。日光は、植物性の天井の所々からしか差し込まない。木や腐葉土に生えている、リン光を発するカビだけが規則的な照明を提供していた。
「休憩と食事をとることは無理ですか?」前にいる案内役に大声で言った。
「ファリネスティの近くだ」と、こだまする返事が返ってきた。「あそこには食べ物がたくさんある」
道はさらに数時間ほど上昇を続け、倒れた木々が固まっている場所を横切り、並んだ木の主枝の1段目、そして2段目へと上昇した。大きな角を曲がりきると、彼らは何十フィートもの高さから流れ落ちる滝の中途にいることが分かった。大量の岩をつかみ、少しずつ自らを引き上げ始めたボズマーに、文句を言う気力は残っていなかった。ボズマーの護衛たちは噴霧の中に消えて行ったが、スコッティは岩がなくなるまで登り続けた。彼は汗と川水を目から拭った。
ファリネスティが彼の目の前の地平線に広がった。川の両側には巨大なグラッドオークの街が不規則に広がっていて、その周りには、まるで王者に群がる嘆願者のように、より小さな木の林や果樹園などが隣接していた。より小さな規模で見ると、この移動する街を形成する木は並外れていたのであろう。曲がりくねった金と緑の王冠を載せ、つるを垂れ下がらせ、樹液で光り輝いている。数百フィート以上もの高さで、その半分の幅。スコッティが今まで目にした何よりも壮大であった。もし彼が、書記の魂を持った餓死寸前の男でなかったら歌でも歌ったであろう。
「ここに居たのか」と、護衛の長が言った。「散歩には十分だったな。冬場であったことに感謝しろ。夏場だと、街はこの地方の最南端にあるんだからな」
スコッティはどう進んだらよいのか分からなかった。人々が蟻のように動き回るこの垂直な大都市の光景が彼の感性をマヒさせた。
「ある宿屋を探しているんですが」一瞬言葉を切り、懐からジュラスの手紙を取り出した。「『マザー・パスコスの酒場』とか呼ばれているらしいですが」
「マザー・パスコストか?」ボズマーはいつもの人を馬鹿にしたような笑いを発した。「あそこには泊まりたくないと思うぞ。訪問者は必ず、主枝の最上段にあるアイシアホールに泊まりたがる。値は張るが、いいところだぞ」
「マザー・パスコストの酒場で人と会うのです」
「もし行くと決めているなら、昇降装置でハベル・スランプへ生き、そこで道順を聞くんだな。ただ、道に迷ってウエスタン・クロスで寝ちまったりするなよ」
どうやらこの一言は彼の仲間たちにとっては気の利いた洒落だったらしく、こだまする彼らの笑い声を背に、スコッティはねじれ曲がった根の階段をファリネスティの基部へと進んだ。地上は葉やゴミが散乱していて、時折、遥か頭上から硝子や骨が落下してくるので、彼は警戒のために首を曲げながら歩いた。入り組んだ可動台はしっかりと太いつるに固定され、この上ない優雅さで滑らかな幹を上下しており、そのつるは牛の腹ほどの腕を持った操作者によって動かされている。スコッティは暇そうに硝子パイプを吹かしている、一番近くの台の操作者に近寄った。
「ハベル・スランプへ連れて行ってもらえませんか?」
男はうなずき、スコッティは数分後に地上100付近にある2本の巨大な枝の屈曲部にいた。渦巻く蜘蛛の巣状の苔が枝の一面を不規則的に覆い、数十戸の小さな建物が共有する天井を形成していた。裏通りには数名しかいなかったが、先の角を曲がると音楽や人々の音がした。スコッティはファリネスティの広場のフェリーマンにゴールドを一枚渡し、マザー・パスコストの酒場の場所を聞いた。
「まっすぐ進んだところにありますが、あそこには誰もいませんよ」フェリーマンは説明しながら、音の方向を指差した。「ハベル・スランプの皆は月曜日には盛大に酒盛りをするのです」
スコッティは注意しながら細い道に沿って歩いていた。地面は帝都の大理石でできた街路のように硬かったが、滑りやすい裂け目が樹皮にはあり、致命的な川への落下の可能性をむき出しにしていた。彼は数分間座って休憩するとともに、高いところからの眺めに慣れようとした。確かに素晴らしい日ではあったが、たった数分の熟視で彼は不安とともに立ち上がった。眼下の下流につながれていた素敵な小さな筏は、彼が見ている間に、はっきりと何インチか動いていたように見えた。しかしそれは、実は全く動いていなかった。彼の周りのものすべてと一緒に、彼が動いていた。それは、たとえではなく、ファリネスティの街が歩いたのである。そして、その大きさから考えると、素早く動いていた。
スコッティは立ち上がり、曲がり角から立ち昇る、煙に向かって歩いていった。それは今までに嗅いだことがないほど美味しそうな丸焼きの匂いであった。書記は恐怖を忘れ、走っていた。
フェリーマンが言った「酒盛り」は木に縛り付けられた巨大な舞台の上で行なわれ、それはどの街の広場にも匹敵するほどの幅があった。そこにはスコッティが今までに見たこともない様々な種類の人々が肩を並べており、多くは食べ、さらに多くは呑み、一部は群衆の上の横枝に腰掛けている笛吹きや歌手の音楽に踊っていた。彼らの大部分は鮮やかな皮や骨の民族衣装を着たボズマーと、数で少々劣る少数派のオークたちであった。雑踏の中を旋回し、踊り、お互いに怒鳴りあいながら進むのは、見るもおぞましい猿人であった。群衆の上に突き出しているいくつかの頭は、最初にスコッティが思ったような背の高い人のものではなく、ケンタウロスの一家であった。
「羊肉は要らんかね?」と、真っ赤な石の上で巨大な獣を丸焼きにしている、しわくちゃな老人が聞いた。
スコッティはすぐさまゴールドを渡し、手渡された足をむさぼり食った。そして、もう1枚ゴールドを渡し、足をもう1本。彼が軟骨を喉に詰まらせたのを見て、老人はクスクス笑い、スコッティに泡立っている白い飲み物を渡した。彼はそれを飲むと、体中がくすぐられているかのように震えるのを感じた。
「これは、なんですか?」と、スコッティは聞いた。
「ジャッガ。発酵させた豚のミルクじゃ。ゴールドをもう1枚出してもらったら、これの大瓶と羊肉をもう少し持たせてやれるが」
スコッティは同意し、支払い、肉を飲み込み、大瓶を持って群衆の中に消えていった。彼の同僚リオデス・ジュラス、ヴァレンウッドにこいと言った男はどこにも見られなかった。大瓶が約四分の一なくなったころ、スコッティはジュラスを探すのをやめた。それが半分なくなったころには、壊れた厚板や裂け目を気にせず群衆と踊っていた。四分の三なくなったころには、まったく言葉が通じない生物と冗談を交わしていた。そして大瓶が完全に空になったとき、彼はいびきをかきながら眠っていたが、周りでは彼の無気力な体をよそに、酒盛りが続けられた。
あくる朝、いまだ眠っているスコッティは誰かの口づけを感じた。彼もそれに応えようと口をすぼめたが、炎のような激痛が彼の胸を襲い、目を開けさせた。牛と同じくらいの大きさの虫が彼の上に座り込み、刺々しい足が彼を押さえつけ、中央の回転刃のような渦巻く口が彼の服を破いた。彼は叫びもがいたが、獣は強すぎた。それは食事を探しあて、完食するつもりであった。
終わった、地元を離れなければよかったと、スコッティは狂乱しながら思った。街に留まり、もしかしたらヴァネック卿の下で働けたかもしれない。もう1回下級書記から始め、また上へ昇っていけたかもしれない。
突然、口がひとりでに開いた。その生物は1度身震いし、胆汁を一気に放出して、死んだ。
「仕留めたぞ!」あまり遠くないところから叫び声。
スコッティは、少々その場から動かなかった。頭は脈打ち、胸は焼けるように痛い。視界の端に動きを見た。この恐ろしい生物がもう1匹彼に向かって走ってきた。彼は自分を解放しようと慌てて動き出したが、出られる前に弓の割れるような音が響き、矢が2匹目の虫を貫通していた。
「上手い!」と、違う声が叫んだ。「1匹目をもう1度射て! 少し動くのを見たぞ!」
今回は矢が死骸に命中する衝撃をスコッティは感じた。彼は叫んだが、どれだけ彼の声が昆虫の体によって押し殺されていたか彼にもわかった。注意しながら足を出して、下から転がり出ようと試みたが、その動きはどうやら射手に、生物が生きていると思わせる効果があったらしい。矢の一斉射撃が放たれた。獣は十分穴だらけになり、その血と、おそらくは犠牲者の血が流れ始め、スコッティを覆った。
スコッティが子供のころ、そのような競技には自身が慣れすぎてしまうまで、帝都闘技場へしばしば戦闘競技を見に行っていた。戦闘の熟練者が秘訣を聞かれたとき、彼は「何をしたらいいのか分からず、盾を持っているのであれば、私はその後ろに隠れている」と言ったのを思い出した。
スコッティはその助言に従った。1時間後、矢が射られている音が聞こえなくなったとき、彼は虫の残骸をどけ、彼に可能な限りの速さで立ち上がった。間一髪であった。八人の射手の集団が、彼の方向に弓を向け射かける準備をしていた。
「ウエスタンクロスで寝るなと誰も教えてくれなかったのか? おまえら酔っ払いがやつらの餌になっていたら、どうやって俺たちはホアヴォアーを根絶したらいいんだ?」
スコッティは頭を振り、舞台に沿って歩き、角を曲がり、ハベル・スランプへ戻った。彼は血だらけで、破れ、疲れていて、発酵した豚のミルクを飲みすぎていた。彼が欲するのは横になれる場所であった。彼は湿っぽく、樹液で濡れ、カビの臭いがするマザー・パスコストの酒場に入った。
「名前はデクマス・スコッティ」と、彼は言った。「ここにジュラスという名の人は泊まっていませんか?」
「デクマス・スコッティ?」と、太った女主人、マザー・パスコストは思案した。「その名前、聞き覚えがあるねえ。ああ、彼が置いていった手紙の相手はあなたのことね。探してみるから、ちょっと待っててね」
火中に舞う 第3章
ウォーヒン・ジャース 著
マザー・パスコストは彼女の酒場である薄暗い穴へと消え、すぐに見覚えのある、リオデス・ジュラスの走り書きがなされている紙くずを持って現れた。デクマス・スコッティはそれを、木の街を覆う大きな枝の数々の間から差し込んでいる、木漏れ日にかざして読んだ。
──
スクッティへ
ボリンウッドのファリネンスティに付いたか! おめでたう! ここに来るまでにいろいろ大変だったろー。残念だけど、思ってるとおり、もー俺はここに以内。川をくだるとアシエって町があって、おれ居る。舟みっけて、こい!さいこーだぜ!けいあく書、一杯もってきたろうな、こいつらたちたくさんタテモノひつよだぜ。こいつらたち、戦闘にちかかったんだけどよ、ちかすぎてカネがねーわけじゃねぜ、ハハッ。出切るだけはやく恋。
ジュラスより
──
なるほど、スコッティは考えた。ジュラスはファリネスティを離れ、アシエと言う場所へ移動していた。彼の下手な筆跡と言葉を失うような文法を考慮すると、その場所はアシー、アフィー、オスリー、イムスリー、ウルサ、クラカマカ、このどれにでも同等になり得るのである。常識的に考えたら、この冒険をやめて帝都へ戻る手段を探したほうが良いのはスコッティにも分かっていた。彼は興奮する人生にその身を捧げる傭兵ではなく、成功を収めた民間建設会社の先任書記なのである、または、先任書記で「あった」のである。この数週間、彼はキャセイ・ラットに身ぐるみをはがされ、へらへら笑うボズマーの一味にジャングルで死の行進をさせられ、餓死寸前になり、発酵したブタの乳でこう惚状態にされ、巨大なダニに食い殺される寸前になり、射手に襲われた。彼は不潔で、疲れ果て、手持ちはたったの10ゴールド。更に、彼をその提案によってこの苦難の連続へと導いた張本人はここに居もしない。完全にこの計画を放棄するのは、賢明で礼儀にかなったことである。
しかし、小さいが、はっきりとした声が頭の中でささやく。
「あなたは選ばれたのだ。最後を見届ける以外に選択肢はない」
スコッティは丈夫そうな老婆のほうを向いた。マザー・パスコストは彼のことを、もの珍しそうに見ていた。「最近、エルスウェーアと衝突寸前になった村をご存じないかを考えていたのですが。アシ…エ、そのような名前なのですが?」
「アセイのことじゃな」にやけながら彼女は言った。「次男坊、ヴィグリルがそこで牧場を経営していてな。川沿いできれいなところじゃ。そこにあんたの友達は行ったのかね?」
「はい」と、スコッティは言った。「最短でそこへ行く方法を知っていますか?」
短い会話の後、さらに素早くファリネスティの根の部分まで行き、そして川岸まで走った。スコッティは巨大で、髪の色が薄く、ふやけたような顔を持ったボズマーと移送の交渉をしていた。彼は自分をバリフィックス船長と呼んでいたが、あまり世間を知らないスコッティでさえ、彼が何であるかは分かった。金さえ渡せば雇えるであろう、引退した海賊で、疑う余地のない密輸者、あるいはもっと酷いこともするのであろう。彼の船は明らかに昔盗まれたもので、壊れかかった帝都式1本マストの帆船である。
「50ゴールドで、2日でアセイに連れて行ってやるぜ」のびのびと、轟くような声でバリフィックス船長は言った。
「10、いや、ごめんなさい、9枚ならあります」と、スコッティは答えてから説明の必要性を感じ、「10枚あったのですが、ここまで連れてきてもらうのに、広場のフェリーマンに1枚あげてしまいました」と、付け足した。
「じゃあ9枚でもいいぞ」と、船長は合意した。「本当のところ、あんたが金を払おうが払うまいが、俺はアセイへ行くつもりだったんだ。まあ、船に乗ってくつろいでくれ、あと数分したら出発だ」
デクマス・スコッティは木箱が高く積み上げられ、船倉から溢れ出た袋が甲板へとせり出すほど貨物を積まれたせいで深く水に沈みこんでいる船に乗り込んだ。それらの袋は、それぞれまったく害のなさそうな品物の名前が刻印されていた。くず銅、豚脂、インク、ハイ・ロックの食事(「牛用」と書かれていた)、タール、魚のゼリー…… スコッティはどのような非道徳的な交易品が船中にあるかを想像し、それが絵となって頭の中を巡りめぐった。
残りの荷物を船中に積み終えるまでにバリフィックス船長が言った数分以上かかったが、1時間後には錨は上がり、アセイに向かう流れに乗っていた。草色をした水面はわずかに波立ち、そよ風に頬を撫でられていた。岸には草木が生い茂り、様々な動物が互いに歌いうなり合うさまを隠していた。周りの穏やかな環境によって心を静められたスコッティは、眠りへと落ちていった。
夜起きた彼は、清潔な着替えと食べ物をバリフィックス船長から受け取った。
「聞いてもいいかね? なぜアセイへ行くのだ?」と、ボズマーは言った。
「あそこで、昔の同僚と合流するのです。帝都でアトリウス建設会社の職員だった私に、契約の交渉をするためにここへ来るよう彼が私に依頼したのです」スコッティは、2人で夕飯として分け合っていた干しソーセージを口にした。「最近のカジートとの戦争で破損した橋や道路や建物などの修理と改装をするつもりです」
「この2年間は辛かった」船長はうなずいた。「でも、俺やあんたやあんたの友達にはいいのかも知れんが。交易路は遮断されているぜ。聞いたか? 今度はサマーセット島と戦争になるかも知れないらしいぜ」
スコッティは首を横に振った。
「俺は、沿岸でスクゥーマの密輸をたくさんやってきた、革命家の部類のヤツらでさえ助けてやってきたぜ。でもな、戦争が俺を堅気の貿易商、商売人にしちまった。戦争で出る最初の犠牲者はいつも堕落した人間だ」
スコッティはお気の毒にと言い、2人は沈黙し、穏やかな水面に映る天空の星や月を見ていた。次の日、スコッティが起きてみると、泥酔して動けず、帆に絡まりながら、ろれつが回っていない舌で歌っている船長を目にした。スコッティが起きたのを見ると彼は、ジャッガの大瓶を差し出した。
「ウエスタンクロスのお祭り騒ぎで懲りてるぜ」
船長は笑い、そして突然泣き出し、「堅気になんかなりたくねえ。昔知ってた他の海賊たちは、今でも犯し、盗み、密輸して、あんたみたいな善良なヤツらを奴隷として売りさばいてるんだ。本当に、初めて合法の荷物を運んだとき、俺の人生がこうなるなんて思ってもいなかったぜ。戻れるのは分かってるさ、でもな、いろいろと見てきた後の俺じゃあ無理だ。俺は破滅だ」
励ましの言葉をささやきながら、スコッティは涙を流す海の男が帆から出るのを手伝った。そして、こう付け足した、「話題を変えてごめんなさい、でも、今どこですか?」
「ああ」バリフィックス船長は惨めにうめいた。「予定より早く到着できた。アセイはそこを曲がったらすぐだ」
「では、アセイは火事のようです」と、スコッティは指を差しながら言った。
タールのように黒い、巨大な煙の柱が木の上へと昇っていた。川が曲がっているところを抜けると、炎が見え、そして黒く焼かれ骨組みだけになった村が見えた。火に包まれ、死にゆく村人たちは岩から川へと飛び込んだ。嘆きの不協和音が耳に届き、私の周囲にはたいまつを持ち、歩き回るカジート兵の姿が見えた。
「ああ、神よ!」ろれつの回らない船長が言った。「また戦争だ!」
「何てことだ」と、スコッティは泣きそうになった。
帆船は炎に包まれた街とは反対側の岸へと流された。スコッティは岸と、その安全性に注目した。恐怖から離れた穏やかな木陰。そのとき、2本の木の葉が揺れ、弓で武装した柔軟なカジートが十数名、地上へと降りてきた。
「見られています」と、スコッティはささやいた。「弓を持っています!」
「弓を持っているって? あたりまえだろう」バリフィックス船長はうなった。「あれは俺たちボズマーが発明したかも知れんが、秘密にしておこうとは考えなかった。政治家め」
「今度は矢に火をつけています!」
「そうだな、たまにあることだ」
「船長、撃っています! 火のついた矢で撃ってきています!」
「ああ、そうだな」船長はうなずいた。「ここで肝心なのは、矢が当たらないことだ」
だが、すぐに命中し始めた。そして最悪にも、2度目の一斉射撃で矢が積み荷のピッチに命中し、とてつもなく大きな青い炎が上がった。船と積荷が粉々になる直前に、スコッティはバリフィックス船長をつかんで船から飛び降りていた。冷たい水の衝撃がボズマーを一時的なしらふにした。彼は既に川の曲がりへと全速力で泳いでいたスコッティを呼んだ。
「デクマス先生よ、どこへ向かって泳ぐつもりだい?」
「ファリネスティへ戻ります!」と、スコッティは叫んだ。
「何日もかかっちまう、それに着く頃には皆アセイへの攻撃のことを知ってるぜ! 見慣れないヤツなんか入れてくれないぞ! ここから一番近い下流の村はグレノスだ、そこなら俺たちを保護してくれるかもしれん!」
スコッティは船長のところまで戻り、燃え盛る村の形跡を後に、並んで川の中央を泳ぎ始めた。泳ぎを覚えたことを、彼はマーラに感謝した。帝都地方はそのほとんどが陸地に囲まれていたため、シロディールの多くの子供たちは泳ぎを覚えなかった。もしミル・コラップやアルテモンで育てられていたなら絶望的であったかもしれないが、帝都自体は水に囲まれていたため、男の子も女の子も皆、船がなくても川を渡れた。冒険者ではなく、書記へと育った人たちでもそうである。
バリフィックス船長のしらふの状態は、水の温度に慣れるにつれて薄れていった。冬であっても、ザイロー川は比較的暖かく、それなりに快適である。ボズマーの泳ぎは変則的で、スコッティに寄ってきたり、離れたり、前に出たり、遅れたりしていた。
スコッティが右を見ると、炎は木々が薪であるかのように燃え移っていた。なんとか追いつかれないようにはしているが、後ろからは猛火が流れてきている。左の岸は、アシの葉が揺れ、何が揺らしているのかを見るまでは、問題がないように見えた。今までに見たことがないほど巨大なネコが群れをなしているのである。彼の最悪の悪夢にも匹敵するようなアゴと歯、赤褐色の毛と緑の目を持つ猛獣であった。その獣たちは泳いでいる2人を見つめながら、速度を合わせて歩いている。
「バリフィックス船長、あの岸へもこっちの岸へも行けません、半熟に煮えるか食べられてしまいます」スコッティがささやいた。「腕の動きとバタ足を安定させてください。普段と同じように息を。疲れてきたら言ってください、しばらく背で浮きましょう」
酔っ払いに理性的な助言をしたことがある人ならば、この絶望感を理解できるであろう。ボズマーが海賊時代の小唄をうめいている最中、スコッティは遅くなったり、早くなったり、左右に流される船長の速度にあわせた。同行者を見張っていないときは、岸のネコに注意した。しばらく続いた直線を抜けた後、右方向へと曲がった。違う村が火に焼かれていた。それは、疑いようもなくグレノスであった。スコッティはその赤々と燃え上がる業火を見つめ、その破壊のさまに恐怖した。そして、船長が小唄をやめたのを聞き逃していた。
彼が振り向いたとき、バリフィックス船長はいなかった。
スコッティは濁った川の深みへと何度も潜ってみた。何もできることはなかった。最後の捜索から浮上したとき、巨大なネコは去っていた、おそらく彼もまた溺れたと思ったのであろう。彼は1人で下流へと泳ぎ続けた。川の支流が最後の防壁の役目を果たしたと見え、延焼はそこで止まっていた。しかし、もはや街はない。数時間後、彼は岸に上がることの賢明さを考え始めた。どちらの岸へ、それが難問であった。
決断する必要はなかった。彼の少し先に、大きな焚き火をたいた岩だらけの島が見えた。ボズマーの一行の邪魔をすることになるのか、はたまた、カジートの一行か、彼には分からなかったが、彼はもう泳げなかった。張りつめて痛む筋肉で、彼は自分を岩の上に引き上げた。
教えられる前に、彼らがボズマーの難民であることが分かった。逆側の岸で、彼をつけ狙っていた巨大ネコと同じ種類の生物の死骸が火にかかっていた。
「センチー・タイガー」と、若い戦士の1人が言った。「ただの動物ではないです―― キャセイ・ラットやオームスや他のカジートと同等の賢さがあります。こいつは溺れてしまっていたので残念です。生きていれば、喜んで殺してやったのに。肉は気に入ると思います。こいつらは砂糖をたくさん食べるせいで、肉は甘いんですよ」
人間ほど知的な生物を食べることができるかどうかスコッティには分からなかったが、ここ数日間やってきたように彼はその行動に自分自身が驚いた。肉は味わい深く、みずみずしく、豚の砂糖漬けのように甘かったが、味付けは何もされていなかった。食べながら彼は、集まった人々を見渡した。悲しげな集団、中には失った家族を想い、いまだに泣いているものもいる。彼らはグレノスとアセイの両方の生き残りであり、全員が戦争のことを話していた。どうして―― はっきりとシロディール出身のスコッティに向けられた言葉である ――どうして皇帝は彼の領土の安全を守らないの?
「シロディール人と合流するはずだったのですが……」彼は、アセイ出身であると踏んでいたボズマーの娘に言った。「彼の名前はリオデス・ジュラス。彼に何が起きたか知りませんか?」
「あなたの友達は知りませんが、街に火がついたときにもアセイにはシロディールがたくさんいました」と、娘は言った。「そのうちの何名かは急いで逃げたと思います。彼らは内陸のジャングルの中にあるヴィンディジへ向かっていました。私や他の大勢も明日そこへ行きます。もし望むのであれば、一緒にどうぞ」
デクマス・スコッティは厳かにうなずいた。岩でゴツゴツしている川の島、彼はできるだけ自分の気持ちを落ち着けようとした。そして努力の末、どうにか彼は眠りに落ちた。しかし、その眠りはあまり深くなかった。
火中に舞う 第4章
ウォーヒン・ジャース 著
18人のボズマーと1人の帝都建設会社の元事務員デクマス・スコッティは、重い足取りでジャングルの中を西へ、ザイロ川からヴィンディジの古い集落へと向かっていた。スコッティにとって、ジャングルは敵意に満ちていて居心地が悪いところだった。巨大に生い茂った木々が明るいはずの朝の日差しを闇で覆ってしまい、彼らの進行を妨げる邪悪な爪のようだった。低木の葉でさえも、邪悪な力によって震えているかのように見えた。さらによくないことに、不安そうなのは彼だけではなかった。彼と共に旅をしているのは、カジートの攻撃を生き延びたグレノスやアセイヤーの地元民だが、その顔は明らかに恐怖におびえていた。
ジャングルの中には何かの感覚、単なる乱心ではなく、その土地固有の慈悲深い精神を感じさせる何かがあった。それでもスコッティは視野の端に、自分たちのあとをつけ木々の間を飛びかいながら移動するカジートの影をとらえていた。だがスコッティがその影のほうに目を向けると気配は瞬時に消えてしまい、そこには最初から誰もいなかったような、ただの暗闇となってしまうのだった。しかし、彼らに見られていることは確実だった。ボズマーたちも彼らの姿に気づき、歩くペースを速めた。
18時間歩いて、虫に喰われ、何千というとげにひっかかれ、ようやく開けた渓谷へと出た。既に夜になっていたが、渓谷には松明の灯りが彼らを歓迎しているかのように一列に並び、ヴィンディジの集落の皮製のテントやそこらじゅうに転がる石を照らしていた。渓谷の端には松明で囲まれた聖域があった。筋くれだった木々が積み重ねられ、神殿を形作っていた。無言のままボズマー達は松明の列の間を通り、神殿へと向かっていった。スコッティも彼らのあとをついていった。密集した木々の一角にぽっかり口をあけた門にたどり着くと、その奥から青白い光が漏れていた。中では何百人ものうめき声が反響しあっていた。スコッティの前にボズマーの娘が手をかざし、彼を止めた。
「あなたには理解できないでしょうが、外の人はいくら友人でも入れないわ。ここはあたしたちの聖域なのよ」
スコッティは頷き、彼らが頭を下げながら神殿の中へと入っていくのを見ていた。最後列にいたウッドエルフが中に入ってしまうと、スコッティは振り返って村の方を見てみた。あそこなら間違いなく空腹を満たせるものがあるだろう。松明の向こうに見える、一筋の煙と鹿の肉が焼かれる微かなにおいが彼を導いた。
そこには5人のシロディールと2人のブレトン、そして1人のノルドがいた。彼らは白く焼けた石の焚き火を囲み、細長く裂いた大鹿の肉を蒸し焼きにしていた。スコッティが近づくと、そこにいた全員が立ち上がった…… いや、正確には1人を除いて。ノルドだけは目の前の大きな肉の塊に目が釘付けだった。
「こんばんは。お邪魔して申し訳ない。私に少し何か食べ物を分けていただけませんか? グレノスとアセイヤーから逃げてきた人たちとここまで1日中歩いてきて、とても空腹なのです」
彼らはスコッティに座って一緒に食べるように勧めた。そして自己紹介をした。
「戦争が再び始まってしまったようですね」と、スコッティは愛想よく言った。
「触らぬ神にたたりなしだ」と、ノルドが肉をほおばりながら言った。「俺はこんなにふざけた文明を見たことないよ。陸ではカジートと、海ではハイエルフたちと戦っている。こんな仕打ちを受ける価値がある場所は、あのムカつくヴァレンウッドぐらいなもんだ」
「しかし、ヴァレンウッドのやつらは、別にあんたのことを嫌ったりしてないだろう」と、ブレトンの1人が笑いながら言った。
「やつらは生まれながらの悪党さ。優しい顔して侵略するところはカジートよりもたちが悪い」ノルドは脂のかたまりを焼けた石に吐き出し、ジュージュー音をさせた。
「徐々に、自分たち領土の森を他国にまで広げていくんだ。だが、思いがけずエルスウェーアの反撃をくらい、慌てふためいているってわけさ。俺はあれほどの悪党は見たことがないね」
「あなたはここで何をしているんですか?」とスコッティは尋ねた。
「俺はジェヘナの宮廷の外交屋さ」とノルドは食べ物の方を向きながらつぶやいた。
「あなたは? 一体ここで何をしているのですか?」とシロディールの1人が聞いた。
「私は帝都にあるアトリウス建設会社で働いています。以前一緒に働いていた仲間から手紙をもらい、ヴァレンウッドへ来るようと書かれてました。もう戦争が終わったので、壊れた建物を建て直す仕事をしている私の会社と大口の契約を結べるだろうというのです。しかし、災難に次ぐ災難で、ここにくるまでに全財産を失い、戦争は再び始まりそうだし、手紙をくれた仲間にも会えないしでほとほと困っています」
「その昔の仲間というのは……」もう1人のレグリウスと名乗るシロディールが小声で言った。「もしかしてリオデス・ジュラスという名ではありませんか?」
「彼を知っているのですか?」
「私もあなたと同じように彼から誘いを受けて来たのです」レグリウスはいやな笑いを浮かべた。「私はあなたの会社とはライバルのヴァネック卿の元で働いており、リオデス・ジュラスも以前そこで一緒に働いていました。私も彼から手紙をもらいました。戦で倒壊した建物の再建を手伝わないか、とね。私はちょうどその時、会社をクビになったばかりでしてね。これは何かのチャンスだと思いましたよ。彼とはアセイヤーで会い、シルヴェナールともっと儲けのいい話をするつもりだと言っていました」
スコッティは叫んだ。「彼は今、どこにいるんですか?」
「私は神学者ではないから、なんとも言えませんが……」とレグリウスは肩をすくめた。「おそらく彼は死にましたよ。カジートがアセイヤーを攻撃した時、奴らはジュラスが彼の船を泊めていた港に火をつけ始めました。あ、いや、私の金で買ったものだから『私の船』ですが。何がなんだかわからないままに、気づいた時には何もかもが燃やされて灰になってました。カジートは動物かもしれませんが、攻撃の心得はあるようですね」
「カジートはヴィンディジのジャングルを通って我々を尾けてきていました」と、スコッティは神経質に言った。「あの梢のあたりを飛び回っていたのは間違いなくやつらの仲間だ」
「ただの猿人の類じゃないのか?」ノルド人はせせら笑うように言った。「何も心配することはねえよ」
「私たちが最初にヴィンディジに入った時、ボズマーが皆あの木のとこに入って行ったんです。彼らは怒りながら“古代の恐怖を我らの敵に解き放て”というようなことをブツブツ言っていました」と言ったブレトンは、その時の情景を思い出し、ブルブル震えていた。「それから1日半もの間、こもったきりなんです。心配なら、あそこを調べてみたらいいんじゃないですか?」
ダガーフォールの魔術師ギルドの代表者と自己紹介したもう1人のブレトンは、仲間が話している間、暗闇を見ていた。「どうもジャングルの中にも何かいるようだな。村の右の端の方を見ている」
「戦から逃れてきた人たちでは?」スコッティは自分が警戒しているのを悟られないような声で尋ねた。
「この時間帯に木々を抜けてくるとはおかしいだろう」とウィザードは小声で答え、ノルドとシロディールの1人が湿った皮のシートを引っ張り出して火にかぶせた。火はたちまちに静かに消えた。ようやくスコッティにも侵入者たちの姿が見えた。彼らは楕円形の黄色い目を持ち、長剣と松明をかかげていた。スコッティは恐怖で固まり、敵に見つかっていないことを願った。
彼は何かに背中を押されたのを感じ、はっと息を飲んだ。
レグリウスが頭上からささやいた。「たのむから静かにしてここを登って」
スコッティは消えた焚き火の横の高い木から垂れ下がる、2本の蔓を結んだロープをつかんだ。彼は急いでそのロープをよじ登り、その努力を無に帰さないように必死に息を殺した。頭上高くのロープの先には、三つ又に分かれた枝の上に乗った、かつて巨大な鳥がこしらえたであろう巣が打ち捨てられていた。スコッティが柔らかく、ワラのいいにおいのする巣の中へともぐりこむと、レグリウスはロープを引き上げた。そこには他に誰もおらず、下を覗いてみるとそこにも誰もいなかった。カジート以外には。彼らは神殿の灯りにむかってゆっくりと進んでいった。
「ありがとう」とスコッティはささやいた。ライバル会社の人が助けてくれたことに深く感謝していた。集落から目を離して辺りに目をやると、より上の方の枝が苔生した渓谷を囲む壁にもたれかかっていることに気づいた。「もっと上に行きましょう」
「バカ言うんじゃない」と、レグリウスは息を殺して言った。「奴らがいなくなるまでここに隠れていよう」
「アセイヤーやグレノスにしたように、カジートがヴィンディジに火をつけたら、私たちは地上にいるのも同然で、確実に死んでしまう」と言うとスコッティは、ゆっくりと用心しながら枝を確かめつつさらに上へと登っていった。「彼らの動き、わかりますか?」
「どうだろうね」とレグリウスはじっと薄暗い中を目をこらして見ていた。「奴ら、神殿の前に集まっている。何か手に持ってるな…… 長いロープみたいだ。前後に垂れ下がっている」
スコッティは表面が濡れてごつごつした崖に向かって伸びる枝の中で一番丈夫そうなのを選び、その上を這っていった。決して距離のあるジャンプではない。実際、石の湿った、ひんやりとするにおいが嗅げそうなほどの距離だった。しかし、一会社員として過ごしてきた彼の人生の中で地上から高さ100フィートもあるところから切り立った岩までジャンプする経験など皆無であった。彼はジャングルで頭上よりもうんと高いところから彼を尾けねらってきた影の動きを思い描いた。彼らのバネがついてるかのような脚、しなやかにものをかっさらおうとする腕。そして彼は飛んだ。
スコッティは岩をつかんだが、縄のように長く厚い苔のほうがつかまりやすそうだった。彼は苔にしっかりつかまって足を前に出そうとしたその時、足がすべって、宙に浮いた。体勢を整えるまでの数秒間、自分が上下さかさまになっているのがわかった。崖から突き出た細い岩のようなところがあり、彼はそこに立ってようやく息をついた。
「レグリウスさん、レグリウスさん」と、スコッティは声にならない声で呼びかけた。しばらくして、枝がゆれ、ヴァネック卿の元部下が、まず彼の鞄、頭、そして残りの部分の順番で姿を現した。スコッティは小声でなにか言おうとしたが、レグリウスは激しく首を振り、下を指差した。カジートの1人が木の下で焚き火の跡をじっと見ていた。
レグリウスは不恰好に枝の上でバランスをとろうとしたが、片方の手だけでそれをやるのはあまりにも困難だった。スコッティは両のひらを丸めてみせ、次に鞄を指差した。レグリウスは嫌そうだったが、鞄をつかみ、スコッティに投げてよこした。
鞄には目に見えないほどの小さな穴が開いており、スコッティが鞄をキャッチした時にゴールドが1枚、下へと落ちてしまった。ゴールドは岩壁に当たって、高く柔らかい音をたて落ちていった。今までに聞いたことがないほど大音量のアラーム音のようだった。
そしてたくさんのことがいっぺんに起きた。
木の下にいたキャセイ・ラートは上を見て、おたけびの声をあげた。そのほかのカジートたちもその声に呼応して、猫のように身をかがめたかと思うと、跳ね上がり、下の枝に飛び移った。レグリウスは、ありえない器用さで上ってくるカジートの姿を自分の下に見てパニックに陥った。スコッティが「絶対に落ちる」と言う暇もなく彼はジャンプした。悲痛な叫び声をあげながら、レグリウスは地面に落下し、衝撃で首を折った。
その時、神殿のあらゆる隙間から白炎の閃光が一気に噴き出した。ボズマーの詠唱の声はもはや乱心じみており、この世のものとは思えないほどになっていた。気を登っていたキャセイ・ラートも動きをとめ、神殿のほうをじっと見た。
「キアゴーだ」とキャセイ・ラートは言って息をのんだ。「荒野の狩人だ」
それはまるで現実世界に裂け目が入ったような光景であった。神殿から恐ろしい獣たち── 全身から触手が生えたヒキガエル、硬い鎧と鋭い棘をもった虫、体表がねばねばした大蛇、神々の顔をした霧状の化け物、これらすべてが怒りに我を失ったように勢いで神殿から飛び出してきた。それら恐ろしい獣たちはまず神殿の前にいたカジートたちの体を引き裂いた。それを見たほかのカジートたちは一目散にジャングルの中へ逃げ込もうとしたが、自分たちの持っていたロープに足をとられた。瞬く間に、ヴィンディジの集落は荒野の狩人たちの幻影の乱心のるつぼと化した。
言葉にならない叫び声や、獣の群れがあげるおたけびの声が蔓延する中、身を隠していたシロディール、ノルド、それと2人のブレトンも全員見つかってしまい、貪り喰われてしまった。ウィザードは自分の姿が見えないよう呪文をかけていたが、視覚に頼らない虫たちにはせっかくの魔法も無力であった。木の下にいたキャセイ・ラートが想像できないほどの力で木を揺さぶり始めた。このカジートの恐怖におびえる目を見て、スコッティは縄状の太い苔を1本、彼に向けて差し出した。
スコッティに差し出されたロープにつかまろうとするカジートの表情は痛ましいほどの感謝の念であふれていた。スコッティがそのロープを引っ張ろうとするとカジートはその表情を変える間もなく落下していった。彼は地面に落ちる前に荒野の狩人に骨まで食いつくされた。
スコッティもその場から逃げようと別の突出した岩に向かって飛びうつった。思いのほかうまくいった。そこから崖の頂上へとよじ登り、ヴィンディジの変わり果てた姿を一望することができた。獣たちの群れはだんだんと膨れ上がり、その数は谷全体へと広がり、逃げ惑うカジートたちを追っていた。その光景はまさに地獄絵だった。
月夜に照らされ、スコッティのいるところからはカジートたちがロープを取り付けようとしていた場所が見えた。その時、雷のような轟音が鳴り響き、雪崩のように次々と巨石が転がってきた。粉塵がおさまると、谷は巨石によって完全に封鎖されてしまった。荒野の狩人たちはそこにとどまった。
スコッティはこれ以上の人食いの饗宴を見ていられず、顔をそむけた。眼前には網の目のように木々の生い茂るジャングルが広がっていた。彼はレグリウスの鞄を肩にかけ、再びジャングルの中へと入っていった。
火中に舞う 第5章
ウォーヒン・ジャース 著
「せっけんだ! この森は愛を食べて生きている。まっすぐ進め! このマヌケでアホな牛め!」
スコッティがジャングルへ降り立つと、すぐにその声が響いてきた。彼は、薄暗い林の空き地をじっと目を凝らしてみたが、そこから聞こえてくるのは、動物や虫の鳴き声、風のざわめきだけだった。先ほどの声は、非常に奇妙で風変わりなアクセントがついており、性別もはっきりせず、震えるような抑揚だが、人間のものであることは間違いないようだ。あるいは、ひょっとしたらエルフの声かもしれない。おそらく、1人でいるボズマーが、たどたどしくシロディール語を喋っているのだろう。何時間もの間ジャングルをさまよった後では、どんな声でも少しは親しみが持て、すばらしく聞こえた。
「こんにちは!」とスコッティは叫んだ。
「カブトムシの名前は? 確かに昨日だった、そうだ!」と言う声が返ってきた。「誰が? 何を? いつ? そしてネズミ!」
「あなたの言ってることがよく分からないんですが」とスコッティは答えた。声がする方向に、荷馬車ほどの太いイチゴの木があり、それに向かって「こわがらないで下さい。私は、帝都から来たシロディールで、デクマス・スコッティと言います。戦争後の再建のお手伝いをしに、ヴァレンウッドへと来ました。ですが、道に迷ってしまいまして」
「宝石の原石に、じっくりと焼かれた奴隷達…… 戦争」そのうめき声は、すすり泣きへと変わっていった。
「戦争について何か知っているんですか? 私は何も知らなくて。ここが国境からどれだけ離れてるかとかも知らないんです」と言ってスコッティは、ゆっくりとその木へと寄っていった。レグリウスの鞄を地面に置き、空いた手をそこに差し出した。「武器は持っていません。私はただ一番近くの街までの行き方を知りたいだけなんです。シルヴェナールで、リオデス・ジュラスという友人と会わなければならないんです」
「シルヴェナールだと!」と声は笑った。スコッティが木の周りを回っていると、さらに大きな笑い声が聞こえてきた。「虫とワイン! 虫とワイン! シルヴェナールの歌は、虫とワインのためだ!」
木の周りには何も見つけることができない。「どこなんです? どうして隠れているんですか?」
空腹と疲労でイライラが爆発し、彼は、その木の幹をたたいた。突然、木の空洞の上の方から、金色と赤色の小さなものが飛び出して来た。それは6つの翼を持った数インチたらずしかない生物で、スコッティは取り囲まれた。トンネルのようなこぶの両側に深紅色の眼がついており、口は常に半分開いていた。彼らに脚はなく、素早く羽ばたかせているその美しい薄い翼は太って張り出した腹を運んでいるかのようだった。しかし、彼らは、火花が散るような速さで、空中を俊敏に動くことができた。そして、かわいそうな事務員の周りをぐるぐる飛びながら、もはや全く意味不明な事を喋り出してしまった。
「ワインと虫、私は国境からどれだけ離れているのか! 学術的美辞麗句、ああ、リオデス・ジュラス!」
「こんにちは、私は武器を持っていなくて怖いよ。煙の巻きあがる炎と一番近い街は、親愛なるオブリビオン」
「太って悪い肉、藍で染めた光の輪、でも、私を怖がらなくていい!」
「どうしてあなたは隠れてるの? どうして隠れてるの? 友達になる前に、私を愛して、ズレイカ様!」
自分の言ったことを真似されるのに腹を立て、スコッティは腕を振り回して彼らを木の上へと追い払った。彼は足を踏み鳴らして森の開けたところまで戻り、数時間前にもそうしたように、レグリウスの鞄を開いて覗いた。もちろん、何か役に立ちそうなものも食べられそうなものも、その鞄のどのポケットにも入ってはいなかった。あるのは、かなりの量の金(ジャングルの中でも、金で問題解決できるだろうさ、と彼は皮肉気に前と同じく口元を歪めた)と、ていねいに畳まれた空白のヴァネック建設会社の契約書、何本かの細い縄、油を塗った防水具。「少なくとも……」とスコッティは思った。「雨の心配はいらないな」
雷のとどろく音が聞こえ、彼は、ここ何週間か思っていたことを確信した。自分は呪われている、と。
その後一時間の間、スコッティは鞄の中にあった防水具を着け、泥の中を這うように進んで行った。森は日光を通さないが、暴風雨には簡単に許してしまう。耳に入るのは、激しく降る雨の音に、頭上でひらひらと飛び、戯言を繰り返す例の生物の声だけだった。彼はその生物に怒鳴り声を上げ、石を投げつけたが、彼らはスコッティを気に入ってしまったようだ。
自分を悩ます奴らに投げつけようとスコッティが大きな石に手を掛けたそのとき、彼は足元がぐらつくのを感じた。雨で地面がぬかるんでいたため突然足元がすべり、潮のようになって、スコッティはまるで小さな木の葉のごとく上下逆さになりながら流されて行った。泥の洪水がおさまるまで、彼は滑り落ち、遂に、25フィート下の河に突っ込んだところで停止した。
嵐は、やって来たのと同じくらい唐突に去って行った。太陽が暗雲を吹き飛ばし、スコッティが海岸へと泳ぐ間、彼の体を温めてくれた。そこにも、カジートがヴァレンウッドを襲撃したことを示す気配があった。近くには小さな漁村があったが、最近になって打ち捨てられたのか、ほとんど活気は無く、死にたての屍のようにくすぶっていた。泥で作られた家も荒廃して灰に戻っており、かつてはそこに積み入れられていたであろう魚の匂いがこびり付いていた。イカダや小船は壊れたまま放置されており、半分が水に浸かってしまっていた。住民の姿はもはやなく、もし誰かいるのならば、死体か、遠くから避難して来た者だろうと思った。何かが廃墟の壁にぶつかる音が聞こえてきた。彼は急いで調べに行った。
「私の名前はデクマス・スコッティですか?」と1匹目の翼の生えた獣が歌った。「私はシロディールですか? ボクは帝都から来たのですか? 私は、戦争後のヴァレンウッド再建のため来たのですが、ここで迷子になってしまったのですか?」
「私は、膨れて、汚れて、猿頭だ!」ともう1匹の仲間が賛同した。「あなたはどこですか? どうして隠れているんですか?」
彼らが喋っているのを尻目に、スコッティは村の他の場所を調べ始めた。野良猫があちこちの物陰に乾ききった肉のかけらや、ひと口サイズの魚肉ソーセージなどを隠していた。しかし、猫たちはこんな壊滅的状態にありながらも汚れた身なりではなかった。食べ物もろくにないだろうに。歩いているうち、かつては石造りの小屋だったであろうあばら家の下から、使えそうな道具を見つけた。骨で出来た弓と2本の矢だ。弦はなくなっていた。火事で燃やされてしまったのだろう。彼はレグリウスの鞄から縄を取り出すと、それで修理した。
その作業の間、あの生き物たちが、彼の頭上を飛び回っていた。「聖リオデス・ジュラスの修道院か?」
「あなたは戦争について知っています! 虫とワイン、黄金色の主人を束縛しなさい、猿頭!」
弦を張り直して、弦を胸まできつく引いたまま弓をつがえて、ぐるりと回してみた。翼のついた獣たちは射手を前にした経験があったようで、霞のほうへ一目散に逃げ去った。スコッティが最初に放った矢は、3フィートほど飛んで地面の上に落ちた。彼は悪態をつき、矢を拾った。マネをする生き物たちは、腕の悪い射手を前にした経験もあったようだ。一度は退散した彼らはスコッティの頭上に戻って来て、嘲笑した。
二回目は、技術面に限って言えば、かなり上達した。彼はホアヴォアーの下から飛び出た時に、ファリネスティの射手達がどんな風に矢を用いていたか、どうやって全員が自分を狙っていたかを思い描いた。両腕を伸ばし、右肘を均等に引いた。弓を引くと右手が下顎をかすめた。矢が指先のように視界のあの生き物を指しているように見えた。しかし矢は的を2フィートほど外し、そのまま石壁に当たって折れた。
スコッティは河岸を歩いていた。もう矢は1本しか残されていなかった。動きの鈍い魚を見つけてこの矢で仕留めるのが現実的だと考えた。弦さえ壊れない限り、外した矢は何度でも河底から持って帰ればいいのだから。彼の前を、ひげのついた魚がゆったりと過ぎ去っていき、彼はそれに狙いを定めた。
「私の名前はデクマス・スコッティ!」あの生き物の1匹がうなり声をあげ、その魚を驚かせてしまった。「この、マヌケでアホな牛め! お前は火の中で踊れ!」
スコッティは、さっきと同じようにその生物を狙ってみた。今度はあの射手たちのような姿勢をとることが出来た。足幅は7インチ開き、膝は伸ばしたまま、右肩を後ろに引くのに合わせて左脚は心持ち前に出す。そして、彼は最後の矢を放った。
どうやら、この矢は例の生物をその矢で串刺しにしたまま廃墟の石の上で焼くのにも便利なようだ。仲間の死を目にした他の連中はすぐに退散してしまったので、彼は、静かに食事を楽しむことができた。その肉はとてもおいしく、一級品のものとなんら変わりがなかった。彼が最後の一口を矢から引き抜いていると、蛇行した河の向こう側から1隻の船が近付いて来るのが見えた。舵を握っているのはボズマーの船員だった。彼は、急いで岸に走り寄り、手を振った。彼らは、顔を背けたまま通り過ぎて行ってしまった。
「なんて残忍で冷酷な奴らだ!」とスコッティはわめいた。「この、悪人、悪党、悪漢、猿頭め!」
そのとき、灰色の頬ひげの男が1人、ハッチから顔を出した。すぐに、それがグルィフ・マロン、シロディールからのキャラバンで一緒だったあの詩人兼翻訳家だったと分かった。
マロンは彼のほうをじっと見てすぐに喜びで目を輝かせて言った。「スコッティ! 君に会えて嬉しいよ。そうだ、ムノリアダ・プレイ・バーの難解な一節について考えを聞かせていただきたい!『世界に涙を流そう、不思議な事物を求めて』で始まるのです。もちろんご存知でしょう?」
「グルィフ、もちろんムノリアダ・プレイ・バーについてお話ししたい」とスコッティは返した。「ではまず、その船に乗せてくれますか」
どんな港を目指していようが船に乗り込めたことに喜んでいようが、スコッティは約束を守る男であった。この船がボズマーの村々の焼け焦げた廃墟を通り過ぎながら河を下っていく間、彼は、何の質問もここ数週間の身の上話もせずに、マロンのアルドメリ神話の密義に関する自分なりの解釈をじっと聞いていた。彼は、学術的知識を要求することなく、単に頷いたり肩をすくめてみせたりするのも、教養ある会話の方法として受け取ってくれた。しかも、上の空にしている彼にワインや魚肉ゼリーさえ振る舞いながら、いくつもの論文を並べて講釈を垂れるのであった。
マロンが些細な引用をノートに探しているとき、ようやくスコッティは質問した、「講釈の内容には劣るのですが、この船は一体どこに向かっているんでしょう?」
「この地方の中心地区、シルヴェナールですよ」読んでいる一節から目も離さずに、マロンは答えた。「ちょっと厄介なのは、僕はまずウッドハースで、ディリス・ヤルミヒアッドが書いたものの原本を持っているというボズマーに会いに行きたかったんです。信じられます? そうは言っても、こうして待っている他はないんですが。ところで、サムーセット島は都市を包囲して、あそこが降伏するまで住民たちを飢えさせ続けるようです。いやな想像ですが、ボズマーは、喜んで共食いするでしょうね。最後に残った1人の太ったウッドエルフが旗を掲げることになる危険がありますよ」
「まったく面倒な話です」スコッティも同じ気持だった。「東の方では、カジートが何もかも焼き払っている。西の方では、ハイエルフが戦いを始めている。北の境界は大丈夫なのでしょうか?」
「もっと悪いですよ」といくらかこちらに気を向けて、マロンは答えた。「シロディールとレッドガードは、ボズマーの避難民を受け入れたがっていない。もちろん、理由はある。彼ら避難民は家も無ければ食物も無い。そんな彼らを受け入れたら、どれだけ犯罪が増えることか」
「そうですね」とちょっとした寒気を感じながら、スコッティは呟いた。「どうも、ヴァレンウッドに足止めされているようですね」
「まったくだ。出版社の方に新しい翻訳本の締め切りが近いと言われているので、早く行きたいのだが。シルヴェナールに特別国境警備の請願書を出せば、無事にシロディールに戻れるようですよ」
「シルヴェナールに請願するのですか? それとも、シルヴェナールで請願するのですか?」
「シルヴェナールでシルヴェナールに請願するんです。この地方独特の奇妙な言い回しで、翻訳家としても興味をそそられるところです。それで、シルヴェナールというのは、彼、いや、彼らと言った方がいいと思うが、彼らは、ボズマー達に最も近しい指導者なのです。で、彼らについて覚えておくべきことは……」とマロンは笑みを浮かべて、とある一節を探り当てた。「これだ。『14の夜、不可解な、世界は踊りだす』これもまた比喩ですな」
「シルヴェナールについて、何ですって?」とスコッティは尋ねた。「覚えておくべきこと、というのは?」
「そんなこと言ったかな」マロンはそう返すと、講義の続きに戻ってしまった。
それから1週間、船は浅瀬に何度かぶつかりながらも、ザイロ川の水面を泡立てながら緩やかに進んで行き、スコッティはシルヴェナールの街を初めて目にすることが出来た。ファリネスティが1本の木ならば、シルヴェナールは1輪の華である。緑、赤、青、白の落ち着いた陰影が壮大に積み重ねられて、水晶で出来た他の部分と共に輝いている。途端に、マロンは何も見ずにまくし立て始めた。こんな風にするのは、アルドメリの作詞法を解説する時くらいのものだ。「この街はこうして森の開けたところに華を開いているのだが、これは、何かの魔法や偶然によるものではない。と言うのも、ここに生えていた木々が半透明の樹液を流して、その樹液でこうして華やかな色の木々が固められて、そして、そこに街並みが造られたのです」そのマロンの説明は興味深いものだったが、スコッティには、この街の美しさを堪能している余裕は無かった。
「すみません、このあたりで一番豪華な宿屋は?」と彼は、ボズマーの船員に尋ねた。
「プリサラホールですよ」マロンが答えた。「私も一緒に泊まっていいですか? この近くに、知り合いの学者がいるんです。会えば、きっと君も気に入ると思うな。彼の家は家畜小屋みたいですけど、アルドメリ神話の氏族、つまりサルマチについては独自の解釈を持っていて──」
「状況が違えば、喜んで何でも受け入れるのですが」とスコッティは微笑んで言った。「でも、この数週間、ずっと地面や小汚い船の中で眠ったり、食べられる物は何でもかき集めたりしなくちゃならなかったんです。おまけに、忌々しい翼を生やした生き物にも、随分と寛大な態度で臨まなくちゃならなかった。明日か明後日あたりにはシロディールへ安全に帰れるように、シルヴェナールに頼みに行ってみます」
2人は互いに別れの挨拶を交わした。マロンは帝都にある出版社の住所を教えたが、スコッティは迅速にそれを忘れることにした。スコッティはシルヴェナールの街並みをぶらついたり、琥珀色の橋を渡ったり、石化した木々で出来た家々に感心したりした。そうして、銀色に輝く水晶で造られた、とりわけ立派な豪邸を見つけた。そこが、プリサラホールであった。
彼は最上級の部屋を頼むと、これも最上級の食事を大量に頼んだ。彼の着いたテーブルの近くでは、ひどく肥えた2人の男、1人はシロディールでもう1人はボズマーだが、ここの食事とシルヴェナール宮殿のものとどちらがおいしいかの議論を交わしながらも、議論の主題は、現在の戦争や資金繰りの問題、そして、この地方の橋の再建へと移って行った。片方の男がスコッティの視線に気付いたのか、彼の方を見返すと、何かに気付いたような目つきになった。
「スコッティか? なんてこった、どこにいたんだ? ここいらの契約、俺1人で取りまとめなくちゃならなかったんだぞ!」
その声には聞き覚えがあった。その太った男はリオデス・ジュラスで、やたらと食べていた。
火中に舞う 第6章
ウォーヒン・ジャース 著
デクマス・スコッティは、座ってリデオス・ジュラスの話を聞くことにした。だが、いまだにこの眼前の太った男が、かつてのアトリウス建設会社の同僚であるとは信じられなかった。辺りには、スコッティがさっきまで食べていたロースト肉の、香辛料の匂いが立ち込めている。この広いプリサラホールの中の周囲の物音はすっかり消え失せていて、まるでジュラス1人しかいないようである。彼は自分がこれほど感受性豊かであることに驚いてしまったが、実際のところ、霜降月初旬に下手な手紙で帝都から彼を導いてくれた男を前に、潮が満ちていくような感慨を味わっていた。
「どこにいたんだ?」と、ジュラスは詰め寄った。「何週間か前には、ファリネスティで俺と落ちあうはずだったろ?」
「もちろん、そこに行ったさ」あまりの剣幕に驚いて、スコッティはどもりながら返した。「そこで『アセイヤーに行け』っていう君のメモを見て、そこに行ったんだが、カジートが焼き払ってたんだ。それで、避難民達と別の村へ行くことになって。その村で、君がもう殺されたって聞いたんだけど?」
「お前、そんなこと信じてたのか?」と、ジュラスがせせら笑った。
「それを教えてくれた人は、君のことをよく知ってたから。レグリウスっていうヴァネック建設委員会の人で、彼も私と同じように戦争の後のヴァレンウッドの仕事を手伝うよう誘われたと言っていたよ」
「ああ、そうだったな」とちょっと考え込んでから、ジュラスは言った。「たった今、その名前を思い出したよ。この商売、きっと上手くいくぜ。何たって、帝都を代表する建設委員会の2人が、工事の入札の手筈を調えるのを手伝ってくれるんだからな」
「レグリウスさんは死んだよ」と、スコッティは言った。「でも、ヴァネック建設委員会の契約書は持って来たけど」
「おお、上出来だ!」と、ジュラスは感嘆の声を上げた。「ふん、お前がそこまで無慈悲になれる奴だったとはなぁ、スコッティ。まぁ、これでシルヴェナールの仕事もやり易くなったな。バスの紹介はまだだったな?」
スコッティはジュラスの隣にいる、ジュラスと同じ位の胴回りを持つボズマーの存在にはぼんやりとしか気付いていなかった。スコッティはバスにそっけなく目礼をしたが、まだどこかうわの空の気持であった。彼の頭には、シロディールへ安全に帰れるように、できるだけ早くシルヴェナールへ嘆願する、ということしかなかった。その後ジュラスと、ヴァレンウッドとエルスウェーアやサムーセット島との戦争からどうやって稼いでやろうか算段している時も、どこか他人事みたいに思えてならなかった。
「俺とあんたの同僚は、いまシルヴェナールについて話してるんだぜ?」と、今までかじっていた羊の脚を置きながら、バスは言った。「ちゃんと話を聞いてないようだが」
「少しぼんやりしてました。シルヴェナールというのは、とりわけすごい人なんですね」
「彼は民衆の代表なんだよ、法律的にも物理的にも精神的にも」と、新しい相棒の常識の無さに苛々しながら、ジュラスが説明してくれた。「ここの連中が健康なのも、ほとんど女ばっかりなのも、彼のおかげだ。もしも庶民が、食べ物や商売や外国からの邪魔に不平を漏らしたら、彼は連中と同じ気持になってその不平を避ける法律を作るのさ。つまり、彼は独裁者なのさ。ただし、民衆のためのだ」
「それは……」スコッティは適当な言葉を探し出した。「戯言だね」
「そうかもしれない」バスは肩をすくめてみせた。「だが、彼は、『民衆の声』という多大な権限を持ってる。その中には、外国の会社による建設許可や契約交換を認可する権利も、もちろん含まれている。信じてくれなくても構わんが。シルヴェナールをお前の所の頭のイカれた皇帝、例えばペラギウスみたいなもんだと考えてみてくれ。今現在、このヴァレンウッドは四方八方から攻撃されてかなり参ってる。シルヴェナールも、よそものに対してはすっかり不信と恐怖を抱いてる。たった一つの民衆の望み── つまりは、シルヴェナールの望みでもあるが── は、帝都が介入してこの戦争を終わらせることだ」
「皇帝が?」と、スコッティが尋ねた。
「あのイカレた皇帝に期待するのは無理かも知れんが」と言いながら、ジュラスはレグリウスの鞄から、空白の契約書を取り出した。「実際、あいつがどうするかなんて誰にも分からん。それより、レグリウス様のおかげで、随分と仕事がスムーズに行きそうだ」
彼らは、シルヴェナールと会うとき、どうやって自己紹介するかについて夜まで話し合った。スコッティは食事をつづけていたが、残りの2人ほどの量ではなかった。太陽が丘に登り始め、光が水晶の壁を通して3人を赤々と照らした。ジュラスとバスは、シルヴェナールに会いに行く代わりに、自分たちの部屋へ戻っていった。スコッティは、自分の部屋に戻ってジュラスの計画に穴が無いかどうか考えを巡らせていたが、冷たく柔らかいベッドに抱かれて、すぐに深い眠りへと落ちてしまった。
次の日の午後にスコッティは目覚め、体の調子が良いのを感じた。言い換えると、おびえてもいた。考えてみれば、この数週間、ずっと生死をさまよっていたようなものだった。極限の疲労を味わったり、ジャングルで獣に襲われたり、飢えてげっそり痩せ細ったり、おまけに、アルドメリの詩作についての議論に巻き込まれたりしたのだ。それに、ジュラス達との、どうやってシルヴェナールを騙くらかして彼の署名入りの完全に合法な契約書をこしらえるか、という討論もあった。そんなことを考えながら着古しの服に着替えると、食べ物とゆっくり考え事ができる場所を求めて階段を下りた。
「起きたか」というバスの声がスコッティの頭上から降って来た。「今から宮殿に行くぞ」
「今から?」と、スコッティは愚痴をこぼした。「見て下さいよ、この格好。今から女を買いに行くのとはわけが違うんですよ。『ヴァレンウッドの民衆の声』とやらは、あなたが独りで届けてきて下さい。風呂にも入ってないんです」
「いいか、この瞬間から、お前は事務員じゃなくて商人見習いだ」スコッティを燦々と陽が差す大通りに引っ張って来て、ジュラスが勿体ぶって宣言した。「まずやらなくちゃいけないことは、将来有望な顧客に何を示し、どういうやり方がしっくりいくかを考えることだ。大体、豪勢な衣装やプロの立ち居振る舞いなんかじゃ、お前はシルヴェナールの旦那を騙せないんだよ。そんな風にやろうとしたころで、失敗するのは火を見るより明らかなのさ。ここは俺に任しとけ。俺やバスも含めて何人かが宮廷に行ってみたが、何かしらヘマをしちまったもんだよ。がっついたり、格式張ったり、商売の話ばかりしようとしたり、な。それで、もう二度とシルヴェナールと会えなくなっちまったわけだ。だが、俺達は今でも居残っている。その後、宮廷についてぼんやりと考えてみたり、宮廷の情報を仕入れてみたり、ピアスを開けてもらったり、ぶらぶら散歩したり、がつがつ飲み食いしてた。あえて言うなら、1ポンドか2ポンドは太ったな。さて、俺達がシルヴェナールの旦那に伝えるべきメッセージは簡潔にして明瞭だ。『私たちにとってではなく、彼にとってとても興味深い面会になるでしょう』だ」
「計画は始まった」と、バスが付け加えた。「大臣に『我々帝都の代表者が到着しました、朝のうちにシルヴェナール様にお会いしたいので、すぐにでも連れて参ります』と伝えておいたよ」
「遅刻してるじゃないか?」と、スコッティは聞いた。
「ああ、大幅にね」とジュラスは笑みで返した。「しかし、それも計画の内さ。慈悲深く、私利私欲を見せずだ。シルヴェナールを、世襲貴族と間違えちゃいけないぜ。奴は、庶民の心の拠り所なんだよ。どうやって彼を丸めこんだらいいか、お前も分かるだろう?」
それから数分間、ジュラスはヴァレンウッドについて何がどれだけ足りないか、それにはいくらの金がかかるかについてという講釈を話しながら歩いた。その額は莫大なもので、規模も費用も、スコッティが今まで扱ったものよりも遥かに大きなものであった。スコッティはそれを注意深く聞いた。彼らの周り、シルヴェナールの街は、ガラスや花々、風のうなり声や心地よい気だるさを鮮明に感じさせた。宮殿に着くと、スコッティは立ち止まりあぜんとした。ジュラスはそんな彼を見つめ、笑った。
「変わってるだろ?」
その言葉の通りだった。緋色の爆発をそのまま凍らせたような、ねじれて不均衡な尖塔が太陽を付き刺さんとばかりに伸びている。小さな村ほどもある庭園には、廷臣や召使い達が、たくさんの昆虫のように、互いの体液を吸う勢いで歩き回っている。花びらのような橋を渡って、3人は不安定な壁に覆われた宮殿の中を歩いて行った。細かく区切られた区画があり、それぞれは日陰の集会所や小さな部屋であるらしい。何度か道を曲がって行くと、一行は壁に囲まれた中庭に到着した。そこには、ドアはなく、どうやら宮殿をぐるりと巡るらせん階段の他にシルヴェナールの所に行く方法はないようだった。つまり、会議室や寝室や食堂を通り抜け、高僧や王妃や宮廷楽団員や、それに大勢の衛兵の側を通って行くのだ。
「実に愉快なところだ」と、バスが言った。「だが、いささかプライバシーに欠けてるな。まあ、そこがシルヴェナールには好都合なんだろう」
宮殿に入ってから2時間後、廊下を歩いていた一行は、剣や弓をちらつかせる衛兵達に呼び止められた。
「私達は、シルヴェナール陛下との謁見を望む者達です」ジュラスは、辛抱強く言葉を選んだ。「こちらは、デクマス・スコッティ氏、帝都の代表です」
一人の衛兵が廊下を曲がって姿を消すと、背丈の高い、革を縫い合わせたローブを着込んだ高貴そうなボズマーを1人連れて来た。シルヴェナールの経済相である。「陛下は、デクマス・スコッティ氏、彼1人との謁見を御所望でいらっしゃる」
とやかく言ったり不安の色を見せたりしている場合では無かった。スコッティは、残る2人の方も見ずに歩を進めた。大体、彼らに泣きついたところで、無関心を装われるに決まっているのだ。大臣の後をついて行って謁見室に通された彼は、この謁見で重要なことを全て暗誦すると、ジュラスの立てた計画を心に思い描いた。
シルヴェナールの謁見室は、壁が天井に向かって次第に内側へ反っていき、緩やかなドーム形をしていた。何百フィートもの高さから、陽光が天井の隙間を縫って、銀色に輝く錦の上に立つシルヴェナールに降り注いでいた。この街や宮殿に比べ、シルヴェナール自身は至って普通に見える。体つきは太っても痩せてもおらず、穏やかで均整の取れた顔立ち、少し疲労の色が見えるが、帝都のどの州議事堂にもいるような、ちょっと変わったウッドエルフというところだ。しかし、彼が高座から降りてきて、スコッティは風変わりなところを見つけた。背丈が非常に低いのだ。
「私は、お前だけと話がしたい」シルヴェナールは、ありふれた、気取らない口調で切り出した。「書類を見せてくれないか」
スコッティはヴァネック建設委員会の契約書を手渡した。シルヴェナールはそれをじっと見ると、「帝都」という飾り文字の上に指を走らせてから、彼に返した。彼は何だか気恥ずかしくなって、床に顔を向けてしまう。「我が宮廷には」とシルヴェナールが言った。「この戦争で儲けようというペテン師どもで溢れ返っている。おおかた、お前や、お前の同僚もそうであろう。しかし、この契約書は本物のようだな」
「もちろんです」スコッティは冷静に応えた。彼のあまり格式ばっていない、へつらう様子もない口調は、シルヴェナールに好印象を与えたようだ。これは、ジュラスに教えられた通りである。「再建が必要な道路の話、アルトマーに壊された港の修復のお話をいたしましょう。それから、経済網の再整備に必要な費用の見積もりをお出しします」
「ところで、どうして2年前にエルスウェーアとの戦争が始まったときに、皇帝は使節を派遣してくれなかったと思う?」と、シルヴェナールがゆうつつそうに尋ねた。
スコッティは、返答する前に、このヴァレンウッドで会ったボズマー達との会話を思い出してみた。彼を国境からここまで護衛してくれた、金に汚くおどおどしていた兵士達。ファラインスティのウェスタンクロスにいた、大酒飲みたちや、害虫駆除(彼も駆除されそうになった)の射手達。ハヴェル・スランプの詮索好きなパスコス母さん。哀れむべき元海賊のバルフィックス船長。悲哀に満ちた、しかし希望を捨てていないアセイヤーやグレノスの避難民達。乱心と殺意に満ち、自身をも滅ぼす勢いのヴィンディジの荒野の狩人。マロンに雇われた、物静かで気難しい船員達。ちょっと風変わりなバス。もしも1つの生物が、それが住む地域の生物の気質を代表するというならば、その生物の個性とはどのようなものだろうか? スコッティは仕事上でも気質上でも事務員である。だから、目録や書類を作ったり、何かをシステムに組み込んだりすることには本能的に安らぎを覚える。もしもヴァレンウッドの人々の気質の欄に何か書き込まねばならないなら、いったい何がふさわしいだろうか。
ほとんど考えるまでもなく答えは出て来た。「否定」だ。
「私はその質問に興味がありません。すぐに商談に移って構いませんか?」と、スコッティは言った。
その昼の間中、2人はヴァレンウッドの再建計画について議論を交わした。全ての契約書に、記入と署名がなされていった。費用がどんどんと加算される一方で、余白にも追加条項が走り書きされていき、それにも署名が重ねられる。こうして素早く交渉はまとめられていったが、その内容は決して考え無しのものではないことに、スコッティも気付いていた。実際のところ、「民衆の声」の計画はかなり効率的なものであり、これに従えば、日常生活も上手く回っていくだろう。つまり、漁獲や経済利益や航路や森林の状態などが、事細かに考えられたものだったのだ。
「この契約の成功を祝して、明日の夜、祝宴を開こう」と、シルヴェナールが最後に言った。
「今夜はどうですか」と、スコッティは答えた。「この契約書を持って、明日シロディールに発たなきゃならないんです。なので、そこまでの路を確保して頂きたい。時間を無駄にしたくないんです」
「よかろう」と言って、シロディールは呼び寄せた経済相に封をした契約書を渡し、祝宴の準備に向かって行った。
スコッティが謁見室を出ると、ジュラスとバスに迎えられた。彼ら2人は、長い間気を揉んでいたせいか、すっかり顔が引きつってしまっている。衛兵達の姿が見えなくなると、すぐに彼に首尾を尋ねてきた。スコッティはすべて説明した。契約書を見せると、バスは、歓喜のあまり涙を流した。
「シルヴェナールを見て、何か驚いたかい?」と、ジュラスが尋ねた。
「背が低かったね。私の半分しか無かった」
「そうなのか?」と言って、ジュラスは少し驚いたようだった。「大方、俺達があんまりにも謁見しようと必死なもんだから、縮んじまったんだろうね。もしくは、民衆の苦境に心を痛めて、かな?」
火中に舞う 第7章
ウォーヒン・ジャース 著
場所:シルヴェナール(ヴァレンウッド)
日付:第三紀397年 11月13日
シルヴェナール宮殿で開かれた祝宴には、ヴァレンウッド再建の仕事を持っていかれたことに嫉妬する官僚や商人達も、全員顔を見せていた。隠そうともしない憎悪の眼差しの中心に居るのは、スコッティ、ジュラス、バスの3人である。スコッティには居心地が悪いだけだったが、ジュラスには、それが快感であるようだ。召使達がロースト肉の乗った大皿を引っ切り無しに持って来るのを見ながら、ジュラスとスコッティはジャッガで乾杯を交わした。
「今だから言えるがな」とジュラスは言った。「正直、お前をこの商談に巻き込んだのはすごい失敗だと思ってたんだよ。だが、な。俺がコンタクトを取ったどの建設会社の連中も、確かに外見は積極的だったがね、お前みたいにシルヴェナールとサシで話付けたり、有り金はたいて冒険に出ようなんていう奴はいなかったんだぜ。ほら、もっと飲めよ」
「もう、いいよ」スコッティは言った。「ファリネスティで十分に飲んだし、それに、酒のせいでダニの化け物に吸われそうになったんだよ。何か別の飲み物を探してくるよ」
スコッティは、大きな銀の瓶から湯気を立てている茶色い液体をカップに注いで飲んでいるのを外交家たちを見つけ、お茶かどうか聞いた。
「お茶だって?」1人が笑いながら言った。「ヴァレンウッドには無いね。これはロトメスだよ」
仕方なく、スコッティは、そのロトメスをもらってちびちびと舐めた。匂いが強く、苦味と甘みがあって、ひどくしょっぱい。初めは、とても飲めたものではないと思われたが、不思議なことに、しばらくすると、そのカップを空けて新しく注いでいるほどだった。体が火照ってきて、この謁見室の物音がちぐはぐに感じられる。しかし、まったく恐怖感は無い。
「あんたか。シルヴェナールから契約を取り付けたっていうのは」と、もう一人の外交家が聞いた。「さぞかし、粘りに粘って、深い話をしたんだろうな」
「いやいやそんなことはありません。商売というものに関して、基本的なところを両方が合意できただけです」とにっこり笑って、スコッティはロトメスの3杯目を注いだ。「シルヴェナールはヴァレンウッドの争いを収めるために帝都とのコネを作っておきたかったし、私も何としても契約を取りたかったし。それで、神の御加護か、両方の利害が一致したということですよ。だから、私のしたことと言えば、契約書に羽ペンを走らせることだけです。あなたにも、神のご加護がありますように」
「あんた、皇帝御用達の会社に長く勤めてるんだろ?」と、最初の外交家が尋ねた。
「帝都では色々とあってね。ここだけの話、実は、もう無職なんだ。アトリウス建設会社で働いてたんだが、クビになった。大体あの契約書も、本当は商売仇のヴァネック建設会社のものだ。レグリウスからもらったんだ。いい奴だったよ。カジートに殺されちまったが」と言ってスコッティは5杯目を空けた。「帝都に戻ったら、アトリウスとヴァネックにサシで話付けるつもりさ。奴らの前でこう言ってやるよ。“この契約書、どっちが欲しい?”ってね。そしたら、2人とも俺にがっついてくるだろうな。誰もどこでも見たことないような奪い合いになるだろうな」
「と言うことは、つまり、あんた、本当は帝都の代表なんかじゃないんだな?」と、最初の外交家が聞き返した。
「俺様の話をちゃんと聞いてなかったのか!?」と唐突に激憤が彼の中を巡ったが、同じく唐突に収まってしまった。そして、にやにや笑いを浮かべると、7杯目のロトメスをつぎ足した。「個人でだって建設会社は作れるんだぜ? そりゃ、確かに今はアトリウスやヴァネックのアホが皇帝の代理人だがな。しかし俺様にだってなれるさ、この契約書さえあればね。俺様のお話は難しすぎるか? 話について来れてるか? みんな、詩みたいなもんさ。火に踊れ。幻覚に従うならば、それはつまり隠喩だ」
「あんたの同僚もかい? あんたの同僚も、代表じゃないのかい?」と、2番目の商人が尋ねた。
スコッティは爆笑して首を振ってみせる。2人の商人は尊敬の念のこもった別れの挨拶をすると、大臣の方へ話をしに行ってしまった。残されたスコッティは、千鳥足で宮殿を抜けると、奇妙に入り組んだ大通りや並木道をふらふらと進んで行く。数時間後、彼はプリサラホールの自室で眠りに落ちていた。ただし、彼のベッドのすぐ近くで。
翌朝、スコッティは、ジュラスとバスに揺り起こされて目を覚ました。まだ目は完全に開いていなかったが、その他の点は良好であった。商人達との会話が、子供時代の記憶のように、ぼんやりと浮かんできた。
「いったいぜんたい、ロトメスは何なんだ?」と、彼は口早に尋ねた。
「ひどい匂いの発酵させた肉汁に、臭みを消すための大量のスパイスが入ってるんだ」と、バスが笑って言った。「一緒にジャッガを飲んでいろと警告しておくべきだったろうな」
「マンダンテの肉については、すぐに知っておくべきだな」と言って、ジュラスも笑った。「ボズマーときたら、ブドウの実や地面を触るのより共食いが好きなんだからな」
「あの外交家達に、私は何て言ったんだ!?」と、スコッティはパニックになりながら叫んだ。
「今のところ、表立って悪いことは起こってない」と、ジュラスが何枚か書類を取り出しながら答えた。「そうだ、例の契約書とお前を安全にシロディールまで運んでくれる護衛が、階段の下まで来てるぞ。急いだ方がいいぜ。シルヴェナールは、ビジネスが迅速に進まないことに、あまり寛容ではいらっしゃらないようだからな。それと、この契約をしっかり履行したら、特別に褒賞が出るらしいぞ。実は、俺はもう幾つかもらってきた」
そう言って、ジュラスは、大粒のルビーで飾られた美しいイヤリングを見せびらかした。バスも同じものを見せた。二人の太った男が部屋を出ていくと、スコッティは急いで着替えと荷造りをした。
シルヴェナールの衛兵の一連隊が、既に宿屋の前に整列していた。彼らはヴァレンウッド軍の正規の武具に身を固めて、羽根飾りの付いた馬車を取り囲んでいる。その光景に呆然としたものの、スコッティが慌ててその馬車に潜り込むと、隊長の号令の下、連隊は出発した。そのスピードは速く、馬車の中の彼も揺られながら外を眺めていた。すると、後ろの方で、ジュラスとバスの2人が手を振っているのが見えた。
「ちょっと待って!」とスコッティは叫んだ。「あなた達は帝都に帰らないのか!?」
「帝都の代表者としてここに残るように、シルヴェナールから言われたんだよ」とジュラスが叫んだ。「また、契約とか交渉とかする必要が出てこないとも限らんだろ。それに、俺達はアンドレイプの勲位ももらったんだぞ! 外国人に与えられる特別な奴だ。心配すんな、また祝宴で会おう! 俺達はこっちで上手くやるから、お前は、アトリウスとヴァネックとの交渉を上手くやるんだぞ。お前なら出来るさ!」
ジュラスはまだ何かアドヴァイスを続けていたようだったが、遠ざかるにつれて、声も遠のいていった。そして、護衛達が通りをぐるっと回ると、すっかり彼ら2人の姿は見えなくなってしまった。それから、ぼんやりとジャングルが見えてきたと思ったら、既にその中を走っていた。そう、この深い森の中、彼は自分の足で苦労して歩いたり、川をゆっくりとボートで下ったりしたのだ。それが、今や、こうして馬車に乗って、悠々と進んでいるのである。木々の緑が瞬く間に後ろへと流れて行く。馬は、草の上を駆けて行く方が、街中の整備された路を走るよりも早いような気がした。ジャングルに特有の奇妙な物音もじめじめした匂いも、全く気にはならない。馬車の窓から覗く風景は、まるで紗幕を通してするジャングル劇が上演されているようだ。
そうして2週間が過ぎた。馬車の中には食べ物も水も充分にあったので、スコッティはただ食べたり飲んだりを繰り返していればよかった。時々、彼は剣で打ち合う音が聞こえたが、周りを見てみた時には、既に馬車は出発してしまった後だった。そして、一行はヴァレンウッドとシロディールとの国境に到達した。そこには、帝都の要塞が居を構えていた。
スコッティは、馬車に乗って来た兵士達にあれこれと書類を見せた。兵士達は質問の集中砲火を浴びせてきたが、スコッティが素っ気なく答えていると通行の許可が下りた。そこから更に数週間かかって、帝都の門の前に到着した。ジャングルを飛ぶように疾駆してきた馬達も、ここコロヴィアの東の見知らぬ風景には、少し戸惑い気味である。それと対照的に、見慣れた鳥、匂い、植物と、その風景を見ているだけでスコッティは活力を取り戻すのだった。そこは正に、数ヶ月前の彼が夢にまで見た故郷なのだ。
帝都の門をくぐると、馬車の扉を開けて、スコッティは不確かな足取りで地面に降り立った。彼が護衛達に何事か言おうと振り向いた時には、既に彼らは森を抜けて南の方へ走り去ってしまっていた。まず彼がすべきことは、近くの宿屋に行って、お茶と果物とパンを食べることだ。もう肉を食べないとしても、それが自分に合っているだろうと彼は思った。
その後すぐに行ったアトリウスとヴァネックとの交渉は、大方納得できるものだった。どちらの建設会社も、ヴァレンウッド再建計画に加わることでどれだけ利益が上がるか、しっかり分かっていたのである。ヴァネックは、この契約に用いられた書類は自社のものであるため、この契約はヴァネック社のものであると主張した。一方、アトリウスは、この契約を成功させたのは自社のスコッティであるため、この契約をアトリウス社のものであると主張した。もちろん、決して彼を解雇した覚えは無い、と付け加えたが。結局、この争いには皇帝による調停が為されることになったが、皇帝は無理だと言った。なぜなら、皇帝の相談役である帝都の魔闘士ジャガル・サルンが長らく消息不明であり、彼無しでは、公平な判断など無理な相談であるからだ。
アトリウスとヴァネックから賄賂をもらい、スコッティは悠々自適の生活を送った。毎週、ジュラスとバスから、交渉の進捗状況を記した手紙が届いた。しかし、彼らの手紙は次第に少なくなっていって、今度は、シルヴェナールの経済相とシルヴェナールその人から緊急の手紙が届くようになった。それによれば、サムーセット島との戦争は、ウッド・エルフからアルトマーに湾岸の島をいくつか移譲することで講和が成立したらしい。また、エルスウェーアとの戦争は依然として続いており、ヴァレンウッドの東方の荒廃はまだ止んでいないようである。そして、アトリウスとヴァネックとの勝負もまだ続いているのだった。
第三紀398年のある気持の良い初春の朝。一人の密使がスコッティの家のドアを叩いた。
「ヴァネック卿が、ヴァレンウッドの再建代理権を入手なされました。つきましては、速やかに、例の契約書をご持参の上、邸宅へいらっしゃいますようお願いします」
「アトリウスは諦めたのかい?」と、スコッティは尋ねた。
「たった今、お亡くなりになりました。偶然にも、凄惨な事故に巻き込まれてしまったようです」と密使は言った。
スコッティは、いつから闇の一党がこの交渉に参入し始めていたのだろうかと考えた。ヴァネックの邸宅へと向かう途中、延々と続く荘厳な、名もないが素晴らしい建築物の間を歩きながら、スコッティはゲームで遊んでいるつもりが、遊ばされているとも限らないと考えていた。商売仇のアトリウスが死んでしまった今となっては、あの金に汚いヴァネックは私の足元を見てくるのではないかと思ったが、有難いことにヴァネックは、凍りつきそうな心で交渉に臨んだスコッティに申し出た通りの金をきっちり払ってくれた。ヴァネックの相談役が言うには、もしも事が上手く進まなかった場合には、別な会社を建てて、引継ぎさせるようだ。
「全てが合法的に収まってなによりだ」と言ってヴァネックはご満悦の表情であった。「今や我々は、かわいそうなボズマーを救済するという誇りある仕事の前途に立っている。もちろん、その分の報酬は頂くが。非常に残念だが君は我が社の代表ではないので、実務はベンダー・マーク君とアルネシアン君とに担当してもらうことになるが。ところで、まだ戦争が続いているようだね」
こうしてスコッティとヴァネックは、シルヴェナールについに名誉の契約の準備が調ったことを告げる手紙を出した。そして数週間後、新事業の発足を祝うパーティーが開かれることになった。スコッティは今や帝都に於ける時代の寵児であり、その記念すべき祝宴には、費用も全く惜しまず注ぎ込まれた。
その祝宴で彼は、この新事業で利益を受けることになる貴族や豪商達と挨拶を交わした。舞踏室には異国風の、しかし何か親しみの持てるバラのような香りが漂っていた。彼がその香りのもとを辿って行くと、長く厚い皿に乗せられた、厚切りのロースト肉に行き着いた。すっかりできあがったシロディール達が、その肉に群がって、味や質感を言い表す言葉を失ったかのように、次から次にその皿へと手を伸ばしている。
「こんなにおいしいもの、今まで食ったことない!」
「丸々太った豚みたいな味の鹿だ!」
「ほら、赤身と脂身がほどよく混ざってるのが分かるだろ? これが最高の一品という証拠さ!」
それらの声につられて、スコッティも少し切り取ってみた。しかし、確かに外はよく焼かれて美味しそうではあるが、中は乾燥したパサパサのもので、決して高級とは言えない代物だった。そして、その皿を置いて引き返そうとした拍子に、彼の新しい雇い主となったヴァネックとぶつかってしまった。
「どこに行ってらっしゃったんですか?」とスコッティは驚きながら言った。
「我が顧客のシルヴェナールのところだ」とヴァネックは威光を見せながら答えた。「そうそう、あれはあちらの住民がアンスラッパと呼ぶ珍味だよ」
スコッティは吐いた。しばらく吐き続けた。宴は一時中断したが、スコッティが彼の家に引き返したあとも、客たちは食事を続けた。珍味、アンスラッパは皆の口を喜ばせていた。その切り身を取ったヴァネックが、中に埋め込まれていた2組のルビーの片方を見付けた時には、それは更なる盛り上がりを見せることになる。ボズマーは何と巧い料理を作るんだとシロディールたちは口々に言い合った。