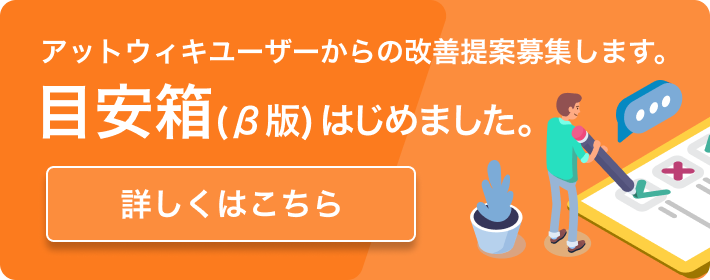オブリビオン図書館
タララ王女の謎
最終更新:
oblivionlibrary
-
view
タララ王女の謎 第1巻
メラ・リキス 著
時は第三紀405年。ブレトンのカムローン王国の建国千年の祝典での出来事である。すべての大通りや狭い小道に、様々な金と紫の旗が掲げられた。非常に簡素なものや王家の紋章が印されたもの、王の臣下の公国や公爵位の紋章が印されたものもあった。大小の広場では楽隊が音楽を奏で、通りや角で異国情緒溢れる新進の大道芸人たちが芸を披露していた。レッドガードの蛇使いや、カジートの曲芸、本物の魔力を持つ手品師。もっとも、手品師たちの見せるきらびやかな芸は、たとえ本当の魔術でなくても見るものに感銘を与えた。
カムローン男性市民の注目を一身に集めたもの、それは「美の行進」であった。一千人もの麗しく若い女性たちが、挑発的な衣装に身をつつみ、セシエテ神殿から王宮までの大通りを踊りながら練り歩いていた。男たちは皆互いに押し合い、よく見えるように首を伸ばし、お気に入りの女性を見つけようとした。その女性たちが売春婦であることは一目瞭然で、このあと夜には「花祭り」が待ち構えていた。その祭典で彼女たちはより親密な「お仕事」をこなすのだ。
ジーナは絹と花びらでところどころ覆われたすらりとした曲線美と亜麻色の巻き毛で、多くの男性の視線を集めていた。年は20代後半にさしかかり、売春婦の中でも決して若いわけではなかったが、間違いなく最も魅力的だった。その物腰から、挑発的な流し目を使い慣れているのは明らかだったが、彼女は壮麗な街の眺めに飽きてそうしているわけでは決してなかった。彼女の故郷であるダガーフォールのごみごみした街並みと比べれば、祝典ムードできらめくカムローンは夢の世界のように感じられた。しかし不思議なことに、彼女はここへ一度も訪れたことはなかったのに、既視感を覚えていた。
国王の娘、ジリア夫人は馬にまたがり宮殿の門をくぐり出ると、すぐさま自分の不幸を呪った。すっかり“美の行進”のことを忘れていたのであった。通りは混沌とし、人々が立ち止まっていた。行進が過ぎ去るまで小一時間は待たなければいけなかった。しかし彼女は、街の南方にある老乳母ラムクの家を訪れる約束をしていたのだった。ジリアはしばし考えをめぐらせ、街の通りを思い浮かべ、行進でふさがれている大通りを避けて通る近道を考えついた。
走り出してしばらくの間は賢明な策を取ったと思っていたが、小道を曲がるとそこには祝典のための仮説テントや舞台で通行止めになっていた。あっという間に、長年──5年をのぞいて──住み続けたこの街で迷子になってしまったのである。
路地から覗き込むと、大通りは依然「美の行進」で盛り上がっていた。そこが行進の最後尾であること、再び迷子にならないことを祈りながら馬を祝典の方へと向けた。彼女は路地の出口に蛇使いがいることに気づいていなかった。蛇がシューシューと音をたてながら頭を膨らませたその時、馬がおびえて後ろ足で立ち上がってしまった。
行進に加わっていた女性たちはハッと息をのむとすぐさま散ってしまったが、ジリア夫人はすぐに馬を鎮めた。彼女は自分のしでかした失態に赤面して、「ごめんなさいね。淑女のみなさん」と言って軍の敬礼をまねてみせた。
「ご心配なさらないでください」と金髪の髪に絹をまとった女性が答えた。「すぐに道を空けますわ」
ジリア夫人は行進が過ぎ去るのを見ながらも、自分と鏡で映したかのごとくそっくりなその女性に目を奪われていた。同じ年頃、同じ背丈、同じ目の色に容姿、どれをとってもほとんど同じだった。その女性も同じようにジリアを見つめ返していた。まるで同じことを考えているかのように。
それはジーナだった。時折ダガーフォールに立ち寄る年老いた魔女が、ドッペルゲンガーのことを話していた。自分に似た姿形で現れ、死の前兆を表すもの。しかし、彼女はまったく怯えなかった。この異国の地で起きたちょっと変わった出来事ぐらいにしか捉えなかったからだ。行進が宮殿の門に辿り着く頃には、そんな出来事もすっかり忘れてしまっていた。
売春婦たちが宮殿の中庭でひしめきあっていると、国王がバルコニーに姿を現した。彼の両隣には護衛隊長と魔闘士が彼からじっと目を離さずに側に仕えていた。国王は中年のなかでは美形なほうであったが、ジーナにしてみれば、正直に言ってそれほどたいしたほどでもなかった。しかし、国王を見たジーナは恐れおののいた。「あれは確か夢で…… そう、夢の中だわ」彼女は国王と夢の中で会ったことがあるのだ。今では2人の間に距離があるものの、夢の中で国王はひざまずいて彼女にキスをしたのだ。欲望からではなく、優しさと礼儀のこもったキスであった。
「淑女のみなさま、このカムローンの偉大な首都や大通りにあなたがたの美を降り注いでくれたことに感謝します」と国王は大声で言い放ち、集まった聴衆の笑いや話し声を一気に鎮めた。誇り高い笑みをたたえたその時、国王とジーナの目が合った。彼は話をやめ、震えた。永遠にも感じられそうなほどの時間、王妃が間に割って入り、演説を続けるよううながすまで2人は見つめあった。
女性たちは夜の祭典に向けて着替えのテントへと向かっていった。そこへ1人の古株の売春婦がジーナに近づいてきた。「国王のあの目、見た? もしあんたがうまく立ち回れば、この祝典が終わる頃には側室に仲間入りできるよ」
「今までさんざん『腹ぺこ』のやつらを見てきたけど、今回のはなんだか違う気がするのよ」とジーナは笑った。「それか馬に乗って突進してきた娘さんと間違えたんじゃないかしらね。彼女は確か王族の人でしょ。彼は多分自分の身内が売春婦の格好をして行進に参加してるのかと見間違えたんじゃないかしら。それはそれでスキャンダルよね」
二人がテントに戻ると、がっちりとした体格の、着飾った頭の禿げた若い男から挨拶を受けた。彼は自己紹介をした。彼の名はストレイル卿といい、皇帝から直々に遣わされた大使であって、彼女たちを雇っているパトロンだそうだ。国王とカムローン王国へのプレゼントとして今回彼女たちを雇い入れた張本人であった。
「『美の行進』は『花祭り』の前座にすぎません」国王と違って大声を出しはしなかったが、彼の地声は十分大きく、はっきりと聞こえた。「すばらしい演出を期待しておりますよ。今回の莫大な経費に見合うようなものを見せていただかないと。さあ、日が沈みきる前に支度してキャヴィルスティル・ロックに行ってください」
大使が心配するほどでもなく、女性たちは皆この仕事のプロフェッショナルだったので、着るものを脱いだり着たりするのは、普通の女性が求められるのより何倍も速かった。彼の召使いが着替えの手伝いをするよう申し出たが、実際彼が手伝うようなことは何一つなかった。女性たちの衣装はいたってシンプルであり、やわらかく、細いシーツのようであり、頭を出す穴が開いているだけであった。ベルトがなければ彼女たちの四肢を露にするだけのガウンのようなものだった。
日が沈むよりも早く売春婦たちはダンサーへと様変わりし、キャヴィルスティル・ロックにいた。そこは海に面する広々とした岬で、「花祭り」には最適の場所であり、まだ灯りのついてない松明が大きな輪になって、ふたのされたかごが置かれていた。女性たちと同様に早めに到着した客で、すでに会場は溢れんばかりであった。女性たちは円の中心へと集まり、時が来るのを待った。
ジーナは膨れ上がる観衆を見ていた。行進の時に出会った王女が彼女の元へと近づいてくるのを見てもさして驚かなかった。彼女は、年老いて短い髪も真っ白となった女性を引き連れていた。その老女は沖合いの島を指差したり、不安な様子であった。王女のほうは何といったらよいかといった緊張した面持ちであった。ジーナはこの手の不安を抱える客には慣れていたので彼女のほうから声を掛けた。
「またお会いしましたね。私、ダガーフォールのジーナと言います」
「さきほどの馬の件、どうかお気を悪くなさらないでくださいね」と言って王女は笑い、幾分安心したかのようだった。「私はジリア夫人・レイズと申します。国王の娘です」
「国王の娘ならば『王女』とお呼びしたほうがよいかしら」とジーナは笑顔で答えた。
「カムローンでは、王家を継ぐ場合のみ、そう呼ばれます。父には新しい女王との間にできた息子がおりますので」とジリアは答えながら、自分の言葉にめまいを覚えた。売春婦に王族の内部事情を詳しく話してしまうとは。「この話題に関連することですが、ちょっと不思議なことをお聞きしてよろしいかしら。今までタララという名を耳にした覚えはございませんか?」
ジーナはしばらく考え、「どこかで聞いたことがあるような名前だわ。なぜ私に?」と答えた。
「わかりません。もしかしたらあなたは知っているんじゃないかと思って」と言ってジリア夫人はためいきをついた。「今までにカムローンに住んだことは?」
「あったかも知れませんが、おそらくうんと小さい頃にですね」とジーナは答えたが、彼女は今は何事も率直に答えるべきだと感じた。ジリア夫人の親しみやすさや、率直な物言いが彼女をそういう気持ちにさせたのかもしれない。「正直に言いますと、9、10歳より前のことはあまりよく覚えておりません。おそらく、両親とこの地に住んでいたかもしれませんが、その両親もどんな人たちだったのか… 私もすごく幼かったので。でも、昔ここにいたような気がするんです。はっきりとは思い出せないのですが、この街も、あなたま、国王もみな…… 見たことがあるような気がします。昔ここにいたことがあるみたいに」と、ジーナは言った。
ジリア夫人はハッと息を飲み、後ずさりした。海を見つめ、ブツブツとつぶやく老女の手をグッと握り締めた。彼女はジリア夫人を驚いたように見て、その視線をジーナの方へと移した。彼女の年老いて半分ほどにしか開かれていない目は、何かをとらえたかのように光が宿り、驚きの声をあげた。その声に今度はジーナが驚いた。国王がもしかしたら夢で会ったかもしれない程度であれば、この老女は確かに知っている顔だった。守護霊のように確かでおぼろげな存在。
「ごめんなさい」と、ジリア夫人は口ごもりながら言った。「この人はわたしの子どもの頃の乳母で、名前はラムクと言います」
「彼女です!」と老女は目を見開き、大声で叫んだ。老女は前へ進み出ようと手を伸ばしたが、ジリアが背中を押さえた。ジーナは自分が裸同然の格好のように感じ、ローブを体のほうへたぐり寄せた。
「違うわよ」とささやいて、ジリア夫人はラムクをしっかりと抱いた。「タララ王女は亡くなったのよ。知ってるでしょ。あなたを連れてくるべきじゃなかたわ。おうちへ帰りましょう」ジーナの方を振り向いたジリア夫人の目には、大粒の涙がこぼれていた。「カムローン王家は、20年以上前に皆暗殺されてしまったのです。私の父はオロイン公爵、国王の弟です。亡き兄の後に、王位を継承しました。ごめんなさい、お騒がせしてしまって。おやすみなさい」
ジーナはジリア夫人と老女が観衆の中に消えていくのを見守った。しかし彼女には先ほどまでの話の内容を考える時間は少しもなかった。日は沈み、いよいよ「花祭り」の始まる時刻となった。暗闇から腰巻とマスクだけを身につけた20人の若い男が松明をかかげて現れた。炎が燃えさかり、ジーナと他の女性たちダンサーがかごへ駆け寄り、中に入っている花やつる草を両手いっぱいに抱えた。
初めに、女性たちはペアを組んで、風に向かって花びらを舞い散らせていた。音楽が盛り上がるにつれて観衆も参加してきた。そこは狂おしくも美しい混沌となった。ジーナは森の妖精のごとく夢中で飛び跳ねた。しかしその時、なんの警告もなしに、ごつごつとした手が彼女を背中から突き飛ばした。
何事かと理解する前に彼女は落ちていった。なんとか意識を失わずにはいたが、気がついた時には彼女は100フィートもの高さのある崖のふもと近くまで落ちていた。彼女は腕をばたつかせ、岩肌をとらえた。指で岩肌を探り、傷を作りながら、なんとか捕まれるところを見つけ、そこにはりついた。しばらくの間、その体勢のまま息を激しくついた。そして彼女は大声で叫び始めた。
音楽と祭りの騒ぎとで、どんなに大声を出しても、崖の上にいる人たちには届かなかった。彼女自身、自分の声が聞き取れなかった。彼女の下には波が激しく打ちつけていた。ここから落ちようものならすべての骨がぐしゃっと折れてしまうであろう。彼女が目を閉じると、あるイメージが浮かんできた。彼女の下に1人の男が立っている。深い知恵と慈悲を持った王が暖かい眼差しで彼女を見上げている。そして、髪は金色に輝き、いたずらが好きそうな顔つきで、親友でもあり身内でもある小さな女の子が現れて、今、ジーナのそばで岩にしがみついていた。
「いい? 飛び降りるコツはね、体の力を抜くことよ。それと幸運ね。大丈夫、あなたは助かるわ」少女は言った。彼女はうなずいて、少女が誰であったかを思い出した。八年間の暗闇が一気に晴れ上がったのだ。
彼女は手を離し、風の上に舞い落ちる木の葉のように落ちていった。
タララ王女の謎 第2巻
メラ・リキス 著
彼女は何も感じなかった。暗闇が彼女の体と心を包んでいた。突然足に痛みが走り、その感覚とともに全身をひどい寒さが包んだ。彼女は目を開け、自分が溺れていることに気付いた。
左足はまったく動かず、右足と腕を必死に動かして頭上に見える月にむかって泳いだ。水流が彼女を水底におし戻そうとしたので長い時間がかかったが、やっとのことで水面にたどりつき、夜の冷たい空気の中に顔を出すことができた。そこからはまだカムローン王国の首都の岩だらけの海岸線が見えたが、彼女が海に落ちたキャヴィルスティル・ロックからはずいぶん離れていた。
落ちたんじゃない。彼女は思った。落とされたのだ。
彼女はしばらく、海流に流されるままになっていた。このあたりの海岸は海面からすぐ切り立った崖になっていた。前方の海岸の上に大きな屋敷の影が見え、近づいてゆくと煙突から出る煙や窓にうつる暖炉の火の光が見えた。足の痛みもひどかったが、それよりもこの水の冷たさは耐えがたかった。暖炉の火にあたりたい一心で、彼女は再び泳ぎだした。
海岸まで泳いできたが、陸に上がろうとして立てないことに気付いた。岩と砂の間を這い進みながら、彼女の目からは涙が零れ落ち海水と混じりあった。花祭りのための衣装だった白い布はぼろぼろに破け、鉛でできた重りのように背中にのしかかった。彼女はとうとう疲れきって前のめりに倒れ、すすり泣きはじめた。
「助けて!」彼女は叫んだ。「聞こえますか、お願い、助けに来て!」
すこし間があってから、屋敷の扉が開き、女の人が出てきた。花祭りで会った、ラムクという名前の老婦人だった。花祭りで、彼女が誰かわかる前に「彼女が来たわ!」と最初に叫んだのがこの老婦人だった。しかし、海岸に倒れた彼女のもとに近づいてくるとき、老婦人の目にその時の輝きはなかった。
「なんてことでしょう、怪我してるのね?」ラムクはささやき、松葉杖のように彼女を支えて立ち上がらせた。「あなたの衣装には見覚えがあるわ。今夜の花祭りで踊っていませんでしたか? 私は王様のご令嬢ジリア・レイズ様と一緒にそこにいたんですよ」
「知ってます。彼女が私たちを紹介してくれたんです」と、彼女はうめくように言った。「私、ダガーフォールのジャイナです」
「ああ、そうでした。見たことがあると思いましたよ」老婦人は笑い、彼女を支えて一歩一歩海岸を進ませ、屋敷へ導いた。「この歳になると、あまり新しいことを覚えておけないの。さあ、暖かいところへどうぞ。足の怪我をみてみましょう」
ラムクはジャイナの体から濡れた布を取り、かわりに毛布で包んで暖炉の前に座らせた。冷えた体が温まって感覚が戻りはじめると、足の激しい痛みが襲ってきた。その時まで、彼女は怖くて怪我を見ることもできなかった。やっと足に目をやったとたん、彼女は吐き気を覚えた。深い切り傷から魚肉のような白い肉が見え、はじけそうに腫れていた。動脈から血が泡をたてて溢れ、床に流れ落ちていた。
「ひどいわね」老婦人が暖炉のそばに戻ってきて言った。「痛いでしょう、かわいそうに。昔の回復呪文を覚えていてよかったわ」
ラムクは床に座り、傷の両側に手を置いた。ジャイナは焼けるような痛みを感じたが、痛みはすぐに軽くなり、ちくちくする感覚だけが残った。彼女が傷のほうを見ると、ラムクが傷の両側に置いたしわだらけの手を互いに近づけているところだった。手が近づくにつれて、ジャイナの目の前で傷が治り始めた。肉が互いにくっつき、腫れが引きはじめたのだ。
「優しいキナレス」ジャイナは息をのんだ。「あなたはいなければ死ぬところでした」
「それだけじゃないわ、きれいな足に傷が残らないようにしておきましたよ」ラムクは笑った。「ジリア様が小さかったころ、よくこの呪文を使ったものですよ。私はあの方のお世話係でしたから」
「そうでしたね」ジャイナはほほえんだ。「でも、ずっと昔でしょう。よく呪文を覚えてらっしゃいますね」
「何かを覚えようとおもったら、たくさん勉強して失敗を重ねないといけないものでしょう、回復の分野でも何でもね。でも、私ぐらい歳をとれば、思い出さなくてもよくなるの。知識が自分のものになるのね。それに、この呪文は本当に何千回も唱えたんですよ。小さいころのジリア様とタララ王女ときたら、いつも切り傷やあざを作っておいででしたから。王宮の登れるところにはどこでも登っておしまいになるんですから、当たり前ですよね」
ジャイナはため息をついた。「ジリア様をとてもかわいがっておられたんですね」
「今でもですよ」ラムクはにっこり笑った。「でも今はもうあの方も大きくなられて、あのころとは違います。ああ、そういえば、さっきはびしょ濡れだったからわかりませんでしたけど、あなたはあの方によく似ていますね。フェスティバルでお会いしたときに言ったかしら?」
「ええ」と、ジャイナは言った。「というより、タララ王女に似ているとお思いになったのでは?」
「ああ、あなたがタララ王女で、ここへお戻りになったのだとしたらどんなに素晴らしいでしょう」ラムクは声をつまらせた。「前の王家の人々がみんな殺されて、皆タララ王女も殺されたに違いないと言っていました。でも遺体は見つからなかったんです。一番の犠牲者はジリア様でしたよ。ひどくお心を痛められて、しばらくのあいだ、正気まで失っておられるようでしたもの」
「どういうことですか?」と、ジャイナはたずねた。「何があったのですか?」
「よそから来た方にお話していいことかどうか。でもカムローンでは皆が知っていることですし、あなたは他人のような気がしませんし… 」ラムクはしばらく迷い、やがて話しはじめた。「ジリア様は目の前で暗殺をご覧になったんです。私が見つけたとき、あの方は血の海になった王の間に隠れて、まるで壊れた人形のようなご様子でした。なにもお話にならず、なにも召し上がりませんでした。私は回復の呪文を唱えましたが、私の力ではあの方のお心を治すことができませんでした。膝の擦り傷とはわけが違ったのです。当時オロインの公爵であられたお父様は、ジリア様を田舎の療養所へ送ってそこで過ごさせることになさいました」
「かわいそうに」ジャイナは涙を流した。
「ジリア様がもとのジリア様に戻るまで、何年もかかりました」ラムクはうなずきながら続けた。「しかしジリア様は、完全にはお治りにならなかったんです。お父様が王になられたとき、ジリア様を王位継承者になさらなかったのは、まだジリア様が完治されていないとお考えになったからです。ある意味、それは正しかったのです。ジリア様はまだ何も思い出せておられませんから」
「もしも──」ジャイナは注意ぶかく言葉を選んで言った。「いとこのタララ王女が生きているとわかったら、ジリア様はよくなるでしょうか?」
ラムクは少し考え、答えた。「そうでしょうね。でも、タララ王女はきっとお亡くなりになったのでしょう。夢みたいなことを望むのはよくありません」
ジャイナは立ち上がった。彼女の足は、まるで怪我などしていなかったかのようだった。彼女の服はすでに乾いており、ラムクが外は夜で寒いからと言ってマントをくれた。扉を出るとき、ジャイナは老婦人の頬にキスをして感謝した。回復の呪文とマントだけではなく、彼女が今までにしてくれた全てのことに対する感謝だった。
屋敷の近くの道は南北に伸びていた。左に行けばカムローンだ。そこにある謎の鍵を握るのは、ジャイナただ一人だった。右へ行けば南のダガーフォール、彼女が20年以上住んでいる町だった。その町の通りにある彼女の店へ戻るのは簡単だったが、少し悩んだあと、彼女は心を決めた。
それほど歩かないうちに、3頭の帝都の紋章のついた馬に引かれた黒い馬車と8頭の騎馬が彼女を追い抜いて行った。前方の森の中の小道に差しかかる前に、彼らは急に馬を止めた。ジャイナは、馬に乗った兵士の一人がストレイル卿の家来のノルブースだと気付いた。馬車の扉が開き、皇帝の大使ストレイル卿その人が降りてきた。彼が、ジャイナと他の女たちを王宮の踊り子として雇った人物だった。
「おまえは!」と、ストレイル卿は不機嫌に言った。「私が雇った娼婦だな? 花祭りの最中にいなくなっただろう? ジャイナ、そうだな?」
「その通りです」ジャイナは苦笑いした。「ただ、私の名前はジャイナではありませんでした」
「そんなことはどうでもいい」と、ストレイル卿は言った。「この南の道で何をしているんだ? 王宮の皆を喜ばせるためにお前に金を払ったんだぞ」
「私がカムローンに戻ったら、喜ばない人がたくさんいますよ」
「どういうことだ」と、ストレイル卿はたずねた。
そして彼女はどういうことか説明し、ストレイル卿は耳を傾けた。
タララ王女の謎 第3巻
メラ・リキス 著
カムローンで行きつけの酒場「ブレイキング・ブランチ亭」を出た直後、ノルブースは彼の名を呼ばれたが、その名は聞き違える類のものではなかった。見まわすと、城付魔闘士のエリル卿が路地の闇から姿を現した。
「エリル様……」と、ノルブースは恭しく微笑んで言った。
「今宵、おまえが出歩いているのを見かけるとは驚いたぞ、ノルブース」と、エリル卿は歪んだ笑みを浮かべて言った。「千年記念の祭り以来、おまえとおまえの御主人殿を見かけることはほとんどなかったが、多忙だったと聞いてはいる。私が聞きたいのは、多忙であった理由だ」
「カムローンでの帝都の利権を守るのは忙しい仕事にございます。大使の細かな時ごときの些事が、エリル様のご興味にかなうとは思えません」
「それが、かなうのだよ」と魔闘士が答えた。「大使殿が最近非常に奇妙な、配慮を欠いた言動をされているのでなおさらなのだ。しかも、花の祭典の娼婦の一人を家に招き入れたそうではないか。名をジーナといったかな?」
ノルブースは肩をすくめて言った。「親方様は恋をされているのかとお見受け致しますが。恋が男に非常に奇妙な言動をさせることは、勿論ご存じであろうかと」
「確かに美しい女ではあるな」エリル卿は笑った。「亡きタララ王女によく似ていると思わぬか?」
「カムローンには僅か十五年しかおりませんので、王女様の生前のお姿は拝見しておりません」
「詩吟でも詠み始めたというならわからんでもないが、宮殿の厨房で年老いた召使いと話して暮らすのが恋だというのか? 私の限られた経験からも、それが身を溶かすような熱愛の現れであるとは思えんがな」と、エリル卿は呆れたように言った。「それに、大使殿は一体あそこに何の用で… あの村の名前が思い出せんが」
「アンビントンでしょうか?」ノルブースは答えたが、直後に後悔した。エリル卿はそのような気配は微塵も見せてはいなかったが、ノルブースは城付魔闘士がストレイル卿が帝都を離れていることを知らなかったのだろうと、直感的に察した。この場を離れて大使殿に報せる必要があったが、焦りは禁物であった。「現地に移動されるのは明日のはずです。確か、帝都の承認が必要な証文に印を押すだけの用件だったかと」
「それだけなのか? 実に退屈な用事だな。それならお帰りになった時にお会いするとしよう」と、エリル卿は会釈をして言った。「詳しく聞かせてもらえて助かったよ。失礼する」
城付魔闘士が角を曲がった直後、ノルブースは愛馬に飛び乗っていた。一、二杯ほど飲み過ぎてはいたが、エリル卿の暗殺者より先にアンビントンに辿り着かなければならないのは明白であった。彼は道路沿いに進めば主人に追いつけるよう祈りつつ、帝都を出て東へと馬を走らせた。
カビと酸っぱくなったビールの臭いがする酒場の座席で、ストレイル卿は帝都の密偵であるブリシエンナ夫人の、密談をする際に多数の人間が集まる場を選ぶという手法に感心していた。アンビントンでは収穫期に入っており、畑仕事を手伝う労働者たちは僅かな給料を酒代に馬鹿騒ぎしつつあった。卿はその場に合わせ、粗い作りのズボンと質素な平民の上衣を着ていたが、それでも人目を引いている気がしてならなかった。連れである二人の女性に比べれば、確かにその通りであった。彼の右手に座る女性はダガーフォールの卑しい界隈に一介の娼婦として出入りするのに慣れていたし、左手に座るブリシエンナ夫人はそれをさらに上回る場慣れぶりであった。
「何とお呼びすべきでしょうか?」と、ブリシエンナ夫人が心配そうに聞いた。
「ジーナと呼ばれるのに慣れていますが、それも変えないといけないかもしれませんね」と、その女性は答えた。「もちろん、そのまま変わらないかもしれないけれど。墓石には娼婦のジーナと書かれるのかもね」
「花の祭典のようにあなたが襲われることのないよう、手を打ちます」と、ストレイル卿が眉をしかめて言った。「ですが皇帝の御助力無しでは、いつまでお守りできるかわかりません。唯一の抜本的な解決法は、あなたを狙っている者共を捕らえ、あなたにも相応の地位についていただくことです」
「私の話を信じていただけるのでしょうか?」ジーナはブリシエンナ夫人の方に向き直った。
「私はもう何年も、皇帝陛下のハイ・ロックでの密偵長を務めてきましたが、これほど奇妙な話を聞くことは稀です。もし大使殿の調査であのような事実が判明していなければ、すぐにあなたが正気を失っているのだと決めつけたでしょう」ブリシエンナ夫人は笑い、ジーナもこれに合わせて微笑んだ。「ですが、今は信じています。正気を失っているのは私なのかもしれませんが」
「御助力いただけるのですかな?」と、ストレイル卿が短く尋ねた。
「地方領に干渉するというのは難しい仕事なのです」と、ブリシエンナ夫人は手元の杯を覗き込みながら言った。「帝都そのものに対する脅威が存在しない限り、関与しないのが無難と考えています。この一件はすなわち、20年前に起きた非常に厄介な暗殺と、その余波なのです。皇帝陛下が諸領の世継ぎ問題全てに関与されてしまっては、タムリエル全体のために何もできなくなってしまうでしょう」
「わかります」と、ジーナはつぶやいた。「自分の正体と境遇を含め、全てを思い出した時、私は何もしないと決意しました。実のところ、カムローンを離れて故郷のダガーフォールに戻ろうとしていたところでストレイル卿と再会したのです。この一件を解決しようと行動を開始したのは、私ではなく彼なのです。卿に連れられて来た時、従妹に会って私が誰であるのか話したかったのですが、卿に禁じられました」
「それは危険過ぎるでしょう」ストレイル卿がうなった。「陰謀がどれほど深いものなのかをわかっていない。永遠に判明しないのかもしれん」
「申し訳ありません、短い質問に長い説明を返してしまう悪い癖がありまして。ストレイル卿に助力いただけるのか、と問われた時、最初に「はい」とお返事すべきでした」ブリシエンナ夫人はストレイルおよびジーナの表情の変わりように笑いをこぼした。「勿論お力になります。ですが、事態を良い方に向かわせるには、皇帝陛下の命のもとで二点、お願いしたいことがあります。一点目は、あなた方が暴いた陰謀の黒幕が何者であるのかを、絶対確実に証明していただきたいのです。誰かに自白をさせる必要があるわけです」
「二点目は……」ストレイル卿がうなずきながら言った。「この一件が地元の些事などではなく、皇帝陛下にご配慮いだたくにふさわしい問題であることを証明することだ」
ストレイル卿、ブリシエンナ夫人そしてジーナと名乗った女性は、その後数時間かけて目的の達成方法を話し合った。とるべき行動が決まると、ブリシエンナ夫人は仲間の一人であるプロセッカスを探しに席を立ち、ストレイル卿とジーナは西にあるカムローンに向けて出発した。森の中に入って間もなくして、遥か前方から疾走する馬の蹄の音が聞こえてきた。ストレイル卿は剣を抜き、ジーナに合図をして馬を自分の後方に配置するよう合図を送った。
その直後、敵が四方八方から襲いかかってきた。斧を持った男が8人潜んでいて、奇襲をしかけてきたのである。
ストレイル卿は素早くジーナを引き寄せ、自分のすぐ後ろへと移乗させた。そして手馴れた様子で、両手で短く模様を描いた。二人の周囲に火炎の輪が現れて外側へと広がり、暗殺者たちに命中した。男たちは悲鳴を上げて膝をつき、ストレイル卿は最も近くにいた敵を馬ごと飛び越えて全速力で西へ向かった。
「ただの大使様じゃなく、魔術師だったなんて!」ジーナは笑った。
「これで交渉が望ましい局面もあると、今でも信じていますよ」と、ストレイル卿が返した。
先ほど遠方に聞こえていた馬とその乗り手に道路上で遭遇してみると、相手はノルブースだった。「御主人様、城付魔闘士です! あなた方がアンビントンにいらっしゃることを知られてしまいました!」
「それも容易くな」エリル卿の声が森の中から鳴り響いた。ノルブース、ジーナそしてストレイル卿の三人は暗い木々の合間を見まわしたが、人影は見当たらなかった。魔闘士の声はそこら中から聞こえるものの、その出どころを特定することはできなかった。
「申し訳ございません、御主人様」ノルブースがうめいた。「できるだけ速くお報せにあがったのですが……」
「来世では飲んだくれに計画を知らせないよう、おぼえておくがいいさ!」エリル卿は笑った。そして三人に狙いを定め、呪文を放った。
指先から出た火球の光に照らされた魔闘士の姿を最初に見つけたのはノルブースであった。エリル卿は後に、あの愚か者は何をしようとしていたのだろうか、と自問することになる。ストレイル卿を火球の通り道から引っ張り出そうと突進したのか。あるいは破滅を免れようとしつつも、右へ避けるべきところで左へ避けただけなのか。それとも、可能性は低そうであったが、主人を救うために身を投げ出したのか。理由はどうあれ、結果は変わらなかった。
彼は火球の通り道にいたのである。
巨大な力の爆発が夜の森を明るく照らし、強烈な反響音が周囲一マイル以内の気を揺らし、そこにとまっていた鳥を揺さぶり落とした。ノルブースとその馬が立っていた地点には、黒ずんだ草のみが残されていた。蒸発どころではすまなかったのだ。ジーナとストレイル卿は爆圧で後方に投げ出され、乗っていた馬は我に返ると一目散にその場から走り去ってしまった。呪文の爆発の残光の中で、ストレイル卿は森の中の一点を凝視していた。驚いた表情の城付闘士と目を合わせていたのだ。
「くそっ」エリル卿はそう漏らすと走り出した。大使も跳ね起きてその後を追った。
「たとえ貴様とはいえ、今の呪文はマジカを大量に消耗しただろう」と、ストレイル卿は走りながら言った。「遠射呪文を放つ場合、目標が遮蔽されないことを確かめることくらい、貴様なら知っているはずだろう?」
「まさかあのうすのろが……」エリル卿は背後から殴りつけられ、言い終わる前に湿った森の地面に転がった。
「まさかではすまないのだよ」ストレイル卿は落ち着いた口調で言い、魔闘士を仰向けに引っくり返し、自分の両膝でその両膝を地面に抑えつけた。「私は魔闘士ではないが、もてる力の全てを貴様の仕組んだ不意打ち相手に使うべきではないことくらいわかっていた。もしかすると考え方の差かもしれんがな。国の遣いとして、私は浪費を好まないのだ」
「何をするつもりだ?」と、エリル卿が情けない声で聞いた。
「ノルブースは指折りのいい部下だった。貴様には苦痛を味わってもらう」大使が僅かに体を動かすと、その両手が眩く輝き始めた。「それだけは確かだ。その後でどれだけ貴様を痛めつけるかは、貴様がこれから喋る内容による。先のオロイン公爵について聞かせてもらおうか」
「何を話せばいい?」エリル卿が絶叫した。
「ひとまず洗いざらい吐け」。ストレイル卿は落ち着きはらった様子で返した。
タララ王女の謎 第4巻
メラ・リキス 著
ジーナが皇帝の密偵、ブリシエンナ夫人に会うことは二度となかったが、彼女は約束を守った。帝都に仕える処刑人、プロセッカスは、ストレイル卿の屋敷に変装してやってきた。ジーナは有能だった。数日もあれば知るべきことは学べてしまいそうだった。
「こいつは単純な魅了の呪文でして、激怒したデイドロスを恋にのぼせた子犬に変えてしまう、ということはありません」と、プロセッカスは言った。「相手を怒らせるようなことを実行するか、そういったことを口にすれば、効果が弱まるでしょう。ちょうど幻惑の流派の呪文のように、あなたに対する相手の認識を一時的にゆがめますが、敬意や憧憬の念を抱かせようとしたら、もう少しマジカ性の弱い魅了を使って対処しなければならないのです」
「わかったわ」ジーナは微笑むと、ふたつの幻惑の呪文を教授してくれて師に感謝した。身につけたばかりのスキルを実践するときがやってきた。
カムローンにある娼婦のギルド屋敷は立派な宮殿で、裕福な街の北部地区にあった。サイロン王子は目隠ししていようが、いつものように泥酔していようが、そこまでたどりつけた。が、今夜の王子はほろ酔いといったところで、これ以上は一滴も飲まないと決めていた。今夜は楽しみたい気分だった。彼らしいやり方で。
「私のお気に入りはどこだね、グリジア?」彼は入ってくるなり、ギルドの女将に申しつけた。
「あの娘は先週のご指名で負った傷がまだ癒えておりませんのよ」と、女将は穏やかに言った。「他の娘はみな出払っておりますわ。けれど、あなたのためにとっておきの娘を残しておきましたの。新人ですけど、きっとお楽しみいただけますわ」
王子が案内されたのはビロードとシルクでぜいたくに装飾された特別室だった。王子が入ってくるのをみて、ジーナはついたての陰から歩み出ると、素早く呪文をとなえた。プロセッカスに教わったように、おおらかな心で信じながら。最初は魔法が効いているのかどうかなんとも言えなかった。王子は残忍な笑みを浮かべてジーナを見ていたが、雲間から太陽がのぞくように、残虐性がさっと晴れた。王子はジーナの手中にあった。彼女に名前を訊いてきた。
「名前と名前の板ばさみになっておりますの」ジーナはからかった。「本物の王子様と愛し合ったことなんてございませんわ。王宮に入ったことすらありませんの。さぞかし…… ご立派なんでしょうね」
「まだ私のものではない」王子は肩をすくめた。「が、いつかきっと王になる」
「あんな王宮で暮らせたら素敵でしょうね」と、ジーナは甘えた声で言った。「一千年の歴史。見るものすべてが古めかしくて美しい。絵画、書物、彫像、タペストリー。皇室の方々は過去の財宝をみんな手放さずに持っておりますの?」
「ああ。くだらないがらくたと一緒に宝物庫の資料室にしまってある。そろそろ、おまえの裸を見せておくれ」
「まずはおしゃべりを楽しんでから。王子様がお脱ぎになりたいとおっしゃるなら、どうぞご自由に」ジーナは言った。「資料室があるとは聞いておりましたけど、巧みに隠されているとか」
「皇族の墓所の裏手にまやかしの壁がある」と、王子は言った。彼女の手首をつかんで引き寄せると、彼女の唇を奪った。と、その目つきが変わった。
「腕が痛みますわ」と、ジーナは叫んだ。
「おしゃべりはおしまいだ、妖艶な売春婦め」王子は怒鳴った。鋭い恐怖心を押さえつけながら、ジーナはつとめて冷静であろうとし、知覚イメージが流れるにまかせた。王子の怒れる口が彼女の唇に触れると、ジーナは幻惑の師から学んだふたつめの呪文をとなえた。
王子は肉体が石と化したのを感じた。その場に凍りついたまま、ジーナが乱れた服装を直して部屋から出ていくのを見ていた。麻痺状態はあと数分しか続かないが、ジーナにとってはそれだけで充分だった。
ジーナとストレイル卿の指示どおり、ギルドの女将はすでに娼婦たちを連れて逃げていた。事態が沈静化すれば、戻ってくるようにとの連絡が彼らから入ることになっていた。この計略の一端を担ってくれたにもかかわらず、女将は一銭も受け取ろうとしなかった。娼婦たちはあの残虐な変態王子に二度と拷問されないですむなら、それだけで充分だからと。
「とんでもない坊やね」法衣の頭巾を上げながら、ジーナは思った。ストレイル卿の屋敷に向かって通りを突っ走っていた。「あの坊やが王になることがなくてよかったわ」
翌朝、カムローンの王と王妃はいつものごとく貴族やら外交官やらと接見していた。人の集まりが悪く、謁見室はがらがらだった。一日を始めるやり方としてはあまりに気だるかった。ひとつの陳述が終わると、いかにも王らしいあくびをした。
「肝心な人たちはどうしてしまったの?」王妃がつぶやいた。「私たちの大切な坊やは?」
「北区のあたりで荒れに荒れているらしい。娼婦に騙されてあとを追ってるようだな」王は愛のある含み笑いをもらした。「なんともできのいい息子だわい」
「それなら、あなたの魔闘士は?」
「きわめて難しい任務にあたらせている」王は眉を寄せた。「が、かれこれ一週間になるし、まるで音沙汰がない。穏やかではないな」
「もちろんだわ。エリル卿をそんなに長い間遠ざけておくべきじゃないもの」王妃は顔をしかめた。「危険な妖術師が私たちを脅してきたらどうするの? あなたは笑うかもしれないけれど、ハイ・ロックの王族が魔術師の家臣をいつも傍らに待機させているのはそのためでしょう。邪悪な付呪から王宮を守るためだわ。こないだだって、哀れな皇帝が付呪に苦しめられたじゃないの」
「側近の魔闘士の手でな」王はくすくすと笑った。
「エリル卿はあんなふうにあなたを裏切ったりはしないわ。わかってるでしょう。あなたがオロインの公爵だった時代から仕えてきてるのよ。エリル卿とジャガル・サルンをそうやって比較するなんて、まったく…」王妃ははねつけるように手を振った。「タムリエル各地の王国をむしばんでいるのは、その類の信頼感の欠如なの。ストレイル卿なら──」
「そういえば彼も行方不明になっているな」王は沈思黙考した。
「大使のこと?」王妃はかぶりを振った。「いいえ、ここにいるわよ。どうしても墓所を訪れてあなたの高貴なる祖先に敬意をささげたいって言うから、場所を教えてあげたわ。おかしいくらい時間がかかってるけど、それだけ敬虔だってことかしらね」
王妃は驚いた。王が立ち上がったのだ。その顔に危機感を浮かべて。「どうして黙ってたんだ?」
王妃が答えようとするまでもなく、話題の主が開け放たれた扉から謁見室に入ってきた。一流貴族が着るような緋色と金色の壮麗なガウンをまとった金髪の女性をその腕に従えて。王妃は、あ然としている夫の視線を追っていき、同じようにあ然とした。
「大使は『花祭り』の娼婦の一人にご執心だったと思ったけど、淑女ではなくて」と、王妃はささやいた。「しかも、あなたの娘にそっくりだわ、ジリア夫人に」
「ああ、瓜二つだ」王は息をのんだ。「ジリアのいとこのタララ姫だ」
謁見室の貴族たちはこそこそと話をしていた。姫が失踪したのは20年前で、王族の他のメンバー同様に殺されたというのが大方の見方だった。その当時から王宮で働いていたものは少なかったが、何人かの古参の政治家がはっきりと覚えていた。玉座の上に限らず、「タララ」という言葉が付呪のように空気中を伝播していた。
「ストレイル卿、そちらのご淑女を紹介していただけませんか?」王妃は丁寧な笑みを浮かべて訊いた。
「しばしお待ちを、王妃様。まずは、火急の件を論じなければなりませんので」ストレイル卿は頭を下げた。「できれば内密に行いたいのですが」
王は帝都の大使をじっと見て、表情から真意を読み取ろうとした。手を振りかざして貴族たちを退出させ、扉を閉じさせた。謁見室に残されたのは王、王妃、大使、数名の近衛兵、それと謎の女性だった。
大使がポケットから一枚の黄ばんだ羊皮紙を取り出した。「王様、兄上とご家族が殺されてあなたが戴冠されたとき、当然のことですが、証文や遺言のような重要書類はすべて、書記官や大臣の管理のもとで保管されました。亡き王の副次的な重要ではない私的文書については、慣習にのっとって、資料室に送られました。この手紙はその中から見つかったものです」
「いったいどういうことなのかね?」と、王は大声で言った。「手紙には何と?」
「王様のことではありません。実際のところ、王様が戴冠なさった時点では、誰かが手紙を読んだところでその意義が理解できなかったでしょうな。手紙はあなたの兄上である亡き王が皇帝に宛てたもので、暗殺の直前に書かれました。ここカムローンのセシエテ神殿にかつて魔術師および僧侶として仕えていた、義賊についての手紙です。その義賊の名は、ジャガル・サルン」
「ジャガル・サルン?」王妃はそわそわしながら笑った。「あらあら、ちょうどサーンのことを話してたのよ」
「サーンは、強力な呪文や忘れられし呪文に関する書物を何冊も盗み出しました。それから、混沌の杖のような秘宝にまつわる伝承も。杖の隠し場所や使い方を知るために。情報はゆっくりと西方のハイ・ロックまでやってきます。皇帝の新たな魔闘士の名がジャガル・サルンだという情報が亡き王の耳に入る頃には、もう何年も過ぎていました。亡き王は手紙をしたためて、背徳の魔闘士について皇帝に警告しようとしました。が、手紙が完結することはなかったのです」ストレイル卿は手紙を高く掲げた。「手紙の日付は385年の、王が暗殺された日です。ジャガル・サルンが皇帝を裏切って『虚構帝都』による10年間の暴政を開始する4年前のことです」
「じつに興味深い話だが」王は吠えるように言った。「私と何の関係があるのだ?」
「帝都は現在、亡き王の暗殺にただならぬ関心を寄せています。そして、あなたの忠実なる魔闘士、エリル卿から自白を取らせていただきました」
王は顔色を失った。「このみすぼらしい虫けらめ、何人たりとも私を脅せるものか。おまえも、その娼婦も、その手紙も、もう二度と陽光をおがむことはあるまい。衛兵!」
近衛兵が剣を抜き放ち、つめ寄ってきた。と、いきなり光がきらめき、プロセッカス率いる帝都の処刑人たちがわらわらとわいてきた。彼らは何時間も部屋に潜んでいたのだ。誰にも気づかれないように影の中で息を殺して。
「帝都の偉大なる太陽、ユリエル・セプティム七世の名において、あなたを逮捕します」と、ストレイルは言った。
扉が開かれ、うなだれた王と王妃が連れ出された。ふたりの息子であるサイロン王子が寄りつきそうな場所を、ジーナはプロセッカスに教えた。謁見室にいた廷臣や貴族は、彼らの王と王妃が奇妙なほど厳粛に王立刑務所へと行進していくさまをながめていた。口を開くものはいなかった。
とうとう声が上がったとき、誰もが仰天した。ジリア夫人が王宮に到着したのだ。「どういうことなの? 王と王妃の権威を奪ったりして、一体どういうつもりなの?」
ストレイル卿はプロセッカスのほうを向いた。「われらとジリア夫人だけで話をしたほうがいい。なすべきことはわかっているな?」
プロセッカスはうなずくと、謁見室への扉をまたもや閉めた。廷臣たちは木の扉に体を押しつけ、ひと言たりとも聞き逃さないよう耳をそばだてた。黙ってはいたが、彼らもまた、ジリア夫人と変わらぬくらい事情を知りたがっていたのだ。
タララ王女の謎 第5巻
メラ・リキス 著
「何の権利を持って父を拘束するのですか?」ジリア夫人は叫んだ。「彼が何をしたと言うの?」
「私はインペリアル司令官、および大使として、カムローンの王者、オロインの元デュークを拘束する」ストレイク卿は言った。「地方の貴族権限のすべてに優先するタムリエルの皇帝の秩序権限に基づいて」
ジーナは前に進みジリアの腕に手を添えようと試みたが、冷たく突き返された。彼女は、今は誰もいない謁見室の玉座の前に、静かに座り込んだ。
「完全に記憶を取り戻したこの若い女性が私のもとを訪れてきたのだが、彼女の話は信じ難いを超越していた、単純に信じられなかったのだ」と、ストレイク卿は話した。「しかし、彼女は確信していたので、私も調査してみるしかなかった。その話に多少なりとも真実性があるか、20年前、この王宮にいた全員と話した。当然、王者と女王が殺害され、王女が失そうしたときは完全な取り調べが行われたが、今回は違う質問があった。その質問とは、2人の従姉妹、ジリア・レイズ夫人と王女の関係だ」
「何度も何度もみんなに言いました、人生で、あの時期だけ何も覚えていないのです」と、涙を浮かべながらジリアは言った。
「それは分かっている。あなたが恐ろしい凶行を目撃し、あなたと彼女の記憶が消えたことは一度も疑ったことがないし」ストレイル卿はジーナを手招きしながら言った。「疑う余地もない。王宮の召使いや他の人たちから、少女たちは密接な間柄だったと聞いた。他に遊ぶ友達もいなく、王女は常に親のそばに居なければいけなかったので、幼い頃のジリア夫人もそのすぐそばにいた。暗殺者が王族を殺しに来たとき、王者と女王は寝室に、そして少女らは謁見室にいた」
「記憶が戻ったときは、まるで封印された箱を開けたようだったわ」と、ジーナは厳かに言った。「20年前ではなく、昨日起きた出来事のようにすべてが鮮明で詳細だったの。私は玉座に座って女帝を演じていて、あなたは演壇の裏に隠れて、私があなたを投獄した地下牢に入れられているフリをしていたの。血まみれの刀をもった知らない男が、部屋に王の寝室から飛び込んできたわ。私に向かってきたから必死で逃げたの。演壇に向かって走り始めたのを覚えているけど、あなたの恐怖で凍りついた顔が見えて、彼をあなたに導きたくなかったわ。だから、窓に向かって走ったの」
「前、一緒にふざけて城壁を登ったことがあったわね、あの崖にしがみついている姿が、一番初めに戻ってきた記憶だったわ。あなたと私が城壁に登って、下から王が降り方を言ってくれたわね。でも、あの日は、あまりにも震えていて、つかまっていられなかったの。私は落ちて、川に着水したの」
「目撃した恐怖のせいか、それとも落下した衝撃と水の冷たさが折り重なってかは分からないけど、頭の中が真っ白になったの。かなり離れた場所でようやく川から自分を引っ張り出したとき、自分が誰だか分からなかったわ。それがそのまま続いたの」ジーナは笑った。「今まではね」
「では、あなたがタララ王女なのですか?」と、ジリアは叫んだ。
「私が混乱したように、単に結果だけを言ってしまうとあなたも混乱してしまうので、その問いに彼女が答える前に、もうちょっと私に説明をさせてもらおう」ストレイル卿が言った。「暗殺者は王宮から逃げられる前に捕まった── 実のところ、捕まると分かっていたはずだ。彼は即座に王族を殺害したことを認めた。彼が言うに、王女は窓から投げ出して殺したと。下に居た召使いが悲鳴を聞き、何かが窓の前を飛び落ちていくのを見ているので、彼はそれが事実であると知っていた」
「子守り役のラムクによって演壇の裏に隠れていた幼いジリア夫人が、恐怖で震えながら喋れずに、誇りまみれで発見されるまで数時間かかった。ラムクはとてもあなたのことを注意深く守っていた」ストラルはジリアに向かってうなずきながら語った。「彼女は、即刻あなたを部屋へ連れて行くよう主張して、オロインのデュークへ、王族が殺害され、彼の娘が殺人を目撃したが生き延びたとの伝言を走らせた」
「そのことは、少しだけ思い出してきました」と、不思議そうにジリアは言った。「ラムクに慰められながらベッドで横になっていたのを覚えています。すごく混乱していて、集中できなかったのです。なぜかは分かりませんが、ずっとお遊びの時間であって欲しいと思っていたのを覚えています。そして、荷物をまとめられて、養育院へ連れられて行かれたのを覚えています」
「もうすぐすべて思い出すわ」ジーナは微笑んだ。「保証するわ。それが思い出し始めた方法よ。一つだけ詳細を掴んだら、すべてが流れこんできたの」
「それです」ジリアは失意で泣きだした。「混乱以外の何も覚えていません。いえ、連れ去られるとき、父が私のことを見てもくれなかったことも覚えています。そして、そのことも、他のことも気にしていなかったことを覚えています」
「皆にとって混迷期だった、特に少女たちにとっては。とりわけ、あなたたち二人が体験したような羽目にあった少女たちには……」と、同情してストレイル卿は言った。「私の理解では、ラムクからの伝言を聞いたデュークは、オロインの王宮を後にして、あなたがこの出来事から回復するまで私設療養所へ送るよう命じ、情報を引き出すために、私設衛兵とともに暗殺者の拷問に着手した。最初の自白をしたとき以降、デュークと私設衛兵以外は暗殺者を見ていなく、暗殺者が脱走しようとして殺されたとき、デュークと彼の衛兵以外誰も居なかったということを初めて聞いたとき、私はそれを重要視した」
「その場に居たことが分かっていたうちの一人、エリル卿と話をしたが、手にしている以上の証拠品を持っているように見せかけ、脅さなければならなかった。危険な作戦ではあったが、願っていたような反応が得られた。とうとう彼は、私が真実であると分かっていたことを自供した」
「暗殺者は……」ストレイル卿は中断し、そして仕方なくジリアの目を見て言った。「相続人の王女も含めて、王族を殺害するために、オロインのデュークによって雇われていたのだ。彼や子供たちに王冠が渡るように」
ジリアは驚き、ストレイル卿を見つめた。「私の父が──」
「暗殺者は、デュークが彼を拘留したら、すぐに報酬が支払われ、脱獄が準備されると言われていた。だが、この悪党は欲を出す場所を間違えて、ゴールドをもっと手に入れようとした。デュークは沈黙させてしまうほうが安上がりだと判断し、彼が事の真相を誰にも話せないように、その場で即刻殺してしまった」ストレイル卿は肩をすくめた。「たいした損失ではないな。それから数年後、幼児期の記憶が完全に欠如していることを除けば、少々動揺してはいるものの、普通に戻ったあなたが療養所から戻った。そしてその間に、オロインの元デュークは兄の変わりにカムローンの王者となっていた。容易くできたことではない」
「ええ」と、ジリアは静かに言った。「もの凄く忙しかったのだと思います。彼は再婚して、もう1人子供がいました。ラムク以外は誰も療養所へ見舞いにきませんでした」
「もし彼が見舞いにいって、あなたを見ていたら……」と、ジーナが言った。「この話はまったく違う展開になっていたかもね」
「どういう意味ですか?」と、ジリアは問いかけた。
「ここが一番驚くべきところだ」と、ストレイル卿が言った。「以前から、ジーナがタララ王女なのかどうかが問われていた。彼女の記憶が戻り、覚えていることを私に話してくれたとき、私はいくつかの証拠をつなぎ合わせた。これらの事実を考えてみよう」
「まったく違う人生を歩んできたあなたたち2人は20年後の今も著しく似ているし、変わらぬ遊び友達、そして少女だったあなたたちは瓜二つだった」
「暗殺のとき、そこに行ったことがなかった暗殺者は、玉座の上に1人の少女しか見ておらず、彼はその子を獲物と思いこんだ」
「ジリア夫人を見つけだしたのは不安定な精神の持ち主で、自分の役目に狂信的な愛着をもっていた子守り役のラムクだった── その種の人は、自分が愛してやまない少女が、行方不明になったほうかもしれないという可能性を絶対に受けいれない。子守り役はあなたを療養所で見舞った、タララ王女とジリア夫人の2人を知る唯一の人物だった」
「最後に」と、ストレイル卿は言い放った。「あなたが宮廷に戻ったとき、5年間がすぎていて、あなたは子供から若い女性へと育っていた事実を考えてもらおう。見覚えはあるが、あなたの家族が覚えているあなたとは完全に一致しない、もっともなことではある」
「理解できません」可哀想な女性は目を見開いて叫んだ。だが、理解できていた。彼女の記憶はひどい洪水のように流れ、集まっていた。
「こう説明するわ……」彼女の従姉妹は腕で包みながら言った。「今は自分が誰なのかわかるわ。私の本名はジリア・レイズ。拘束された男は私の父親、王者を殺した男── あなたの父を。あなたがタララ王女なのよ」