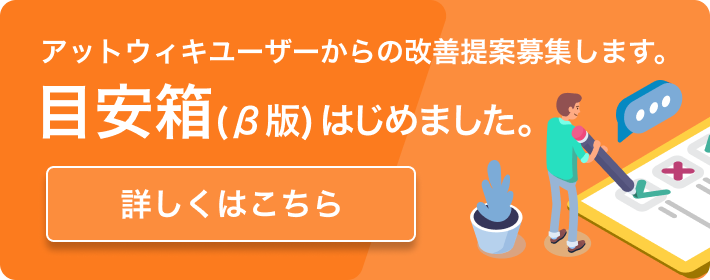オブリビオン図書館
ドゥーマー太古の物語
最終更新:
oblivionlibrary
-
view
ザレクの身代金
ドゥーマー太古の物語 第1部
マロバー・サル 著
ジャレミルは彼女の庭園に立ち、召使いが持ってきた手紙を読んだ。手にしていたバラの束が地に落ちた。一瞬、鳥のさえずりが消え、雲が空を覆った。丁寧に育て、作り上げてきた安息の地が暗闇に包まれた。
「息子は預かった」手紙にはそう書かれていた。「近いうちに身代金の要求をする」
やはりザレクは、アッガンに辿り着けなかったんだわ。道中の強盗、多分オークか憎たらしいダンマーに、上品な乗り物を見られて人質にとられたんだわ―― ジャレミルは柱にもたれ掛かり、息子に怪我がないかを案じた。彼はただの学生で、装備の整った男たちと戦えるような子ではないけど、殴られたりしていないかしら―― 母親の心には、想像するに耐え難いことであった。
「もう身代金を要求する手紙が来たなんて言わないでよね」聞き覚えのある声と見慣れた顔が垣根の隙間から見えた。ザレクであった。ジャレミルは涙を流しながら、急いで少年を抱きしめに行った。
「何が起こったの?」彼女は声を上げた。「誘拐されたんじゃなかったの?」
「されたよ」と、ザレクは行った。「フリムヴォーン峠で、もの凄く大きなノルド3人が、僕の乗り物を襲ったんだ。マサイス、ユリン、コーグ、この3人は兄弟だって分かったの。母さんにも見せてあげたかったな、本当に。もし正面玄関をくぐろうとしたら苦労すると思うよ」
「何が起こったの?」と、ジャレミルは再度問いかけた。「助けられたの?」
「助けを待とうとも考えたんだけど、身代金要求の手紙を送るって分かっていたし、母さんが心配性なのも分かっているから。だから、アッガンの先生がよく言っていた言葉を思い出したんだ、落ち着いて、周りを良く見て、敵の弱点を探る」ザレクはにっこりと笑った。「彼らは本当に怪物だったから、すこし時間が掛かっちゃったけどね。それで、彼らがお互いに自慢しあっている話を聞いたとき、彼らの弱点は虚栄心だって分かったの」
「それで何をしたの?」
「カエルに近い、幅広い川を見下ろす小高い丘の森のキャンプで鎖につながれていたの。コーグが、あの川を泳いで往復するには1時間近く掛かるだろうって、他の二人に話しているのを聞いたんだ。二人とも同感でうなずいていた、そのとき話しかけたんだ」
「僕なら30分で戻ってこられるね」そう僕は言ってやった。
「無理だ」と、コーグが言い放った。「おまえみたいな子犬より、俺のほうが早く泳げる」
「そこで、2人とも崖から飛び降りて、真ん中の島まで泳いで帰ってくるって決めたんだ。お互いの岩まで行ったとき、コーグが義務付けられているみたいに水泳のコツを僕に説教し始めたんだ。最大の速度のための、連動した腕と足の動きの重要性。息継ぎは、頻繁すぎて遅くならず、少なすぎて息切れしないように、必ず3、4回水を掻いたあとにすることがどれだけ肝心か。彼が言うコツに同意して、うなずいたんだ。それでお互いに崖から飛び込んだの。1時間ちょっと掛けて島まで泳いで帰ってきたけど、コーグは戻ってこなかった。彼は崖の下にある岩で頭をかち割っていたんだ。水の動きで水面下の岩が分かったから、飛び込むのに右の岩を選んだの」
「それで戻っちゃったの?」と、驚いたジャレミルは聞いた。「そのときに逃げたんじゃないの?」
「そのとき、逃げるのは危険すぎたよ」と、ザレクが言った。「彼らは僕を簡単に捕まえられただろうし、コーグが消えた責任も負わされたくなかったしね。彼に何が起きたか分からないと言ってから、ちょっと捜した後で、彼らはコーグが競争のことを忘れて、向こう岸で食料でも狩っているのだろうって思ってくれたの。僕が泳いでいたのは見えていたし、彼の失そうに関係があるとは思えなかったんだろうね。兄弟は僕が逃げられないように理想的な場所を選んで、岩の多い、崖のふちに沿ったところにキャンプを張り出したんだ」
「兄弟の一人、マサイスが、下の入り江の周りを巡る土の質と、岩の緩やかな傾斜について意見を言い始めたんだ。競争に理想的だ、そう彼は言った。僕がその競技について何も知らないことを伝えると、彼は競争に適した技術の一部始終を教えたがったんだ。変な顔を作って、どれだけ鼻から息を吸って口から出すことが必要かとか、どのように膝を適切な角度まで持ち上げるかや、足運びの重要性などをね。一番重要なのは、勝つつもりなら走者は積極的な、でも疲れすぎない速度を保つべきだと言った。二番手を走ってもいい、もし最後に追い抜く意志と体力があるならって言ったんだ」
「僕は熱心に聞き入ったよ、そしてマサイスは、夜になる前に入り江のふちの周りで簡単な競争をすると決めたんだ。ユリンは僕たちに、戻るときに薪を持ってこいと言った。僕たちは細道を過ぎたらすぐに、崖のふちに沿って走り始めたの。息や足取りや足運びは彼の忠告通りにしたけど、最初から全速力で走った。彼の足のほうが長いにもかかわらず、最初の角を曲がったとき、僕は彼の数歩前を走っていたんだ」
「彼の目は僕の背中に置かれていて、マサイスは僕が飛び越えた崖の割れ目が見えなかったんだ。叫ぶ間もなく下に落ちて行ったよ。キャンプに居るユリンのところへ戻る前に、数分かけて何本か小枝を拾ってから戻ったんだ」
「まったく、調子に乗って」と、しかめ面をしたジャレミルが言った。「間違いなく、その時に逃げればよかったのに」
「そう思うかもしれないけど」と、ザレクは同意しながら言った。「でもね、あの地形を見れば分かるよ―― 大きな木が何本かあって、他は低い木ばかりだったんだ。ユリンは僕が居ないことに気付いただろうね。すぐに追いつかれたら、マサイスが居ないことを説明するのがとても難しかったと思う。だけどね、手短に周辺を見て回れたおかげで何本かの木をじかに見られたから、最後の計画を立てられたんだ」
「僕は何本かの小枝を持ってキャンプに戻り、マサイスは大きな倒木を引っ張っているから、戻るのに時間がかかっているとユリンに言ったんだ。そうしたらユリンはマサイスの腕力をあざ笑って、彼では生きている木を引き抜いて燃やすには時間がかかると言ったんだ。僕は言ってやったんだ、そんなことはできないでしょうと」
「『見せてやるよ』と彼は言い、10フィートもの木を楽々と引き抜いたんだ」
「『でも、それはただの苗木だ』と僕が意見したんだ。『大木を引っこ抜けると思ってたのに』」彼の目は、僕の視線を追い、その先にある素晴らしい大木を見た。ユリンはその大木をつかんで、凄まじい力で根から土を離そうとゆすり始めたんだ。それで、木の一番上の枝から垂れ下がっていた蜂の巣が緩んで、彼の頭の上に落ちたんだ。
「母さん、僕はその時逃げたんだ」ザレクは少年らしい誇らしさで締めくくった。「マサイスとコーグは崖の下、そしてユリンは蜂の大群に飲み込まれて必死になっているときにね」
ジャレミルはもう一度息子を抱きしめた。
出版社注:
私は「マロバー・サル」の作品を出版する事に気が進まなかったが、グウィリム大学出版局がこの版の編集を依頼してきた時、この機会にきっぱりと事実を明確にしようと決めた。
学者たちはマロバー・サルの作品の正確な年代に関して同意していないが、それらの作品は、初代シロディール帝都の崩壊とタイバー・セプティムが台頭するまでの空白期間に、一般的な喜劇や恋愛物語で有名な劇作家「ゴア・フェリム」によって書かれたものであるという説に大多数が同意している。現在の説が支えるのは、フェリムは本物のドゥーマーの物語をいくつか聞き、金儲けのためにそれらを舞台に適応したり、自分の劇を書き換えたりしたという点だ。
ゴア・フェリムは自分の作品に妥当性を持たせるために、まただまされやすい人々にとってさらに貴重であるよう、ドゥーマーの言語を翻訳できる「マロバー・サル」の人物像を作り上げた。注目すべきは、「マロバー・サル」と彼の作品が激しい論争の題材になったが、実際に誰かが「マロバー・サル」に会った信頼性のある記録もなければ、同名の人物が魔術師ギルドやジュリアノス、または他の知的団体に所属していた記録もない。
どうであれ、「マロバー・サル」の物語の中でドゥーマーは、ダンマーやノルドやレッドガードさえも服従させ、現在でさえも解明されていない遺跡を作った、恐ろしくて計り知れない種族に類似点を持っている。
種たるもの
ドゥーマー太古の物語 第2部
マロバー・サル 著
ロリックのハムレット村は、単調な灰色と褐色の砂丘やデジャシスの岩山に抱かれた、静かでのどかなドゥーマーの集落であった。なんの草木もロリックには生えていないが、黒く変色した大きな枯れ木が街中のいたるところに転がっていた。幌馬車で到着したカムディダは、彼女のあたらしい街に落胆した。彼女は父の家族が暮らしていた、北の森林地帯に慣れていた。ここには木陰や広々とした空もなければ、水もすくない。ただの荒れ地に見えた。
母親の家族がカムディダと弟のネビスを引き取り、とても優しく孤児たちに接したが、彼女は見知らぬ村で寂しかった。そんなとき、給水所で働くアルゴニアン老女に出会い、カムディダは友達を得た。名前はシゲルス、そして彼女の家族は広く、麗しかった頃のロリックに、ドゥーマーが現れる何世紀も前から住んでいたと言った。
「なんで木々は死んだの?」と、カムディダは聞いた。
「アルゴニアンしかこの地に居なかった頃、私たちにはあなた達が使うような燃料や木製の建物の必要がなかったから、木を切らなかったのよ。ドゥーマーが来たときも、私たちやこの土地にとって神聖なヒストの木を傷つけないかわりに、必要な時は工場とかを使わせてあげていたの。その後、お尋ね者とかも出ず、何年も平穏な暮らしが続いたわ」
「それで、何が起こったの?」
「あなたたちの科学者が、ある樹液を蒸留して、成形して、乾かすことでレジンと言う弾力性のある鎧を作れることを発見したの」と、シゲルスは言った。「ここで育つほとんどの木の樹皮のしたにはちょっとしか液体がないの、でもヒストの木は違うわ。多くは樹液で溢れていたの、それはドゥーマーの商人たちを強欲にしたわ。商人たちはジュニンという木こりを雇って、利益のために聖なる木の伐採を始めたの」
アルゴニアン老女はほこりが舞う大地を見て、ため息をついた。「もちろん私たちアルゴニアンは皆反対したわ。私たちの家だったし、ヒストの木は一度消えたらもう戻らないもの。商人たちは考え直してくれた、でもジュニンたちは私たちを打ちのめすつもりだったの。ある恐ろしい日、彼の並外れた斧の腕前は木々だけではなく人にも通用すると証明したの。彼の行く手を阻んだ人たちは、老若男女を問わずバラバラに切り倒されたわ。ロリックのドゥーマーたちは皆、家の扉を閉じて殺人の叫び声に耳を閉ざしたの」
「ひどい」と、あえぎながらカムディダは言った。
「説明するのは難しいけど……」と、シゲルスが言った。「私たちにとって、木々の死に比べたら、生きているものの死はたいしたことじゃないのよ。分かって欲しいのは、私たちにとってヒストの木は母であり、目指す場所なの。体を破壊されるのはどうってことないの、でも私たちの木々を滅ぼすことは、私たちを根絶やしにすることなの。そしてジュニンがヒストの木に斧を向けたとき、彼はこの土地を殺したの。水は枯れて、動物は死に、木々によってその命を支えられていた生き物はみな干からびて、ほこりとなったのよ」
「でも、まだここに居るの?」カムディダは聞いた。「なぜ去らなかったの?」
「私たちは身動きが取れないの。私は死に行く最後の数人の1人なのよ。私たちの多くは先祖代々の林を離れて暮らしていけるほど強くはないし、今でも時折り、ロリックの空気に生きる気力を与えてくれる香りが漂っているわ。私たちが全員いなくなるまで、それほど時は掛からないわ」
カムディダは目に涙が浮かんでくるのを感じた。「そうしたら私は木々もなく、友達もいないこんな場所で独りぼっちになっちゃう」
「私たちアルゴニアンには良い表現があるわ」悲しそうな微笑を浮かべ、カムディダの手を取りながらシゲルスは言った。「種の最良の土壌は心の中にあるものなのよ」
カムディダが手の中を見ると、そこにはシゲルスが渡した小さくて黒いものがあった。種であった。「死んでるみたい」
「ロリックの中のある一ヶ所でしか育たないのよ」と、老アルゴニアンは言った。「街外れの丘に建つ古い小屋の外よ。私はそこへは行けないの、所有者に見られたら、その場で殺されてしまうし、他の私と同じ種族の人たちのように、今では自分を守るには脆すぎるの。でも、あなたならそこへ行って種を植えられるわ」
「どうなるの?」と、カムディダは聞いた。「ヒストの木が戻るの?」
「いいえ。でも、木の力の一部は戻るわ」
その夜、カムディダは家を抜け出し丘へと向かった。シゲルスが話した小屋は知っていた。叔父と叔母からは絶対にそこへは行かないようにと言われていた。近くまで行くと、扉が開き、老いてはいるが屈強な体格の男が大斧を肩に乗せて現れた。
「おい、ここで何をしている?」彼は詰問した。「暗くてトカゲ野郎と間違えそうになったぞ」
「暗くて道に迷ってしまったのです」彼女は瞬時に答えた。「ロリックにある家へ帰ろうとしているのですけど」
「では早く行け」
「ロウソクを1本貰えませんか?」彼女が聞いた。「ぐるぐると同じところを歩いていて、明かりがなかったらまたここに戻ってきてしまいそうです」
老人はブツブツ言いながら家の中へと入っていった。カムディダは素早く穴を掘り、できるだけ深く種を埋めた。男は明かりを灯したロウソクを持って戻ってきた。
「絶対ここへは戻るなよ、もし戻ったら……」うなり声で彼は言った。「真っ二つにしてやる」
彼は暖かい家の中へと戻っていった。次の朝、目覚めた彼は扉を開けると、小屋が巨大な木の中に完全に閉じ込められていることに気付いた。斧を拾って、木に向かって次から次へと切りかかるが、打ち破れなかった。横から切ってみたが、木は治癒してしまった。上下左右から切って、くさび形の切り込みを入れようとしたが、木は治癒してしまった。
ジュニンのやせ衰えた体が、鈍り、折れた斧を手に持ち、開け広げられた扉の前に横たわっているのを誰かが発見するまでにはかなりの時がすぎた。何を切っていたのか皆には謎であったが、刃にはヒストの樹液が付いていたとの伝説が、ロリックでささやき始められた。
それから暫らくして、小さな砂漠の花が乾いた土を押し分けて、育ち始めた。新しく植えた木々や植物も、豊かにとは言えなかったとしても、それなりに育ち始めた。ヒストの木は戻らなかったが、カムディダやロリックの人々は、夕暮れ時のある時刻になると、過去の偉大な木々の長い陰が、街や丘を包み込んでいることに気付いた。
出版社注:
『種たるもの』はマロバー・サルの物語りの1つで、何に由来するかは誰もが知っている。この物語は、南モロウウィンドのアルゴニアの奴隷に源を発する。マロバー・サルは単に、ダンマーと記されたところをドゥーマーに変え、ドゥーマーの遺跡で見つけたと主張した。さらに、アルゴニア版は、ただ単に彼の「原本」を改作しただけであると後に主張した。
明らかにドゥーマーの地名ではないロリックは、簡単に言うと、存在しないのである。その上、ロリックとはゴア・フェリムの劇中で頻繁に、ダンマーの男という意味で間違って使われていた名前である。アルゴニア版の物語はたいていヴァーデンフェル島のテルヴァンニの街かサドリスモーラを舞台とする。もちろん、零の神殿の「学者」と言われている人たちは、この物語は「ロルカーン」と関連していると言うであろう、同じ「ロ」の文字から始まっているだけで。
狙いどころ指南書
ドゥーマー太古の物語 第3部
マロバー・サル 著
オスロバーの族長は、彼の賢者たちを集めこう言った。「毎朝、家畜が死んでいる。何が原因なのだ?」
ファングビス戦闘隊長は言った。「モンスターが山から下りてきて、家畜を食べているのかもしれません」
治癒師ゴーリックは言った。「新種の疫病が原因かもしれませんな」
ベラン司祭は言った。「女神に助けていただくには、生けにえを捧げる必要がある」
賢者たちは生けにえを捧げ、彼らが女神からの答えを待つ間、ファングビスは師匠ジョルタレグの下へ行きこう言った。「ゾリアの棍棒の鍛造や、それを戦闘でどのように使うのかを実によく教えていただきましたが、今は自分の技能をいつ使えばよいのかを知る必要があります。女神からの回答があるまで、または薬が効くまで待つのでしょうか。それとも山にいると分かっているモンスターを退治に行くのでしょうか?
」
「『いつ』は重要ではない」と、ジョルタレグは言った。「『どこ』なのかが重要だ」
ファングビスはゾリアの棍棒を手に持ち、暗い森の中を遠く、偉大な山のふもとまで歩いた。そこで彼は2匹のモンスターに出会った。オスロバーの族長の家畜の血でぬれていた片方は、連れが逃げるあいだ彼と戦った。ファングビスは「どこ」が重要であると言った師匠の言葉を思い出した。
彼はモンスターの急所5ヶ所を殴った。頭、股間、喉、背中、胸。五ヶ所を5回ずつ殴り、モンスターは倒された。そのモンスターは運ぶには重すぎたが、それでも意気揚々としてファングビスはオスロバーへ戻った。
「おーい、家畜を食べたモンスターを殺しました」と、彼は叫んだ。
「モンスターを殺したという証拠はどこにあるのだ?」と、族長は聞いた。
「おーい、私の薬が家畜を救いましたぞ」と、治癒師ゴーリックは言った。
「おーい、我が生けにえによって女神が家畜を救ったのだ」と、ベラン司祭が言った。
朝が2回すぎたが家畜は無事であった、しかし、3日目の朝、また族長の家畜が10匹殺されていた。治癒師ゴーリックは彼の書斎へ新しい薬を探しに行った。ベラン司祭はさらなる生けにえの準備を行なった。ファングビスはゾリアの棍棒を手に、またしても暗い森の中を遠く偉大な山のふもとまで歩いた。そこで、オスロバーの族長の家畜の血でぬれた、もう一方のモンスターに出会った。彼らは戦い、またしても、「どこ」が重要であると言った師匠の言葉を思い出した。
彼がモンスターの頭を5回殴ると、モンスターは逃げた。山沿いに追いかけ、彼が股間を5回殴ると、モンスターは逃げた。森の中を走りながら、ファングビスはモンスターを追い越し、喉を5回殴ると、モンスターは逃げた。オスロバーの田畑に入り、ファングビスはモンスターを追い越し、背中を5回殴ると、モンスターは逃げた。砦の下ではモンスターが嘆く音を聞き、族長や賢者たちが顔を覗かせた。彼らはそこから族長の家畜を殺したモンスターを見守った。ファングビスがモンスターの胸を5回殴ると、モンスターは死んだ。
ファングビスの名誉を称えて大きな祝宴が開かれ、その後2度とオスロバーの家畜が殺されることはなかった。ジョルタレグは彼の弟子を抱きしめ、こう言った。「やっと“どこ”で敵を殴ればよいのかを覚えたようだな」
出版社注:
この物語もまた、ヴァーデンフェル島のアッシュランダー族に明らかな起源を持つ物語であり、彼らの最古の物語の1つである。「マロバー・サル」は単に登場人物の名前を「ドワーフ」らしい名前に変え、彼の書籍として再販売したのである。物語に登場する偉大な山は、森に覆われているとの記述をよそに、明らかに「赤き山」である。流星や後の大噴火が赤き山の植物を破壊し、今日の荒廃した外観を与えた。
原始的なアッシュランダーの文化を示唆するこの物語は学術的な興味を引くが、物語の中には今日のヴァーデンフェル島に存在する、遺跡のような「砦」での生活のことを話している。ヴァーデンフェル島とスカイリムの間の「オスロバー」砦についてさえも言及しているが、まばらに定住者が住むヴァーデンフェル島外の砦のうち、今日まで現存するものは少数である。学者たちは誰がいつこれらの砦を造ったのかについて合意しないが、太古のアッシュランダー族は今日のように麦わら小屋の野営地を設置するのではなく、これらの砦を使用していたことが、この物語や他の証拠からも明白である。
言葉遊びが寓話の教訓を形成する── どこでモンスターを殺すべきか(砦の下)はモンスターのどこを殴って殺すかと同等に重要である── これは多くのアッシュランダー物語の典型である。この物語のような簡単ななぞ掛けであっても、アッシュランダーや滅んだドゥーマーたちには好まれていた。ドゥーマーは通常なぞ掛けを出題する側として表現されるが、アッシュランダーの物語のように解く側ではない。
キマルヴァミディウム
ドゥーマー太古の物語 第4部
マロバー・サル 著
いくつもの戦いをへて、戦争の勝利が見えてきた。チャイマーはマジカや剣術においては秀でていたが、ジナッゴの手による洗練された防具を装備したドゥーマーの装甲兵が相手では、勝てる見込みはきわめて薄かった。“ランド”の平和維持を第一に考えた武将スソヴィンは、「野獣」カレンイシル・バリフと休戦協定を結んだ。スソヴィンは「紛争地域」を獲得し、その代償としてバリフに強力なゴーレムを授けた。北方の蛮族の襲撃からチャイマーの土地を守ってくれるだろう、と。
この贈り物にバリフは満足し、野営地に持ち帰った。ゴーレムを目にすると、仲間の戦士たちはあ然とした。金色に輝くその姿は、誇りに満ちたドゥーマーの騎士そのものだった。その強さを試そうと、彼らはゴーレムを闘技場の真ん中に立たせて稲妻の魔法で打ち抜いた。ゴーレムは目にもとまらぬ早業でほとんどの雷撃をよけてみせた。腰をくねらせることで、バランスを崩さずに攻撃の矛先をかわすことができた。さらに火の玉が弧を描いて飛んでくると、膝を折ってコマのように回転しながら巧みに攻撃をかわした。何度かよけられないこともあったが、もっとも頑丈にできている胸や腹部で攻撃を受け止めていた。
俊敏さと力強さを併せ持ったその創造物に、戦士たちは歓声をあげた。ゴーレムを守備の要に据えておけば、スカイリムの蛮族が村を襲ってきても返り討ちにしてやれそうだった。彼らはゴーレムを、「チャイマーの希望」を意味する「キマルヴァミディウム」と名づけた。
バリフは一族の全家長を連れて、ゴーレムを私室へと持ち込んだ。そこで彼らはキマルヴァミディウムの力、スピード、回復力を徹底的に試した。その設計に穴は見つからなかった。
「丸裸の蛮族め、襲撃にきてこいつを目にしたらどんな顔をするかのう」家長のひとりが高らかに笑った。
「われらではなく、ドゥーマーに似ているのが口惜しいがな」カレンイシル・バリフはゴーレムをとっくりとながめた。
「そもそも、休戦協定など受け入れるべきではなかったのだ」と、強硬派の家長が言った。「武将スソヴィンに冷や汗をかかせるにはもう遅すぎるかのう?」
「遅すぎるということはない」と、バリフは言った。「が、やつの装甲兵たちは手ごわいぞ」
「私の情報では──」と、バリフの諜報参謀が言った。「スソヴィンの兵は夜明けとともに目覚める。その一時間前に襲撃すれば、やつらは赤子も同然だ。まだ水浴びも終えてないだろうから、鎧を装備しているはずがない」
「鎧職人のジナッゴをひっ捕らえて、鍛工術の秘訣を吐かせることもできよう」と、バリフは言った。「善は急げだ。明朝、夜明けの一時間前に襲撃するぞ」
段取りは整った。チャイマーの兵は夜のうちに進軍し、ドゥーマーの野営地になだれ込んだ。キマルヴァミディウムを中心とする第一陣を攻撃に送り込んだが、肝心のゴーレムは調子がおかしくなってチャイマーの兵を襲いだした。それに加えて、ドゥーマーは防具一式を装備し、睡眠も充分にとっており、万全の戦闘態勢にあった。奇襲は失敗し、「野獣」カレンイシル・バリフをはじめとするチャイマーの上官はほとんど捕虜となった。
チャイマーたちは何も訊かないことで誇りを守ろうとした。と、スソヴィンはある仲間から“天啓”を与えられて、奇襲攻撃のことを知ったのだと説明した。
「わが陣にスパイがいたというのか」バリフは皮肉っぽく笑った。
捕虜のそばで立ちすくんでいたキマルヴァミディウムが、頭を取り外した。鋼鉄の体からジネッゴの顔がのぞいた。そう、鎧職人の。
「八歳のドゥーマーはゴーレムを作れる」と、ジネッゴは言った。「だが、ゴーレムになりきれるのは真に偉大なる戦士と鎧職人だけだ」
出版社注:
この話は本作品集の中でも、ドゥーマーの伝承を本源とする数少ない物語のひとつである。エルフ語による旧版とは表現法がかなり異なるが、大筋は変わらない。「キマルヴァミディウム」とはおそらく、ドゥーマー語の“ヌチャマサンダムズ”のことではなかろうか。この言葉はドワーフの鎧や「アニムンクリ」の設計図にも散見されるが、その意味は不明である。もっとも、「チャイマーの希望」でないことだけは確かだ。
重装鎧を使ったのは、おそらくドゥーマーが最初である。この話で特筆すべきは、重装鎧を身につけた男が大勢のチャイマーを欺くことができたという事実と、チャイマーの戦士の反応である。この話がはじめて語られた時代には全身を覆う鎧はまだ珍しく新しかったが、その一方で、ゴーレムや大隊長のようなドワーフ製の創造物は広く知られていた。
学術的にはたいへん貴重なことに、マロバー・サルはオリジナル版の数箇所を手を加えずに残している。その一例が、エルフ語版に見られる原文の一節、「八歳のドゥーマーはゴーレムを作れるが、八人のドゥーマーはひとつになれる」である。
この伝承に関して、私のような研究者が興味深いと感じることのひとつが、「召命」という言葉である。この伝承にかぎらず、ドゥーマーの種族には言葉を介さないマジカ的な交信能力が備わっていたと伝えられている。ある記録によると、サイジック教団もそうした神秘の知識があったという。いずれにしても、「召命」なる魔力について具体的に述べた文書は残されていない。
シロディールの歴史家であるボーグシルス・マリエーは、この「召命」こそがドゥーマーの失踪の謎を解く決め手になるとはじめて提唱した人物である。彼の仮説によると、第一紀668年、各所に暮らしていたドゥーマーが、有力な哲学者兼妖術師(ある資料では「カガーナク」と呼ばれている)のひとりに呼び集められ、大いなる旅へと出発したのだという。それは崇高なる叡智を求める旅であるため、ドゥーマーたちはあらゆる都市や土地を投げうってまで、ひとつの民族として、未知なる山嶺を究めようとしたのだと。
錬金術師の詩歌
ドゥーマー太古の物語 第5部
マロバー・サル 著
マラネオ国王おかかえの錬金術師が持ち場を去った
研究所での実験中に爆発事故を起こしたからだ
国王のおふれが回された
新しい術師を募集する
薬や何かを混ぜるのだ
王が選ぶと決めたのは
術と道具を使えるものだけ
愚かな術師はもうたくさん
検討、会議、話し合い
王は候補を2人に決めた
イアンスィップス・ミンサークとウンファティック・ファー
どちらもとにかく野心でいっぱい
どちらがすごいか競うのだ
王は「試験を行う」と
薬草、宝石、書物にお鍋、軽量カップを用意した
透明ドームの屋根の下、部屋に2人は通された
「飲むと姿が見えなくなる薬を作り出せ」
笑い上戸の王様はやっぱり笑ってこう言った
イアンスィップス・ミンサークとウンファティック・ファー
2人は作業に取り掛かる
薬草刻んで金属溶かし、奇妙なオイルを精製し
釜に入れたら温めて用心深くあわ立たす
中身を鉢に移したら混ぜて混ぜて混ぜまくる
時々互いを盗み見て、相手の様子を確認し
45分も経ったころ、
イアンスィップス・ミンサークとウンファティック・ファー
どっちも自分が勝ったと思い、相手にウィンクしてやった
マラネオ国王こう言った
「それでは今から自分たちの作った薬を飲んでみろ
なべからひとさじすくい取り味見をして見せてくれ」
ミンサークが薬を口にするやいなや彼の姿は消え失せた
ファーも味見をしてみたが、彼の姿はそのままだった
「銀とブルーダイヤモンドと黄色の草をちゃんと混ぜたと思うのか?」
王は笑って教えてやった。「見てみろガラスの天井だ
光がお前を惑わせて使うべきだった材料の
色を変えてしまったのだ」”
「ところで何を混ぜたのかな」浮かれてうるさい声がたずねた
「レッド・ダイヤモンドと青い草、それに金ではないのかな?」
「(ドゥーマーの神の名前)の力によって」ファーは若干おびえて言った
「私は自分の知能を高める薬を作りました」
出版社の注釈:
この詩は明らかにゴア・フェリムの書く文体であり、解説も特に必要ない。AA/BB/CCという単純な旋律を踏んでいて、歌のようであるが意図的におかしな律動にしてある。あきらかにおかしな名前、ウンファティック・ファーとイアンスィップス・ミンサークというジョークが繰り返し現れる。最後にきわめつけなのが、錬金術師が頭の賢くなる薬を発明してしまうところだ。あたかも偶然の発明のように装っているが、空位期間にある聴衆の反知的探求に対して訴えかける形となっている。しかし、結局はドゥーマーに却下されてしまうことになるのだが。
マロバー・サルはドゥーマーの神の名を用いることを嫌がる特徴がある。そう呼んでよいかどうか分からないところもあるが、ドゥーマー信仰は、彼らの文化の複雑で難解な一面でもある。
千年の間に、この詩歌は学術書以外からは姿を消し、ハイ・ロックでは居酒屋の歌として有名になった。ドゥーマーの人々と同じような運命である。
結婚持参金
ドゥーマー太古の物語 第10部
マロバー・サル 著
イナレイはグナルで最も裕福な地主であった。彼は、娘のゲネフラと結婚する男のために、長年にわたって莫大な額の持参金を蓄えてきた。彼女が結婚を承諾できる年齢に達すると、彼はゴールドをしまい込み、娘を結婚させると公表した。彼女はは顔立ちがよく、学者であり、運動も万能ではあったが、気難しく考え込んでいる印象を与える容貌であった。花婿候補として名乗りをあげてくる男たちはこの性格上の欠点を気にしていなかったし、それ同等に彼女の特性にも関心がなかった。男たちは皆、ゲネフラの夫、そしてイナレイの娘婿として莫大な富が手に入ることを知っていた。それだけで、何百もの男たちがゲネフラのもとへ求愛に訪れるに十分であった。
「我が娘と結婚する男は……」と、イナレイは参列者たちに言い放った。「金銭欲から結婚を希望してはならぬ。私が満足する自らの富を示さなければならぬ」
その簡単な表明によって、彼らのわずかな財産では地主を感心させられないと分っていた男たちの大多数は離れていった。それでも以後数日間、数十名は良質なキラーク布と銀糸で仕立てた衣服をまとい、異国の召使いたちを引き連れ、素晴らしい乗り物に乗って現れた。訪れた男たちでイナレイに認められたものの中でも、ウェリン・ナリリックの服装はひと際輝いていた。誰も聞いたことがないこの若い男は、ドラゴンの群れに引かせる眩い黒檀の乗り物に乗り、非常に珍しい仕立ての衣服を身にまとい、グナルの誰も今までに見たことがないような幻想的な召使いの行列に付き添われて到着した。従者の目は前後左右に着いていて、召使いたちはまるで宝石を散りばめたかのような外観であった。
それでも、イナレイにとって十分ではなかった。
「我が娘と結婚する男には、自分が知的であることを証明してもらう。私の義理の息子、そして一緒に仕事をする上で、無知な男はほしくない」と、彼は宣言した。
この宣告で、贅沢な生活の中でほとんど物事を考える必要が無かった大多数の求婚者が失格となった。それでも、それからの数日間、才覚と教養を披露したり、過去の偉大な賢者の言葉を引用したり、基本原理や錬金術に関する持論を披露する男達が数人訪れた。ウェリン・ナリリックも同様に、彼がグナルの郊外に借りた別荘で食事をともにするようイナレイにお願いした。そこで地主は、数多くの筆記者がアルドメリ語の小冊子を翻訳する姿を目にし、その若者の、少々的外れではあるが興味をそそる知性を楽しんだ。
イナレイはウェリン・ナリリックに十分感心していたが、それでもなお、別の課題を出した。
「私は娘を深く愛している」と、イナレイは言った。「また、娘が結婚する男にも彼女を幸せにしてほしい。もし彼女を笑わせることができる男がこの中に居るならば、娘と莫大な持参金を与えよう」
それからの数日間、求婚者たちは列をなし、彼女に歌を捧げたり、深い愛情を示したり、彼女の美しさをこれ以上ない詩的な言い回しで表現した。ゲネフラは憂うつさと嫌悪で彼らを睨むばかりであった。彼女の側に居たイナレイは、とうとう失望し始めた。求婚者たちは皆、この課題を果たせずにいるのだ。ここでやっと、ウェリン・ナリリックが部屋に入ってきた。
「私があなたの
娘を笑わせましょう」と、彼は言った。「思い切って言いますが、私と彼女の結婚を認めていただいた後に、彼女を笑わせます。もし、婚約から1時間経っても彼女に喜んでいただけなかったら、結婚は破棄していただいて結構です」
イナレイは娘のほうを向いてみた。笑ってはいなかったが、目の中に、彼女がこの若者に対して陰湿な興味を持った色が伺えた。他の求婚者たちはそんな反応すら彼女から得られなかったので、彼は同意した。
「もちろんのことながら、持参金は結婚してからでなければ支払われない」と、イナレイは言った。「婚約だけでは不十分だ」
「持参金を見せていただけますか?」と、ウェリンは頼んだ。
この宝がどれだけ有名で、恐らくこの若者が実際に手にすることはないだろうと考えたイナレイは了承した。彼はかなりウェリンのことが気に入っていた。イナレイの命令で、ウェリン、イナレイ、不機嫌そうなゲネフラ、そして城代の一行は、グナルの砦奥深くへと進んだ。最初の扉を開錠するにはルーン文字を連続で押さなければならなかった。もし一つでも押す文字を間違えたならば、毒矢の一斉射撃が盗賊を見舞ったであろう。イナレイは次の警備策を特に誇りに思っているようだ── 錠は18本の回転式の刃で構成され、3本の鍵を同時に回すことで入室が許される。刃は、一つだけの鍵穴を破ろうとする者を切り刻むように作られている。ようやく一行は保管室に辿りついた。
完全にカラだった。
「ああ、ロルカーンよ、強盗に入られた!」イナレイは悲痛に言った。「しかし、どうやって? 誰がこんなことをできたのだ?」
「恐れながら申し上げますが、かなりの才能がある強盗のようです」と、ウェリンが言った。「長年にわたってあなたの娘を遠くから愛し続けた男でしたが、人を感心させるようなごう奢さも教養もありませんでした。でもそれは、彼女の結婚持参金が私にその機会を与えてくれるまでの話です」
「貴様が?」と、とても信じられないイナレイは叫んだ。その時、さらに信じ難いことが起きた。
ゲネフラが笑い始めたのだ。彼女は、このような盗賊と出会えるなどとは夢にも思っていなかった。彼女は、激怒している父の目前で、ウェリンの両腕の中に飛び込んで行った。しばし時がたち、イナレイも同様に笑い始めた。
ゲネフラとウェリンは1ヶ月もしないうちに結婚した。彼は実際貧乏であったし教養も無いに等しかったが、この義理の息子と一緒に仕事を始めてからの富の増えかたにイナレイは驚きを隠せなかった。ただし、その過剰なゴールドの出どころに関しては絶対に聞かないようにした。
出版社注:
乙女の心を得ようとする男に対して、父が(一般的には裕福な男か王者)すべての求婚者に試練を課す物語はよくあります。もっと最近の物語で例えると、ジョル・ヨリベス著『ベニタールの四人の求婚者』です。登場する人物の行動はドゥーマーの柄に合っていません。今日では、誰も彼らの結婚に関する風習を知るものも居ませんし、結婚自体が存在したか知る由もありません。
「ドワーフの消失」に関して、本書や、マロバー・サルが著述した他の書物から、一つの奇妙な説がもたらされています。その説は、ドゥーマーは実際ニルンを離れてはおらず、ましてやタムリエル大陸からも出てはいない、彼らはいまなお変装して我々の間に潜んでいると唱えています。これらの学者達は「アズラと箱」の話を引き合いに出して、ドゥーマーが理解することも支配することも出来なかったアズラを恐れていたことを示唆し、アズラの目を逃れるために、彼らがキマルやアルトマーの作法や服装を真似たとしています。
アズラと箱
ドゥーマー太古の物語 第11部
マロバー・サル 著
ナイルバーは若いころは冒険心にあふれていたが、やがてとても賢い老ドゥーマーとなり、真理の探究や俗説の見直しに生涯をささげた。彼は実にいろいろな定理や論理的構造を打ち出しその名を世間にとどろかせていった。しかし彼にとって世界の多くはいまだなお不思議なものに満ち、とりわけエイドラとデイドラの本質は謎そのものであった。探求の結果、神々の多くは人類などによるつくりごとであるという結論に達した。
しかしながら、ナイルバーにとって神道力の限界以上の疑問はなかった。偉大なる存在がこの世全体の支配者なのであろうか? もしくは謙虚な生き物たちが自ら己の運命を切り開く力を持っているのだろうか? ナイルバーは自分の死期が近いと予感し、最後にこの疑問に挑まなければならないと感じた。
彼の知人でアシーニックという聖なる鐘の司祭がいた。司祭がベタラグ=ズーラムを訪れた際に、ナイルバーは彼に神道力の本質の探究に挑むつもりであることを話した。アシーニックは恐れおののき、そのような謎に手を出さないよう説得するもナイルバーの決心は固かった。司祭は神への冒涜になることを恐たが、最後には愛する友のため手伝うことに同意した。
アシーニックはアズラを召喚した。司祭が彼女の力への信仰を誓ういつもの儀式を行い、アズラが司祭には危害を加えないことを約束すると、ナイルバーと彼の多くの教え子たちは召喚の間へと大きな箱を運び入れた。
「この地に降り立つアズラよ、あなたは黄昏と暁の神であり、神秘の支配者である」とナイルバーは語りかけ、できるだけ従順な態度に見えるようにした。「あなたの知識は絶大です」
「そのとおり」とデイドラは微笑んだ。
「たとえば、この箱の中には何が入っているのかお分かりでしょうね」とナイルバーは言った。
アズラはアシーニックの方に向き直った。険しい顔だった。司祭は急いで、「神よ。このドゥーマーはとても賢く、尊敬された人物です。どうか私を信じてください。これは貴方様のお力を試すためではございません。しかし、この科学者と疑い深い連中の念をはらすため貴方様のお力をどうかお見せください。何度私のほうから説明しても、彼はその目で確かめたいという信念を持っているのです」と釈明した。
「もしこのドゥーマーたちが持ち込んだやり方で私の力を示すのであれば、その力はこれまで行ってきたことよりも印象的な業となるであろう」とアズラは怒鳴り、そしてナイルバーの目を真っ直ぐに見た。「箱の中には赤い花が1本入っている」
ナイルバーは表情を変えず、箱を開けて中身を見せた。箱の中身は空だった。
教え子たちはいっせいにアズラの方を向くと、彼女は姿を消していた。唯一アシーニックだけが彼女が消え去る前に「神の業」を見た。彼はただ何もしゃべることが出来ず、震えているだけであった。彼は呪いがふりかかった、と確信した。しかし先ほど証明された神道力についての考え方の方が呪わしかった。ナイルバーは青ざめ、足元もおぼつかなかったが、彼の顔は恐れではなく喜びで輝いていた。疑問に過ぎなかった真実の証拠を見つけた、という笑顔だ。
教え子の2人は彼を支え、もう2人は司祭を支え、召喚の間から出て行った。
「私は長い年月をかけて研究してきた。数え切れないほどの実験をこなし、独学で何ヶ国語も学んだ。最終的な真実を私に教えてくれた技術でさえ、ただ食べていくためだけに努力する貧しい若者だった頃に身に着けたやり方だ」と賢者は言った。
ベッドに上がる階段に連れて来られた時、彼のゆったりとしたローブのたもとから1枚の赤い花びらが落ちた。ナイルバーはその夜、息を引き取った、彼の死顔は知り得たことに満足して穏やかなものだった。
出版社注:
これはドゥーマーのオリジナルの物語とはまったくの別物である。エルフ語に翻訳したものとも異なるが、物語の本質は同じものである。ダンマーにはナイルバーに関する同じような話が伝わっているが、その物語では、アズラはひっかけであることを見破り、答えることを拒んだ。彼女は疑念にかられたドゥーマーを殺し、ダンマーには冒涜に対して呪いを与えた。
エルフ語版では、アズラは空箱ではなく、直方体に変化する球体を入れた箱で試された。もちろんエルフ語版は、オリジナルのものに非常に近いもので、また難解な内容でもあった。おそらく「舞台マジック」の説明はゴア・フェリムがこのようなトリックを劇中で魔術を使わずに試した経験にもとづいてフェリム自身が付け加えたものである。
このマロバー・サル版ではナイルバーは孤独に描かれ、ドゥーマーの持つ多くの長所を表現した。ナイルバーの疑念はエルフ語版ほど絶対的なものでなく、ドゥーマーや貧しい司祭の名もなき家に呪いがかけられてもなお称賛されている。
神の本質が何であるにしろ、またドゥーマーがそれに対していかに正しかったか、または誤っていたかとしても、この物語はドワーフがタムリエルから消えた謎を解き明かしている。ナイルバーたちはそもそもエイドラとデイドラを欺くつもりはなかったのかもしれないが、彼らの疑念は神々の命に背いていた。