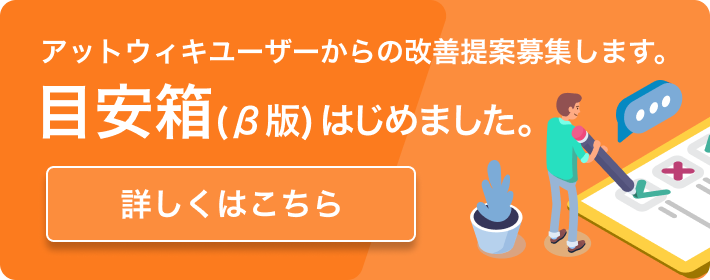オブリビオン図書館
レヴェン四部作
最終更新:
oblivionlibrary
-
view
「物乞い」
レヴェン 著
エスラフ・エロルは豊かなノルドの王国、エロルガードの女王ラフィルコパと王者イッルアフのあいだに生まれた5人の子供たちの最後の子であった。妊娠中、女王は身長の2倍もの幅があり、分娩には開始から3ヶ月と6日間かかった。エスラフを押し出した後、彼女は顔をしかめ、「ああ、清々した」と言って亡くなったのは、なんとなく理解できる。
多くのノルド同様、イッルアフは妻のことはあまり気にかけてはいなかったし、子供たちはそれ以下であった。よって、彼がアトモラの古の伝統に従い、愛する配偶者の後を追うと宣言した時、家臣たちは戸惑った。彼らはこの2人がとりわけ愛し合っていたとも思っていなかったし、まずそのような伝統が存在していたことを知らなかった。それでも、北スカイリムの辺境、特に冬期は、退屈が一般的な問題であり、庶民たちはこの退屈を和らげてくれた、王家のちょっとした、それでいて劇的な出来事に感謝した。
彼は王室に仕えるもの全員と、太り、うるさい彼の5人の小さな相続人たちを前に集め、財産を分け与えた。息子イノップには彼の称号を、息子ラエルヌには彼の土地を、息子スオイバッドには彼の富を、娘ライスィフィトラには彼の軍隊をそれぞれ与えた。イッルアフの相談役たちは、王国のためにも遺産をすべてまとめておくことを提案したが、イッルアフは相談役の人々のことを、ついでに言えば王国のことさえもそれほど大切には思ってはいなかった。公表を終え、彼はダガーで喉を引き裂いた。
かなり内気な看護人の1人は、王の生命が徐々に消え行く中、ようやく話しかける決心がついた。「殿下、5人子、エスラフ様のことをお忘れですが」
イッルアフはうめき声をあげた。血が喉から吹き上げる最中、集中するのはいささか難しい。王者はむなしく何か遺贈できるものはないか考えたが、何も残っていなかった。
彼は口から血を飛ばし、いらつきながら言った。「では、エスラフも何か選べばよかったではないか」そして、亡くなった。
生まれて数日の赤ん坊が、彼の正当な遺産を要求することを期待されているのは、間違いなく不公平である。
誰も彼を引き取らないので、内気な看護人、デゥルスバが赤ん坊を家へと連れて行った。それは老朽化した小さな小屋で、その後の数年間で、さらに老朽化していった。仕事が見つからず、デゥルスバは家財道具をすべて売り払い、エスラフのための食べ物を買った。彼が歩き、喋れる歳になったころには、彼女は壁や天井も売ってしまっていたので、家と呼べるものは床しかなかった。もし、あなたがスカイリムへ行ったことがあるのであれば、その状況がどれだけ不十分かを理解してもらえるであろう。
デゥルスバはエスラフに、彼が生まれたときの話も、彼の兄弟が遺産でかなり良い生活をしている話もしていない。前にも述べたように、彼女は内気であり、その話題を切り出すことを難しく感じていた。彼女がどれほど内気なのかの証拠に、彼がどこから来たのかに関して少しでも質問すると、デゥルスバは走って逃げてしまうのである。実際それが、逃げることが彼女のすべてに対する答えなのである。
とにかく、彼女と話をするために、エスラフは歩くことを覚えるとほぼ同時に走ることを覚えた。最初は義理の母についていけなかったが、時と共に、早く短い短距離走を予測した場合は、つま先を主に使って走り、デゥルスバが長距離走に旅立ちそうなときは、競歩のようにかかとを主に使って走ることを学んだ。彼女からは必要な答えのすべてを得られなかったが、走ることだけはしっかりと覚えた。
エスラフが成長していた数年間で、エロルガード王国は残酷な場所になっていた。王者イノップには公庫がなかった。富はすべてスオイバッドが引き継いだのである、王者には土地からの収入がなかった。土地はラエルヌが引き継いだのである、王者には民を保護する軍がなかった。ライスィフィトラが軍を引き継いだのである。さらに、彼は子供であったため、王国のすべての決定は、予想以上に腐敗した評議会を通っていた。王国は、搾取的に税が高い国となり、犯罪は頻発し、近隣国から定期的に侵略を受けていた。タムリエルの王国として特に異例の状況とは言えないが、とはいえ嫌な状況ではあった。
ついに収税官がデゥルスバのあばら家にきて、この家の状況から徴収できる唯一のもの、床を持っていってしまった。抗議するよりも、この可哀想で内気な女性は走り去ってしまい、エスラフは2度と彼女の姿を見ることはなかった。
家もなく、母もおらず、エスラフはどうしたらよいのか分からなかった。寒さにはデゥルスバの家で慣れていたが、彼は空腹であった。
「肉を一切れくれませんか?」彼は街路を少し下ったところにいるブッチャーに聞いてみた。「すごくお腹が空いてます」
この男は少年のことを何年も前から知っていて、しばしば妻に、この子が天井も壁もない家で暮らしていることをどれだけ気の毒に思っているかを話していた。男はエスラフに微笑みかけ、「どこか他へ行け、さもなくば叩くぞ」と言った。
エスラフは急いでブッチャーの下を去り、近くの酒場へ向かった。酒場の主人はかつて王者の宮廷で従者をしており、この少年が本来ならば王子であることを知っていた。この可哀想な少年が街路を歩く姿を何度も見ており、その都度、運命の残酷さにため息をついた。
「何か食べるものをくれませんか?」と、エスラフは酒場の主人に聞いた。「すごくお腹が空いてます」
「俺がおまえを料理して食っちまわないで、良かったな」と、酒場の主人は答えた。
エスラフは急いで酒場を後にした。その後、一日中、少年はエロルガードの善良な民に食べ物を乞うた。一人だけ、彼に何かを投げてくれたが、それは食べられない石であった。
夜が迫ったとき、ぼろぼろの服を着た男がエスラフに近づき、何も言わずに果物と干し肉を手渡した。少年は受け取り、目を見開き、むさぼり食いながら男に愛想よく感謝した。
「もし明日、おまえが街路で物乞いをしている姿を見かけたら……」男はうなった。「おまえを殺してやる。ギルドが1つの街に許可する物乞いの数は決まっている。おまえは、丁度その枠から溢れる。商売あがったりだ」
エスラフ・エロルは走り方を学んでおいて幸運であった。彼は一晩中走った。
エスラフ・エロルの物語は「盗賊」という本に続く。
「盗賊」
レヴェン 著
もしこのエスラフ・エロールの連続物語の第1巻、「物乞い」を読んでいないのなら、すぐさまこの本を閉じて出直していただきたい。
さて、今この本を閉じなかったお優しい読者の方、あなたにならお話ししよう。私が最後にエスラフを見た時、彼はまだ少年だった。彼は孤児で、物乞いとなり、彼の故郷であるエロルガードから遠く離れたスカイリムの冬の荒野を走り抜けていた。彼は長年、そこここで走っては止まりを繰り返し、大人になった。
食べ物を得る方法でもっともやっかいなのは人から恵んでもらうことだと、エスラフは身をもって体験していた。荒野の中で食べ物を見つける方がはるかに易しく、もしくは誰も見てない市場の棚から盗むほうが簡単だ。唯一やってはいけないことは食料を買うお金を得るために働き口を探すことだ。これは必要以上にやっかいなことになる。
エスラフにとっては、ゴミ漁りや物乞い、泥棒するほうが楽であった。
初めて盗みを犯したのはエロルガードから出た直後、ホアベルドのちょうど東に位置する村、ジェンセン山近くにある岩だらけの場所にあるタンバーカー南部の森の中であった。エスラフはひどくお腹が空いていた。4日間で口にしたのはガリガリにやせ細った生のリスだけだった。その時、肉の焼けるにおいと煙があがっているのが見えた。吟遊詩人の一団が野営をしていたのだ。エスラフは茂みの中からそっと覗き、彼らが料理をこしらえ、笑い、戯れ、歌を歌っているのが見えた。
食料を恵んでもらえるよう頼んでいたが、それまでの道中ずっと断られていた。だからエスラフは走って飛び出し、肉をつかみ取り、火にたじろいでそのまま近くにあった木によじ登ってガツガツと食べ始めた。その間、吟遊詩人たちは木の下から彼を見上げ、笑っていた。
「この後はどうする気だい? 泥棒さん」そう言いながら笑っていたのは赤髪の美しい女で、体中にタトゥーを入れていた。「あたしたちに捕まってお仕置きされないように、どうやってここから出て行くのかしら?」
空腹が満たされてくると、エスラフは彼女の言うことももっともだと思った。彼らの輪の中に落ちることなくここから逃げる唯一の方法は、小川の方へと伸びる枝を伝って下りていくしかなかった。一歩間違えば50フィートほどの崖の下へと落ちてしまう。しかし、この方法が一番賢い策だと考え、エスラフはゆっくり枝の方へと這っていった。
「安全な落ち方は知ってるのか?」カジートの若者が叫んだ。エスラフよりやや年上のようで、華奢な体つきであったが筋肉はついており、ちょっとした動きにも優雅さが感じられた。「そんなことはやめて、こっちへ下りて来い。首を折っちまうような馬鹿な真似はやめろよ。それよりもお前を何発か殴ったら、家まで送り届けてやるよ」
「もちろん、落ち方ぐらい知ってるさ」エスラフは返事をしたが、彼らのほうへは戻らなかった。もちろん落ち方のコツなんてものは知らず、あとは成り行きに任せるしかないと思った。だが、50フィートもの高さから下を見下ろせば、誰もが動けなくなるだろう。
「大盗賊さんよ、あんたを見くびって悪かった」カジートはニッコリ笑いながら言った。「知ってると思うが、足から真っ直ぐ落ちると、卵みたいに割れちゃうぜ。まあ、それでも俺たちの手から逃げられることにはなるがな」
エスラフはカジートのヒントを受け、川へと飛び込んだ。優雅に、とは言えないまでも彼は無傷であった。年月が過ぎ、彼はこれよりも高い場所から飛び降りる場面に何度か出くわした、もちろん大体は盗みを働いた後にということだ。時には下に水がないときもあったが、彼は基本的な技を学んでいった。
エスラフは21歳の誕生日の朝、ジャレンハイムの町を訪れた。誰がこの町で一番の金持ちで、泥棒に入るのに絶好の相手か、すぐにわかった。この町の中心に難攻不落の宮殿がそびえたっており、その持ち主はスオイバッドという、神秘的な雰囲気の若い男だった。エスラフはすぐに宮殿を見つけ、観察した。これまでの彼の経験からいうと、このような要塞化された宮殿に住む人間には、頑丈な警備で固められた地下に物を隠すおかしな癖がある。
その宮殿は新しく、そのあたりから察するに、スオイバッドが金を手に入れたのもつい最近のことであろう。衛兵が定期的に見回りをしていることから、盗みに入られるのを恐れているようだ。この宮殿で特徴的といえるのが、石壁よりも100フィートも高くそびえる塔だった。このスオイバッドという男がエスラフが考えるような偏執症であれば、その塔から宮殿内の宝庫の場所が分かるだろう。金持ちというのは自分の財産をいつでも目にすることができるようにするものだ。つまり、この塔の真下に金目のものがあるのではなく、城内の中庭のどこかにあるのだ。
塔の照明灯は一晩中点けられていたので、エスラフは大胆にも真昼の時間帯に狙おうとした。おそらくスオイバッドも寝ているに違いないと考えた。衛兵もよもやそんな時間帯を狙って泥棒が入ってくるとは思っていないだろう。
そういうわけで、真昼の太陽が宮殿を照らすころ、エスラフは正門近くの壁をよじ登り、胸壁の裏に隠れて待った。中庭は平坦で荒涼としており、隠れる場所はほとんどなかったが、2つの井戸が見えた。1つは衛兵たちが時折水をくみ、喉の渇きを癒していた。しかし、もう1つのほうにはまったく衛兵が立ち寄らないことに気づいた。
宮殿に金品を運びこむ商人の馬車が通り、衛兵たちの気がそれる短いチャンスが訪れるまで待った。皆の注意が馬車に向いてるのを確認し、エスラフは壁から井戸の方へ足元から優雅に飛びこんだ。
軟着陸とは行かなかった。というのも井戸にはエスラフがにらんだとおり水ではなく、財宝で埋め尽くされていたからだ。それでも、彼は落ちたあとの受け身の取り方も学んでいたので、傷1つなかった。じめじめした地下の宝庫であったが、ポケットに詰めれるだけ詰め、まさにその場を立ち去ろうとしたその時、塔へと続くらしいドアのところにリンゴほどの大きさの宝石を見つけた。ここにある中で一番高価なものだと思ったエスラフは、パンツを広げそこへねじこんだ。
ドアは塔へと続いており、エスラフは静かに、すばやく階段の吹き抜けを上っていった。頂上へ到着すると、この宮殿の主の私室へと辿り着いた。そこは豪勢な装飾が施され、大変貴重な美術作品やら、飾りつきの剣や盾が壁に飾られていた。エスラフは、おそらくシーツの下でいびきをかいてるのがスオイバッドだと思った。彼はそれ以上は調べようとせず、窓へ這って進み、鍵を外した。
この高さからのジャンプは危険だろう。塔から壁を通り越し、反対側の木の枝まで飛ばなければいけなかった。木の枝で怪我をしてしまうかもしれないが、その下には怪我を防げそうな干草の山があった。
エスラフがその部屋から飛び出そうとしたその瞬間、部屋の主が目覚めて「私の宝石!」と叫んだ。
エスラフは目を大きく見開いて部屋の主としばし見つめ合った。彼らは瓜二つだった。驚くべきことではない、彼らは兄弟であったのだ。
この話は「戦士」の巻へと続く。
「戦士」
レヴェン 著
この本は4巻の本からなる連続物語の3巻目になっている。もし最初の2巻、「物乞い」および「盗賊」を読んでいない場合は、そちらを読むことをお勧めする。
スオイバッド・エロルは自分の過去についてあまり知らなかったし、知りたいとも思ってはいなかった。
子供のころ、彼はエロルガードで暮らしていたが、王国はとても困窮しており、その結果、税金は非常に高かった。彼は多額の遺産を管理するには若すぎたが、彼の破滅を心配した召使いたちが彼をジャレンハイムに移動させた。なぜその地が選ばれたのかは誰も知らない。とうの昔に死んだ召使いの1人が、子供を育てるには良い場所だと思ったのであろう。他に案を持つものもいなかった。
若きスオイバッドよりも甘やかされて育った子供たちもいると思うかもしれないが、恐らく実際にはそんなことはないだろう。育つにつれ、彼は自分が金持ちであることを理解したが、他には何もなかった。家族も社会的地位もなく、警護もまるでなかった。忠誠心は真には買えないと知ったのは1度ではない。自分に巨大な財産という強みしかないことを充分に分かっている彼は、それを守り、そして可能であれば増やすことに必死になった。
一般的にも、良い人たちの中に強欲なものはいるが、スオイバッドは富の入手と貯蓄以外にはまったく興味を持たない珍しい人種であった。彼は富を増やすためならば何でもするつもりで、彼は実際に、魅力的な土地を攻撃するための傭兵を秘密裏に雇い、その後、誰も住みたがらなくなったときに買い上げるといった方法をとった。当然、攻撃はそれで止み、スオイバッドは有益な土地を格安で手に入れることになる。最初はいくつかの小さな農家から始まったが、最近はさらに野心的な作戦行動を行い始めている。
北中央スカイリムには、地理的に興味深いアールトと呼ばれる地域がある。そこは周囲を氷河によって囲まれている休火山低地であるため、土壌は火山によって温められるが、常に霧雨状態で空気は冷たい。そこではジャズベイと呼ばれるブドウが快適に育つが、それはタムリエルの他のどの場所でも萎れて死んでしまう。この奇妙なブドウ園は私有物であるため、そのブドウから作り出されるワインには希少価値があり、極めて高価である。皇帝がこのワインを年に一度飲むには、帝都評議会の許可が必要であると言われている程である。
アールトの所有者を苦しめ、彼の土地を安く手放させるためには、かなりの数の傭兵を雇わねばならなかった。よって彼は、スカイリムにおける最高の私兵集団を雇う必要があった。
スオイバッドはお金を使うことが好きではなかったが、リンゴと同じ大きさの宝石を、ライスィフィトラと呼ばれる将軍に支払うことを承知した。もちろん、支払いは任務が成功したときに行なわれるので、まだ渡してはいなかったが。しかし、こんな素晴らしいものを手放すことを分かっている彼は、夜も眠れなかった。彼は盗賊が夜うろつくのを知っていたので、倉庫を監視するためにいつも日中に寝た。
ある日、うつらうつらした眠りからスオイバッドが昼頃に起き、突然、彼の寝室で盗賊に出くわした。その盗賊こそ、エスラフであった。
エスラフはどのように窓から飛び降り、要塞化された大邸宅の壁の表にある百フィート下の木々の枝に体をあて、いかに積んである干草に身を投じるかを沈思していた。そのような離れ技に挑戦したことがある人はおそらく、かなりの集中力と度胸が必要であると言うであろう。寝ている富豪が起きたのを見たとき、その両方とも吹き飛んでしまい、エスラフは飾ってある装飾用の大きな盾の裏に潜み、スオイバッドが再び眠りにつくのを待った。
スオイバッドが再び寝ることはなかった。彼は何も聞いてはいないが、誰かが一緒に部屋の中にいることを感じた。彼は立ち上がり、部屋の中をうろうろし始めた。
スオイバッドは歩き回ったが、徐々に自分が想像しているだけだと思い込んだ。そこには誰もいない。彼の富は無事だ。
何か物音を聞いたとき、彼はベッドに戻りかけていた。振り向くと、ライスィフィトラに渡すことになっている宝石が、アトモラの騎兵用の盾から少し離れた床上に見えた。盾の裏から手が伸びてきて、それを拾い上げた。
「盗賊だ!」スオイバッドは叫び、宝石で装飾されたアカヴィリ剣を壁からつかみ下ろし、盾に向かって突進していった。
エスラフとスオイバッドの「戦い」は偉大な決闘の記録には残らない。スオイバッドは剣の扱いを知らなかったし、エスラフは盾による防御に関して無知であった。その戦いはぎこちなく、不細工であった。スオイバッドは激怒していたが、繊細な飾り付けを傷めて価値を下げてしまうような使い方を心理的にできなかった。エスラフは盾を彼と剣の間に置くようにしながら、盾を引きずりつつ動き続けた。何といっても、それが盾防御の要である。
スオイバッドは盾を殴りながら叫び、その盾は殴られる反動で部屋を移動していった。宝石はライスィフィトラという名の偉大な戦士に約束されていると説明し、返してくれるならスオイバッドは喜んで他のものを渡すと、彼は盗賊と交渉すら試みた。エスラフは天才ではなかったが、それでもそれが嘘だと判った。
主人の呼び出しに応え、スオイバッドの衛兵が寝室に到着したときには、窓の近くまで盾を追いつめていた。
スオイバッドよりも遥かに剣の力量に富む彼らは盾にのし掛かったが、そこには誰もいなかった。すでにエスラフは窓から飛び降り逃走していたのだ。
懐にしまったゴールドを鳴らし、巨大な宝石が体に擦れるのを感じつつ、ジャレンハイムの街路を重そうに走るエスラフは、どこに行けば良いのか分からなかった。ただ、この街にはもう戻れないということと、宝石の所有権を持つライスィフィトラという名の戦士に会うことだけは絶対に避けなければならないことはわかっていた。
エスラフ・エロルの物語は、「王者」に続く
「王者」
レヴェン 著
読者諸君、この連続物語の3巻、「物乞い」「盗賊」「戦士」を読み、記憶に留めていない場合は、結末へとたどり着くこの最終巻に書かれている内容を理解することは難しいだろう。お近くの本屋でのお求めをお勧めする。
前回の物語は、いつもの如くエスラフ・エロルが命をかけて逃走しているところで幕を閉じた。彼は多量の金と非常に大きな宝石を、ジャレンハイムのスオイバッドという名の富豪から盗んだ。その盗賊は北へと逃げ、盗賊らしくありとあらゆる非道徳的な快楽のために、金を湯水の如く使った。この本を読んでいる淑女や紳士を動揺させてしまうような内容なので、詳しくは述べないことにする。
手放さなかったのはあの宝石だけである。
愛着があって手放さなかったわけではなく、彼から買い取れるほどの金持ちを知らなかったからである。何百万もの価値がある宝石を手にしながら、無一文という皮肉な状況に彼は陥っていた。
「これと交換で、部屋とパンとビールの大瓶をくれないか?」あまりにも北すぎて、その半分が亡霊の海に面する小さな村、クラヴェンスワードの酒場の店主に彼は聞いた。
酒場の店主はそれを疑わしげに見た。
「ただの水晶だよ」と、エスラフはすぐさま言った。「でも、きれいじゃない?」
「ちょっと見せて」鎧に身を固め、カウンターの端にいた女性が言った。許可を待たずに彼女は宝石を手に取り、見つめ、そしてあまり優しくなさそうな笑みをエスラフに向けた。「私のテーブルで一緒にどう?」
「実は、ちょっと急いでいるので」と、宝石に向かって手を伸ばしながらエスラフは答えた。「またの機会に」
「友であるこの酒場の店主に敬意を表して、私も部下も皆、ここにくるときは武器を置いてくる」宝石を返さず、カウンターに立てかけてあったほうきを手に取りながら、何気なく彼女は言った。「でも、これだけは断言できるわ。私はこれを武器としてかなり有効に使える。もちろん、武器ではないけれど、気絶させるたり骨の1本や2本を折る程度、そして── 1度中に入ったら……」
「どのテーブルだい?」エスラフは即座に聞いた。
その若い女性は、エスラフがいまだに見たことがないほど大きなノルドが10人座っている、酒場の裏にある大きなテーブルへと彼を連れて行った。彼らはエスラフのことを、踏み潰す前に一瞬の観察に値する奇妙な虫であるかのような無関心さで見つめた。
「私の名前はライスィフィトラ」と彼女は言い、エスラフは瞬きをした。それはエスラフが逃走する前に、スオイバッドが口にした名前であった。「彼らは私の副官たち。私は気高い騎士たちから成る大きな独立した軍の指揮官。スカイリム最高の軍よ。つい最近、ラエルヌと言う男が我々の雇い主がスオイバッドと言う男にブドウ園を売り渡すことを強要するため、アールトにあるブドウ園を攻撃する仕事を与えられたわ。我々の報酬は、とても有名で間違えようのない、飛び抜けた大きさと質の宝石のはずだったの」
「依頼通りにやり遂げ、スオイバッドの下に謝礼を受け取りに行ったら、彼は最近泥棒に入られたために支払えないといったわ。でも最終的には私たちの言うことを聞き、貴重な宝石の価値に匹敵するくらいの金を支払った。彼の宝物庫を空にはしなかったけれど、結局はアールトの土地を買えないことになったわ。よって、私たちは十分な支払いを受けられなかったし、スオイバッドは金銭的な痛手を負い、ラエルヌの貴重なジャズベイは一時的に意味もなく台無しにされたの」ライスィフィトラは続ける前に、ゆっくりとはちみつ酒を1口飲んだ。「さて、よく分からないから教えてくれない? 私たちが手に入れるはずだった宝石を、どうしてあなたが持っているの?」
エスラフはすぐには答えなかった。
その代わり、左にいる髭を生やした蛮族の皿からパンを1切れ取り、食べた。
「すまない」と口をモグモグさせながら彼は言った。「いいかい? 宝石を取ることは、やめたくてもやめられないし、実際のところ別に構わない。そして、どのようにして私の手に入ったかを否定するのも無駄なことだ。要するに、これは、あなたの雇い主から盗んだ。もちろん、あなたや気高い騎士たちに被害を加えるつもりはなかったが、あなたのような人にとって、盗賊の言葉など相応しくない理由も理解できる」
「そうね」ライスィフィトラは答え、顔をしかめたが、目は面白がっているようである。「相応しくないわね」
「でも私を殺す前に──」エスラフはパンをもう1切れつかんで言った。「教えてくれ、あなたのように気高い騎士が、1つの仕事で2度報酬を得るのは相応しいことなのか?
私にはなんの名誉もないが、支払いのためにスオイバッドが損害を被り、今はその宝石を手にしている。よって、あなたの莫大な利益はあまり誇れるものではないと思うのだが」
ライスィフィトラはほうきを拾い上げ、エスラフを見た。そして笑い、「盗賊よ、名は?」
「エスラフ」と、盗賊は言った。
「今回は我々に約束されていたものなので、宝石はいただくわ。しかし、あなたは正しい。1つの仕事で2度支払いを受けるべきではないわ。なので──」ほうきを置きながら女戦士は言い、「あなたが我々の雇い主よ。我々に、何をさせますか?」
多くの人々は自分の軍隊にかなりの使い道を見出すであろうが、エスラフはその1人ではなかった。頭の中を捜してみたが、最終的には、後に支払われる貸しにしておくことに決まった。彼女の野蛮性にも関わらず、ライスィフィトラは素朴な女性であり、彼女が指揮するその軍に育てられたことを彼は知った。戦闘と名誉が彼女の知るすべてであった。
エスラフがクラヴェンスワードを離れたとき、彼には軍の後ろ盾があったが、1ゴールドすら持っていなかった。近いうちに何かを盗まなければいけないのは分かっていた。
食べ物を拾い集めようと森の中をさまよっていると、彼は奇妙な懐かしさに襲われた。ここはまさしく子供のころにいた森で、当時も空腹で食べ物を拾っていた。道に出たとき、彼は優しく間抜けで内気な召使い、デゥルスバによって育てられた王国に戻ってきたことに気付いた。
彼はエロルガードにいたのだ。
そこは彼の幼少期よりもさらに絶望の深みへと堕ちていた。彼に食べ物を拒否した店の数々は皆、板が打ち付けられ放棄されていた。そこに残されている人々は皆、うつろで絶望した姿であり、彼らは税金、専制政治、野蛮人の侵略によってやつれきっていて、弱りすぎて逃げることすらできない人々であった。エスラフは、若いころにここから出られた自分がどれだけ幸運だったかを実感した。
しかし、そこには城があり、王者がいる。エスラフはすぐさま公庫に侵入する計画を練った。普段どおりその場を注意深く観察し、警備や衛兵の習慣などを記録した。これには時間がかかったが、結局、警備も衛兵も存在しないことに彼は気付いた。
彼は正面の扉から中に入り、がら空きの廊下を下って公庫へ向かった。そこは、何もなさで満ちていた。1人の男が居る以外は。彼はエスラフと同年代だったが、さらに老けて見えた。
「盗むものは何もない」と、彼は言った。「かつて存在したこともないがな」
王者イノップは年齢以上に老けているが、エスラフ同様の白金髪、そして割れた硝子のような青い眼を持っていた。その上、スオイバッドやライスィフィトラにも似ていた。エスラフは破滅させられたアールトの地主、ラエルヌとは知り合いにこそならなかったが、見た目は似ている。当然のことである。彼らは兄弟なのだから。
「何も持っていないのか?」と、エスラフは優しく聞いた。
「この王国以外は何もない。忌々しいことだが」王者はぼやいた。「私が玉座に就くまでは強力で、富んでいたのだが、私はそのどれも相続しなかった、ただ称号のみ。私の全人生に責任がのし掛かっていたが、それを正しく推し進める資質を持ったこともなかった。生得の権利であるこの荒野を見渡すと嫌になる。もし王国を盗むことが可能であるならば、それを止めたりなどしない」
結局、エスラフは王国を盗むことにした。それからしばらく後、エスラフがイノップとして知られるようになったが、それは身体的な相似から容易な偽装であった。本物のイノップはイレキルヌと名を変え、喜んで彼の領地を離れ、最終的にはアールトのブドウ園で素朴な労働者となった。初めて責任から開放された彼は、心から喜んで新しい人生に取り組み、そして長い年月が彼から溶け出した。
新しいイノップはライスィフィトラへの貸しを回収し、彼女の軍を使ってエロルガード王国に平和を取り戻した。安全になった今、商売や交易がその地に戻り、エスラフは税額を下げ、それらの成長を促した。それを聞き、常に富を失うことを恐れているスオイバッドは、生誕の地へ戻ることを決心した。彼が何年か後に死ぬとき、彼はその強欲から相続人の指名を拒否したため、王国が彼の全財産を受け取った。
本物のイノップからいい評判を聞いたエスラフは、その財産の一部を使ってアールトのブドウ園を購入した。
これによってエロルガードは、王者イッルアフの5人目の子によって以前の繁栄に返り咲いた──
エスラフ・エロル、物乞い、盗賊、お粗末な戦士、そして、王者。