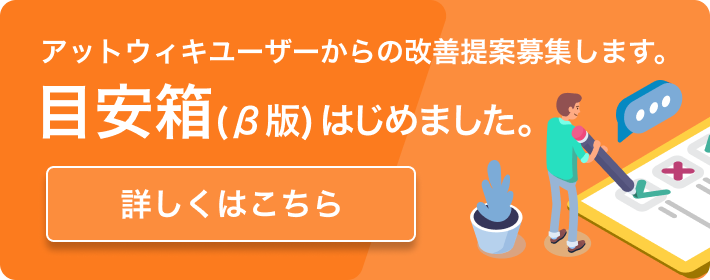オブリビオン図書館
アクラシュの最後の鞘
最終更新:
oblivionlibrary
-
view
アクラシュの最後の鞘
タバー・ヴァンキド 著
第三紀407年、暑い夏の日、ベールで顔を覆った若くて美しいダンマーの女性が、テアのとある鍛冶屋の親方のところへ足しげく通っていた。地元の住民は彼女の顔を一度も見たことはなかったが、彼女の姿かたちや身のこなし方からきっと若くて美しい女性に違いないと思っていた。彼女と鍛冶屋の親方はお店の裏に引っ込み、店を閉め、数時間の間、弟子たちを帰らせた。昼下がりには、彼女は店から去っていき、また翌日同じ時間に現れるのだった。当然のごとくいろんなゴシップが飛び交ったが、それはとるに足らないもので、たとえばその年取った親方がそのような美しく魅力的な体型の女性とやることとは…… といったがさつな冗談ばかりであった。数週間後にはその定例訪問もなくなり、ティアのスラム街の生活も元に戻っていったのであった。
訪問が止んで1─2ヶ月のこと、近所の酒場にて酒をしこたま飲んだような1人の若い仕立屋がその鍛冶屋に聞いてきた。「それであのおトモダチとはどうしてるんだ? 振っちまったのかい?」
鍛冶屋はその手の噂話が流れていることは知っていたので「彼女は素敵な女性だよ。2人の間には何もなかったよ。ましてや相手は私だ」と答えた。
「それじゃ毎日彼女は何しにきてたわけ?」と、居酒屋の娘はなんとかこの話を広げようとして聞いてきた。
「そうだな」と鍛冶屋は答えた「武具の作り方を教えていたんだ」
「そんなはずないだろう」と言って、仕立屋は笑った。
「彼女はただ私の芸術的な部分に特別惹かれただけさ」と鍛冶屋はちょっとした誇りをちらつかせ、今はなき幻想をなつかしむように言った。「私は彼女に剣の修繕方法を教えたのだ。それもありとあらゆる、刃のこぼれや破損、細い亀裂、割れた柄頭、刀の鍔の片側、柄の部分など、具体的にだ。最初は彼女もまったくの素人で刃物の中子で柄を固定するやり方さえ知らなかったよ。もちろん始めた頃はまったくの手探り状態さ。まあ、それも当然だが。しかし自分の手が汚れることなんか全然気にもしていなかったさ。立派な刃物についてるような小さな金銀の細工の継ぎ合わせ方まで教えたよ。神が神々しい金敷から引っ張り出したかのような、鏡のような光沢を出させる磨き方もね」
居酒屋の娘と仕立屋は大声で笑った。鍛冶屋が何を言ったとしても、鍛冶屋が話すその若い女性の訓練の様子は、遠い過去の悲恋のように聞こえた。
居酒屋にいた地元の人々の多くが鍛冶屋の感傷的な物語を聞いていたが、話題はもっと重要な噂話へと移った。街の中心で上から下まで一気に内臓をえぐられた奴隷商の殺人の話だ。この2週間で6体の死体が発見された。この犯人を「解放者」と呼ぶものもいたが、この街では奴隷商に対する恨みはさほど強くはなかった。どちらかといえば、初期の犯罪の手口が頭を切り落とす手口だったため、「切断者」と呼ばれるほうが多かった。シンプルに体に穴を開けられたり、切り刻まれたり、内臓をえぐられたりといった、そのほかの手口はもあったのだが。
熱狂的なよた者たちが次の犠牲者の殺され方で賭けをする一方で、今のところ生き残った奴隷商たちの多くは、その土地の領主であるセルジョ・ドレス・ミネガウアのところに集まっていた。ミネガウアはドレス家のケチな用心棒であったが、奴隷商仲間の主要メンバーであった。もうすでに彼は落ち目になっていたが、皆は彼の元へ知恵を拝借しに集まったのである。
「我々はこの『切断者』と呼ばれるものがどんな人物であるのか、しかるべき調査にふみこまなければならない」ミネガウアは贅沢に作られた暖炉の前に座りこう言った。「犯人が奴隷制と奴隷商に対して理由のない憎しみを抱いているのは確かである。それに、剣の名手でもある。犯人は我々の背後からそっと忍び寄り、十分な警戒態勢をしいている我々の住居に侵入してくる。私にはどうも犯人は外部の人間としか思えない。実際、モロウウィンドの住人が我々に対してこんな攻撃はしてこまい」
奴隷商たちはみな、この意見に頷いた。このようなトラブルは外部の人間が決まって起こすもので、それはいつも当たっていた。
「わしがあと50歳若ければ暖炉に飾ってあるアクラシュの剣をつかんで出て行くのに」と言ってミネガウアはそのキラキラと輝かんばかりの武器を大きな動きをもって指差した。「そしてお前たちとともに犯人探しへ向うのだが。居酒屋にギルド本部にと犯人の居所を探し回り、この手で首を切り落としてやろうぞ」
奴隷商たちは慎ましやかに笑った。
ソロン・ジェレスという1人の若いおべっかつかいの男が、「あなたのその剣を我々にお貸しいただけませんか?」と熱い口調で頼んだ。
「アクラシュの剣の使い心地はさぞよいものであろう」とミネガウアは息をついた。「だが、わしが引退するときに二度と使わないと誓ったのだ」
ミネガウアは娘を呼び、奴隷商たちにフリンを持ってくるように言うと、みなが必要ないと断った。その日の晩に「切断者」を捕まえにいくというのに酔っていては困るからだ。高い酒を断るほどの彼らの熱意の強さに、ミネガウアは心が打たれた。
最後の奴隷商が帰っていくと、ミネガウアは娘の頭にキスをし、アクラシュの剣に尊敬の念を込めた視線を送りベッドへふらふらと歩いていった。ミネガウアがベッドに入るやいなや、娘ペリアは暖炉に飾られた剣を持ち出し、家の裏手を飛ぶように横切っていった。カザフが馬小屋でじっと彼女の来るのを待っていた。
カザフは物陰から彼女の前に飛び出ると力強く彼女を抱きしめ、長く甘いキスをした。彼女が寄り添うまま、彼は彼女を抱きしめていたが、ようやくペリアは身を離し、彼に持っていた剣を手渡した。彼は刃をかざしてみせた。
「どんなに優秀なカジートの鍛冶屋でもこの鋭さは作り出せないだろう」と、カザフは誇らしげに恋人を見つめながら言った。「昨晩だってうまく殺ってみせた」
「その通りよ。鉄の銅よろいの上から切り込まなきゃいけなかったしね」と、ペリアは言った。
「奴隷商たちも今や警戒をしだしている。集まってどんなことを話していた?」
「外部の人間の仕業だと思ってるわ」と言って、彼女は笑った。「よもやカジートの奴隷がこれまで数々の「切断」をやってのける技術を持っているとは思ってないわ」
「君のお父上はまったく疑ってないのか? 彼の大事なアクラシュの剣が今回の事件に一役買っていることを」
「前日とまったく変わらずそこにあると信じて疑ってないわ。あたしが抜け出たことに誰かが気づく前に戻らなければいけないわ。時々、乳母が結婚式の詳細について尋ねてくるの。まるで私になにか選択権があるかのようにね」
「約束するよ」とカザフは真剣な眼差しで言った。「『奴隷取引王朝』を確立させるためだけの政略結婚なんか絶対にさせないよ。このアクラシュの剣の最後の鞘は君の父上の心臓だ。そして父を失った君は奴隷を全員解放し、もっと文明の進んだ州に移動し、そこで君は好きな相手と結婚できる」
「その相手とは誰かしら」とペリアはからかい、馬小屋から走り去った。
夜が明ける前にペリアは起きて庭を這い出し、新緑の蔦の中に隠されたアクラシュの剣を見つけた。刃は比較的、鋭いままだが、表面に垂直の傷がたくさん入っていた。「また1人、首を切り落とされたんだわ」そう思いながら軽石で丁寧に痕跡を消しさり、最後に塩と酢でもってピカピカに磨き上げ、父親が朝食に起きだす前に暖炉の上のもとあった場所へと戻した。
ケミリス・トロム、彼女の夫となる予定であった男の首が胴体から数フィートも離れた州で発見された事件を聞いた時、彼女は別段悲しんでるふりもしなかった。父親は娘が結婚を嫌がっていたことを知っていた。
「なんということだ。あの青年は非常によい奴隷商だったのに。しかしまあ、我が家の良き同胞となるべき若い男はほかにいくらでもいるからな。ソロン・ジェレスなんてどうだ?」
その2日後、ソロン・ジェレスの元へ「切断者」が訪れた。もみ合いはそう長くは続かなかったが、ソロンはちょっとした護身用の武器を持っていた、それは毒性植物の抽出液に浸した1本の針で、たもとに隠し持っていた。致命的な打撃を食らったあと、前面へと倒れこんだその時、カザフのふくらはぎをそのピンで刺した。彼が剣を返しにミネガウアの家に着いたその時、そのまま彼も倒れこんでしまった。
視界がかすむ中、彼はひさしをつたってペリアの部屋へ上り、窓をコツコツと叩いた。しかし、ペリアは答えず、深い眠りへと落ちていた。それもカジートの恋人とのすてきな未来を夢みながら。彼は強く窓をたたいたため、ペリアは眼を覚ましたが、隣の部屋で眠る父親も目を覚ましてしまった。
「カザフ!」と、娘は窓を開けて叫んだ。彼女の隣に立っていたのはミネガウアだった。
彼が見たものは、自分の所有物である奴隷が、自分の所有物である剣を握り、自分の所有物である娘の頭を切り落とさんとしているところだった。突如、ミネガウアに若い力がみなぎり、息絶え絶えのカジートに近寄り、手から剣を奪った。娘が止めるよりも先に彼は娘の恋人の心臓を突き刺した。
一旦落ち着きを取り戻すと、ミネガウアは剣をその場に落とし、衛兵を呼ぶためにドアへと向かった。ふと彼の頭に、娘はケガはしてないまでも治癒師が必要だ、という考えがよぎった。ミネガウアは娘の方へ振り返った。しばらく、何が何だかわからなかった。強烈な一撃を受けた感じがしたのだが、それが剣だとは思わなかった。まず血を見て、次に痛みに気づいた。自分の娘がアクラシュの剣で自分を突き刺したのだと気づく前に彼は死んでしまった。剣はようやく、おさまるべき最後の鞘を無事見つけたのであった。
一週間後、公式な調査を終え、ガウシュの遺体は邸宅内の敷地に無縁仏として埋葬された。セルジョ・ドレス・ミネガウアの墓は歴代の家族の墓と肩を並べるよう、壮大な霊廟の一角に埋葬された。野蛮な「切断者」として次々と商売仲間を殺していくという裏の一面を持った貴族の奴隷商の葬式を見に、多くの見物人が集まった。式場内は厳粛な静けさが漂ってはいたが、誰もがその奴隷商の人生の最後の場面を想像した。奴隷商は乱心に駆り立てられ、自分の娘を手にかけようしたが、幸か不幸か忠実なる奴隷に止められ、持っていた剣で自分を刺してしまった。
見物人の中にはあの年老いた鍛冶屋もおり、彼はベールで顔を隠したあの若い女性の姿を見た。それが彼女がこの街を去る前の最後の姿であった。