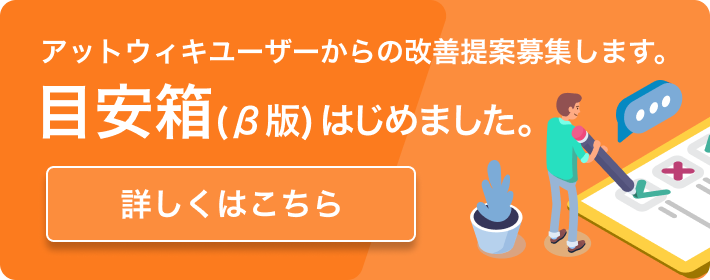オブリビオン図書館
大いなる旅
最終更新:
oblivionlibrary
-
view
大いなる旅
ウォーヒン・ジャース 著
ヴァララは美しくて、優しく、かわいらしく、賢く、可憐で、元気の良い少女だった。両親の望んだもの全てをもって生まれてきたような子だった。あまりにも完璧な子だったので、両親は彼女の将来に期待をせずにいられなかった。父親はマンセンという名の成り上がり者だったが、娘が将来位の高い人物と結婚するに違いないと信じており、帝都の王妃になるかもしれないとすら思っていた。母親はシネッタという気の弱い女性で、娘は自分の力で栄光を掴むだろうと思っており、偉大な騎士や魔術師になったヴァララを思い描くのだった。両親それぞれの期待は大きく、ときには娘の将来について言い合いになったりもした。しかし、どちらの予想通りにもならなかった。健やかに育つと思われた娘は、重い病にかかってしまったのだ。
どこの神殿につれて行っても、あきらめるように言われるだけだった。魔術師ギルドでは、ヴァララの症状が非常に珍しく、致命的で、効果的な治療法はないとまで言われた。彼女は近いうちに死ぬ運命にあるのだ。
帝都の権威ある施設が何もできなかったので、マンセンとシネッタは魔女や流浪の妖術師、その他社会の闇に住む人々に望みをかけた。
「ひとつだけ、治してくれそうな場所がある」ロスガリアン山脈の人里離れた峰に住む薬草師は、訪ねてきた夫婦に言った。「オレンヴェルドの魔術師ギルドじゃ」
「でも、魔術師ギルドにはもう行ってみましたよ」と、マンセンは言った。「彼らは何もできなかったんです」
「オレンヴェルドに行け」と、薬剤師はなおも言った。「そこへ行くことを誰にも告げずにな」
現在の地図にはオレンヴェルドという地名はなく、それがどこなのかを探すのは大変だった。やっとのことで、スカイリムの本屋にあった第二紀の地図作成法に関する古書の中にその地名を見つけることができた。オレンヴァルドは北の海に浮かぶ島にある町の名前だった。そしてその島は、ウィンターホールドから夏潮に乗って船で一日のところにあるらしかった。
娘を冷たい海風から守るために暖かい布で何重にもくるみ、夫婦は古い地図だけを頼りに船を出した。二日近くのあいだ、船は同じところをぐるぐる回り続け、夫婦はなにかの罠にかかったような気持ちで不安になった。そんなとき、やっと島影が見えた。
打ち寄せる波が砕けて霧になり、そのむこうに2つの崩れかけた石像が見えた。その石像の間が港になっているらしかった。港の船はみなぼろぼろで沈みかけていた。マンセンが港に船をとめ、3人はこの絶海の孤島の町に足を踏み入れた。
窓の割れた酒場、涸れた泉のある広場、崩れた宮殿、焼け焦げた住宅、からっぽの商店、打ち捨てられた馬小屋。全てが荒れ果て、動くものといえば海から吹く風だけだった。風がぼろぼろの町を吹き抜けると、気味の悪い叫びのような音があたりに響いた。全ての通りや小道に沿って墓場が並び、ところどころで倒れた墓石が道をふさいでいた。
マンセンとシネッタは顔を見合わせた。寒気がするのは、風のせいだけではなかった。それから彼らはヴァララに目をやり、また歩き出した。彼らの目的地 ―― オレンヴェルドの魔術師ギルドへ。
暗い巨大な建物の窓にろうそくの火が輝いていた。この死の島に人がいることはわかったが、夫婦はまだそれほど安心できなかった。彼らは扉を叩き、中で待っているであろう恐ろしいことに向き合う覚悟を決めた。
扉を開けたのは、縮れた金髪で、太った、中年のノルド女性だった。その後ろに、同じく中年の人のよさそうな禿げたノルド人男性が立っていた。その後ろにおとなしそうな10代のブレトンのカップルが、子供のような落ち着きのなさを見せながら立っていた。それに、ひどく年老いた赤い顔のブレトンの男性がおり、夫婦に向かって嬉しげに笑いかけていた。
「あらあら、なんてこと!」と、ノルドの女性が驚いた様子で言った。「ノックの音が聞こえたとき、空耳にきまってると思ったわ。お入りなさい、さあ、外は寒かったでしょう!」
三人は招かれるまま扉をくぐり、ギルド本部が少なくとも廃墟ではなかったことにほっとした。建物の中はきれいに掃除されており、明るく、華やかに飾り付けられていた。そして、そこにいた人々の自己紹介がはじまった。このギルドに住んでいるのは2家族で、ノルドのジャルマーとネット、そしてブレトンのライウェル、ロザリン、ウィンスター老だった。彼らはみな愛想がよく親切で、マンセンとシネッタがここへ来た目的と、治療師や薬剤師に見放されたことを話しているうちに、温めたワインとパンを持ってきてくれた。
「それで……」と、シネッタは涙を流して言った。「オレンヴェルドの魔術師ギルドを、見つけられるかどうかもわからなかったんです。でも、やっと見つけてここまでやって来ました。お願いします、どうか助けてください、あなたがたが最期の望みなんです」
ギルド本部に住む5人も、これを聞いて目に涙をためた。ネットがやかましく鼻をすすった。
「ああ、それはそれは、辛かったでしょうね」と、このノルド女性は泣き叫ぶように言った。「もちろん、助けますとも。お嬢ちゃんはすぐ元気になりますからね」
「本当のことを言うと……」」ジャルマーの声は少し冷静だったが、彼もまた心を動かされているのは明らかだった。「ここは魔術師ギルドですが、私たちは魔術師ではないのです。この建物が捨てられていたので、住んでいるだけなのです。それにここは、私たちの大いなる旅の目的にもぴったりでしたから。私たちは死霊術師です」
「死霊術師?」シネッタは震えだした。こんな気のいい人たちがそんな恐ろしいことをやっているのか?
「そうですとも」ネットがほほえみ、シネッタの手を握った。「私たちの評判が悪いのは知ってますよ。残念ですけど。昔から良くは言われてなかったけど、最近じゃあの気はいいけど頭の良くない大賢者ハンニバル・トレイヴンのせいで――」
「あんなやつ虫の王に食われちまえ!」と、突然、老人が苦々しげに叫んだ。
「もう、ウィンスター」ロザリン少女が老人をなだめ、頬を赤らめてシネッタに謝った。「ごめんなさい、普段は急に怒鳴ったりしないんだけど」
「いや、ウィンスターの言うとおりですよ。最後にはマニマルコがなんとかするでしょう」と、ジャルマーが言った。「でも今は、とにかくやっかいなことになってるんです。トレイヴンが死霊術を禁止したもので、私たちは隠れなきゃいけなくなったんです。それでなきゃ、死霊術を捨てなくちゃならないんですから。本当に死霊術を捨ててしまった者もいますが、馬鹿げたことですよ」
「オレンヴェルドは、タイバー・セプティムが自分の墓場をつくったせいで誰も住まなくなって、忘れられたんです」と、ライウェルが言った。「ここを探し当てるのに1週間かかったけど、僕たちにとってはすごくいいところですよ。ほら、死体もたくさんあるし……」
「ライウェル!」ロザリンがたしなめた。「この人たちを怖がらせないでよ!」
「ごめんなさい」と、ライウェルはおどおどした笑顔で謝った。
「あなたがたがここで何をしているかはいいんです」と、マンセンが、厳しい調子で言った。「どうやって娘を助けていただけるのかが知りたいんです」
「そうですね」ジャルマーが肩をすくめた。「私たちにできるのは、娘さんが死なずにすんで、二度と病気にかからないようにすることです」
シネッタは息をのんだ。「お願いします! どんなお礼でもしますから!」
「そんなものいりませんよ」と、ネットはそう言うと、ヴァララをそのでっぷりと大きな腕に抱いた。「なんてかわいらしいお嬢ちゃんなの。元気になりたいのよね、かわいこちゃん?」
ヴァララは力なく頷いた。
「ここで待っててください」と、ジャルマーが言った。「ロザリン、この人たちにこんなパンよりちゃんとしたものをお出ししなさい」
ネットがヴァララを連れて行こうとしたので、シネッタは慌てて彼女を追いかけた。「待ってください、私も行きます」
「ああ、気持ちはわかりますけど、呪文がきかなくなると困りますから」と、ネットは言った。「何も心配いりませんよ、私たちはこんなこと、もう何十回もやってるんですから」
マンセンが妻の肩を抱き、落ち着かせた。ロザリンは急いで台所に行き、焼いた鶏肉と温めたワインのおかわりを持ってきた。彼らは黙ってそれらを食べた。
突然、ウィンスターが身震いをした。「あの女の子が死んだぞ」
「ああ!」シネッタが息をのんだ。
「いったいどういうことです!?」と、マンセンは叫んだ。
「ウィンスター、そんな余計なこと言わなくて良かったんじゃないか?」ライウェルが老人を叱り、それからマンセンとシネッタに向かってこう説明した。「あの子は、死なないといけなかったんです。死霊術っていうのは、病気を治すんじゃなくて、死者を甦らせる術だから。生まれ変わらせて、病気の部分だけじゃなく、全身を新しくするんです」
マンセンは怒りに震えながら立ち上がった。「あの異常者どもが娘を殺したというのなら――」
「殺していません」と、ロザリンが遮って言った。控えめだった瞳には情熱の炎が燃えていた。「娘さんは、ここに入ってきた時にはもうほとんど息がなかったんです。厳しいことを言ってごめんなさい、でも、娘さんを懸命に助けようとしてるあの2人を『異常者』なんて言わないで」
「でも、あの子は生き返るんでしょう?」と、シネッタはひどく泣きながら言った。
「もちろん」と、ライウェルが顔中で笑って言った。
「ああ、ありがとうございます。ありがとうございます」シネッタはそう言うとますますひどく泣き出した。「本当に、どうしていいかわからなくて――」
「お気持ちはわかりますよ」と、ロザリンが、ウィンスターの腕を優しくさすりながら言った。「このウィンスターが死にそうになった時、私も彼のために何でもしようという気持ちになりましたもの。ちょうど今のあなたたちのように」
シネッタはそれを聞いてほほえんだ。「お父さんはおいくつなのかしら?」
「息子です」と、ロザリンが訂正した。「ウィンスターは6歳です」
部屋の反対側から、小さな足音が近づいてきた。
「ヴァララ、お父さんとお母さんのところへ行って抱きしめてあげなさい」と、ジャルマーの声が言った。
マンセンとシネッタは振り返った。そして、叫び声があたりに響きわたった。