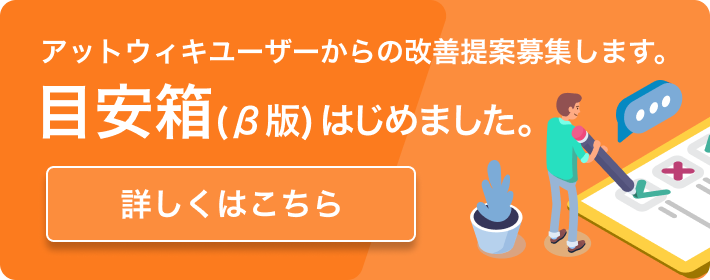オブリビオン図書館
パルラ
最終更新:
oblivionlibrary
-
view
パルラ 第1巻
ヴォンヌ・ミエルスティード 著
パルラ。パル・ラ。初めてその名を聞いたときのことを覚えている。そこまで昔の話じゃない。ミル・コラップの西にある豪邸の“物語と獣脂の舞踏会”での出来事だった。私と魔術師ギルドの修練僧は思いがけず舞踏会に招待されたのだった。まあ、驚いて腰を抜かすということはなかった。ミル・コラップ── 第二紀に富裕層のリゾート地として栄えた街── には数えるほどの貴族しか暮らしていない。振り返ってみるに、神秘的な祝日には妖術師と魔術師がいたほうがさまになったということだろう。なんでもござれの小さなギルド修道院の生徒という以上の魅力が私たちにあったわけではなく、やはり、他の選択肢が限られていただけに過ぎない。
一年近くのあいだ、私にとって家と呼べる場所は、やたら広いだけでお粗末なミル・コラップ魔術師ギルドの敷地内の一角だった。唯一の仲間である同輩の修練僧たちも仕方がないからと私と付き合っているという感じで、師匠たちは、僻地のギルドで教えることを苦々しく思っていたため、その怒りを発散するように生徒をいじめ抜いた。
私はすぐに幻惑の流派に惹きつけられた。賢者は私のことを、科学的呪文だけでなくその哲学的基盤をも愛する有望な生徒と評してくれた。光や音や精神といった目に見えないエネルギーを歪めるという概念が、どことなく私の本分を刺激したのだろう。破壊や変性といったけばけばしい流派、回復や召喚のような聖なる流派、錬金や付呪といった実践的な流派、神秘のようなよくわからない流派、そのどれも私向きではなかった。ありふれたものをちょっとした魔法でそれ以上のものに見せかけることに、私は至上の喜びを感じたのだった。
その哲学を私の単調な暮らしに当てはめようとしたら、持てる以上の想像力が求められたろう。朝の授業のあと、私たちは雑用を命じられた。夜の授業まではまだ時間があったからだ。私の仕事は、最近亡くなったギルドの住人の書斎を片づけて、呪文の解説書、お守り、初期刊本といった遺品を分類することだった。
みじめで退屈な仕事だった。賢者テンディクスは筋金入りのがらくた収集家だった。なんの価値もなさそうなものを捨てようとするたびに、私は叱責された。しだいに、故人の所持品をしかるべき学部に届けられるようになった。回復の薬は回復の賢者へ、物理的現象の書物は変性の賢者へ、薬草や鉱物は錬金術師へ、魂の石と魔道具は付呪師へ。付呪師への配達をひとつすませると、毎度のことながらむげに扱われて、その場を去ろうとした。と、賢者イルサーに呼び止められた。
「ぼうず」と、かっぷくの良い老人は道具をひとつ、手渡してきた。「こいつを破壊しろ」
ルーン文字が刻み込まれた小ぶりの黒い円盤で、骨のような赤橙色の宝石の指輪で縁取りされていた。
「すみません、賢者」私は口ごもった。「あなたに見せておくべきだと思ったので」
「火にぶちこんで燃やしてしまえ」彼はぶっきらぼうに命じると、背を向けた。「ここには持ってこなかったことにしておけ」
私は興味をかき立てられた。というのも、イルサーにこうした反応を起こさせるものはひとつしかなかったからだ。死霊術。私は賢者テンディクスの書斎に戻って彼のメモを読みあさり、円盤に関する記述がないものか探した。残念ながら、ほとんどのメモは奇妙な暗号でしたためられていて、無力な私には解読できなかった。私はこの謎解きに夢中になり、夜の部屋の、賢者イルサーその人が教鞭をとる付呪の授業にも遅刻しかけた。
それからの数週間、私は時間を使い分けて、がらくたの山を分類し、届けものをし、円盤を調査した。自分の直感は正しかった。円盤はまさしく死霊術の秘宝だったのだ。メモの大部分は解読できずじまいだったが、私にははっきりとわかった。この円盤で愛する人を墓から蘇らせられると賢者は考えたのだ。
悲しいことに、その時がきた。分類が終わって部屋がすっきりと片づいたのだ。私は別の仕事をあてがわれた。ギルドが所有する野獣畜舎の手伝いだった。少なくとも、これでようやくギルドの修練僧といっしょに働けるわけだった。それから、ギルドにお使いにやってくる庶民や貴族と触れ合う機会も巡ってくる。かくして、私がこの仕事についているときに、「物語と獣脂の舞踏会」へのお誘いがギルドの全員に対して届けられたわけである。
華やかな夜になりそうだったが、それに花を添えるのが、ハンマーフェル出身の若くて豊かで未婚の孤児という女主人だった。つい1、2ヶ月前、帝都の片隅の森林地帯にあるさびれたわが街に、旧家の邸宅と土地を取り戻すために彼女はやってきた。ギルドの修練僧たちは老婦人のように、この謎めいた若い娘のうわさ話に花を咲かせた。彼女の両親に何が起きたのか。彼女はどうして祖国を去ったのか、それとも祖国を追われたのか。その名をベタニキーといい、私たちにわかっているのはそれだけだった。
私たちは誇らしげに入会の儀式の法衣を身につけ、舞踏会に臨んだ。壮麗な大理石のロビーで、従者が私たちの名前をひとりずつ読み上げた。貴族になったような気分だった。盛りあがりをみせる人々の輪の中心へ小走りに駆けていくと、盛大な賛辞を浴びせられた。もちろん、それが終わるともののみごとの誰からも相手にされなくなった。本質的には、私たちはどうでもよい存在で、頭数を増やすために舞踏会に呼ばれたにすぎない。「さくら」なのだ。
有力者たちが完ぺきな丁重さで私たちを押しのけていった。シャウディラ婦人がバルモラとの外交予定についてリムファーリン公と話し合っていた。オークの武将が笑い上戸のお姫様を強姦や略奪の話でもてなしていた。ギルドの3人の賢者は、痛々しいほどか細い貴族の未婚夫人といっしょに、ダガーフォールの幽霊のことを気にかけていた。帝都や各地の最高裁判所でのスキャンダルの噂について、彼らは分析し、そっと笑い飛ばし、やきもきし、乾杯し、はねつけ、評価し、軽んじ、警告し、覆した。私たちがそばにいても目をくれようともしなかった。幻惑のスキルで透明化しているかのように扱われた。
私はワインのビンを持ってテラスに出た。月が増えていた。空に浮かぶ月も、庭の巨大プールに照り映える月も、変わらぬくらいに明るい。プールの脇に立ち並ぶ白い大理石の彫像がその燃えるような光をとらえて、闇夜に浮かぶたいまつのように輝いていた。それはもう幻想的な光景で、私はうっとりと見とれていた。石となって永遠に生きつづける見知らぬレッドガードの像にも魅了されていた。女主人はまだ越してきたばかりのため、彫像のいくつかは、そよ風にはためく防水布がかけられたままになっていた。どのくらいそうしていたのかはわからないが、気がつくと私は独りではなかった。
彼女はとても小柄で浅黒かった。肌だけでなく着るものも。そのせいで影のように見えた。彼女が私のほうを向いた。とても美しく、若かった。せいぜい17歳といったところか。
「あなたが女主人様?」と、私はようやく訊いた。
「ええ」彼女は顔を赤らめてはにかんだ。「けど、私ったらひどい女主人ね。新しくお隣さんになった方々と中にいるべきなんでしょうけど。話題がかみ合わなそうなの」
「あの人たちが、私と話題がかみ合ってほしくないと思っているのは、もうはっきりしてますけどね」私は笑った。「魔術師ギルドで修練を卒業したら、もう少し平等な目で見てくれるんでしょうか」
「シロディールでは、何が平等なのかまだよくわからないの」彼女は顔をしかめた。「私の文化では力で認めさせるわ。期待してるだけじゃだめ。私の両親はふたりとも偉大な戦士だったの。私もそうなりたい」
彼女は視線を芝生に落としてから彫像に向けた。
「彫像のモデルはご両親ですか?」
「お父さんのパリオムよ」彼女はそう言って、等身大の像を身振りで示した。鍛えあげられた肉体を恥らうことなくさらけだし、もうひとりの戦士の喉をつかんで、すらりと伸びた剣でその首を斬り落とそうとしていた。現実味にあふれる描写だった。パリオムの顔はのっぺりしていて、狭い額が醜くすらあった。髪はぼさぼさで、無精ひげを生やしていた。歯並びの悪ささえ再現されていた。彫刻家がそういった誇張をすることは考えられない。実際のモデルの特徴を余すところなく表現しようとするのでなければ。
「それと、お母さん?」私はすぐそばの像を指差した。威厳のあるずんぐりした戦士の女性で、マンティラとスカーフを身につけ、子供を抱いていた。
「いやだわ」彼女はけらけらと笑った。「あれは私の叔父の昔の乳母よ。お母さんの像はまだ防水布がかかったままなの」
どうしてそんなことを口走ったのかわからないが、私は彼女が指差した像の防水布を取り払おうと言った。たぶん、そうなる運命だったのだ。それと、会話を続けたいというわがままな欲望からか。私は恐れていた。話題を提供できなければ彼女はパーティ会場に戻ってしまい、ふたたび独りで取り残されるかもしれない。最初、彼女はためらった。湿気が多く、急に冷え込むこともあるシロディールの気候に像をさらしてよいものかどうか思いあぐねているとのことだった。全部の像を防水布でおおうべきかもしれない、とも言った。ひょっとすると、彼女もただ会話を長引かせていただけで、私と同じように、よそよそしい会話でも止めたくなかったのかもしれない。できるだけパーティ会場には戻りたくなかったのだろう。
数分後、私たちは防水布をベタニキーの母親の像から取り外した。このときだった。私の人生が永遠に変わったのは。
彼女は飼いならされていない自然そのものだった。黒い大理石で作られた不恰好な怪物と取っ組み合い、雄たけびをあげ、すらりと伸びた華麗な指で怪物の顔を引っかいていた。怪物はその鉤爪で愛撫するように彼女の胸をわしづかみにし、致命傷を負わせようとしていた。お互いの脚をからみつかせて、さながらダンスをしているようだった。私は陶酔しきっていた。このしなやかだが力強い女性は表面的な基準でははかり知れない美しさをたたえていた。誰が彫刻したのであれ、女神の顔や姿だけでなく、その力や意志までもどうにかして表現してみせていた。悲壮感と高揚感のどちらも漂わせていた。私は瞬間的かつ宿命的な恋に落ちていた。
修練のひとりであるゲリンが会場を離れて背後から近づいてきたことにも私は気づかなかった。このとき、私が「神々しい」という言葉をつぶやいていたのは間違いない。というのも、ベタニキーが「ええ、神々しいわ」と、大陸の向こうから響くような声で返事をしたのが聞こえたからだ。「だから、雨風にはさらしたくないの」
それから、私ははっきりと耳にした。石が水に落ちたように。グレンがこう言ったのだ。「これはすごい。パルラ様ですね」
「お母さんのことを知ってるのね?」ベタニキーはグレンのほうを向きながら訊いた。
「出身がウェイレストなので。故郷はハンマーフェルとの国境沿いでしてね、あなたの母上のことを知らないものなどおりません。忌まわしい野獣の大地を馬で駆けめぐった勇猛果敢な女性ですから。あの戦いでお亡くなりになられたのでしたのよね?」
「ええ」と、彼女は悲しげに言った。「怪物を道連れにしてね」
しばらく、私たちは押し黙っていた。私はこれ以降、この晩のことをまるで覚えていない。翌日の夕食に招待されたような気もするが、私の魂と心は完ぺきに、そして永遠に、その像に奪われてしまっていた。ギルドに戻ってからも、私は熱に浮かされたような夢を見るばかりで、一睡もできなかった。白い光が散乱し、あらゆるものがぼやけて見えた。美しくも恐ろしいある女性を除いては。そう、パルラをだ。
パルラ 第2巻
ヴォンヌ・ミエルスティード 著
パルラ… パル… ラ… その名前は心に深く刻み込まれている。授業中、教官の言葉に集中しようとしている時も、気がつけばその名をささやいている。唇が無音の「パル」をかたどり、舌を軽く弾いて「ラ」を成す、あたかも目の前にいる彼女の霊に口づけをするが如く。乱心として自覚している点を除けば、あらゆる点において乱心の沙汰だ。恋に落ちたことは分っていた。彼女が気高い女レッドガードで、星も霞む程美しい猛烈な戦士だったことは分っていた。彼女の若い娘ベタニキーがギルドに程近い領主邸を受け継ぎ、そして彼女が私のことを好きな、ひょっとしたら夢中になっていることも分っていた。パルラが恐ろしい獣と戦い、殺したことも分っていた。パルラは死んでいることも分っていた。
前にも言ったが、乱心であることを自覚している、故に、狂っている訳ではない。確かなのは、愛しいパルラが怪物と繰り広げた最後の、恐ろしく、致命的な戦いの彫像を見に、ベタニキーの邸宅へ戻らなければならないことだ。
私は戻った、何度も何度も。もしベタニキーが同輩と違和感なく交流できる、違った性格を持った貴婦人であったなら、それほど戻る機会はなかったであろう。私の汚れた妄想に気付かない、無邪気な彼女は私との時を歓迎した。何時間も話し、笑い、そして毎回、光を反射する池の周りを散歩すると、必ず母親の彫像の前で息を忘れて立ちすくむ。
「先祖の一番輝いている姿をこのように残すのは素晴らしい伝統ですね」と、探るような彼女の視線を感じながら、私は言った。「また、職人も無比の腕前だ」
「信じてくれないでしょうけど」と、笑いながら彼女が言った。「曾祖父がこの習慣を始めた頃、ちょっとした騒ぎになったのよ。私たちレッドガードが家族を敬う気持ちは大きいのだけれど、私たちは戦士であって芸術家ではないわ。だから彼は、最初の彫像を作るために巡業していた芸術家を雇ったの。誰もが彫像を称賛したわ、芸術家がエルフであることが明らかになるまでは。サマーセット島から来たアルトマーだったの」
「それは大変だ!」
「そのとおり」ベタニキーはまじめに首を縦に振った。「あの気取ったエルフの手が、気高いレッドガード戦士の姿を作り出したと思うと、考えるのも嫌だし、冒とくだし、非礼だし、想像できるすべての悪に値するわね。でも、曾祖父の心は彫像の美しさしか見ていなかったの。最高のもので先祖を称える彼の哲学は私たちにも受け継がれているわ。種族文化に忠義を示せたとしても、劣る芸術家に親の彫像を作らせるなど考えもしなかったわ」
「どれもみな美しいです」そう私は言った。
「でも、私の母親の彫像が一番のお気に入りなのよね」と、彼女は笑いながら言った。「他の彫像を見ているようでも母の彫像を見ているものね。私のお気に入りでもあるのよ」
「もっと彼女のことを教えてくれませんか?」と、軽い声で、会話を交わすように問いかけた。
「母なら、自分はたいしたことないって言っただろうけど、彼女は素晴らしかったわ」と、娘は花壇の花を摘みながら語った。「私がまだ小さい頃に父親が死んだから、母はいろいろな役目を負ったけど、すべてを楽々とこなしたわ。私たちは沢山の事業を手がけているけれど、彼女はしっかりと運営していたわ、今の私など及ばないくらいにね。彼女が微笑みかけるだけで皆従ったし、意に反した人たちは酷い目にあったわ。気も利いたし、可愛らしくもあったけど、いざ戦いになったら恐ろしく強かった。数え切れないほど戦に出たけど、一瞬たりとも見捨てられたとか、愛されていないなんて思ったことはなかったわ。死にさえも勝てると思っていたわ。愚かなのは分ってる、でも、彼女がアレと戦いに行ったとき―― あの恐ろしい生物、いかれたウィザードの研究室から生まれた化け物、母が二度と帰ってこないなんて思ってもみなかった。彼女は友には優しく、敵には無慈悲だったわ。最高の女性だったの」
思い出から、可哀想なベタニキーの目には涙が溢れた。自分の歪んだ想いを満たすために、彼女の心をこれほど抉るとは、私は何と言う悪党なのだ? 私以上にシェオゴラスが困惑させた人間はいないであろう。自分が涙ぐんでいることに気付くと同時に、胸いっぱいに欲望が広がるのを感じた。女神のように見えるパルラは、娘の話からすると実際に女神だったのだろう。
その夜、床に就くために服を脱いでいたら、テンディクサス教官の研究室から数週間前に盗み出した黒い円盤を再発見した。その存在を半分忘れかけていたが、愛する者を生き返らせることができると魔術師が信じた死霊術の秘宝である。ほとんど本能的に、私はその円盤を胸に押し当て、「パルラ」とささやいていた。
一瞬にして部屋の中に寒気が充満し、白い吐息が空中に漂った。恐怖を感じ、私は円盤を落とした。判断力が戻るまでに少々時間が掛かったが、避け難い結論に達した: この秘宝は私の欲望を満たせる。
愛しい人をオブリビオンのしがらみから解放しようと明け方まで試みたが、無駄に終わった。私は死霊術師ではない。教官の誰かに手伝ってもらうことも考えてみたが、イルサー教官に円盤を処分するように命じられていたのを思い出した。もし彼らのもとへ行き、彼らが円盤を処分することになれば、私はギルドから追放されてしまう。そして、愛する人を呼び寄せる、唯一の鍵も失われてしまうことになる。
次の日、私はいつもの半無気力状態で教室にいた。イルサー教官自ら、彼の専門分野である付呪学についての講義を行っていた。彼の声には変化がなく、内容も退屈だったが、次の瞬間、教室からすべてが消え去り、私は光の王宮に居るような感覚に陥った。
「人々が私の分野の科学を想像する場合、彼らの大多数が発明の過程を想像します。魔力と呪文を融合させて物体に注入する。魔法の刃、または指輪の創作。しかし、熟練した付呪師は触媒の働きもします。何か新しいものを創作できる精神は、古いものから巨大な力を引き出すこともできるのです。初心者が暖かさを生み出せる指輪も、入門僧の手に掛かれば森林を灰の山にすることが可能です」と、含み笑いをしながら肥えた男は言った。「そのようなことを勧めている訳ではありません。それは破壊学の人達に任せましょう」
その週、修練僧は皆それぞれの専門分野を選択するよう求められた。私が、今まで愛してきた幻惑学に背を向けたことに、皆が驚いた。あのような上辺だけの魔法に愛着を持っていた自分のことをばかばかしく思えた。あの円盤の力を解き放つ手段となる付呪学に、今は、知力のすべてが注ぎ込まれている。
それからの数ヶ月間はほとんど寝なかった。自分を鼓舞し、力を与えるために、一週間のうち数時間をベタニキーや私の彫像とすごした。それ以外の時間は、付呪に関するすべてを学べるように、イルサー教官か彼の助手と一緒にすごした。彼らは私に、物体の中に蓄えられたマジカの真髄を教えてくれた。
「どれほど巧みに唱えても、どれほど華々しく唱えようとも、簡単な呪文でも、一度唱えてしまえば、はかない、そして今だけのものでしかない」と、ため息をつきながら、イルサー教官は言った。「しかし、居場所を与えれば、生きているようなエネルギーへと成長し、熟成され、そして成熟する。よって、未熟なものが手に入れても、そのエネルギーの表面をなでることしかできない。君は自分のことを、地面の奥深くへと潜りこんで、金脈の中心部を掘りあてる坑夫であると考えなさい」
毎晩、研究室が閉鎖した後に、学んだことを復習した。自分自身の力の増加を感じるとともに、また円盤の力も増大していた。「パルラ」そうささやきながら、ルーンに付いた小さなかすり傷や宝石の面に触れつつ、秘宝の奥深くへと潜りこんだ。時には彼女のすぐ近くまで行き、手が触れあうのを感じたこともある。しかし、必ず大きく暗い何かに念願の夢の実現を阻まれる、死の現実なのだろう。その後は必ず抗し難い腐敗臭が漂い、最近では隣の部屋の修練僧が文句を言い始めている。
とりあえず、「何かが床板の下に入りこんで死んだのでしょう」と、申し出た。
イルサー教官は私の学識を称賛し、さらなる研究のために、時間外でも彼の研究室を使うことを許してくれた。それにもかかわらず、何を学んでもパルラが近づいているとは到底思えなかった。ある晩、すべてが終わった。こう惚の中、彼女の名をうめき、あざができる程に円盤を胸に押し付けながら体を揺らしていると、窓から突然差し込んだ稲妻の光が集中を遮った。暴風雨がミル・コルップを覆った。雨戸を閉じて、机へと戻ると、円盤は粉々になっていた。
私は泣き狂い、そして笑った。莫大な時間と研究を注いだ後のこれ程大きな損失は、私の脆く壊れかかった心では受け止め切れなかった。熱にうなされながら、翌日と翌々日はベッドですごした。もし私が治癒師を多く抱える魔術師ギルドの一員でなかったら、おそらくこの世には居なかっただろう。実際、私は仲間の若い学者たちにとって良い研究対象だった。
やっと歩けるまで回復した私は、ベタニキーに会いに行った。彼女はいつもと変わらず魅力的で、一度も酷かったであろう私の顔色や見た目には触れなかった。ついに、池の周りの散歩を丁寧に、かつ堅く辞退したとき、彼女に心配する理由を与えてしまった。
「でも、彫像を見るのが大好きじゃない」と、彼女が叫んだ。
私は彼女に真実とそれ以上のことを話す義務があると感じた。「お嬢さん、私は彫像以上にあなたの母親を愛しています。あなたと一緒にあの神聖な彫像の覆いを解いたときからの数ヶ月、彼女以外のことは何も考えられずにいました。私のことをどう思っているかは分かりませんが、彼女を生き返らせる方法を学ぶことに心を奪われていたのです」
ベタニキーは目を見開いて私を見つめた。そして、ついに言った。「どんな悪趣味な冗談か分からないけど―― 出て行って欲しいわ」
「冗談だったらと願いました、信じてください。でも、私は失敗したのです。愛が足らなかったのではないと思います、なぜなら私以上に誰かを強く愛した人はいないからです。もしかしたら、付呪師としての技量が足らなかったのかもしれませんけど、決して修練不足からではありません!」自分の声が荒げ、怒鳴り散らしているのは分かっていたが、もう止められなかった。「ひょっとしたら、あなたの母と私が一度も会ったことがないのが原因かも知れません、でも死霊術の呪文は術者の愛だけが考慮されるはずだし。もう、何が原因だったのか分からない! もしかすると、あの恐ろしい生物、彼女を殺したあの怪物が何らかの呪いを死の間際に掛けたのかも知れない! 私はしくじったんだ! そして、理由も分からない!」
小さな女性からは考えられない、驚くべき速さと力でベタニキーは私に体当たりした。そして彼女は叫んだ、「出て行け!」私は扉から飛び出した。
彼女が叩きつけるように扉を閉める前に、私は惨めな謝罪をした。「本当に申し訳ない、ベタニキー、でもこれは考慮してください、あなたに母親を連れ返してあげたかったのです。乱心じみているのは分かっています、でも、私の人生の中で確かなのは一つだけ、それは、私はパルラを愛していることです」
彼女は閉まりかけていた扉を少しだけ開き、震えながら問いかけた。「誰を愛していたって?」
「パルラ!」と、私は神々に向かって叫んだ。
「私の母の」彼女は腹立たしげにささやいた。「名前はザーリス。パルラは怪物よ」
私は暫くの間閉じられた扉を見つめ続け、魔術師ギルドまでの長い道のりを歩き始めた。私の記憶は、ずっと以前に愛する人の名前を初めて耳にし、あの彫像に魅入った「物語と獣脂」舞踏会のことを、細部まで思い起こしていた。あのブレトンの修練僧、ゲリンが話していた。彼は私の後ろに立っていた。彼は女性のことではなく、獣の話をしていたのか?
ミル・コルプの町はずれと交差する曲がり道を曲がったとき、それまで座って私を待っていた大きな影が地面から立ち上がった。
「パルラ」うめき声を上げた。「パル…ラ」
「くちづけを」それが、ほえた。
これで私の物語りは、今現在に追いつきました。愛は赤い、血のように。